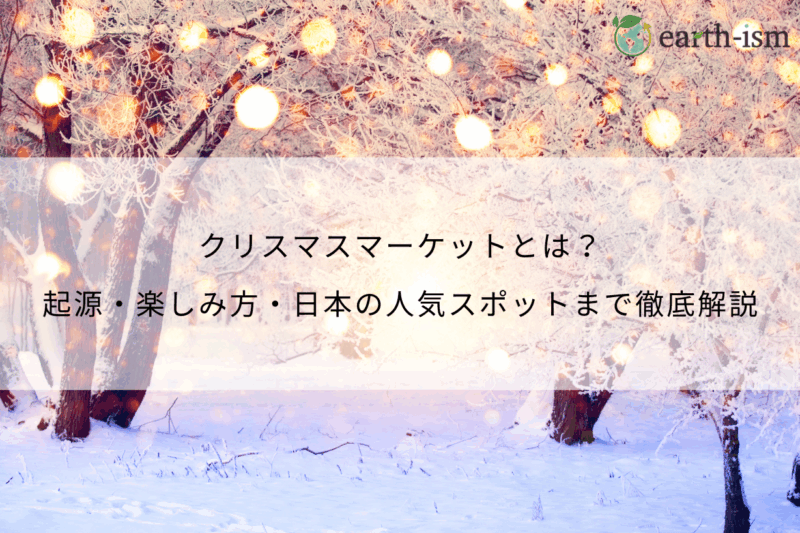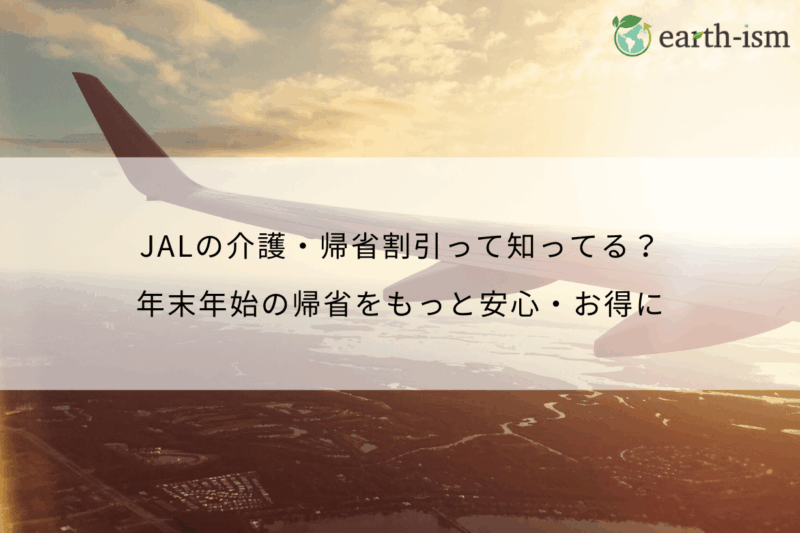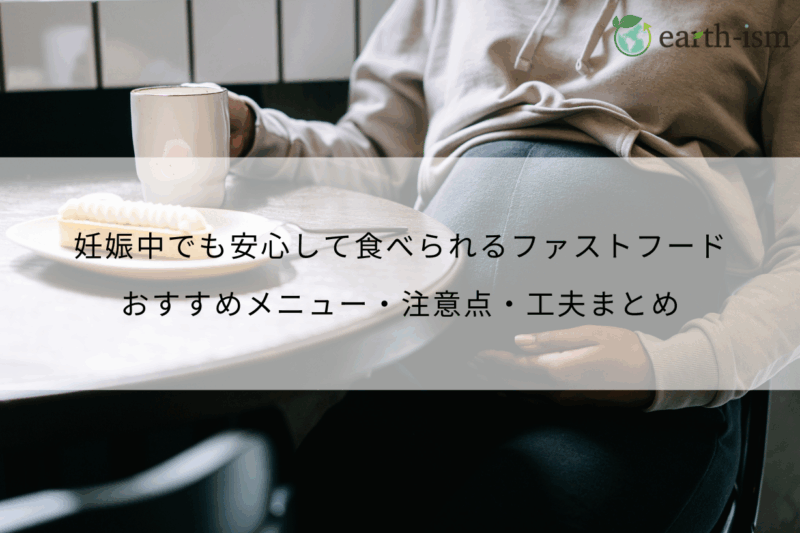「なんかフラフラする…」 子どもの熱中症、親が知っておきたい予防と対処のすべて
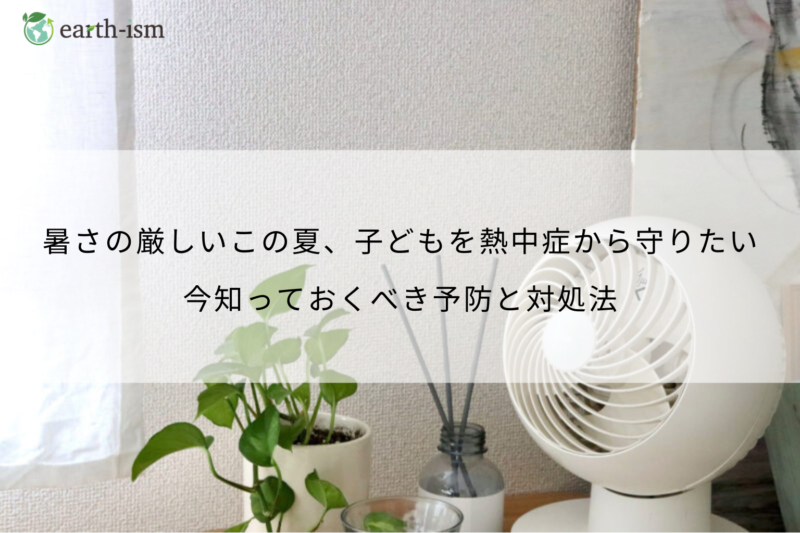
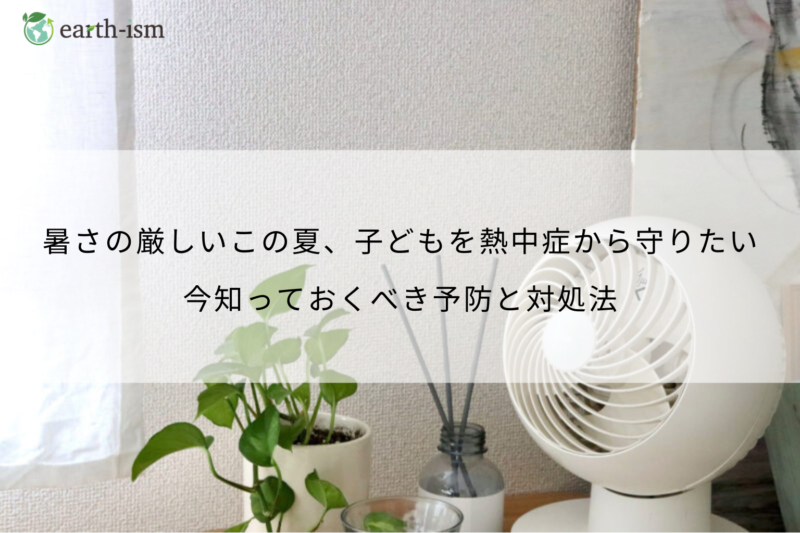
Contents
地球温暖化により、気温40℃も珍しくない昨今。年々、暑さが厳しくなっていると感じている人も多いのではないでしょうか?
そんなときに注意したいのが「熱中症」。特に子どもは体温調節機能が未熟であり、大人以上に熱中症リスクが高いため注意が必要です。
そこで本記事では、子どもの熱中症に焦点を当て対策や対処法について解説していきます。
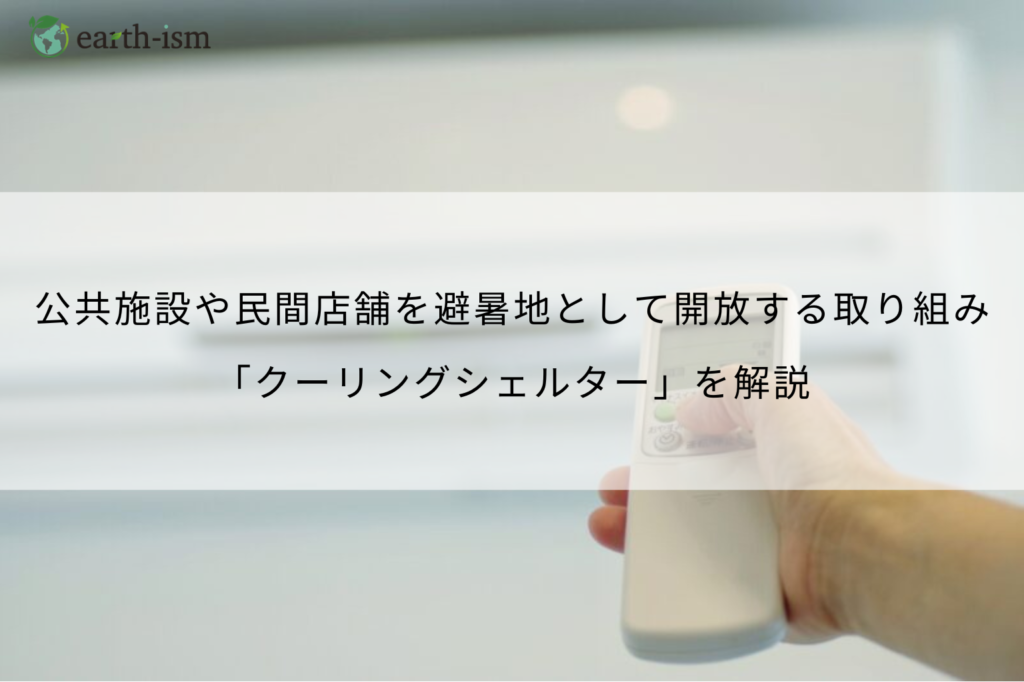
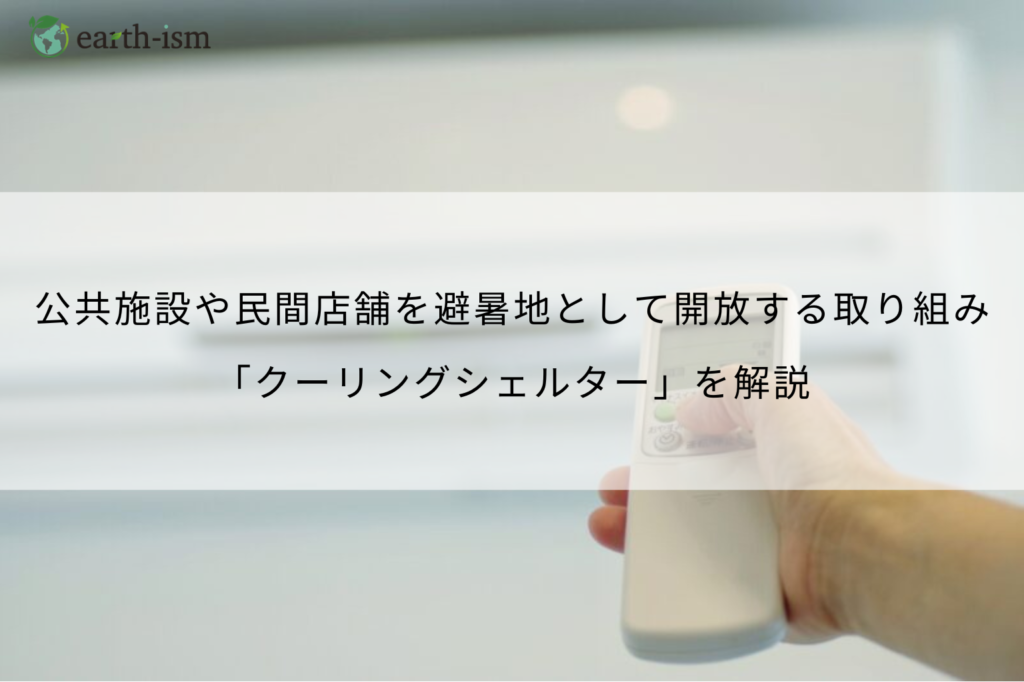
小さなSOSを見逃さない:子どもの熱中症サインとは


まずは、子どもの熱中症の症状や年齢別の気づき方について見ていきましょう。
◆ 初期症状リスト(見た目・行動・言葉)
下記の症状は熱中症のサイン。普段と違う様子はないか、子どもをよく観察しましょう。
早めに気づくことが命を守ります。顔が赤い/ぐったりしている/頭が痛い/「気持ち悪い」と言う/ぼーっとしている/汗が急に出なくなる など
◆ 年齢別の気づき方
幼児は自分の健康状態を言葉で表すことが難しいため、大人が表情や動作に注目してあげることが必要です。
また小学生くらいになると、体調が悪くても我慢してしまったり、遊びに夢中で気づかなかったりする場合があるので注意しましょう。
異変を見逃さないよう、子どもの日常の変化をキャッチすることが大切です。
熱中症になったら? 親がすぐできる正しい対処法
子どもが熱中症になってしまった場合の対処法について解説します。
涼しい場所に移動し、服を緩める
エアコンの効いた室内など涼しい場所に移動し、通気性を良くするために服を緩めましょう。
水分補給(イオン飲料や経口補水液が理想)
意識があり誤嚥が起きないようであれば、水分補給をさせましょう。イオン飲料や経口補水液が適しています。
体を冷やすポイント(首・脇・足の付け根など)
濡らした冷たいタオルで体を拭きましょう。そして、首や脇、足の付け根など太い血管が通っている場所を保冷剤や氷で冷やします。
ぐったりしている・意識がもうろう→救急車を呼ぶ判断のタイミング
呼びかけても応じずぐったりしていたり、意識がもうろうとしていたりする場合には、ためらわずに救急車を呼びましょう。


事前に守る。毎日の「熱中症予防ルーティン」


熱中症を事前に防げるよう、日々のなかでできる「熱中症予防ルーティーン」について解説していきます。
◆ 朝の体調チェック:体温・食欲・元気度を観察
子どもの異変にいち早く気づけるよう、体温、食欲、元気度を毎朝チェックしましょう。また、睡眠を十分にとるなど日頃から生活リズムを崩さないことも大切です。
◆ 登園・登校時の注意点
次に、登園、登校時に気をつけるポイントを見ていきましょう。
帽子・水筒・汗拭きタオルは必須三種の神器
帽子、水筒、汗拭きタオルは外出時の必須アイテム。十分に水分補給ができるよう、水筒は大きめのものを持たせてあげると良いでしょう。
通学路が日陰かどうかも確認ポイント
子どもは大人と比べて身長が低いため、地面からの照り返しの影響を大きく受けてしまいます。
そのため、通学路が日陰であるかもチェックしたいポイントです。
「お水、飲んだ?」「暑かったら先生に言っていいんだよ」
子どもだけでは熱中症を予防することはできないため、大人による気配りが欠かせません。タイミングを見て「お水、飲んだ?」と聞いてあげれば、子どもも水分補給しやすくなります。
また、日頃から「暑かったら先生に言っていいんだよ」と声掛けしていれば、体調不良時に安心して大人を頼ることができるでしょう。
自宅でできる熱中症対策×サステナブルアイテム
自宅でできるサステナブルな熱中症対策アイテムについてご紹介します。
◆ エコで快適なアイテム選び
暑い時期に快適に過ごせるおすすめエコアイテムを見ていきましょう。
リネン素材の通気性ウェア/竹製ひんやりマット
リネンや竹といった天然素材は汗ばむ季節にピッタリ。リネンは通気性が良いため蒸れにくく、竹は触れると冷たさを感じ、抗菌作用もあるのが特徴です。
見た目にも涼しいので、夏はこれらのアイテムを取り入れてみるのはいかがでしょうか。
保冷剤を活用した再利用可能なネッククーラー
さまざまなデザインのものが販売されており、夏のクールダウンにおすすめ。保冷剤を使用しているため、何度でも再利用可能な点がポイントです。
電力を抑えた冷風扇・気化熱グッズ
エアコンと比べて電気代を節約できる冷風扇。近頃は卓上タイプも販売されています。
◆ 食でできる予防習慣
熱中症予防には、食習慣も大切。おすすめ食材について見ていきましょう。
夏野菜(きゅうり・トマト)で水分補給+ミネラル
水分を多く含むきゅうりやトマトといった食材は体を冷やす効果があります。
また、ビタミンやミネラルが豊富な夏野菜は夏バテ予防にもなるので、意識して食べると良いでしょう。
発酵食品(味噌・納豆)で腸内環境を整え、体調を崩しにくく
乳酸菌などが含まれている発酵食品は、腸内環境を整え、免疫力アップに役立ちます。冷たいものばかりを食べると胃腸の働きが低下するため、味噌汁を飲むこともおすすめです。
塩分補給には、梅干しや塩昆布も◎
熱中症予防には水分だけでなく塩分補給も重要です。
おすすめ食材は梅干しや塩昆布。手軽に手に入るため食事に取り入れやすいですね。
覚えておきたい、受診の“赤信号”


病院へ受診すべき熱中症の症状について見ていきましょう。
「水が飲めない」「意識があいまい」「嘔吐やけいれん」→すぐに医療機関へ
「水が飲めない」「意識があいまい」「嘔吐やけいれん」といった症状がある場合には、ただちに病院へ連れていき医師に診てもらいましょう。命に関わる危険性もあるため、迅速な対応が鍵となります。
#8000(子ども医療電話相談)の利用方法
子ども医療電話相談をご存知でしょうか?
夜間や休日に、子どもの症状に対して病院受診をすべきか判断に迷った際、電話機から「#8000」をプッシュで、小児科医師や看護師に相談できるものです。
1人で悩まず、必要な場合にはぜひ活用しましょう。
かかりつけ医への早めの相談が鍵
持病がある場合は、熱中症の対処法について早めにかかりつけ医に相談しておくのがポイント。子どもの健康状態を把握しているかかりつけ医から、適切なアドバイスを受けましょう。
地球も、子どもも守る。気候変動と熱中症のつながり
気候変動と熱中症との関係について見ていきましょう。
熱中症は「気候変動」が引き起こす“身近な問題”
長年、気候変動による気温の上昇が深刻な課題とされていますが、実は地球環境と熱中症には深い結びつきがあります。
地球温暖化が進むと猛暑日が増え、熱中症リスクも高まっていくため、これは私たちにとって身近な問題といえるのです。
子どもたちの未来のために、私たちにできる選択肢
温暖化対策を行うことは、熱中症リスクを減らすことにも繋がっていきます。例えば、節電や節水、ゴミを減らすなど小さいアクションでも取り組めることはたくさんあります。
子どもたちや地球の未来のために、私たちが環境のためにできることを考えていかなければいけません。
まとめ:親の“予防する力”が、未来を守る


命を落とす危険性もある熱中症。子どもだけでは対策が難しいからこそ、まずは親が熱中症についての知識を付けることが大切です。
かけがえのない子どもの命を守るために「予防する力」を高めていきましょう。