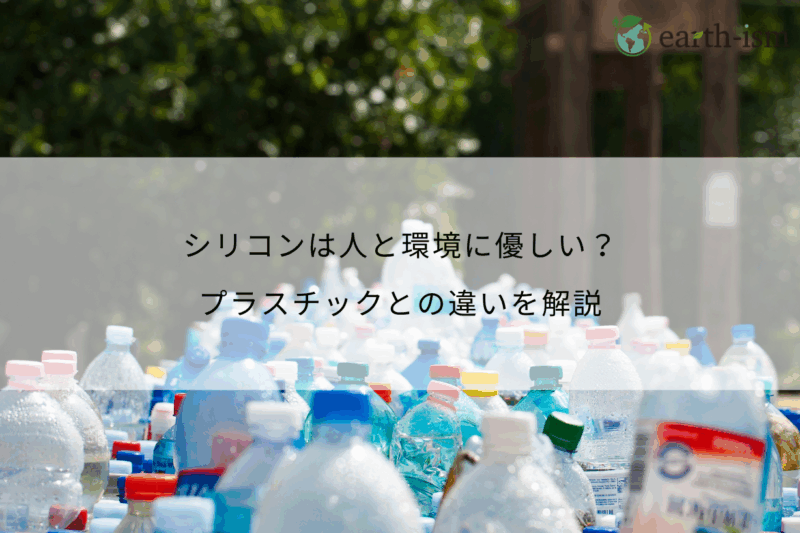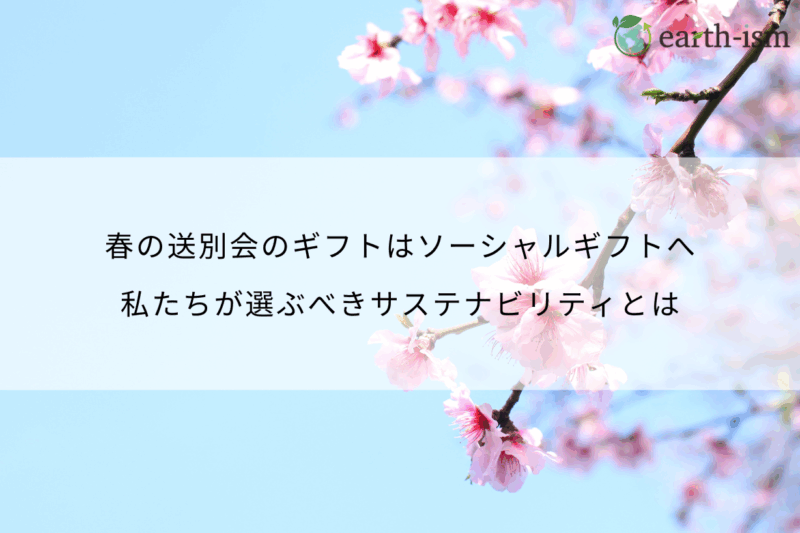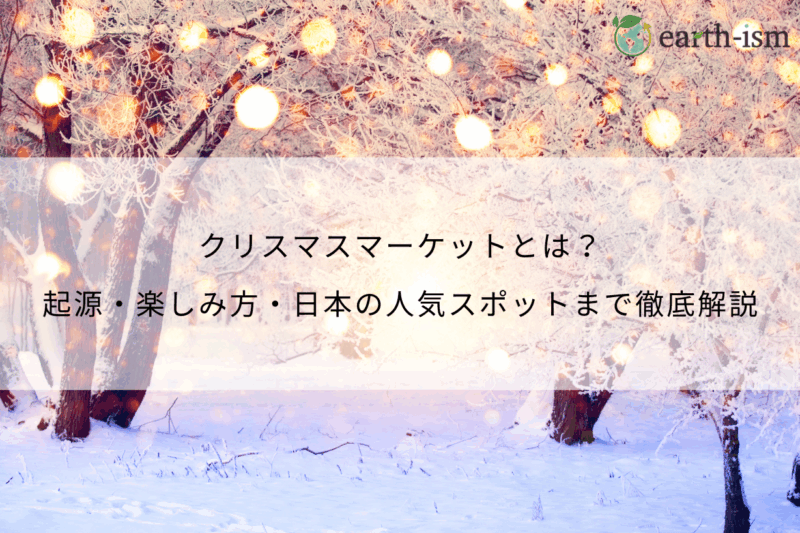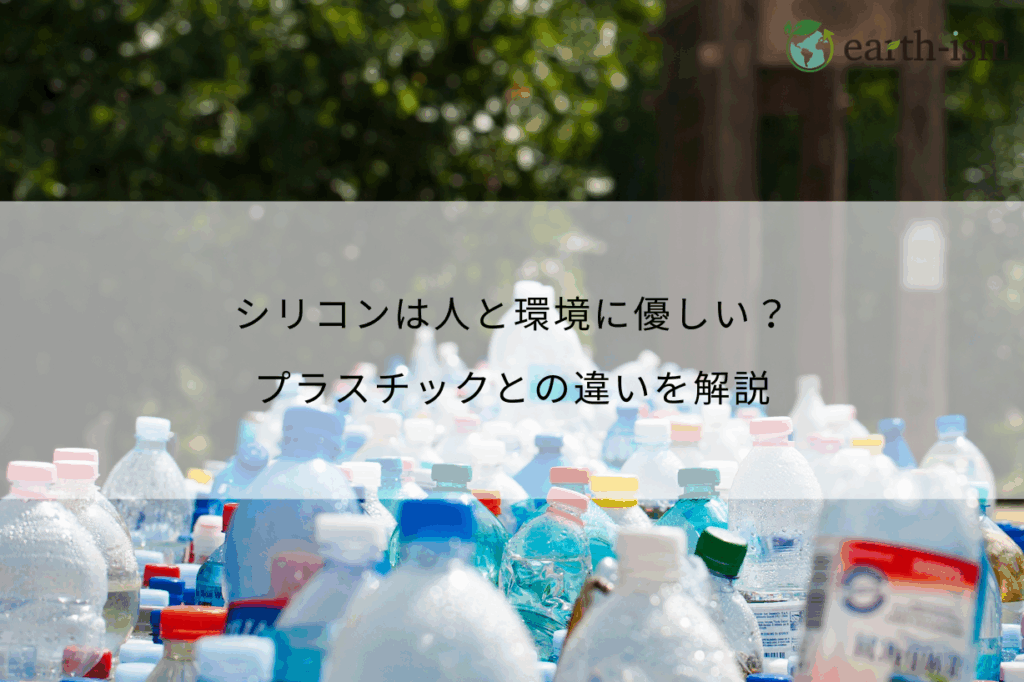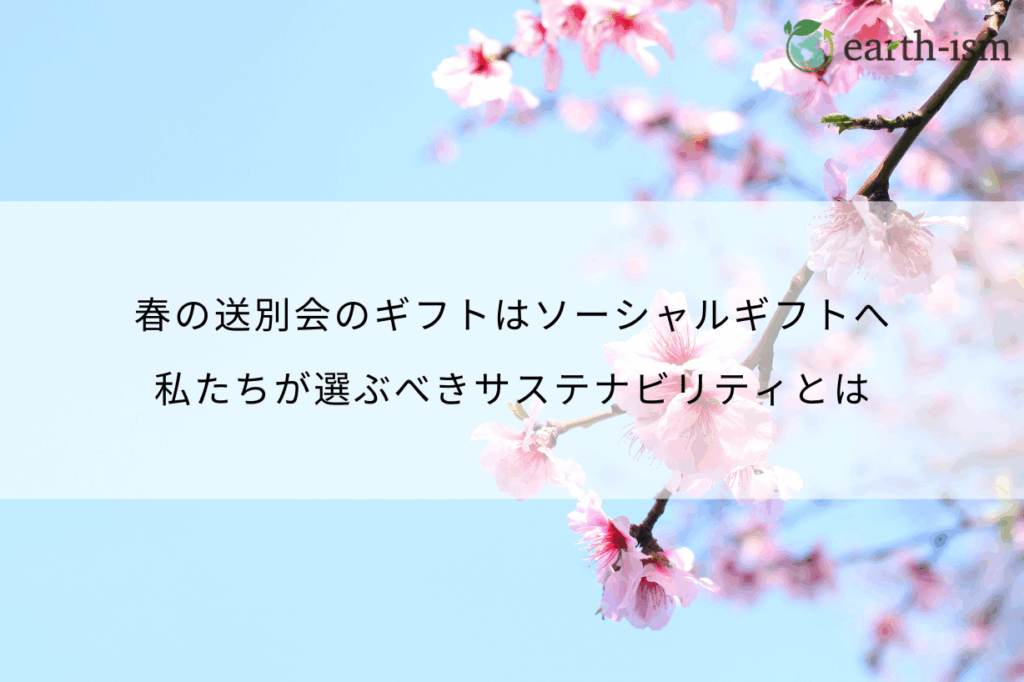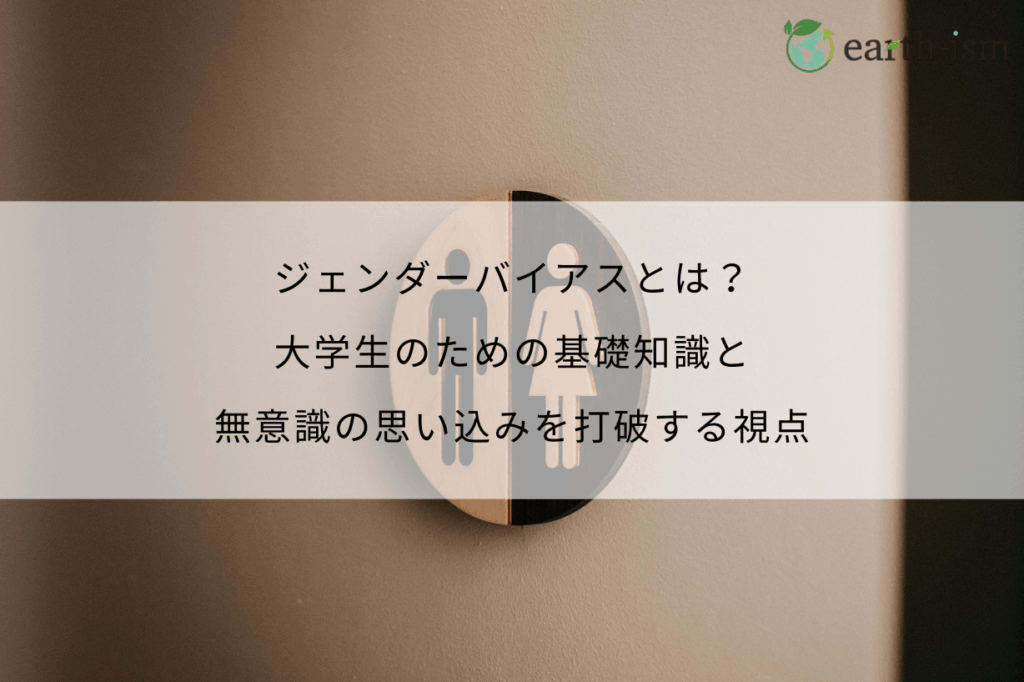オンデマンドバスとは?新しい地域移動サービスの特徴と課題を解説


Contents
近年、地方都市や郊外を中心に導入が広がっている「オンデマンドバス」。電話やアプリで予約でき、利用者の行き先に合わせて柔軟に運行するこのサービスは過疎化や高齢化が進む地域の移動手段として注目を集めています。その一方で「遠回りになる」「希望した時間に乗れない」といった声が上がっているのも事実です。
そこで本記事では、オンデマンドバスの仕組みや導入が進む背景、その特徴と課題をわかりやすく解説します。さらに実際の乗車体験もレポートし、利用の参考になる情報をお届けします。
オンデマンドバスとは


オンデマンドバスとは、相乗り、予約制を採用した新しい交通機関です。
従来の路線バスが決められたルートや時刻表に沿って走るのに対し、オンデマンドバスはスマートフォンアプリや電話で予約を受け付け、AIが効率的なルートを自動で組み立てて走行します。
AIによるルートの最適化は空車や低乗車率を減らせるため、運行コストの削減にもつながります。このような特徴から全国の自治体や民間事業者で導入が進みつつあり、地域の移動手段の確保や生活の利便性向上に貢献しています。
デマンドバスとオンデマンドバスの違い
デマンドバスとオンデマンドバスと両方の言葉を見聞きしますが、どちらも利用者の要求(デマンド)に応じて運行されるバスという意味で使われることが多く、定義上の明確な違いはありません。
しかし最近ではAIやスマートフォンアプリなどの先端技術を活用したバスをオンデマンドバスと呼ぶことが増えています。利用者の予約情報に基づき、リアルタイムで最適なルートを自動生成できるため、乗降位置も柔軟に設定可能です。その結果、運行の効率性や利便性が高く、先進的な交通サービスとして注目されています。
つまりオンデマンドバスはデマンドバスの一種であり、特にAIによる効率化・最適化が図られた新しい形態のデマンド型交通を指していると言えます。
バス利用者は半減、事業者の8割が赤字という現状
バスは通勤、通学、通院などの移動を支える生活に欠かせない存在です。しかし郊外や地方では路線バスの廃止や減便が相次いでいます。その背景には人口減少による利用者の減少や、運転手不足などがその要因として挙げられています。
国土交通省から報告されている「交通政策白書」よるとバスの乗車人数(輸送人員)は1985年に約 69億9,800万人だったのに対して、2022年には約36億1,800万人と約半分に落ち込んでいます。さらに「地域公共交通の現状」によると2023年度には一般路線バスの事業者73.7%が赤字であることが明らかになりました。
こうしたデータからバスの運営状況が厳しいことがわかりますが日常の移動手段としてバスを利用している人も多く、地域での重要性は変わっていません。
オンデマンドバスのメリットと課題


こうした現状のなか自治体では住民の移動手段を確保する解決策としてオンデマンドバスの導入を進めています。ここではオンデマンドバスのメリットと課題を、利用者と事業者両方の目線から見ていきましょう。
オンデマンドバスのメリット
オンデマンドバスはスマートフォンや電話で予約するシステムです。AIが交通状況や乗車人数を考慮して最適なルートを提示するため、無駄な待ち時間や遠回りが削減できます。また運営者側には不要な迂回や空走を減らすことで燃料費や人件費などを抑えられます。
- 時刻表に縛られず希望の時間に利用できる
- 無駄な待ち時間や遠回りを削減できる
- 不要な迂回や空走を減らすことで燃料費や人件費を削減できる
オンデマンドバスの課題点
一方で、利用者が集中すると待ち時間が発生するほか、運行エリアや時間が限定されるといった課題も指摘されています。またアプリ操作や予約に慣れていない高齢者には負担となることもあるでしょう。電話予約を受け付けている場合が多いですが、土日は営業していない自治体もあります。
- 乗車の際には予約しなければならない
- アプリ操作に不慣れな高齢者には使いにくい場合がある
- 利用者が多い場合は待ち時間が長くなったり遠回りになったりすることがある
- システムや端末の導入など初期費用がかかる
さらに、運営者はハードウェアやシステム導入などの初期費用が大きな課題です。
実際に導入されたオンデマンドバス
実際にオンデマンドバスはどのように導入されているのでしょうか。
長野県塩尻市では乗降拠点が312カ所に
例えば長野県塩尻市では地域住民の移動手段として地域振興バスを運行していましたが、利用者減少や大型バス運転手の人手不足といった課題を抱えていました。
そこでワンボックスカーを利用したオンデマンドバスサービス「のるーと塩尻」の導入を開始しました。以来、実証実験として利用者調査を行いながら生活に必要な施設へのアクセス向上に取り組んでいます。2020年から開始したのるーと塩尻は、2023年には312カ所まで乗降拠点を拡大しています。
愛知県豊明市ではスポンサーシステムを導入
さらに愛知県豊明市ではオンデマンドバス「チョイソコ」が2018年より実証実験運行を開始し、2021年には本格導入されました。特徴的なのは民間企業がエリアスポンサーとして協賛金を払うことで自社施設などに停留所を設置できることです。
これにより企業は集客を期待できます。また乗降拠点を資源ごみ置き場に設置するという取り組みも行われており、高齢者や足の不自由な人でも自宅近くでの乗降が可能になりました。収集車が停車できるように設計されているためバスの一時停車にも適しています。
このように地域によって、目的や運用方法が異なります。住民の生活利便性向上に特化する場合もあれば、観光客の移動手段を考慮する場合、高齢者支援を重視する場合もあります。地域のニーズや人口構成に応じて最適な運行形態を設計できる点もオンデマンドバスの大きな特徴です。
本当に便利?オンデマンドバスを乗車体験


実際に利用した人からは「タクシーなら2,000円近い距離を300円で移動できた」「家の近くに停留所ができて便利」「楽に移動できた」といった好意的な声が聞かれます。一方で「路線バスでは不要だった乗り換えが必要になった」「通常10分の距離が遠回りで40分かかった」「予約時間から大幅に遅れた」などの不便さを指摘する声もあります。
そこで利便性や課題を体感するためオンデマンドバスを体験してきました。今回乗車したのは福岡県宗像市を走行するオンデマンドバス「のるーと宗像」です。
宗像市ではコミュニティバスが運行されていますが、毎日運行していないエリア、一日2便など運行本数が少ないエリアもあり利用が制限されています。のるーとの運行エリアはまだ限定的ですが、住民の移動を支える取り組みとして期待されています。
アプリの登録や予約は簡単


まずはApp Storeでアプリをダウンロードしました。電話番号でのSMS認証を完了させると、ログイン画面へ遷移するので必要項目を入力すれば初期設定は完了です。
早速予約しようとしたところ、画面には現在地を示す地図と「今すぐ予約」と書かれた検索バーがありました。エリア内にいれば地図上に停留所が表示されるので、タップしていけば出発地と目的地は簡単に指定できます。
乗降スポットが表示されていなくても「今すぐ予約」をタップし、スポット名を入力することでも予約可能です。Google Mapsなどの地図アプリを使用している利用者な使いやすいシンプルなUIだと感じました。
しかし、高齢者のなかにはフィーチャーフォンを使っている方も多く、アプリの登録方法が分からない場合もあります。そのため、自動音声による電話予約が利用できるのは安心だと感じました。ただし、オペレーターは土日に対応していないためこの点を不便に感じる人もいるでしょう。
希望よりも予約時間は遅くなったが目的地まではスムーズ
今回は利用日当日に予約しました。11時に予約しようとしたところ11時15分の乗車に変更されていました。さらにその後も数分ですが、出発予定時刻は後ろに変更されていました。
帰りの乗車も希望時間よりも遅い時間に設定されたため、バスの運行状況や遅延の可能性を考慮して予約時間を設定したほうがよいでしょう。
一方、オンデマンドバスは決まったルートがないため、路線バスのように利用者のいない乗降場所に停車することはありません。今回はコミュニティバスだと10カ所ほど停留所に立ち寄るところを、行きでは2か所、帰りは停車なしで目的地に到着でき、とても早く移動できました。
バスは狭いが短時間なら問題なし
バスは8人乗りのワンボックスカーでした。座席最後部は荷物が置けるスペースになっていました。3歳の子どもを連れてベビーカーも一緒に乗車。中腰で最後部までベビーカーを運ぶのは大変だと感じていたところ、他の乗客の方に最前部の座席を譲っていただきベビーカーを支えながら乗車できました。座席スペースは狭く窮屈ではありましたが長時間の乗車ではないので苦にはなりませんでした。
バスの乗客のほとんどがご年配の女性でした。60~70代の方がスーパーマーケットから病院前で降りたり、イベント帰りの50~70代の女性たちが駅へ向かったりするのに利用していたようです。今回乗車していた利用者の乗降はスムーズで何度か利用されている印象を受けました。とドライバーの方に聞くと、ご高齢の方は電話で予約しているのことでした。
今回は問題なく利用できましたが、一番気になったのは出発時間の調整です。余裕をもった時間で予約をしておく必要があるでしょう。
まとめ


今回は新たな移動手段として注目されているオンデマンドバスについて解説しました。
地域ごとに抱える課題や運用方法は異なりますが、共通しているのは「住民に必要な移動手段を提供する」という点です。まだ発展途上のサービスのため課題がありますが、地域に適した公共交通の新しい形として今後の動向と発展が注目されます。