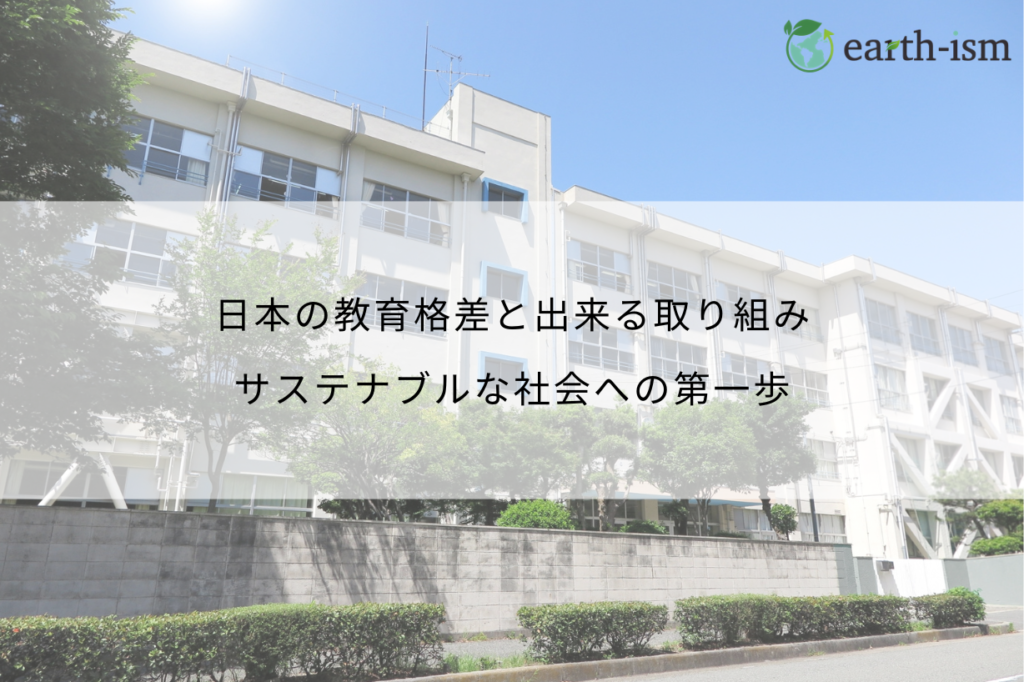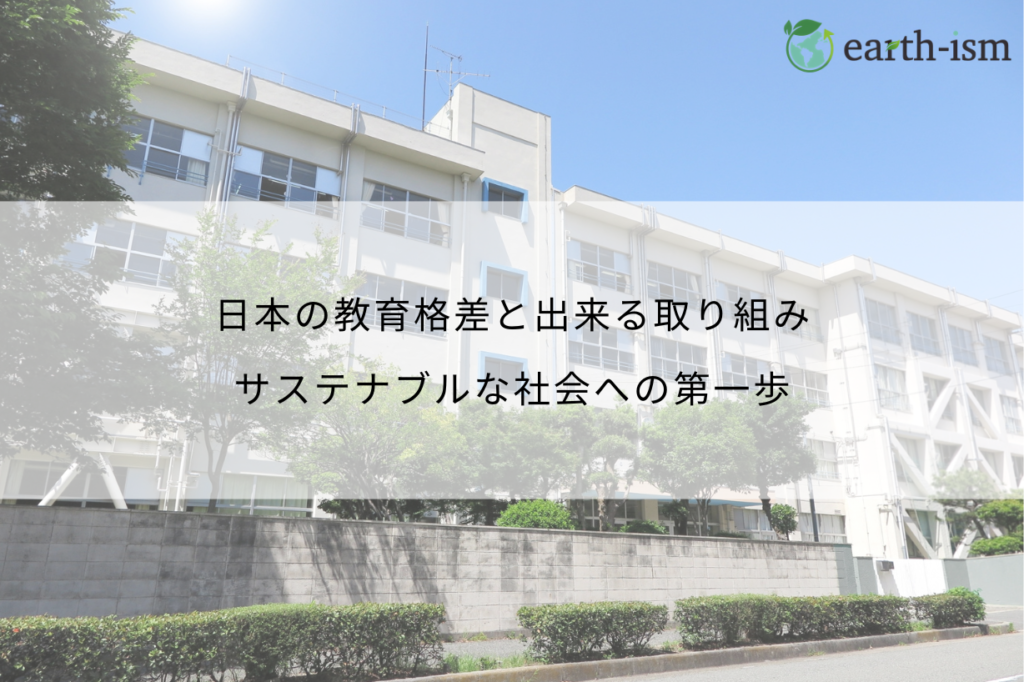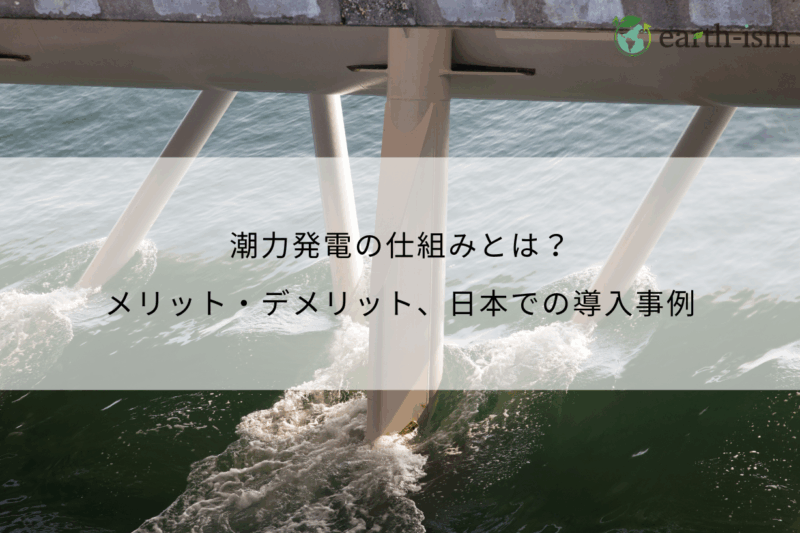【2025年最新】エコスクールとは?効果や認定校事例を徹底解説
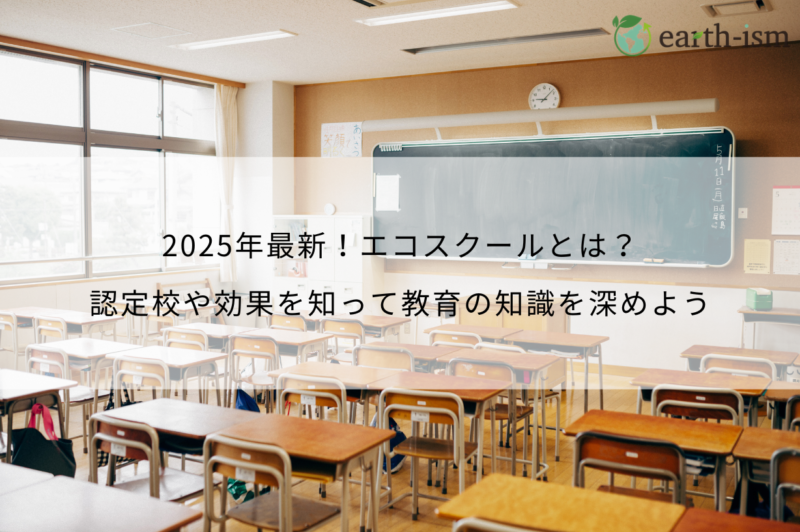
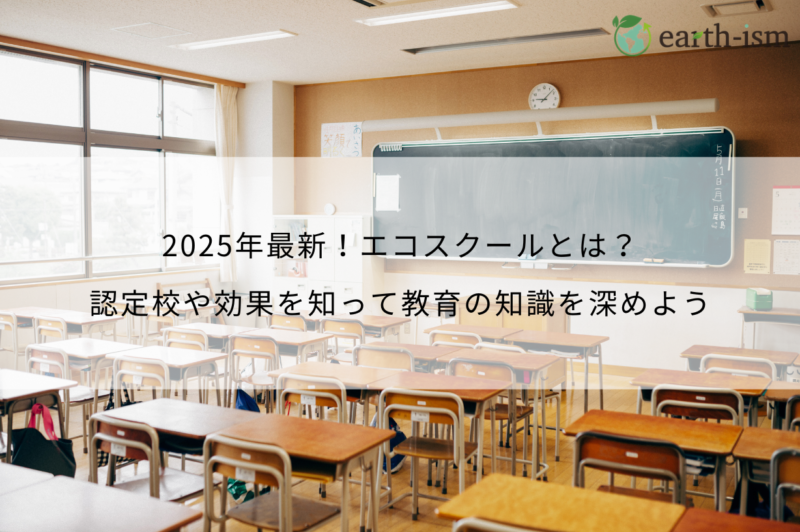
地球温暖化やエネルギー問題が深刻化するなか、学校教育の現場にも「環境配慮」の視点が求められています。そんな時代のニーズに応える形で注目を集めているのが「エコスクール」です。エコスクールとは、環境にやさしい設計や運営を取り入れた学校施設であり、単なる省エネ建築ではなく、子どもたちの環境学習の場としても活用されるのが大きな特徴です。
この記事では、2025年現在の最新情報をもとに、エコスクールの基本的な考え方から、その効果、さらに全国の認定校の具体的な事例までを詳しく解説します。
これからの学校づくり・地域づくりを考えるうえで、エコスクールが果たす役割とは何か。その全体像を把握しておくことによって、お子さんの教育に役立てましょう。


エコスクールとは


エコスクールとは、学校そのものを環境にやさしい施設として整備し、子どもたちの環境意識を育てる拠点としても活用する取り組みです。文部科学省が平成9年度から本格的に推進しており、単なる校舎の整備にとどまらず、「環境に配慮した学びの場」としての役割を担っています。
エコスクールは地域社会とのつながりも意識して整備されます。地域住民に開かれた施設として、防災拠点や環境啓発の場として活用されることもあります。つまり、エコスクールは子どもたちの学びを深めるだけでなく、地域全体に環境への気づきと行動を促す発信拠点としての役割も果たしているのです。
エコスクール整備の3つのポイント
エコスクールを整備する際には、「施設」「運営」「環境」の3つの視点からの配慮が重要です。以下に、それぞれの観点で留意すべきポイントを整理します。
やさしく造ること|施設面への配慮
まず、学校施設は子どもたちが安心して学び、過ごせる空間であるべきです。健康的で快適な学習・生活空間の確保はもちろん、周辺の自然環境や地域との調和も重視されます。また、設計・建設の段階から環境への負荷を最小限に抑える工夫を取り入れることが求められます。
賢く・永く使うこと|運営面への配慮
次に、学校を長く有効に使うための運営上の工夫が必要です。建物や設備は耐久性に優れ、将来的な改修や用途変更に対応できる柔軟性を持つことが望まれます。また、太陽光や風力といった自然エネルギーを活用し、資源やエネルギーを無駄なく使う仕組みを整えることも重要です。
学習に資すること|環境面への配慮
最後に、学校そのものが環境教育の場となるように工夫します。たとえば、再生可能エネルギーの活用状況や省エネの工夫を子どもたちが直接見たり触れたりできるようにすることで、日常的に環境について学べる機会を提供します。施設全体が「生きた教材」となることを目指します。


エコスクールに認定されている代表的な学校5選


エコスクールは、環境に配慮した設計・運営を通じて、子どもたちの学びと地域とのつながりを深める拠点として注目されています。ここでは、文部科学省のパイロット事業や「エコスクール・プラス」に認定された、代表的な5校の取り組みを紹介します。
1. 釧路市立阿寒中学校(北海道)
北海道の豊かな自然に囲まれた阿寒中学校では、地元の森林資源を活用した木造校舎が建設されました。木のぬくもりを活かした設計により、快適で落ち着きのある学習環境が実現されています。
校舎そのものが地域の自然と一体化しており、生徒たちは日常的に環境との関わりを感じながら学ぶことができます。学校施設をそのまま教材として活用する姿勢が高く評価されています。
2. 金ヶ崎町立金ヶ崎中学校(岩手県)
金ヶ崎中学校では、太陽光発電をはじめとする自然エネルギーの活用が進んでいます。創エネ(エネルギーの創出)と省エネ(エネルギーの節約)を組み合わせた施設運用により、エネルギー自給の実現と温室効果ガスの削減を目指しています。
こうした設備は単なる省エネ対策にとどまらず、授業や学校行事を通じて、生徒の環境意識を高める学習資源にもなっています。
3. 二本松市立東和小学校(福島県)
東和小学校では、地域の森林や自然と調和した施設づくりが進められました。建設資材には地元の木材を多く使用し、地域資源を最大限に活用することで、地域経済への貢献と環境負荷の低減を両立しています。
校舎や設備は、生徒が環境保全の重要性を実感できるよう工夫されており、自然との共生を肌で感じながら学ぶことができます。
4. 港区立御田小学校(東京都)
都市部に位置する御田小学校では、省エネ設備や太陽熱利用システムの導入に加え、エネルギー使用状況を「見える化」する取り組みが行われています。
校舎内にはリアルタイムでエネルギーの使用量や発電量が確認できるモニターが設置されており、子どもたちが自らの行動とエネルギー消費の関係を学ぶことができます。さらに、地域住民にも開かれた防災・環境拠点としての役割も果たしています。
5. 瑞浪市立瑞浪北中学校(岐阜県)
瑞浪北中学校は、省エネ・創エネ・蓄エネの各技術を結集し、ZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)を実現した先進的なモデル校です。校舎では高効率な換気・照明・冷暖房設備が整備されており、年間のエネルギー消費を実質ゼロに近づけています。
また、太陽光発電による電力供給や、設備の運用状況の見える化を通じて、生徒が日常的にエネルギーについて考える仕組みが整っています。
教材として活用されるエコスクールの実践事例


エコスクールは、環境に配慮した設計にとどまらず、その設備や取り組みを教育活動に取り入れることで、環境学習の質を高めています。以下に、実際に学校で行われている活用事例を紹介します。
愛知県・瀬戸市立品野台小学校
山に囲まれた自然豊かな立地を活かし、平屋建ての校舎には太陽光発電システムや雨水利用設備が導入されています。教育活動としては、学校ビオトープ内の水田での田植え体験や、太陽光発電量の記録とグラフ作成を通じて、エネルギーについての理解を深める取り組みが行われています。
福島県・いわき市立中央台南中学校
ニュータウンの新設校として、環境モデル校を目指して設計されました。中庭を中心に据えた配置と自然採光の導入により、開放的で環境にやさしい空間が生まれています。
生徒たちは、雨水利用の仕組みを調査・発表する活動や、学校紹介ビデオで環境配慮設備を紹介するなど、主体的に学びを深めています。
福井県・南越前町立南条小学校
太陽光や風力、水力発電、さらに太陽熱給湯といった自然エネルギー設備が整い、校舎の中庭にはビオトープも設けられています。中でも特徴的なのが、校舎の赤レンガ。これは生徒たちが回収したガラス瓶をリサイクルしてつくられた建材で、環境学習を身近に体感できる象徴的な教材となっています。
環境・エネルギー教育の先進的事例


環境配慮型の設備を導入するだけでなく、それらを教育に直結させることで、より実践的な学びが展開されています。
福岡県・糸田町立糸田小学校
地熱、太陽熱、雨水などの自然エネルギーを活用した設計がなされており、校内にはエネルギー使用状況を「見える化」する電子掲示板が設置されています。
低学年には視覚的に理解しやすい図を用いた指導、高学年には木材活用や資源循環をテーマにした授業が行われ、発達段階に応じた環境教育が実践されています。
鳥取県・日吉津村立日吉津小学校
太陽光発電設備の導入をきっかけに、学校全体の環境教育が活発化しました。中国電力による出張授業では新エネルギーや電気自動車について学び、近隣のイオン店舗でのエコ活動を見学する機会も設けられています。
こうした学びを経て、生徒たちは学校の電力使用状況にも関心を持ち、節電活動を自発的に行うようになりました。
滋賀県・東近江市立箕作小学校
子どもたちが日常の中で環境を意識できるよう、学校設備には様々な工夫が施されています。
たとえば、毎日使う机や椅子には県産材を使用しており、身の回りの素材に目を向けることで、自然や資源への関心を育てるきっかけとなっています。
まとめ


これからの時代、子どもたちにとって「環境への理解」は教科書の中だけでは完結しません。エコスクールは、そうした未来を見据えた新しい学びのかたちです。省エネや自然エネルギーを取り入れた校舎、環境と調和した設計、そしてそれを教材として日々の授業に生かす。エコスクールは、学校そのものが“生きた教科書”となる場所です。
実際に、太陽光発電のデータを記録してグラフを作成したり、雨水の利用状況を調べて発表したりと、子どもたちは五感と頭をフルに使って環境を学んでいます。また、再生素材でできた校舎の一部に自分たちの関わった成果が使われていたりすると、学びが「実感」として心に残ります。
さらにエコスクールは、地域とのつながりも大切にしています。地域の資源を使った校舎づくり、防災拠点としての機能、企業や団体と連携した出張授業など、学校を中心とした地域の学び合いの場にもなっています。
つまりエコスクールとは、子どもたちの「環境を考える力」と「自分で行動する力」を育てる場所。家庭や地域とつながりながら、未来の社会を担う力をじっくりと育てていく教育のかたちなのです。