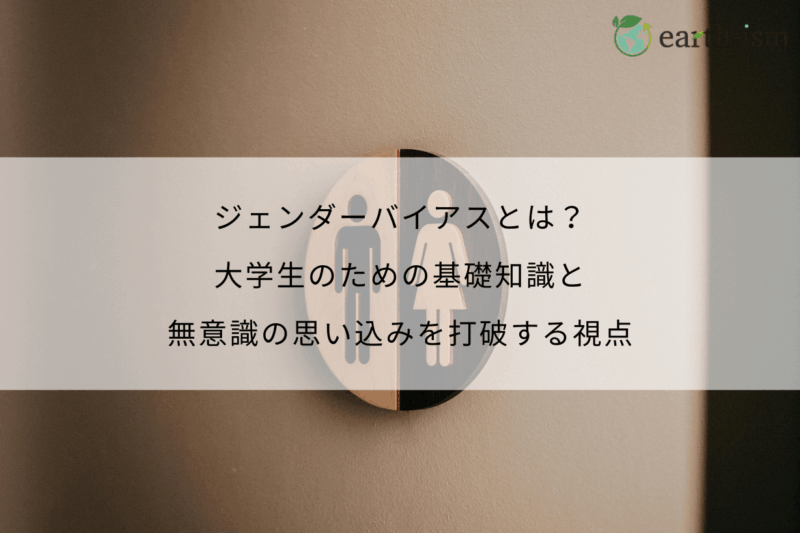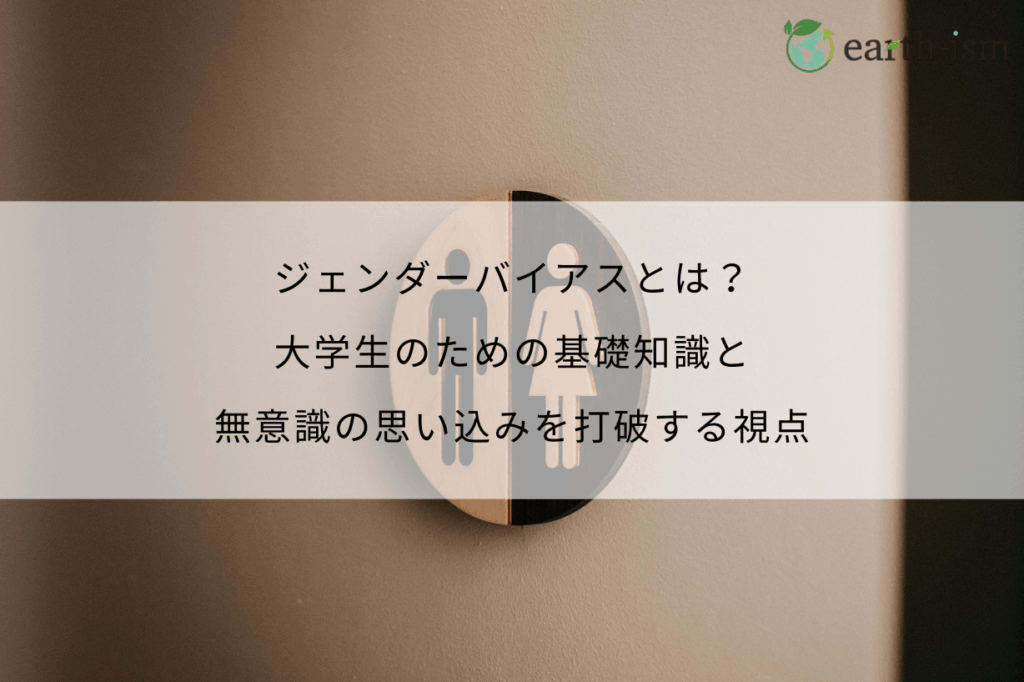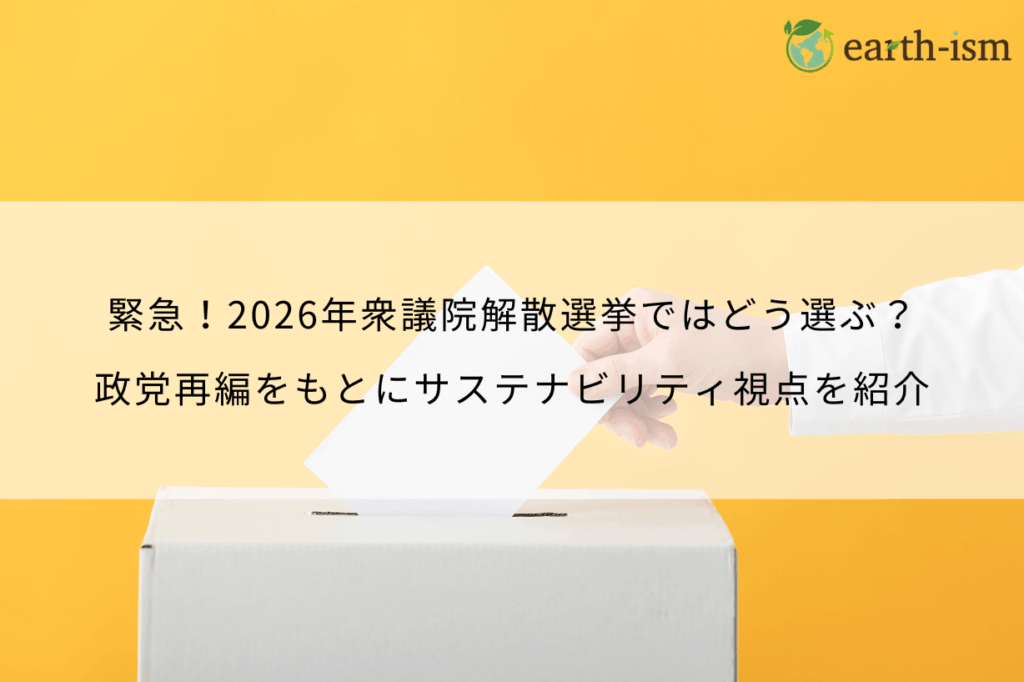2025年も狩猟解禁日は11月15日!獣害の現状やジビエ料理などを解説


Contents
秋が深まり、山々の木々が色づく頃になると、日本各地で「狩猟解禁日」がやってきます。2025年も例年通り、11月15日に全国的な狩猟シーズンが始まります。
狩猟と聞くと一部の趣味や伝統文化のように感じるかもしれませんが、実は農作物を守る「獣害対策」や、食文化を支える「ジビエ料理」と深く結びついています。
この記事では、狩猟解禁日の意味や期間の理由、獣害の現状、ジビエの価値、そして狩猟をめぐる課題について詳しく解説します。
狩猟解禁日とは?いつ・なぜ決められているのか


狩猟解禁日は法律で定められた「猟期」の始まりを示し、野生動物や生態系を守りながら人と自然が共生するための仕組みです。
解禁日は地域ごとに違う?
全国的には11月15日〜翌年2月15日が「狩猟期間(猟期)」とされています。しかし、気候条件や野生動物の生息環境によって各地域で異なります。
- 北海道:10月1日開始〜1月31日まで
- 本州・四国・九州:11月15日〜2月15日が一般的
この期間は、各都道府県が鳥獣保護管理法に基づいて定めています。環境省の指針を踏まえつつも、地域ごとの特性に合わせて細かく調整されているのです。
なぜ期間が決まっているのか
狩猟期間が法律で管理されているのは、野生動物の個体数を守るためです。春から夏は繁殖期にあたり、この時期に無制限に狩猟が行われると個体数が急激に減少してしまいます。そのため、繁殖期を避け、秋から冬に限定して猟を許可することで、生態系のバランスを守る役割を果たしているのです。
ただし、最近ではヒグマからの被害が高まっていたり、キョンが千葉県以外でも見られていたりと、いわゆる「獣害」が多発している傾向にあります。そのため、今後狩猟解禁日についての見方が変わることもあるかもしれません。
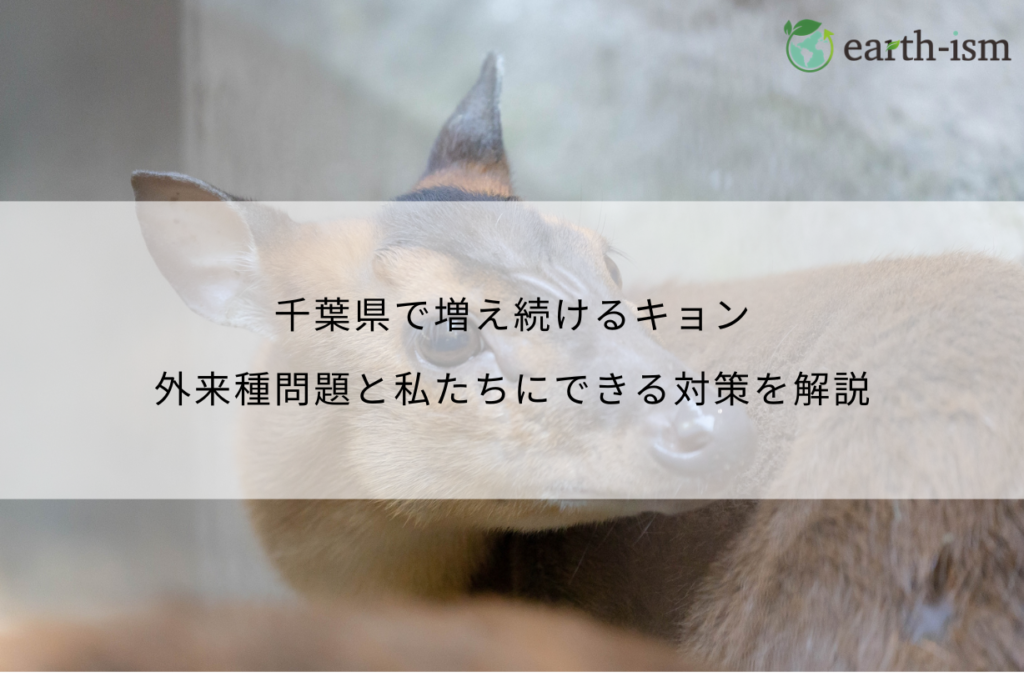
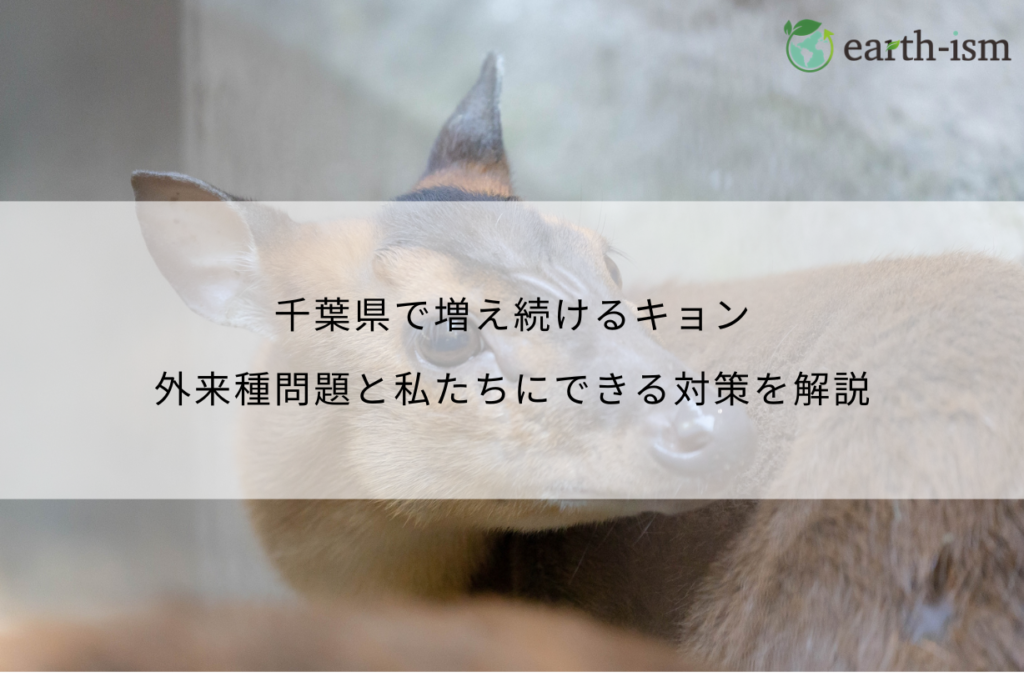
現代の狩猟は、誰が・何のために行っているのか?
近年の狩猟は、単なる伝統文化ではなく、獣害対策やジビエ肉の活用など「暮らしを守る仕組み」として注目されています。
農村だけでなく、都市部にも広がる“新ハンター”
近年、狩猟免許を取得する人は必ずしも農村部に限りません。20〜30代の若者や女性の免許取得が増加しており、「新ハンター」と呼ばれる層が登場しています。背景には、キャンプやアウトドアブームによる自然回帰の志向、そして環境や食の持続可能性を大切にするサステナブル志向の広がりがあります。
狩猟の主な目的
- 鳥獣害対策:農作物を荒らすシカやイノシシ、住宅地に出没する動物の数を調整
- ジビエ活用:獲物を食肉として利用し、地域の食文化に還元
- 資源循環:皮革・毛皮・骨などを活用し、無駄なく命を使い切る
現代の狩猟は「趣味」や「伝統」にとどまらず、社会や生活を支える役割を担っています。
獣害の現状と、狩猟による調整の必要性


狩猟は「趣味」ではなく、獣害の抑制や生態系維持のために不可欠な活動です。
深刻化する「鳥獣害」被害
農林水産省によると、2024年の農作物被害額は年間約164億円にものぼり、前年比+8億円となっています。被害をもたらす主な動物はシカ、イノシシ、サル、カラスなど。田畑を荒らすだけでなく、森林の植生や都市部の安全にも影響を及ぼしています。
人里に動物が降りてくるのは、人間が山林の管理を手放し、耕作放棄地や放置森林が増えたことも一因です。


狩猟は「命の管理」でもある
狩猟は「動物を殺す行為」として残酷に見られることもありますが、実際には生態系のバランスを整える管理行為という側面が強いものです。極端な保護も、極端な駆除も、自然の均衡を崩す原因になります。狩猟はSDGs目標15「陸の豊かさも守ろう」に直結する活動でもあり、命と向き合う責任を伴う行為なのです。
最新ニュースから見る獣害の“いま”
農作物被害の最新データとして、2025年3月時点で報じられた愛媛県の事例は、獣害の深刻さと対策の限界を如実に示しています。以下の要点をご覧ください。
- 愛媛県内では、昨年度の野生動物(イノシシ・シカ等)による農作物被害額は約3億5000万円にのぼる
- 県は年間3万3000頭の捕獲を目標としていたが、ハンターの高齢化・担い手不足により実績はその約7割の2万4000頭にとどまった
- 推定生息頭数は、イノシシが約5万4600頭、シカが約4万8000頭に達するという厳しい現状
この地域レベルの最新報告は、日本全国に共通する課題を象徴しています。被害対策の目標設定と実際の捕獲数、人材の高齢化ギャップが明らかになったことで、獣害対策における「実行力と担い手の確保」の難しさが浮き彫りになりました。
最新ニュース:クマによる人身被害が過去最悪ペースに


- 2025年度(4〜7月)のクマによる人身被害は55人(死亡3人)
- 過去最悪だった2023年度同時期とほぼ同等のペース
- 2023年度は通年で219人被害、死亡6人。特に秋(9〜10月)に集中
- 2025年8月、北海道・羅臼岳で26歳男性が襲われ死亡
環境省の発表によれば、2025年度は4月から7月のわずか4カ月で55人がクマによる被害を受け、そのうち3人が命を落としています。
さらに2025年8月には、北海道斜里町の羅臼岳で登山中の26歳男性がクマに襲われ、全身多発外傷による失血で死亡する痛ましい事故が発生しました。地元メディアの報道によれば、被害男性は下山途中に突然襲われ、両太ももから大量に出血しながらクマと必死に格闘。同行していた友人が素手で殴って追い払おうとしましたが敵わず、そのまま茂みに引きずり込まれたといいます。
現場は日本百名山の一つとして登山客も多い場所であり、「観光地でも安全とは限らない」現実を突きつけた事件となりました。
こうした事例は、単なる「山奥での事故」ではなく、人間の生活圏と野生動物の境界が曖昧になっている現代的な獣害の象徴です。近年は農作物や森林だけでなく、人命にも深刻な被害が及んでおり、行政・地域社会・ハンターが連携して個体数調整や安全対策を講じる必要性がかつてないほど高まっています。
ジビエのエシカルな価値|狩猟解禁期間で私たちができること


狩猟解禁日から始まる猟期は、ジビエ料理や地域資源の活用にもつながります。
食肉としての「命の重さ」
スーパーに並ぶ肉は、私たちにとって「商品」ですが、ジビエは“元は野生動物だった”という実感を伴う食材です。どんな環境で育ち、どんな人の手で得られたかを知ることで、命をいただく重みを意識できます。
地産地消・フードロス対策にもなるジビエ
地元で仕留められた獲物を地元で消費することで、食材の地産地消が実現します。また、これまで山に放置されがちだった獲物を食肉や加工品として活用することで、命を無駄にしないフードロス対策にもつながります。ジビエは低脂肪・高たんぱくで栄養価が高く、ダイエットや健康志向の食材としても注目されています。
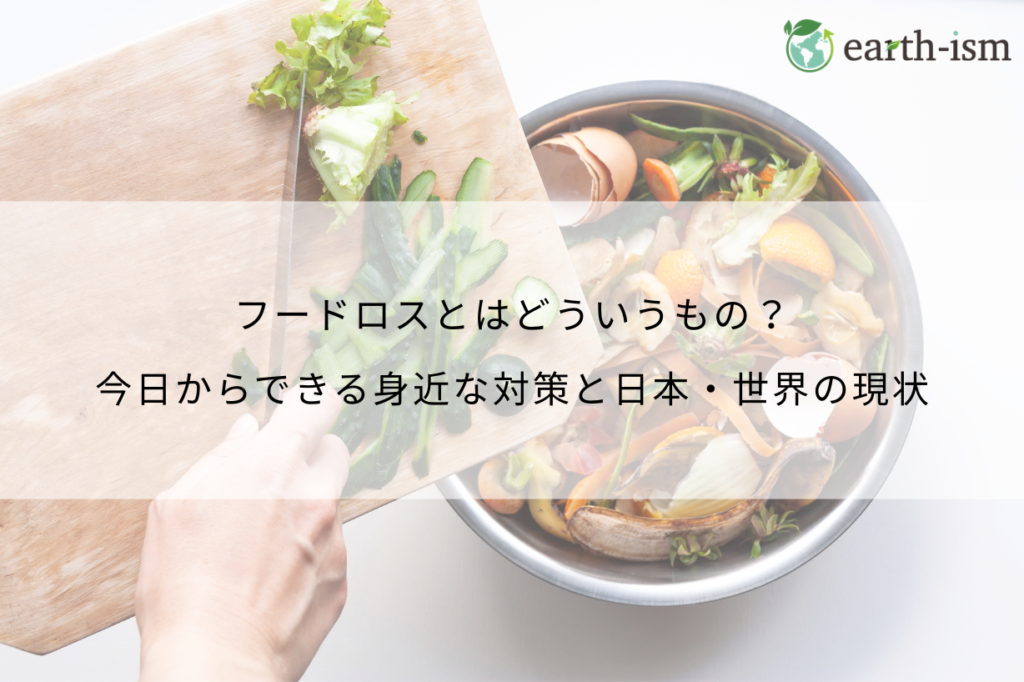
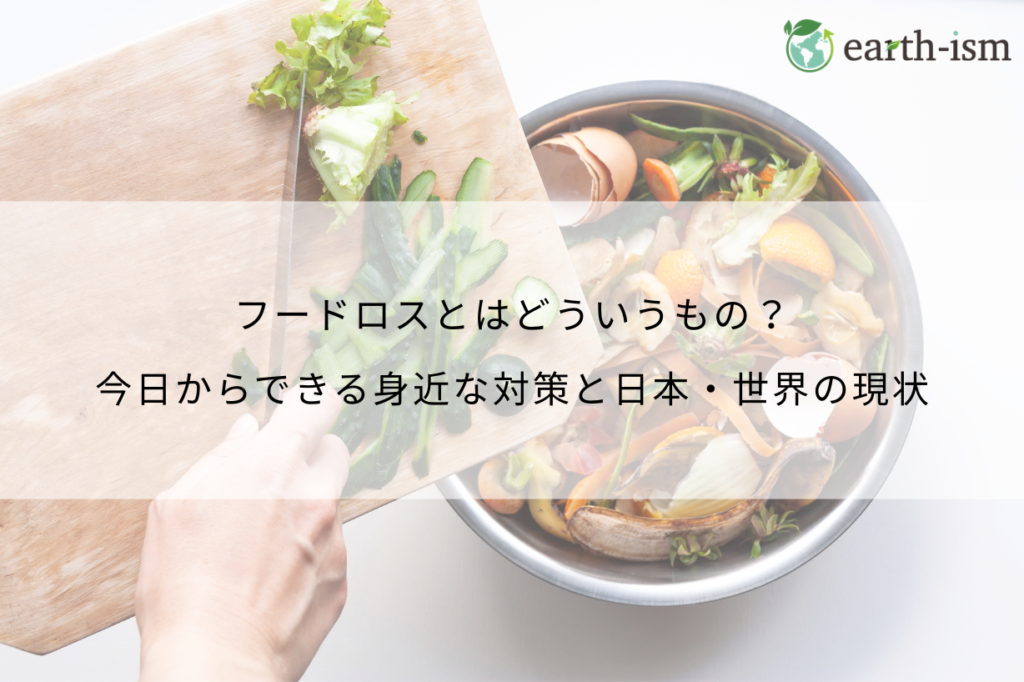
ジビエ消費の拡大事例
長野県「信州山肉ジビエプロジェクト」
信州山肉ジビエプロジェクトは、地元の飲食店と連携し、捕獲したシカやイノシシを地域資源として活用。地域経済にも還元されています。
ファミリーレストランでのジビエフェア
2023年にはサイゼリヤなど大手ファミレスがジビエフェアを開催。ジビエが特別な料理から、身近な外食メニューへと広がりつつあります。
狩猟における課題|ハンターの高齢化と行政連携
狩猟が社会に必要とされる一方で、担い手不足と技術継承の課題が浮き彫りになっています。
60代以上が7割以上。担い手不足の現状
環境省の調査では、狩猟者のうち60代以上が7割以上を占めています。鳥獣害対策を担うハンターの高齢化は深刻で、担い手不足は地域インフラの維持にも直結する問題となっています。狩猟は「趣味」ではなく、地域を守るための社会的役割を果たしているのです。
必要なのは“技術の継承”と“社会的な理解”
狩猟には銃の取り扱いだけでなく、解体や皮処理、衛生管理といった高度なスキルが必要です。これらを次世代に継承する仕組みがなければ、獣害対策も食肉活用も進みません。近年は猟友会だけでなく、行政、企業、教育機関が連携し、狩猟技術やジビエ処理を学ぶ場が広がっています。社会全体で支える仕組みが今後の課題です。
まとめ:狩猟解禁日は暮らしと命をつなぐ節目


狩猟解禁日は、単なる「狩りの開始日」ではありません。
- 農作物を守るための獣害対策
- 野生の命を循環させるジビエ利用
- 過剰繁殖を防ぎ、自然の均衡を保つ生態系管理
これらが重なり合う、私たちの暮らしに直結する節目なのです。
近年は農作物被害額が年間140億円を超える一方で、クマによる人身被害も過去最悪ペースで推移しています。北海道・羅臼岳での痛ましい事故が示すように、獣害は山間部だけの問題ではなく、都市や観光地でも「誰にでも起こり得る現実」となりました。
その一方で、捕獲された命をジビエ料理として食卓にのせ、資源として無駄なく活用する動きも広がっています。長野や高知での地域プロジェクト、ファミリーレストランのジビエフェアなど、獲る・守る・食べるが循環する仕組みが少しずつ形になりつつあります。
ただし、ハンターの高齢化や担い手不足という課題は依然として深刻です。狩猟は趣味ではなく、地域を支える「社会的インフラ」であり、技術継承や行政・教育との連携が不可欠です。
2025年11月15日、狩猟解禁日。そのニュースを耳にしたとき、単なる季節の風物詩ではなく、私たちの暮らしの安全や食の未来とつながる重要な日であることを思い出してください。狩猟は、自然と人間がともに生きるための知恵であり、今も必要とされ続けている営みなのです。