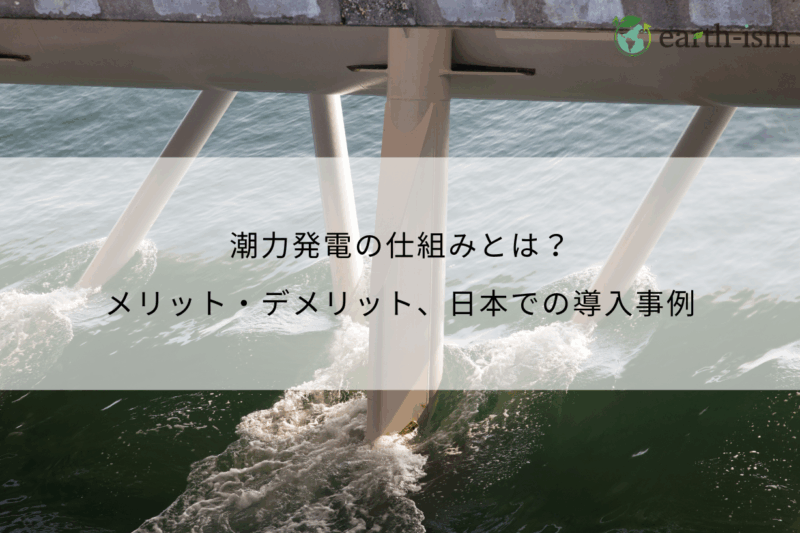【SDGs目標4】日本の教育格差と出来る取り組み|サステナブルな暮らしの第一歩
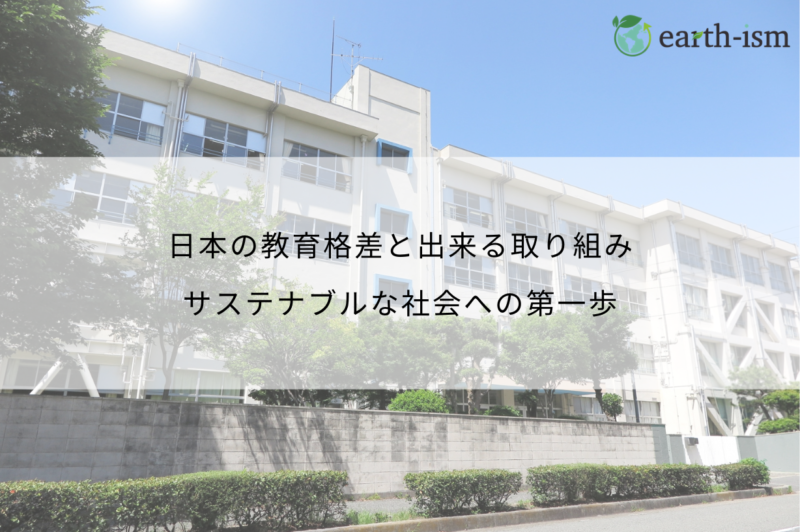
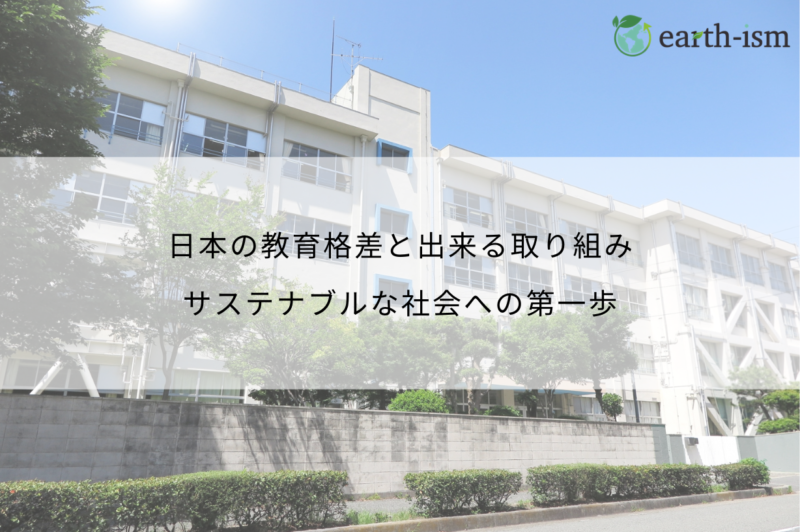
Contents
エシカルな選択は、食やファッションだけでなく「教育」からも始められます。
この記事では、SDGsの教育分野、特に目標4「質の高い教育をみんなに」へ焦点を当て、日本の教育格差と、それを解消する取り組みについて紹介します。あなたの日常の小さな気づきが、未来の誰かのチャンスになるかもしれません。
一見すると「日本には教育格差なんてない」と感じるかもしれません。しかし現実には、7人に1人の子どもが貧困状態にあるとされ、教育の機会に大きな差が生まれています。この格差は、やがて就労や健康、そして世代を超えた貧困の連鎖にもつながっています。ぜひ、この記事で一読してみてください。


SDGsが掲げる「質の高い教育をみんなに」
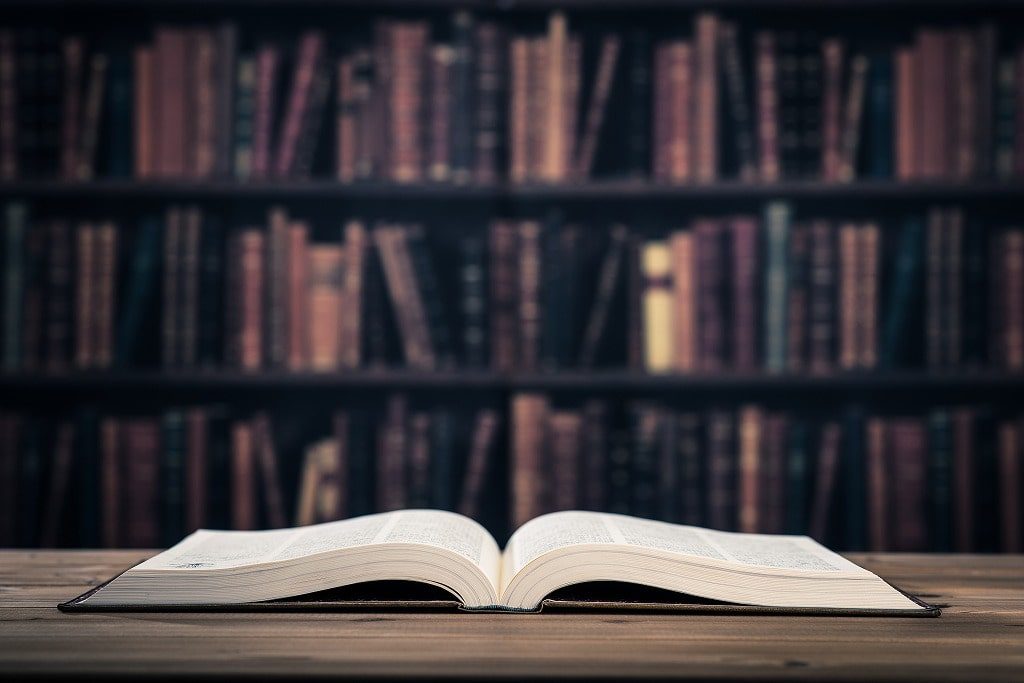
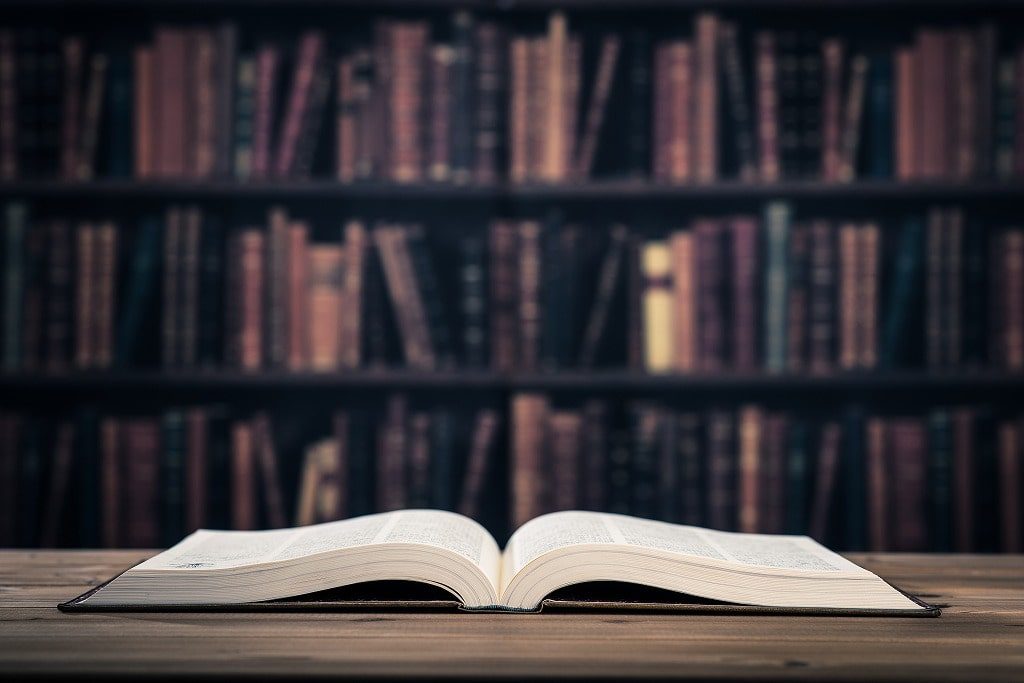
国連が掲げる持続可能な開発目標(SDGs)の中で、目標4は「すべての人に包摂的かつ公正で質の高い教育を提供すること」です。これは、世界中すべての人が、経済状況や性別、居住地に関係なく、学びの機会を平等に持てるようにすることを目指しています。
SDGsにおける教育の役割
目標4「質の高い教育をみんなに」は、他の目標を支える土台といえるほど重要なものです。教育の機会を平等にすることは、貧困削減、雇用創出、健康増進など、社会全体の持続的な成長にもつながります。
教育を取り巻く世界と日本の課題
世界では今も多くの子どもたちが学校に通えず、日本国内でも「見えにくい教育格差」が広がっています。経済状況や家庭環境によって、子どもたちが持つべき「学ぶ権利」が左右される現実は、見過ごせない問題です。
教育は、個人の可能性を引き出すだけでなく、社会全体の安定と発展にも直結します。


日本における教育格差の実態


日本における教育格差にはどのようなものがあるか、以下で見ていきましょう。
所得と学力・進学率の関連
文部科学省や教育調査によると、家庭の年収が高いほど、子どもの学力や進学率が高くなる傾向が見られます。たとえば、大学進学率は年収400万円未満の家庭では約30%なのに対し、800万円以上の家庭では約70%に達します。
学校外教育費と格差の拡大
塾や習い事といった学校外教育にかけられる費用の差は、学力格差を生み出す要因のひとつです。中には、学習環境を整えることすら難しい家庭も存在し、教育機会の不均衡がより広がってしまっています。
貧困の連鎖と教育
このような教育格差は、低学歴→非正規雇用→低収入→子どもの貧困といった「貧困の連鎖」に直結します。教育の機会を確保することは、貧困の連鎖を断ち切る鍵なのです。
教育格差をなくすための日本の支援制度


教育格差の是正に向けて、日本ではさまざまな制度や取り組みが存在します。ここでは経済、就労、生活の3つの側面から紹介します。
経済支援:進学をあきらめないために
経済的な理由で進学をあきらめることがないよう、さまざまな制度が用意されています。たとえば「母子父子寡婦福祉資金貸付制度」。20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女子または男子、寡婦等に貸し付けができる制度です。
資金の種類は修学金、授業開始資金など様々な種類があります。経済、就労、生活のために必要となる費用を保証人ありの場合、無利子で貸し付けが可能になります。
就労支援:家庭の安定が子どもの未来を守る
安定した生活基盤がなければ、子どもも安心して学べません。シングルマザーやファザー向けに、職業訓練や就労支援プログラムも実施されています。教育支援とあわせて、親の就労環境のサポートも必要不可欠です。
生活支援:学べる環境づくりのベース
学びの場は、家庭や学校だけではありません。各地域では、放課後子供教室や無料学習支援教室などの取り組みも広がっています。地域のコミュニティが子どもたちの居場所となり、学びを支える大切な役割を果たしています。
文部科学省が取り組んでいる支援で「放課後子供教室」があります。放課後に子供たちの居場所を作り、校庭や空き教室を解放してスポーツや文化活動ができるようにする取り組みです。
自治体にもよりますが、放課後にひとり親の子供を対象に高校進学のための勉強会を開催するところもあります。そこでは、大学生がボランティアで先生となり勉強を教えています。
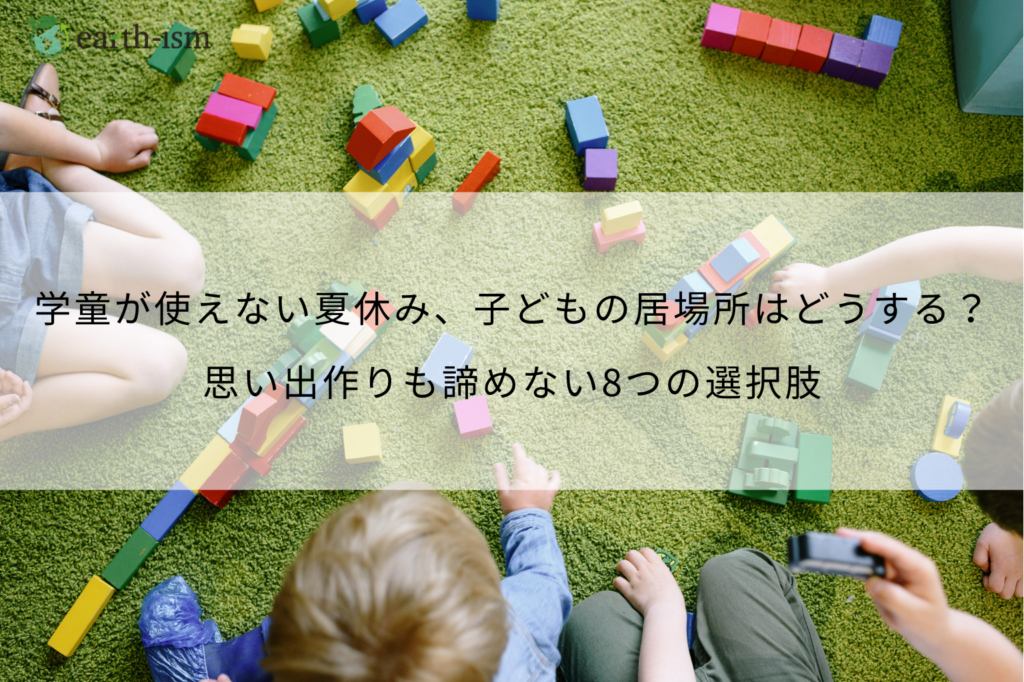
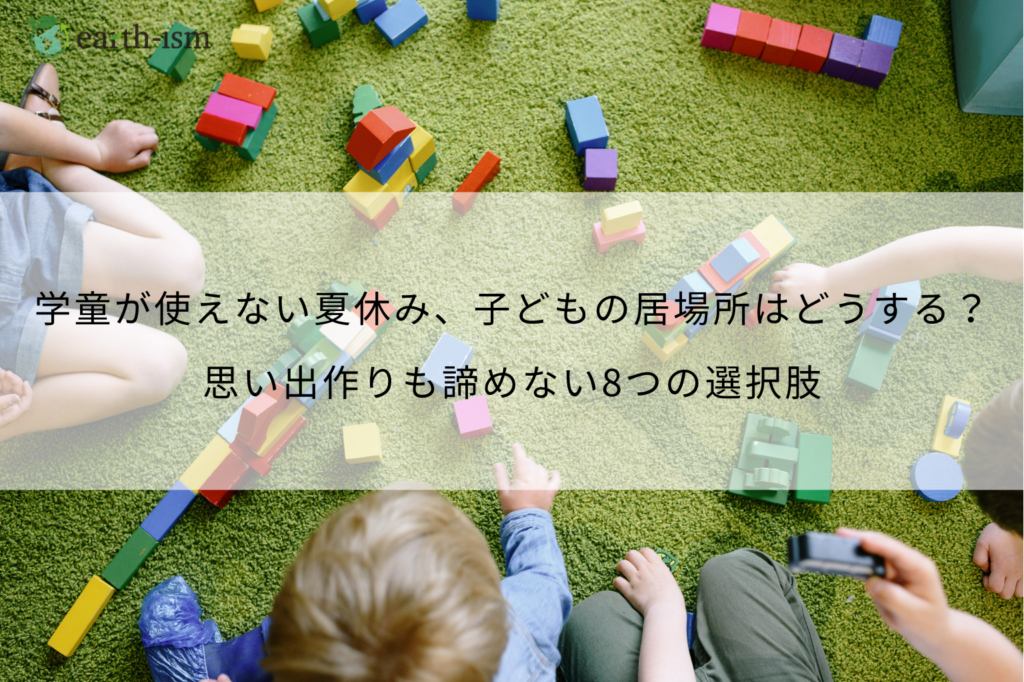
令和の教育的貧困|目に見えない格差が生む現代の危機


かつて「教育格差」といえば、進学率や学力テストに表れるような“数字”で可視化されてきました。しかし令和の今、その実態はより複雑で、表に出にくい形で子どもたちの生活に影を落としています。
家庭に居場所がない、学習習慣が身につかない、社会との接点が極端に乏しいなどの課題が、子どもたちの未来を狭めています。
トー横キッズと「見捨てられた感覚」
東京・歌舞伎町周辺で話題になった「トー横キッズ」は、教育的貧困の象徴とも言えます。家庭や学校に居場所を持てず、夜の街で仲間を求める子どもたちは、金銭的困窮だけでなく、心の貧困=関係性の欠如に直面しています。
「誰も自分のことを見てくれない」「どうせ将来なんて期待できない」――そうした感覚が、社会からの孤立をさらに深め、暴力や搾取のリスクにさらされる結果につながっています。
闇バイトに走る10代|学ぶ以前に生きることが困難な現実
さらに深刻なのが、闇バイトや詐欺の“実行役”としてリクルートされる若者の増加です。中高生がSNSを通じて「すぐにお金が欲しい」「学費を稼ぎたい」という理由で犯罪に巻き込まれるケースも後を絶ちません。
背景には、家庭の経済的な不安定さと、教育・支援制度の届かなさがあります。「親も忙しくて話せない」「学校では相談しづらい」。そんな孤立の中で、子どもたちは学ぶどころか、生き抜くために危険な選択をせざるを得なくなっています。
私たちにできること|教育格差と向き合うアクション


教育格差の解消は、制度だけでなく私たち一人ひとりの意識と行動にもかかっています。
アクション1:寄付やクラウドファンディングに参加する
教育支援を行うNPOや財団への寄付、プロジェクト型のクラウドファンディングを通じて、困難な状況にある子どもたちを直接支援することができます。
アクション2:学習支援ボランティアとして参加する
地域やオンラインでの学習支援に参加することも、子どもたちにとって大きな力になります。時間が限られていても、週1回1時間の関わりが子どもにとっては貴重な学びの機会です。
アクション3:情報を発信し、共感の輪を広げる
教育格差についての情報をSNSなどで発信することで、社会的な関心を高めることができます。誰かの共感が、次のアクションにつながるきっかけになります。
アクション4:身近な教育環境を見直す
自分の子どもや周囲の子どもたちがどのような環境で学んでいるのかに目を向けることも大切です。意外と気づいていない課題が、すぐそばにあるかもしれません。
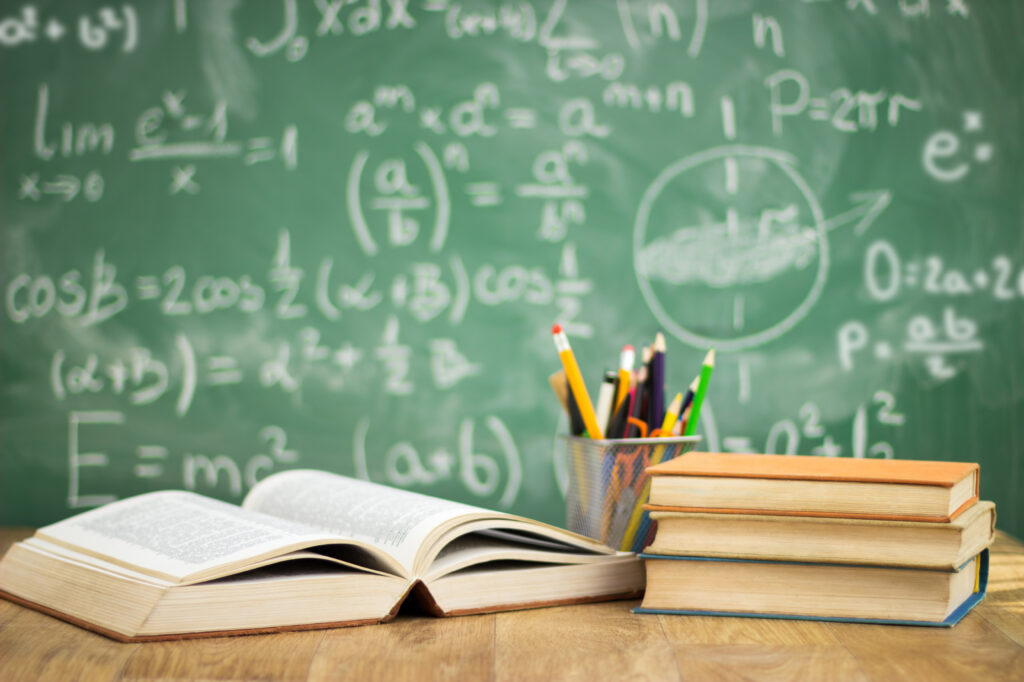
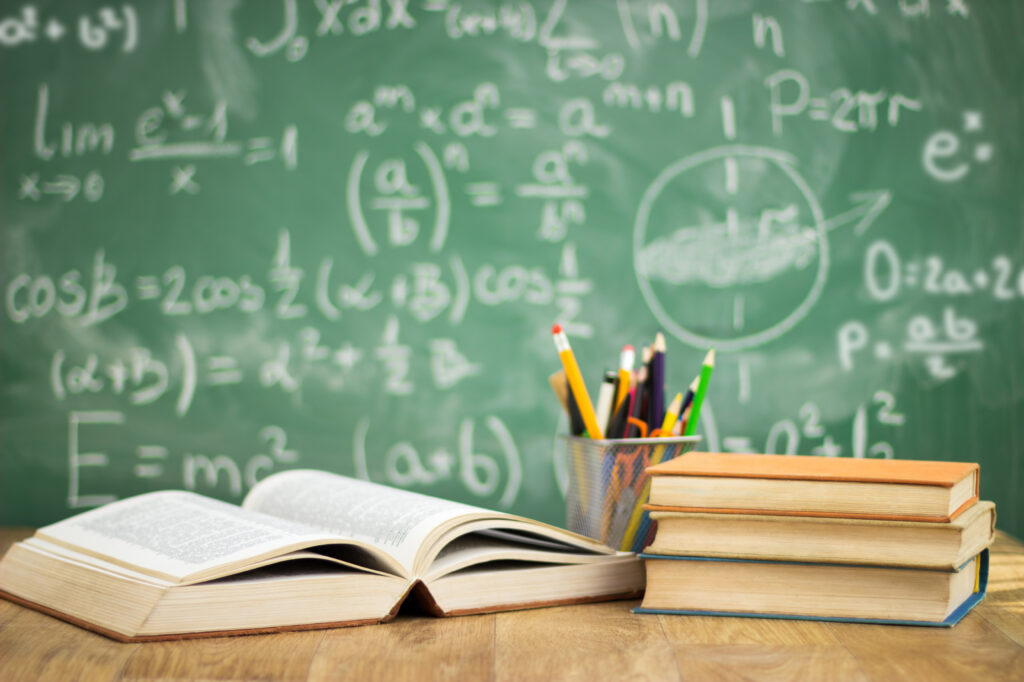


まとめ|「教育格差をなくす選択」は、誰にでもできる


教育は、すべての子どもに与えられるべき「未来の選択肢」です。格差の存在を知り、それに対して「何ができるか」を考えること自体が素晴らしい行動といえます。
あなたの小さな行動が、子どもたちの未来を支える力になります。サステナブルな暮らしの第一歩として、「教育」という切り口から社会を見直すことが、持続可能な社会づくりの出発点です。