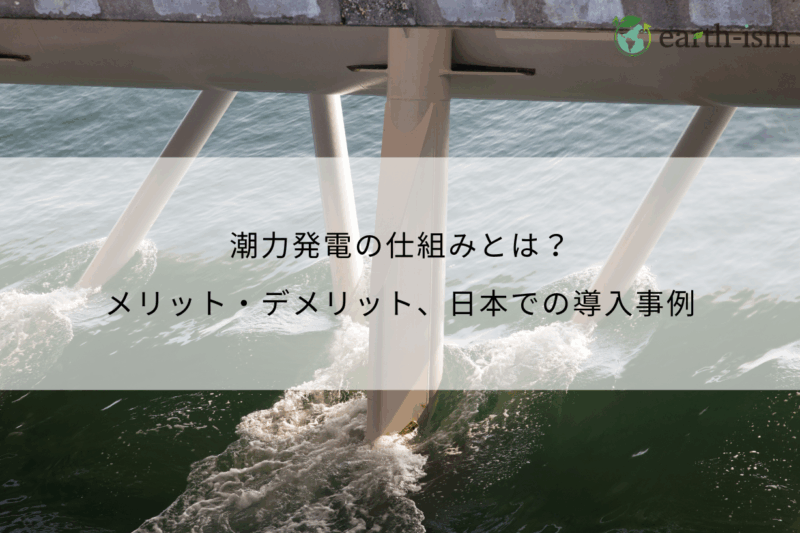フェアトレードが“当たり前”な国イギリス|その理由と日本が学べること
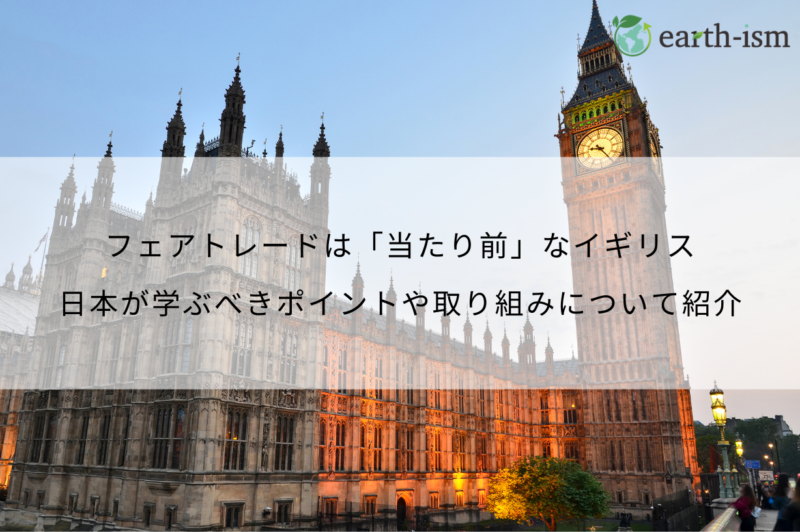
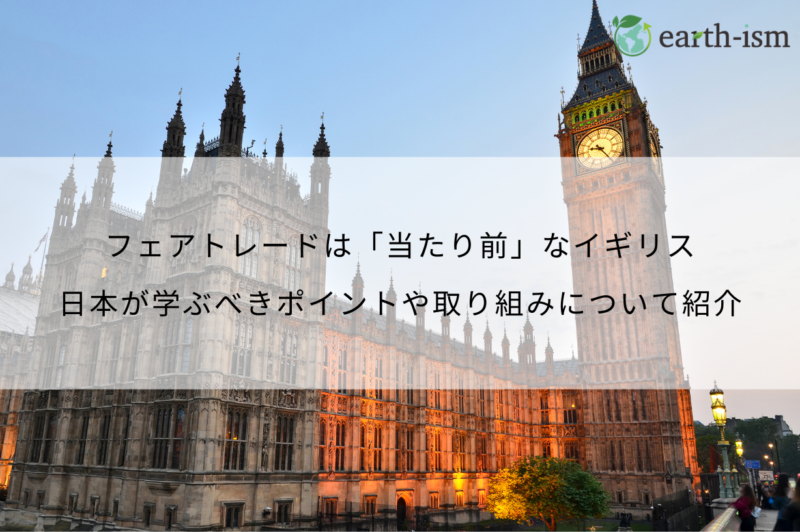
Contents
途上国と先進国における公正・公平な貿易を目的としたフェアトレード。SDGsの広がりとともに、「選ぶことは、支えること」という意識が社会に根づきつつあります。
その中で注目されているのが、イギリスのフェアトレード事情。スーパーやカフェ、学校でも、フェアトレード商品が「特別な選択」ではなく「当たり前の選択」になっている国です。
この記事では、イギリスがなぜフェアトレード先進国と呼ばれるのかを探りながら、日本にとってのヒントを見つけていきます。


イギリスではフェアトレードが“日常”になっている


イギリスはフェアトレード認証制度をいち早く導入し、日常のあらゆるシーンに取り入れてきました。
たとえばスーパー。イギリスの大手スーパー「Co-op」は、自社のチョコレート、紅茶、バナナなどでフェアトレード認証品の取扱いを強化。フェアトレードバナナだけで、年間1億本以上販売する規模です。
カフェチェーン「カフェ・ネロ」「プレタ・マンジェ」「コスタ」などでも、フェアトレードのコーヒーがスタンダード。日本では「意識が高い人の選択肢」になりがちですが、イギリスでは「日常でよく飲むコーヒー」が自然とフェアトレードになっています。
イギリスがここまでフェアトレードが浸透している理由


イギリスがここまで浸透している背景には、「フェアトレード・スクール」や「フェアトレード・ユニバーシティ」という教育制度の存在や、行政の存在があります。
フェアトレード・スクール
小学校から大学まで、フェアトレードの意義を学び、校内でフェアトレード商品を導入したり、学園祭で啓発イベントを行ったりする取り組みが盛んです。生徒たちは自然と「誰がつくったのか」「どんな背景があるのか」を考える習慣が身につきます。
このような取り組みが広がった結果、イギリスではフェアトレードの認知度が高く、子どもでも「これはフェアトレードかな?」と意識するようになっています。
フェアトレード・タウン
さらに、イギリスでは自治体単位でフェアトレードを推進する「フェアトレード・タウン運動」が進んでいます。
2001年、最初のフェアトレード・タウンとしてランカスター州ガースタングという小さな町が認定されました。町のカフェや学校、企業などが連携してフェアトレード商品を優先的に扱う体制を整え、市民もそれを支持しました。
この動きはイギリス全土に広がり、現在では600以上の自治体がフェアトレード・タウンとして認定されています。地方から国全体へとムーブメントが広がった好例といえます。


日本はなぜフェアトレードが根づかない?
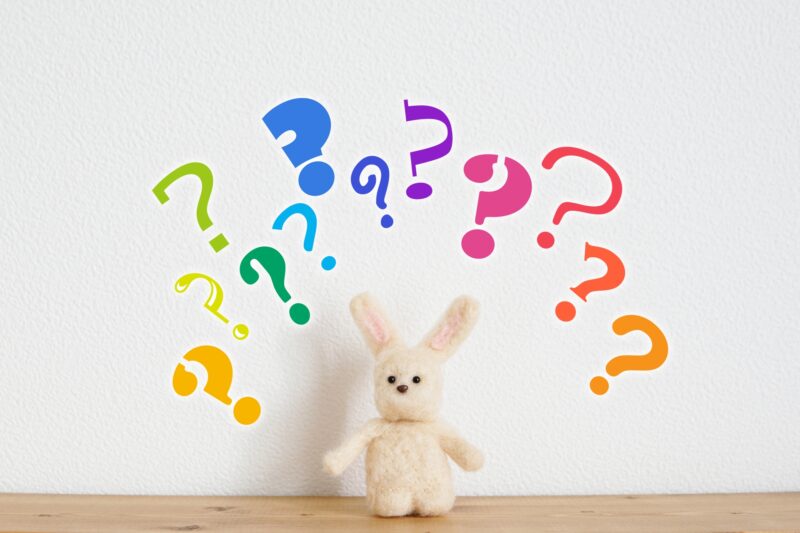
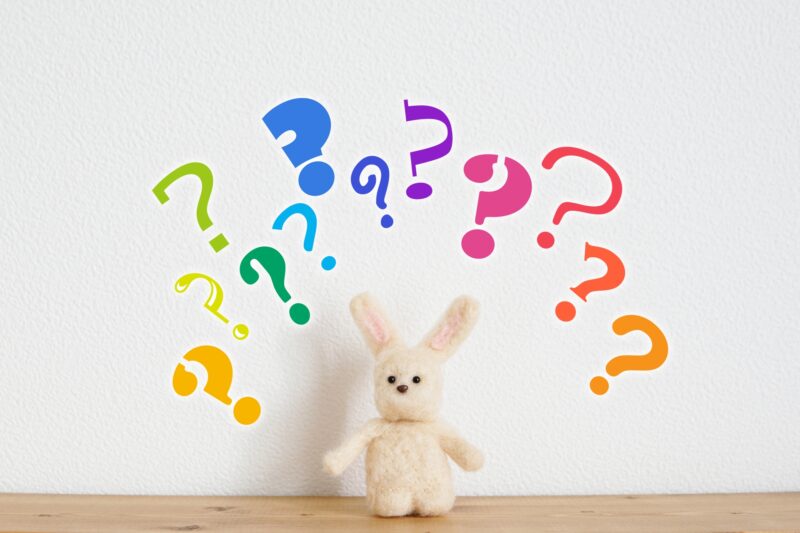
一方で、日本ではどうでしょうか。
フェアトレードの認知度は依然として低く、特に一般スーパーでの選択肢は限られています。チョコレートやコーヒーでいくつか認証商品はあるものの、「価格が高い」「手に入りにくい」「信頼性が分からない」といった声も根強く、まだ“当たり前”には遠いのが現状です。
とはいえ、日本ならではの可能性もあります。それが「応援消費」という文化です。


応援消費から始める“わたし基点”のエシカル


日本では「ちょっと高くても、誰かのためになるなら買いたい」という消費者心理が根づいています。震災復興や地域支援を目的とした“応援消費”が広がったのも記憶に新しいところ。
フェアトレードも、ただの「高い商品」ではなく、「誰かの暮らしを応援する選択肢」として提示すれば共感を得やすいはず。実際、フェアトレードチョコレートのPeople Treeなどでは、購買者の多くが女性で、応援の気持ちから選んでいるというデータもあります。
日本で参考にできること|イギリスに学ぶフェアトレードの取り組み


では、日本でフェアトレードを広げるには、どんな取り組みが必要なのでしょうか。
フェアトレードスクールの推進
日本のフェアトレードスクールは、静岡文化芸術大学がフェアトレード大学として誕生したのみ。高校以下の学校を対象とした「フェアトレードスクール・プログラム」をフェアトレードフォーラムジャパンは推進するとしています。
現状学園祭でのフェアトレード商品の販売イベントや出張授業などの取り組みは存在しますが、今後義務教育レベルでSDGsなどを交えて継続的にフェアトレードを学ぶ体制作りが求められています。
企業のサステナビリティ戦略
企業にもSDGs達成のため具体的な取り組みが求められています。就職活動中の学生や投資家たちも、企業のサステナビリティへの向き合い方を見て判断をする時代だからです。
販売する商品自体をフェアトレード商品に切り替えること、来客用に出すコーヒーを切り替える、原材料をフェアトレードへと転換させることなどの取り組みがフェアトレード普及と企業のイメージアップにつながり、結果的に双方のメリットとなるのです。


フェアトレードタウンの推進
フェアトレードタウン発祥の街、イギリスのガースタンでは、街の商品をなるべくフェアトレード製品にしようという運動の末、70%まで普及させた歴史があります。
現在国内では6都市がフェアトレードタウンとして認定されていますが、さらに多くの街がフェアトレードタウン運動に加わることでフェアトレード推進は前進することでしょう。日本におけるフェアトレード普及には明るい兆しも見えてきています。行政が「市内の企業や学校に認証商品を使うよう促す」などの支援をすれば、市民も動きやすくなります。
まとめ│イギリスに学ぶフェアトレードの取り組み


イギリスが見せてくれたのは、「日常にフェアトレードが根づく社会」の姿です。それは特別な人だけの運動ではなく、スーパーやカフェ、学校や町全体が連動しているからこそ実現できたもの。
日本でも、少しずつその土壌はできています。「高いから」「難しいから」と避けずに、小さな行動から始めてみませんか?
自分のために、そして誰かのために。私たちの選択が、少しずつ世界を変えていきます。