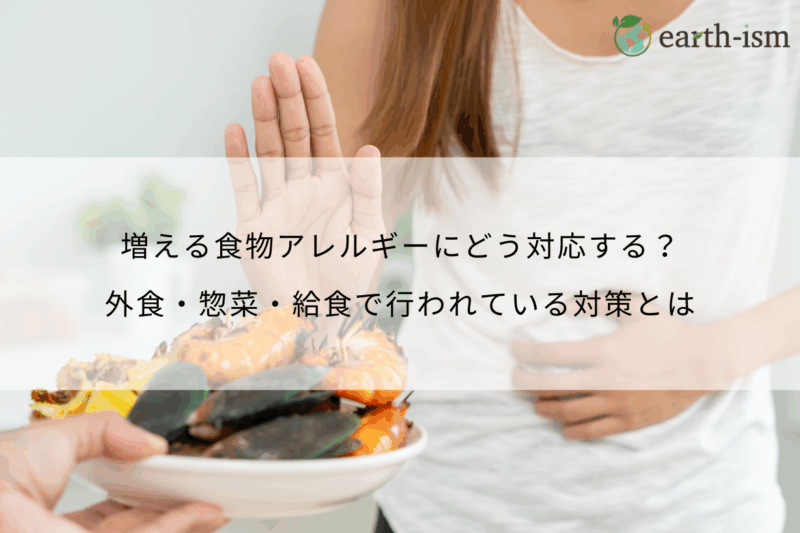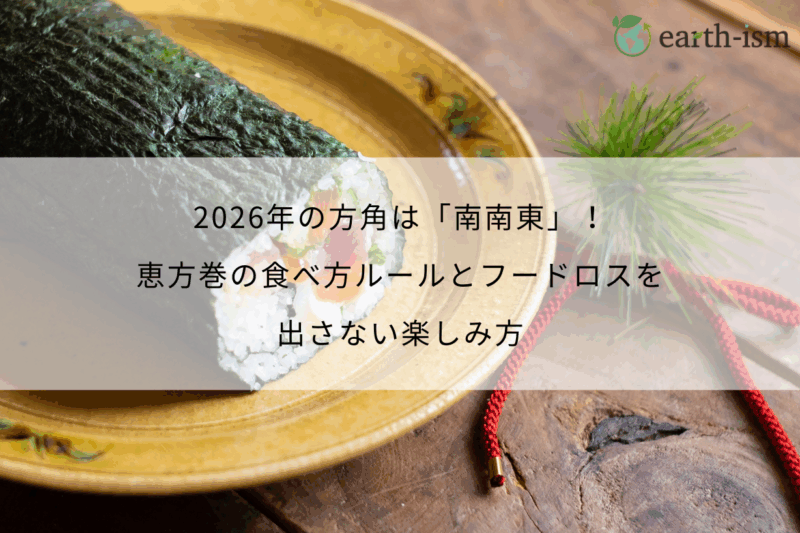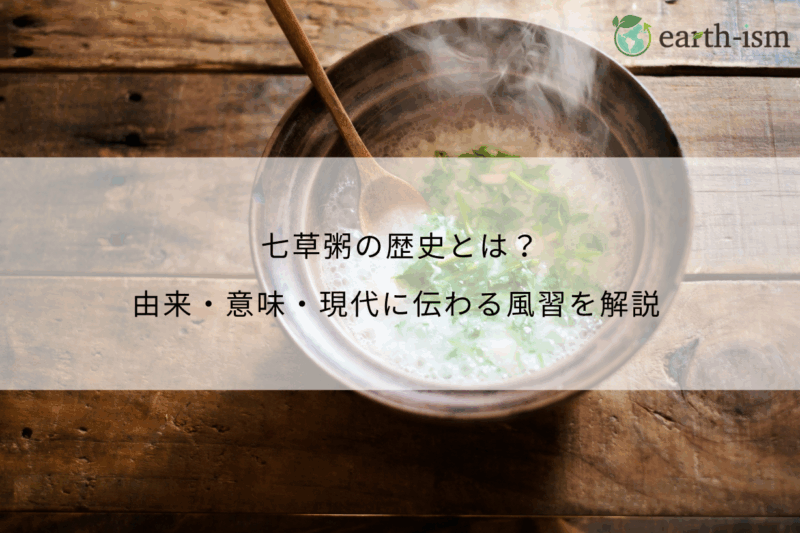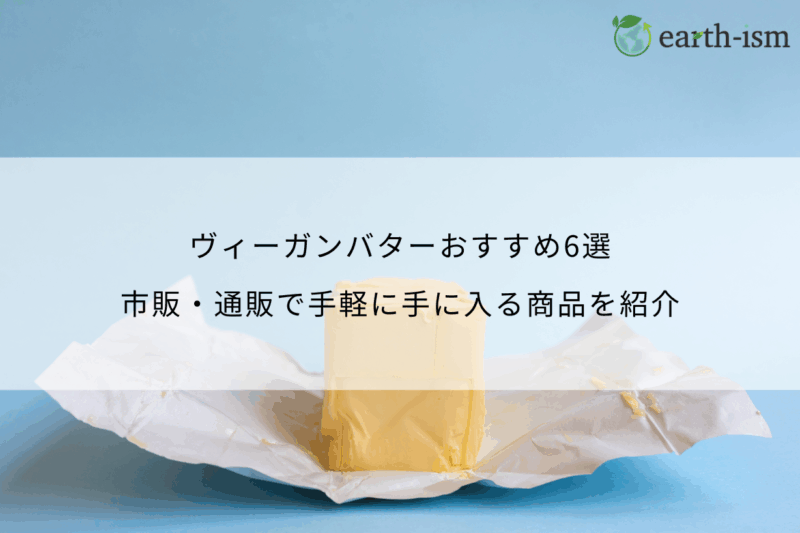クラフトウイスキーが人気である理由とは?国内・海外のサステナブルな蒸留所も紹介
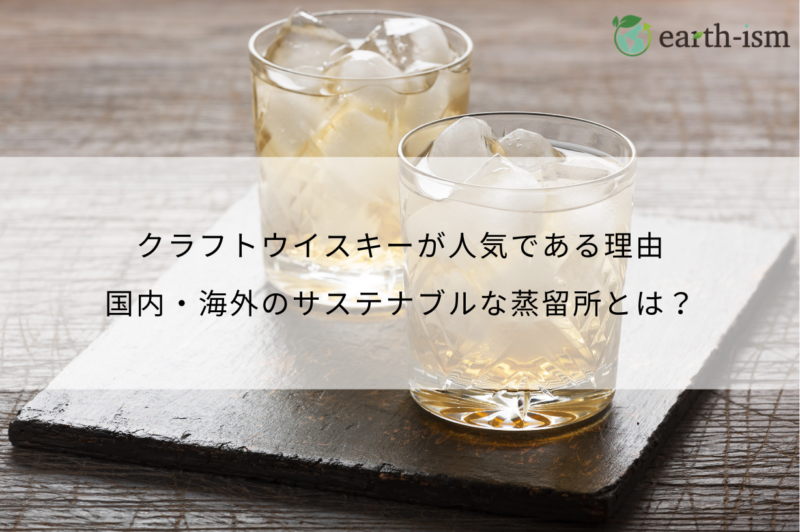
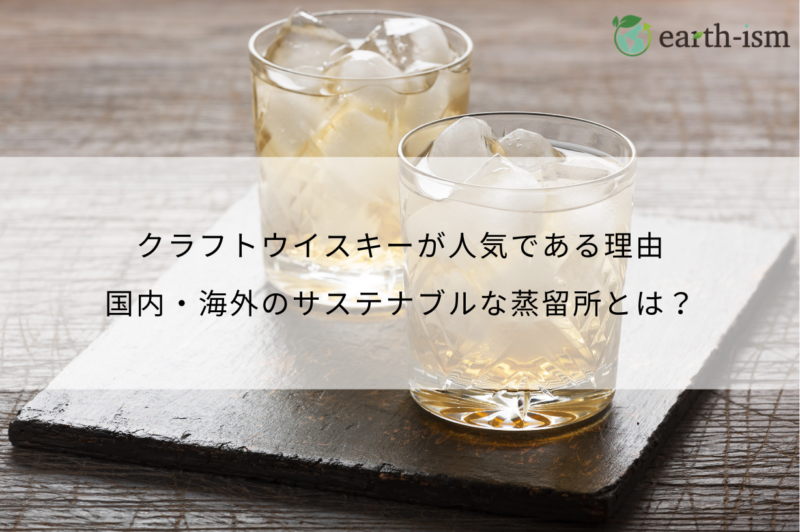
Contents
クラフト飲料といえばビールやコーラがよく知られていますが、近年はクラフトウイスキーの人気も高まっています。
クラフトウイスキーの魅力は、造り手のこだわりが反映された個性豊かな味わいにあります。
日本では小規模な蒸留所が相次いで誕生しており、その品質は世界的なコンテストでも高く評価されています。さらに、そうした蒸留所のなかには環境への配慮や地域との共生に取り組むところが増えており、ウイスキーの味わいだけでなく、造り手の姿勢や価値観にも関心が集まっています。
この記事では、クラフトウイスキーの魅力や人気の理由に加え、環境に優しい取り組みを行う国内外の蒸留所を紹介します。持続可能なものづくりに関心がある方も、ウイスキーが好きな方もチェックしてみてくださいね。
クラフトウイスキーとは


クラフトウイスキーとは小規模な蒸留所で生産されるウイスキーのことを指します。
大手メーカーなどで生産されるウイスキーは生産規模が大きいため安定供給・安定品質のための原料や製造方法が選択されますが、小規模蒸留所では原材料の選定や仕込み、蒸留、熟成までの過程で、造り手の個性やこだわりが反映されるのが特徴です。
そのため独自の風味や香りが生まれやすく、蒸留所ごとに異なる個性豊かな味わいが楽しめます。
| クラフトウイスキー | 一般のウイスキー | |
| 生産規模 | 小規模 | 大規模 |
| 製造方法 | 細部にこだわる | 自動化、効率重視 |
| 原料 | 地元産など厳選して調達 | 広範囲から大量に調達 |
| 味わい | 作り手の個性が出る | 一定の品質を保持 |
| 価格 | 希少性があるため高め | 手頃な価格 |
世界で注目されている日本のクラフトウイスキー


そもそもクラフトウイスキーが注目されるようになったのは、1990年代のアメリカで始まったクラフトビールブームの影響が大きいとされています。クラフトビールの人気に後押しされるかたちで小規模蒸留所の設立が相次ぎました。
日本では2000年代から世界的なコンテストで国産ウイスキーが高く評価されたことを機に、海外から注目されるようになりました。国税庁による「最近の日本産酒類の輸出動向について」の調査によると、2024年のウイスキー輸出量は436億円と、日本酒を上回って酒類の輸出で第1位を記録しています。
こうした動きからも日本のウイスキーが国際的に高い評価を受けていることがうかがえます。海外からの評価が高まったことで現在ではスコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダと並び、日本も世界5大ウイスキーの産地と称されています。
日本のクラフトウイスキーの魅力


国内でも2010年代に起こったハイボールの流行なども追い風となりウイスキーの需要が高まり、2010年代中頃から個性的な小規模蒸留所が各地に次々と誕生しています。
小規模蒸留所は、地元産の原材料を使用したり、伝統技術と最新設備を融合させたりと、独自のスタイルを追求しています。クラフトでありながらも世界的なコンテストでの受賞歴もあり、国際的にも日本のクラフトウイスキーのブランド価値が高まっています。
サステナブルな取り組みをする国内の蒸留所


ウイスキー文化研究所が発行する『日本蒸留所年鑑 JAPANESE WHISKY YEAR BOOK 2025』によれば、国内には124の蒸留所があります。
さまざまな蒸留所が各地に点在するなか、ここではサステナブルな取り組みに焦点を当てていくつかの蒸留所を紹介します。味わいだけでなく、造り手の姿勢や価値観も銘柄を選ぶ際の大切な判断材料になるはずです。
三郎丸蒸留所(富山県砺波市)
富山県砺波市にある三郎丸蒸留所は1952年に創業した老舗の蒸留所です。鋳造技術を活かした独自の蒸留器を使用し燃料の消費を抑えるとともに、地下水を活用する井水式クーラーや屋根散水システムを導入し電気使用量の削減に取り組んでいます。
また富山県産ミズナラを樽に使用することで森林資源の循環利用と地域林業も支援しています。ミズナラは日本特有の木材で加工が難しく樽材への使用可能面積が少ないという課題があるものの、その希少性と独特の風味から世界中のウイスキー愛好家から高い評価を受けている樽材です。
この樽は三郎丸蒸留所のウイスキーの特長であるスモーキーな香りに深みをもたらしています。
三郎丸蒸留所の銘柄は国内外のウイスキーコンテストで数々の賞を受賞しており、最近ではイギリスの国際的なコンテストであるワールド・ウイスキー・アワード(WWA)2025のシングルモルト部門で「三郎丸Ⅳ カスクストレングス」などが部門最高賞を受賞しました。


井川蒸留所(静岡県静岡市)
静岡市の山間部、標高1,200mに位置する井川蒸留所では「自然を守り、自然を活かす」という理念のもと、約24,430haという広大な社有林の自然を活かしたウイスキーづくりが進められています。
湧水を仕込み水に使うことで水の運搬に伴うエネルギーやCO₂排出を抑えるほか、自生するミズナラを樽材に用いて森林資源の循環利用にも取り組んでいます。
さらに2024年にはウイスキーの売上の一部を南アルプスの自然環境調査に活用する「Sharing for the Alps」というプログラムを立ち上げました。これは野生動物による植生被害や森林病害、外来植物の拡大といった環境問題を抱える南アルプスの保全と価値向上を目的とした取り組みです。
井川蒸留所のシングルモルト「デッサン」は、南アルプスの自然環境と生態系からインスピレーションを受けて展開されているシリーズです。
2024年に第1弾「Flora(フローラ)」が発売され、2025年には第2弾「Fauna(ファウナ)」が登場しました。「Flora」はスモーキーさのない柔らかく華やかな味わいを、「Fauna」はスモーキーで力強い味わいを表現しています。2020年設立の新しい蒸留所ですが「Tokyo Whisky & Spirits Competition 2023」での受賞歴があり、今後の活躍が注目されている蒸留所のひとつです。


瀬戸内蒸留所(広島県呉市)
広島県呉市にある瀬戸内蒸留所はジンとウイスキーづくりに取り組む蒸留所です。100年の歴史を持つ日本酒「千福」の蔵元・三宅本店が手がけ、2022年に開所しました。
灰ケ峰の伏流水を仕込み水に使用しており、これは遠方からの水輸送に比べて輸送エネルギーやCO₂排出を抑えることが可能です。さらにひと樽ごとの個性を尊重する少量生産に取り組んでいます。必要な分だけを丁寧に生産することで、過剰な在庫や廃棄リスクを最小限に抑えています。
瀬戸内蒸留所が生産しているウイスキーは「ニューボーン瀬戸内」。原料や製造方法にこだわり、瀬戸内の自然を樽の味わいの変化に活かすために外気温と同じ場所で貯蔵しているのが特徴です。
また「クラフトジン瀬戸内 甘夏」では傷などがあることで販売できない瀬戸内産の甘夏を使用し、フードロスの削減に貢献しています。
サステナブル観点で注目したい海外の蒸留所


サステナブルな取り組みは日本にとどまらず世界の蒸留所でも進んでいます。ここでは環境配慮を重視した海外の蒸留所を紹介します。
ノックニーアン蒸留所(スコットランド)
2017年に設立されたノックニーアン蒸留所(Nc’nean Distillery)はスコットランド西部にある蒸留所で、持続可能なウイスキー生産の先駆者として知られています。
再生可能エネルギーによる蒸留で温室効果ガスの排出を実質ゼロに抑え、容器には100%リサイクルガラス製のボトルを採用するなど、環境への配慮が徹底されています。
ウイスキーは100%スコットランド産のオーガニック大麦と独自酵母を用い、長時間の仕込みと発酵によって生まれるフルーティな味わいが特徴です。
テーレンペリ蒸溜所(フィンランド)
テーレンペリ蒸留所(Teerenpeli Distillery)はフィンランド南部に位置するラハティ市で2002年に設立されました。ラハティ市は積極的に環境対策に取り組んでいる都市で、2021年には欧州グリーン首都賞を受賞しています。
この環境先進都市にあるテーレンペリ蒸留所でもサステナブルな取り組みが行われており、特に注目したいのが蒸留に使うエネルギーの多くを自社の木質ペレット工場から供給していることです。木材ペレットは木くずや間伐材を使用した燃料で、化石燃料のようにCO₂を大量に排出しないため再生可能な資源として注目されています。
また原料に使用する大麦の多くはラハティ市周辺の農場から調達されており、地域の農業資源を活用しています。
テーレンペリ蒸留所の代表的な銘柄には、バーボン樽熟成の「KULO」やピート香が特徴の「SAVU」、シェリー樽熟成の「KASKI」があります。特に「KULO」は豊かな香りとまろやかな味わいでおすすめです。
まとめ


造り手のこだわりや地域性が楽しめる日本のクラフトウイスキーは、世界中のウイスキー愛好家から注目されています。近年では各地の蒸留所で環境負荷の低減や地域資源の活用といったサステナブルな取り組みも進んでおり、味わいだけでなく背景にある理念やCSR活動にも関心が寄せられています。
今回紹介した蒸留所のように持続可能なものづくりを追求する蒸留所は今後もますます注目されることでしょう。この記事が、ウイスキーをはじめとするお酒を選ぶ際の新たな視点となれば幸いです。