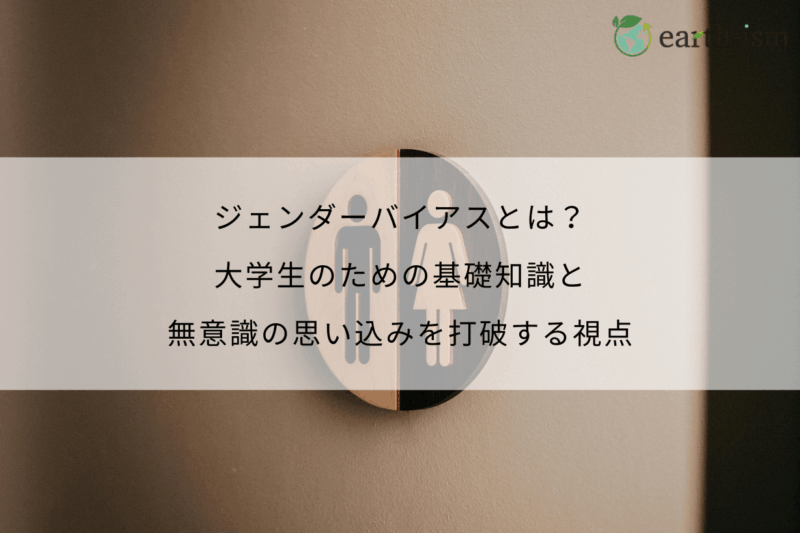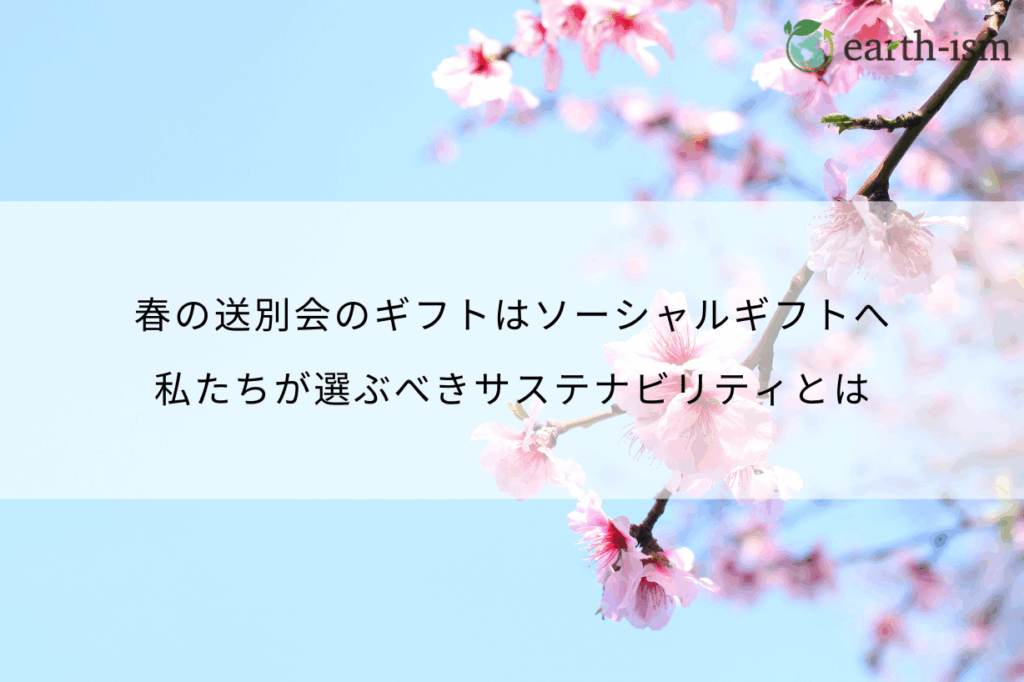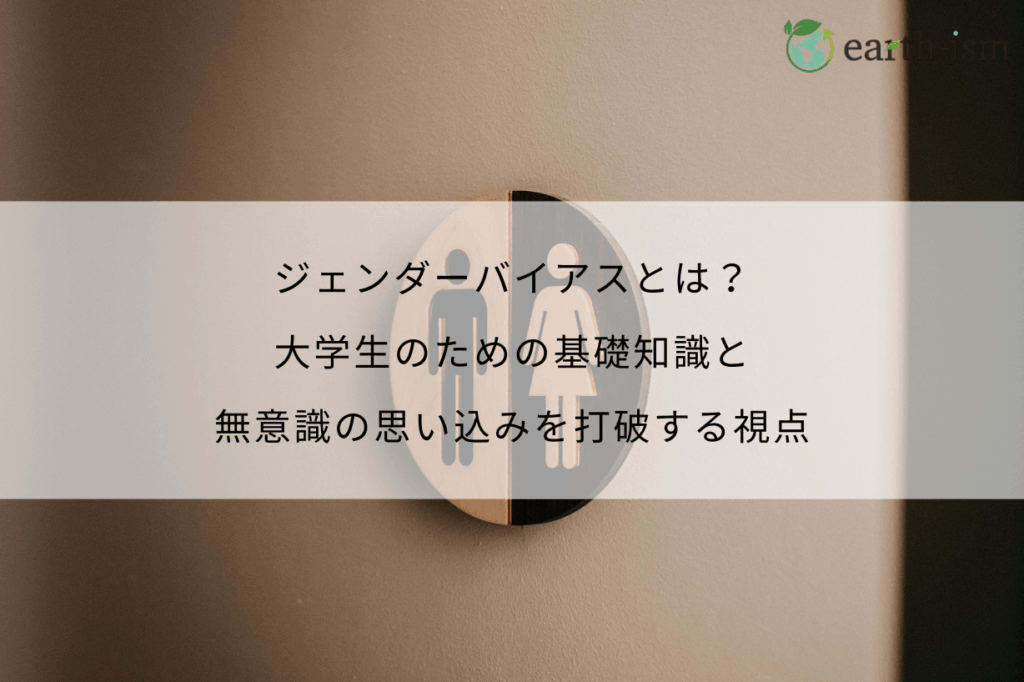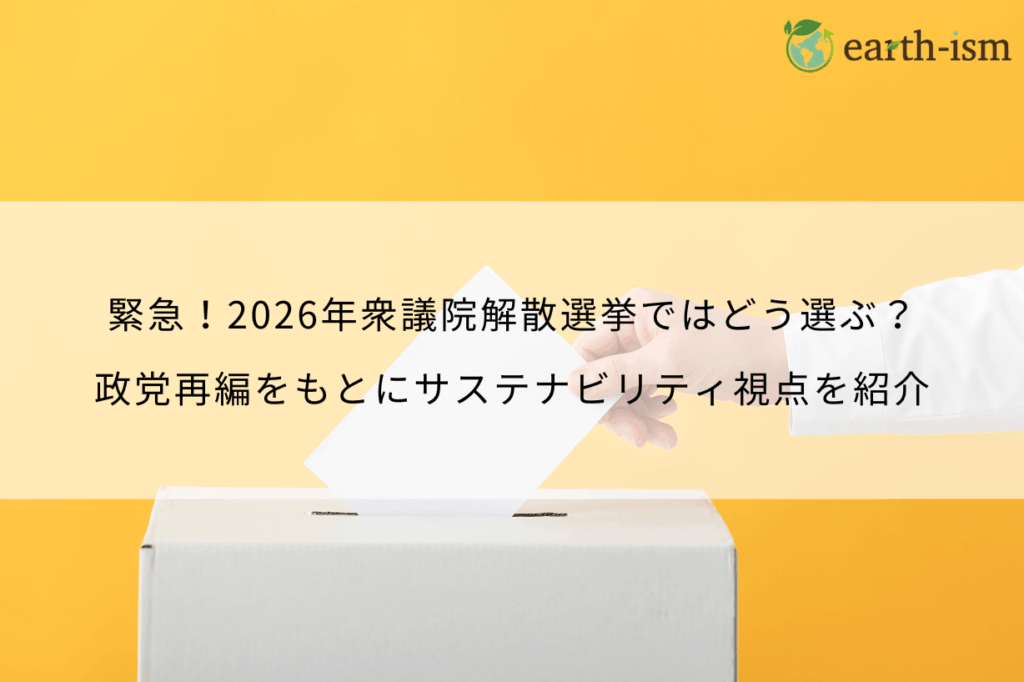サステナビリティとは?効果や企業の取り組み事例などを徹底解説


Contents
近年、世界中で「サステナビリティ(持続可能性)」の重要性が高まっています。環境問題や社会課題への対応が求められる中、多くの企業がサステナビリティを経営の中心に据え、積極的な取り組みを進めています。
しかし、「サステナビリティとは具体的に何を指すのか?」「企業が取り組むことでどのような効果があるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。


この記事では、サステナビリティの基本的な概念から、その必要性、企業にとってのメリット、さらには実際の取り組み事例までを詳しく解説します。
環境配慮だけでなく、社会的責任や経済的な持続可能性も含めた幅広い視点で、サステナビリティの本質を深掘りしていきます。企業の最新の取り組みを知り、自社の戦略に活かしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
サステナビリティとは


サステナビリティ(Sustainability)とは、環境・社会・経済の持続可能性を確保しながら、現在および未来の世代が豊かに生きられるようにする概念です。企業活動においても、単なる利益追求だけでなく、長期的な社会貢献や環境保護を考慮することが求められています。
3つの「E」
サステナビリティは、以下の3つの「E」に基づいて考えられます。
Envirronment(環境)
環境への負荷を最小限に抑えることが、サステナビリティの最も重要な要素の一つです。企業は再生可能エネルギーの活用、CO2排出量の削減、資源循環型のビジネスモデルの構築などを通じて、環境保護に貢献することが求められます。
Equity(公平性)
社会的公平性の確保もサステナビリティの重要な要素です。ジェンダー平等や労働環境の改善、地域社会への貢献など、多様な人々が公正に機会を得られる社会を実現することが求められます。
Economy(経済)
持続可能な経済成長を目指すこともサステナビリティの一環です。短期的な利益だけでなく、長期的な成長や社会貢献を考慮しながら事業を展開することが、企業の存続にとっても重要になります。
サステナビリティが注目されている理由
サステナビリティが注目される背景には、環境問題の深刻化、国際的な規制強化、企業リスクの回避、消費者意識の変化、サプライチェーン全体での対応が求められていることが挙げられます。
地球温暖化や資源枯渇への対策が急務となる中、SDGsやESG投資の拡大により、企業の持続可能な経営が求められています。また、環境対応を怠るとブランド価値の低下や規制強化による経営リスクが発生する一方、サステナブルな取り組みを行うことで競争力の向上につながります。
さらに、消費者のエシカル意識の高まりにより、環境配慮型の商品やサービスの需要が拡大。企業単体だけでなく、取引先を含むサプライチェーン全体での対応が不可欠になっています。
サステナビリティ経営とは
サステナビリティ経営とは、環境・社会・経済の3要素をバランスよく考慮しながら事業活動を行う経営手法です。企業が持続可能な社会を実現するためには、事業の中核にサステナビリティを組み込むことが不可欠です。
企業がサステナビリティに取り組むメリット


サステナビリティ経営を推進することで、企業は以下のようなメリットを得ることができます。
企業イメージが向上する
サステナビリティに積極的に取り組むことは、企業のブランド価値を高め、消費者や投資家からの信頼を得る大きな要因となります。
特に環境や社会貢献に配慮した製品・サービスは、エシカル消費を意識する層に選ばれやすく、企業の競争力向上にもつながります。また、サステナブルな経営を行う企業はメディアにも取り上げられやすく、ポジティブな広報効果も期待できます。


従業員からの満足度が上がる
企業がサステナビリティに取り組むことで、従業員の働きがいを向上させることができます。社会的意義のある仕事に携わることで、社員のモチベーションが上がり、企業へのエンゲージメントが高まります。
特に環境保護や社会貢献活動を重視する企業では、働くこと自体に誇りを感じる社員が増え、離職率の低下にもつながります。また、サステナブルな働き方の推進(テレワーク、長時間労働の是正など)も、従業員の満足度を高める要因となります。
人材確保につながる
近年、求職者の多くが企業のサステナビリティへの取り組みを重要視しています。特に若い世代は、環境問題や社会課題への関心が高く、企業が持続可能な社会の実現に貢献しているかを重視する傾向があります。
そのため、サステナブルな経営を実践する企業は、優秀な人材を引きつけやすく、採用競争力を強化できます。また、サステナビリティを推進する企業文化が根付いていると、従業員の定着率も向上し、長期的な成長につながります。
サステナビリティへの取り組みの導入手順


サステナビリティ経営を成功させるためには、以下のステップで取り組みを進めることが重要です。
1.サステナビリティへの理解を深める
まず、サステナビリティの基本的な概念を理解し、自社の業界や事業に関連する課題を把握することが重要です。SDGs(持続可能な開発目標)やESG(環境・社会・ガバナンス)といった国際的な枠組みを学び、自社にとって適切な取り組みを見極めましょう。
また、業界の最新動向や他社の成功事例を参考にすることで、より実践的なアイデアを得ることができます。
2.目的・目標を設定する
サステナビリティ活動を成功させるには、明確な目的と具体的な目標を設定することが欠かせません。例えば、「CO2排出量の削減」「リサイクル率の向上」「サプライチェーンの透明性確保」など、企業の事業戦略と連携した目標を立てましょう。また、目標は定量的に設定し、進捗を測定できるようにすることがポイントです。
3.ロードマップを検討する
目標を達成するためのロードマップ(実施計画)を策定し、短期・中期・長期のステップを明確にします。
例えば、短期的には社内の意識改革や小規模なプロジェクトを実施し、中長期的にはサプライチェーン全体での取り組みや新しいビジネスモデルの導入を目指すなど、段階的に進めることが重要です。
また、KPI(重要業績評価指標)を設定し、定期的に進捗をチェックしながら改善を図ることが成功のカギとなります。
【独自事例】サステナビリティに取り組む企業3選


ここでは、サステナビリティに積極的に取り組んでいる企業の事例を、earth-ismページから紹介します。
株式会社エコマスター
三豊市は2006年の合併後、新たな焼却炉建設を白紙撤回し、「燃やさない」ごみ処理方式を公募しました。同時期にエコマスターの先代社長がイタリアのトンネルコンポスト方式に出会い、事業化を模索。両者の思いが重なり、日本初のトンネルコンポスト方式が採用されました。
導入には市議会の反発や技術の適用疑問がありましたが、実証実験を重ね、2017年に稼働。現在、この方式は全国的に注目され、ごみを資源化する新たなモデルとして評価されています。
エコマスターは普及を目指し、自治体や事業者への支援、地域教育にも力を入れています。今後、環境問題解決と持続可能な社会づくりに貢献していくことが目標です。
詳しくはこちらのページをご覧ください。


株式会社LODU
株式会社LODUは、金沢工業大学の学生団体からスタートし、2021年に起業した学生発のスタートアップ。ゲームを活用してSDGsの意識・行動変容を促すことを目的に活動しています。
創業のきっかけは、SDGsに取り組む教授との出会いでした。クラスメートや他学科の学生を巻き込み、50人規模の団体に成長後、大学院修士2年目に法人化。現在は大学研究員としても活動しています。
LODUのゲームは「協力型」が特徴で、勝敗ではなく共通のゴールを目指します。代表作「THE SDGsアクションカードゲームX(クロス)」は、SDGsの「トレードオフ」を学ぶ教材。企業や自治体向けの研修に活用され、英語版・スペイン語版など世界展開も進行中。今後は一般向けのゲーム提供にも注力し、楽しみながら社会課題を学べる機会を広げていきます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。


三起商行株式会社
ミキハウスは、持続可能な社会の実現に向けてさまざまな事業を展開しています。まず、「お子様連れ世帯向け防災グッズ」の提案では、避難所で不足しがちな子ども用品を考慮し、防災グッズを開発。自治体の防災倉庫や避難所にも活用できるアイテムを提供しています。
次に、「裁断くずをタオルに」するサーキュラーエコノミー推進事業では、裁断くずを再資源化し、今治タオルと提携したミニタオルを製造。アップサイクルを実感できる製品としてイベントなどで配布されています。
「ネウボラ事業」では、自治体と連携し、赤ちゃん向けの安心・安全な育児パッケージを提供。すでに全国の自治体で採用されています。さらに、「足育のためのお子さまの足の計測すくすくプロジェクト」では、子どもの足の発育をサポートする計測会を実施し、正しい靴選びの重要性を伝えています。
詳しくはこちらのページをご覧ください。


まとめ


サステナビリティは、企業が成長を続けながら環境や社会に貢献するために不可欠な考え方です。環境(Environment)、公平性(Equity)、経済(Economy)の3つの「E」のバランスを考慮しながら持続可能な経営を行うことで、企業のブランド価値向上や優秀な人材確保にもつながります。
自社に適したサステナビリティ施策を実践するためには、具体的な導入手順を明確にし、経営戦略と統合することが重要です。長期的な視点で取り組むことで、企業の競争力強化と社会的責任の両立を実現しましょう。