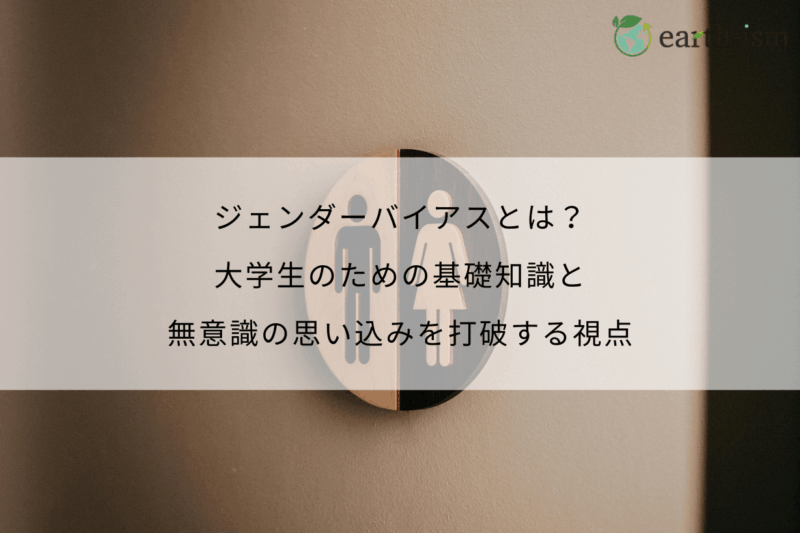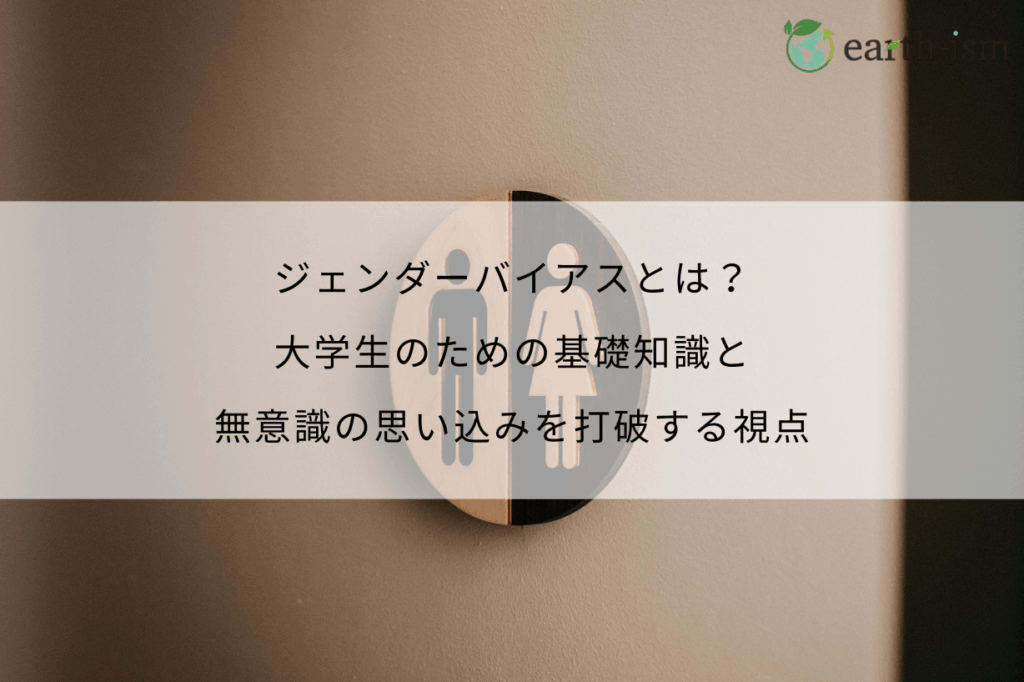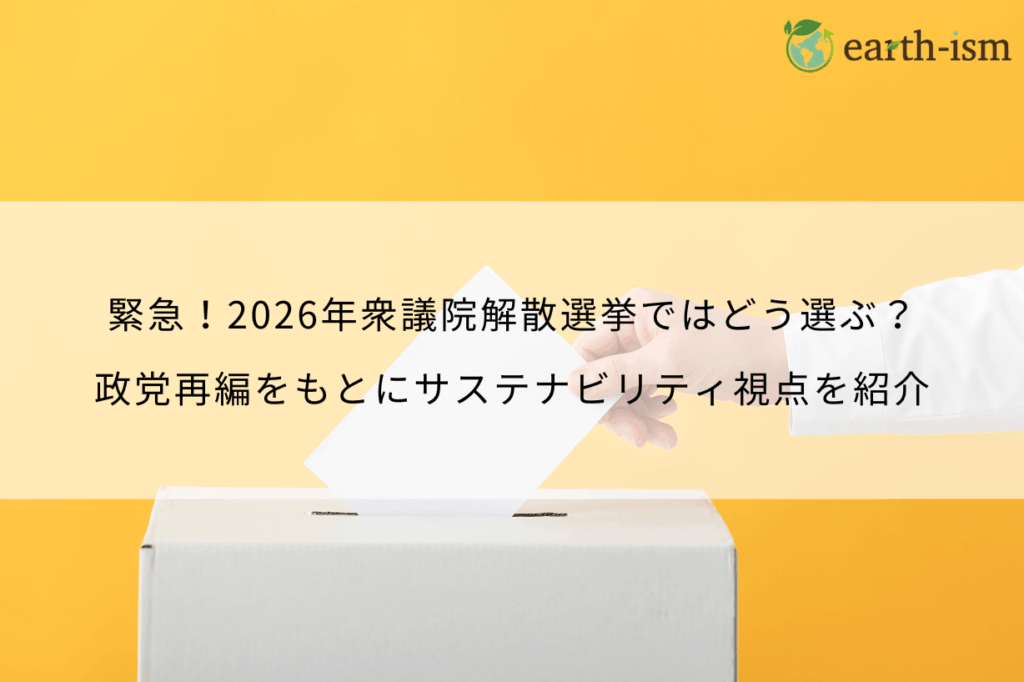リデュースとは?リサイクルとの違いや具体的な事例を中学生向けに解説
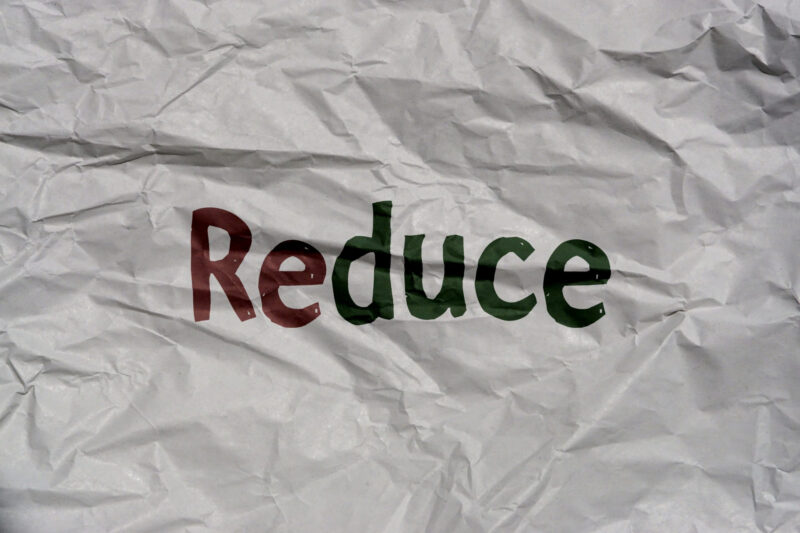
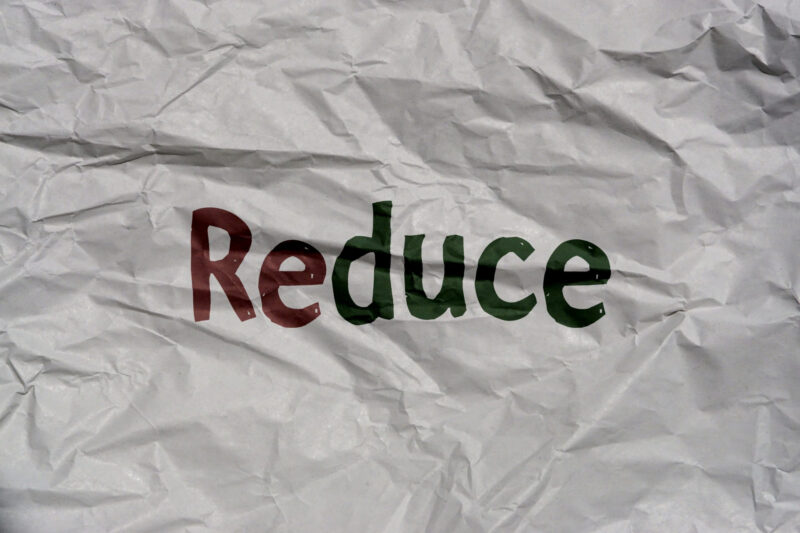
Contents
「リデュース(Reduce)」とは、ゴミを減らすことを意味する言葉です。私たちが普段使っているものをできるだけ無駄にせず、ゴミを減らすことで、環境への負担を小さくすることができます。
リサイクル(Recycle)が使い終わったものを新しいものに作り変えるのに対し、リデュースは「そもそもゴミを出さないようにする」ことを目指します。たとえば、買い物をするときにレジ袋をもらわずマイバッグを使うことや、必要のないものを買わないことがリデュースの実践例です。
リデュースを意識して生活すると、地球の資源を大切にすることにつながります。それでは、具体的な事例やリサイクルとの違いについて詳しく見ていきましょう。
リデュースとは?


リデュース(reduce)とは、「ゴミの量を減らすこと」を意味します。環境問題を解決するための「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」の1つで、最も重要とされています。
リデュースは、「そもそもゴミを出さないようにする」ことを目的としており、資源の無駄遣いを減らし、環境への負担を少なくするために行われます。
リデュースは 「物を使う前に、ゴミを減らす工夫をする」 ことがポイントです。リサイクルと違い、新しい資源を使わずにゴミを減らすため、環境にとってより効果的な方法とされています。
リデュースが必要とされている背景


リデュース(Reduce)が重要視されているのは、ゴミの増加や資源の枯渇、環境汚染が深刻化しているためです。以下でリデュースが必要となっている背景を説明します。
1. ゴミの増加と処理問題
食品の包装や使い捨てプラスチック製品の使用が増加し、それに伴いゴミの量も年々増え続けています。特に、コンビニエンスストアやスーパーで販売される商品には、多重包装が施されていることが多く、購入後すぐに廃棄される包装材が大量に発生しています。
また、宅配サービスやオンラインショッピングの普及により、梱包材として使われるダンボールやプラスチックフィルムの廃棄量も急増しています。しかし、こうしたゴミを処分するための焼却施設や埋め立て地には限りがあり、すでに多くの国や地域でゴミの処理能力が限界に近づいているのが現状です。
2. 資源の枯渇
私たちが日常的に使用している紙やプラスチック、金属などの多くは、地球上の限りある資源から作られています。例えば、紙の原料となる木材は森林から伐採されますが、過度な伐採によって森林の減少が進み、生態系への影響が懸念されています。
また、プラスチック製品の原料となる石油や、電子機器に使用されるレアメタル(希少金属)も、埋蔵量には限りがあり、将来的に枯渇する可能性があります。大量生産・大量消費の社会では、資源が一方的に消費されるだけでなく、短期間で廃棄されることで、再利用が難しくなり、資源の枯渇を加速させています。
3. 環境汚染の深刻化
ゴミの中でも、特にプラスチックごみの問題は深刻化しています。使い捨てプラスチック製品は、一度使用された後すぐに廃棄されることが多く、適切に処理されないまま自然環境に流出するケースが増えています。
海洋に流れ出たプラスチックごみは、波や紫外線によって細かく砕かれ、マイクロプラスチックとして長期間海中を漂い続けます。このマイクロプラスチックを誤って飲み込んだ魚や海洋生物が体内に取り込み、最終的には食物連鎖を通じて私たちの食卓に戻ってくる可能性も指摘されています。


さらに、ゴミを焼却する際には大量の二酸化炭素(CO₂)が発生し、地球温暖化の原因となります。温暖化の進行により異常気象が頻発し、干ばつや豪雨、森林火災のリスクが高まることで、生態系や人々の生活にも影響を与えています。これらの環境問題を抑えるためには、ゴミそのものを減らすリデュースの考え方が不可欠です。
4. リサイクルだけでは限界がある
リサイクルは、使用済みのものを再利用することで資源の有効活用を図る方法ですが、すべてのゴミをリサイクルできるわけではありません。実際には、リサイクル可能な資源であっても、回収・分別・再加工の過程でコストやエネルギーがかかるため、環境への負担が完全にゼロになるわけではないのが現状です。
特に、プラスチックはリサイクルされる過程で品質が劣化し、何度も再利用することが難しい素材の一つです。そのため、リサイクルに頼るだけでは資源問題やゴミ問題の解決にはつながりません。
リユース、リサイクルとの違い
「リデュース(Reduce)」「リユース(Reuse)」「リサイクル(Recycle)」は、環境を守るための 「3R」 と呼ばれる取り組みですが、それぞれの目的や方法には違いがあります。
| リデュース(Reduce) | リユース(Reuse) | リサイクル(Recycle) | |
| 意味 | ゴミを減らす | 繰り返し使う | 資源として再利用する |
| 目的 | そもそもゴミを出さない | 使えるものを長く活用する | ゴミを新しい製品に生まれ変わらせる |
| 環境負荷 | 最も低い (ゴミを出さない) |
低い (そのまま再利用) |
やや高い (加工が必要) |
3Rの中で最も優先すべきなのは「リデュース」です。なぜなら、ゴミを出さないことが一番環境に優しいからです。次に、使えるものを繰り返し使う「リユース」が続き、最後にどうしてもゴミになったものを資源として活用する「リサイクル」があります。
リデュースの具体的な事例


次に、リデュースの具体的な事例を3つ紹介します。
エコバッグの活用
コンビニやスーパーで買い物をするとき、レジ袋をもらわずに エコバッグを持参 することで、使い捨てのプラスチックごみを減らすことができます。レジ袋は一度使っただけで捨てられることが多く、環境への負担が大きいため、マイバッグを活用することがリデュースにつながります。
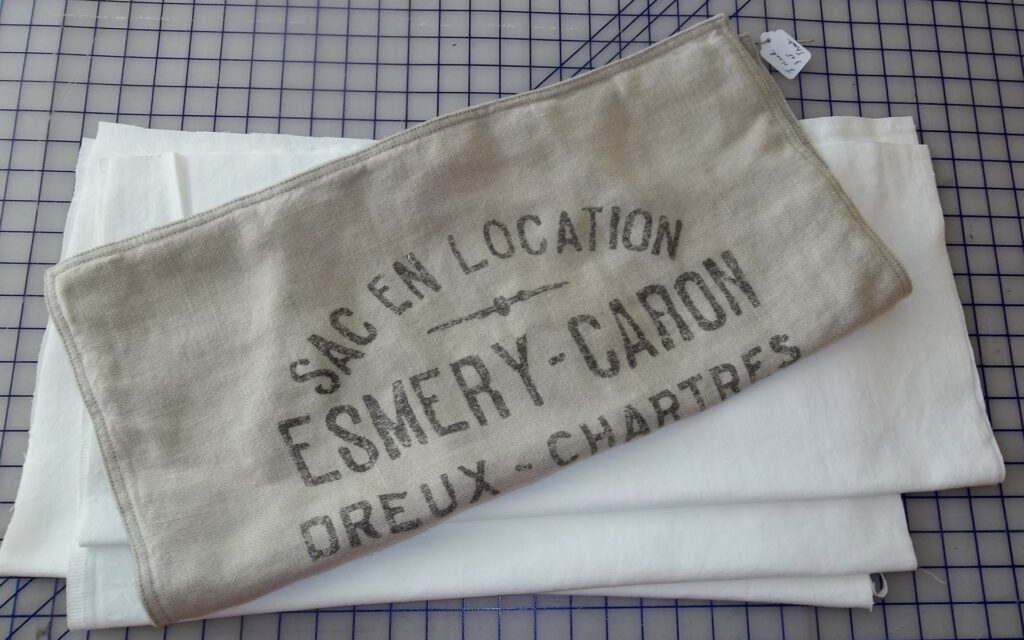
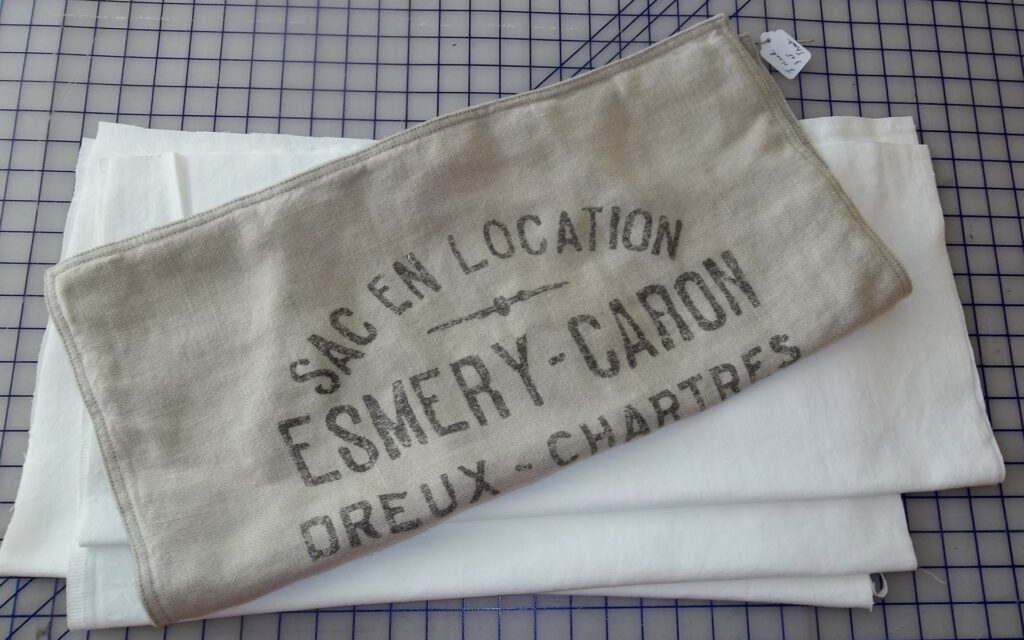
マイボトルやマイストローなど、マイ〇〇の活用
カフェや飲食店でペットボトル飲料や使い捨てカップを買うのではなく、マイボトルやマイカップ を持ち歩くことで、ゴミを減らすことができます。さらに、プラスチック製の使い捨てストローの代わりに、マイストロー(ステンレスや竹、シリコン製) を使うことで、プラスチックごみを削減できます。


フードロスの防止
食べ物を無駄にしないことも、リデュースの重要な取り組みの一つです。日本では大量の食品が廃棄されており、フードロスの削減が求められています。食べ物を捨てることは、食品を作るために使われた水やエネルギーも無駄にすることになるため、環境負荷を減らすためにもリデュースが必要です。


3Rの先にある「4R」「5R」とは?


環境問題を解決するために「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」が広く知られていますが、さらに環境負荷を減らすために「4R」「5R」という考え方も登場しています。
4Rとは
3Rに加えて、「リフューズ(Refuse)」または「リペア(Repair)」のいずれかを追加したものが4Rと呼ばれています。
リフューズ(Refuse)とは、不要なものを受け取らないことを意味します。そもそもゴミになりそうなものを手にしないことで、環境への負担を減らすことができます。例えば、レジ袋や使い捨てストローを断る、不要なチラシや試供品をもらわないといった行動がこれに該当します。
一方で、リペア(Repair)を4Rの一つとして考える場合もあります。リペアとは、壊れたものを修理して使い続けることを指します。靴やカバンを修理して長く使う、スマートフォンや家電を修理して買い替えを防ぐといった取り組みがこれにあたります。
どちらの考え方も、ゴミの発生を抑え、資源の無駄を減らすことにつながります。
5Rとは
5Rは、3Rにリフューズとリペアの両方を加えたものを指します。3Rに比べて、より積極的にゴミを減らし、資源を有効に活用することを目的としています。
リフューズの考え方を取り入れることで、そもそも不要なものを受け取らず、ゴミの発生を未然に防ぐことができます。また、リペアを加えることで、壊れたものを修理し、使い続けることで廃棄物を減らすことが可能になります。
例えば、衣類を修理して着続ける、家具を修理して再利用する、家電を修理して長期間使用するなどの行動が、5Rの実践例として挙げられます。
3Rから4R、5Rへの進化
従来の3Rは、ゴミの削減に向けた基本的な取り組みとして広く実践されてきました。しかし、環境問題の深刻化に伴い、より踏み込んだ対策が求められるようになり、4Rや5Rの考え方が重要視されるようになっています。
特に、リフューズを意識することで、ゴミそのものを発生させない生活が可能になります。また、リペアの考え方を取り入れることで、物を大切に使い続ける文化を育むことができます。これらの取り組みを日常生活に取り入れることで、環境負荷をより効果的に軽減することができます。
今後、環境問題への対策として、3Rにとどまらず、4Rや5Rを意識した行動が求められるようになるでしょう。まずは身近なことから取り組み、持続可能な社会の実現に向けた一歩を踏み出すことが大切です。
まとめ


ゴミの増加と処理の限界、資源の枯渇、環境汚染の深刻化といった課題に対応するためには、使い捨てを減らし、長く使えるものを選び、必要以上にものを持たないといった意識が欠かせません。
また、リサイクルは環境保護に有効な手段ではあるものの、すべての資源が再利用できるわけではなく、エネルギーやコストの面でも限界があります。そのため、リサイクルよりも前に、そもそもゴミを生み出さないリデュースを優先することが重要です。
今後、持続可能な社会を目指すためには、個人の消費行動だけでなく、企業や自治体による取り組みも不可欠です。過剰包装の削減やリペア文化の促進など、社会全体でリデュースを推進することで、資源の有効活用と環境負荷の軽減が実現できます。日々の生活の中で、小さな行動を積み重ねることが、未来の地球環境を守る第一歩となります。