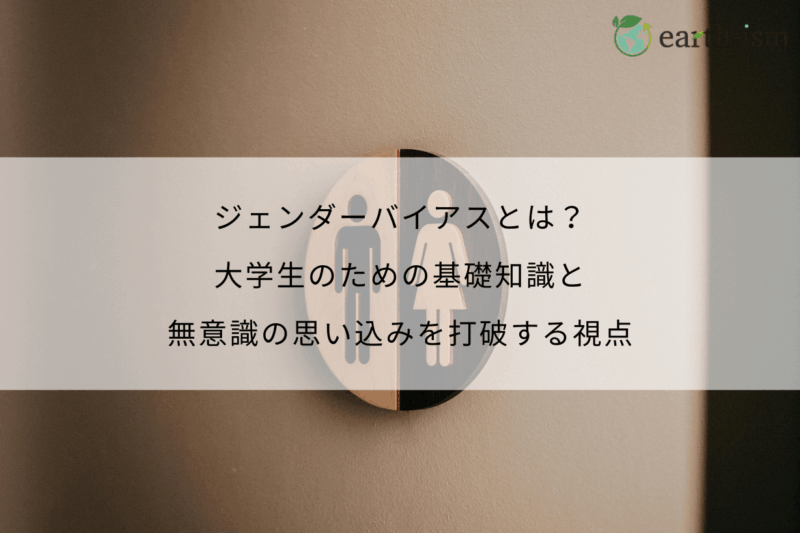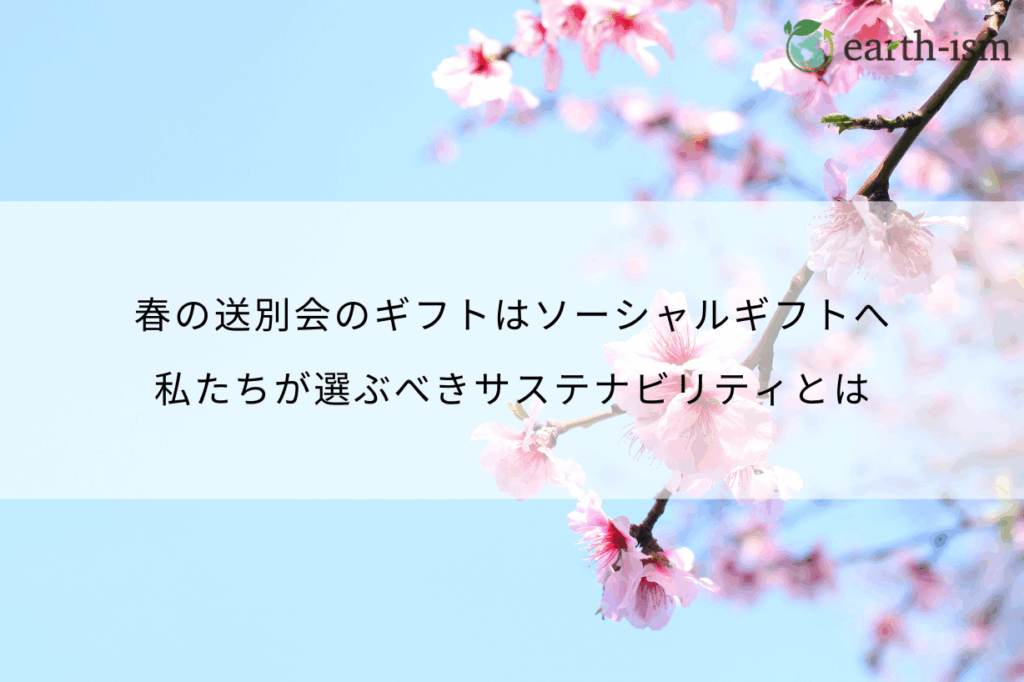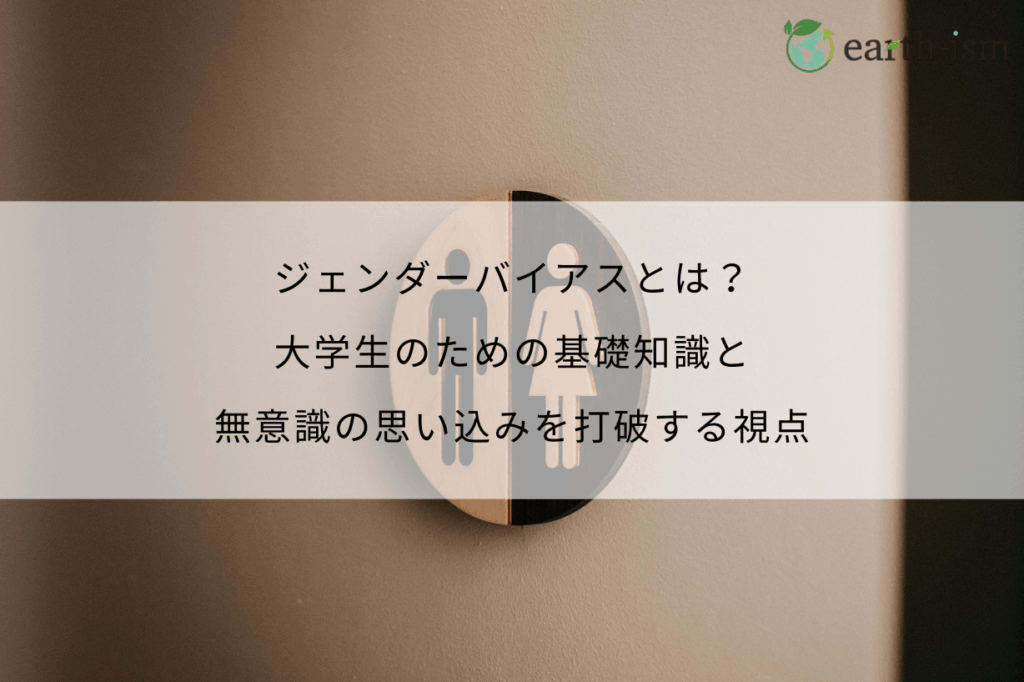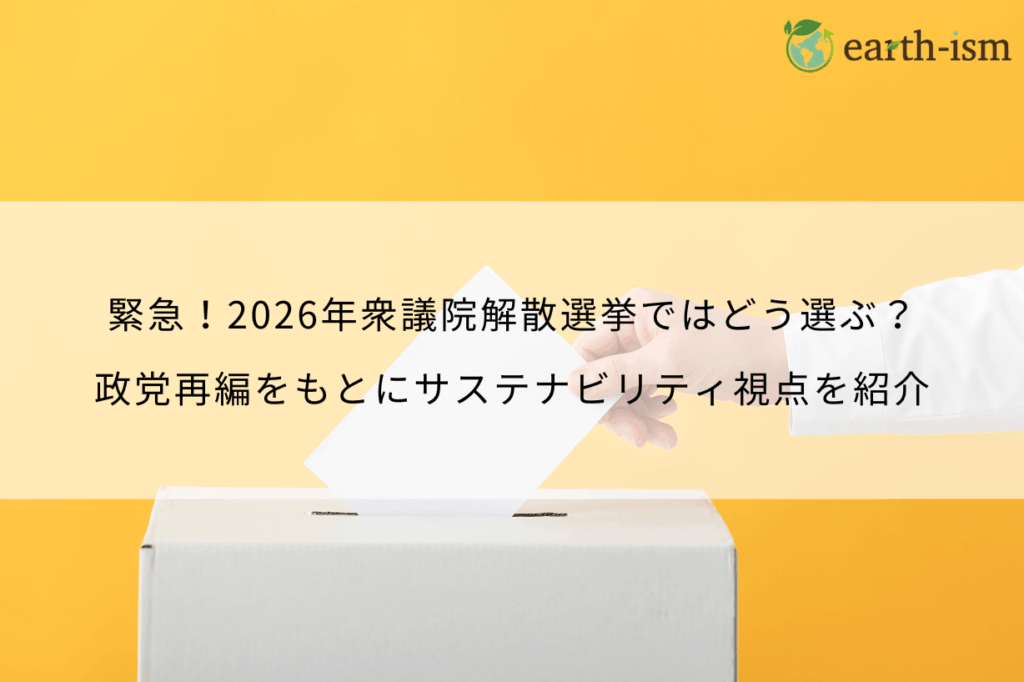絶滅危惧種を守るためにできる5つのこと│種類や対策などを解説
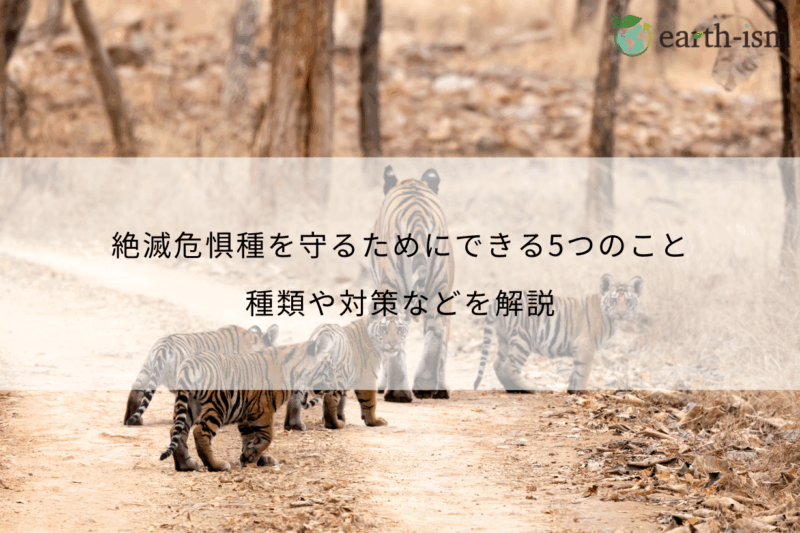
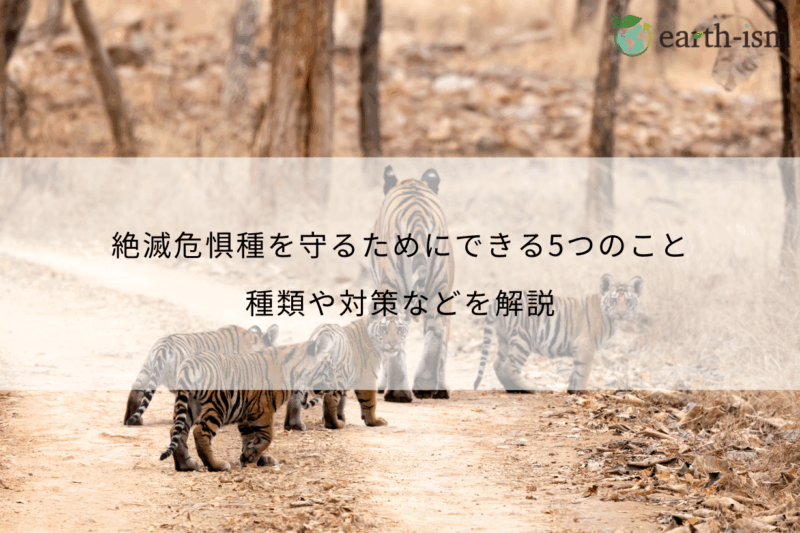
Contents
「もうすぐ、ウナギが食べられなくなる!?」
そのようなニュースが、2025年7月に報道されたことを覚えていますか?
EU(ヨーロッパ連合)は、日本人が食べているニホンウナギを、絶滅のおそれがある生物の国際的な取り引きを規制するワシントン条約の対象に加えるよう提案しました。規制の対象は、ウナギそのものだけではなく、稚魚のシラスウナギ、加工品のかば焼きも含まれます。
日本の水産庁は「ニホンウナギの十分な資源量は確保されている」として、EUに反対しています。
絶滅危惧種とは?基本の定義と分類


絶滅危惧種という言葉は、具体的にはどういう意味なのでしょうか?下記で詳しく見ていきましょう。
IUCNと環境省のレッドリスト
絶滅危惧種をまとめたリストは「レッドリスト」と呼ばれます。これは1948年に設立されたIUCN(国際自然保護連合 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources)が、1966年に公表したリストの表紙が赤色だったためです。
レッドリストは9つのカテゴリーに分けられています(ランク、マーク、定義の順)。
1.絶滅 EX(Extinct) すでに絶滅したと考えられるもの
2.野生絶滅 EW(Extinct the Wild) 野生の個体が絶滅し飼育下でのみ存続しているもの
3.深刻な危機 CR(Critically Endangered) ごく近い将来、野生での絶滅の危険性が極めて高いもの
4.危機 EN(Endangered) CRほどではないが、近い将来、野生での絶滅の危険性が高いもの
5.危急 VU(Vulnerable) CRやENほどではないが、近い将来、野生での絶滅が心配されるもの
6.準絶滅危惧 NT(Near Threatened) 近い将来、CR、EN、VUにランクされる可能性があるもの
7.低懸念 LC(Least Concern) 絶滅の危険は低いと考えられるもの
8.データ不足 DD(Data Deficient) 絶滅の危機を評価するための十分な情報がないもの
9.未評価 NE(Not Evaluated) まだ評価が行われていないもの
引用元:環境省|レッドデータブック
日本は1978年に、当時の環境庁がIUCNのメンバーに加入しました。1991年から、日本版のレッドリストを作成しています。基本的にIUCNのランクに準じていますが、CRとENを「絶滅危惧Ⅰ類」とし、CRを「絶滅危惧ⅠA類」、ENを「絶滅危惧ⅠB類」。VUを「絶滅危惧Ⅱ類」としています。
各ランクの意味
ランクは、生息数、生息数の減り方の度合いや見込み、生息地の広さなどの基準に基づいて定められています。この中で、「深刻な危機(CR)」「危機(EN)」「危急(VU)」にランクされているものを、特に「絶滅危惧種」と呼んでいます。
日本版レッドリストの場合は、「絶滅危惧種Ⅰ類(CR、EN)」「絶滅危惧種Ⅱ類(VU)」が相当します。
日本に存在する絶滅危惧種の数と推移
日本では、1991年からレッドリストが環境省によりまとめられ、おおむね5年ごとに大規模な見直しがされ、また再検討が必要なものはその都度改訂版が作成されています。レッドリストに掲載されたものを解説したレッドデータブックも編纂されています。
1991年、第1次レッドリストの絶滅危惧種の数は110種ほどでしたが、2000年の第2次レッドリストでは対象となる生き物が広がったこともあり、2400種近くが絶滅危惧種となっています。
その後、第3次、第4次とその数は増加し、2020年の5回目の改訂版では3772種が絶滅危惧種に数えられています。現在は、第5次レッドリストの評価作業が進められている最中です。
なぜ絶滅危惧種が増えているのか?3つの主な要因


生き物が絶滅していく背景についての詳細を見ていきましょう。
原因1:人間活動による生息地の破壊
1960年に30億人だった世界の人口は、2024年に81億人に増えています。人の生活する場所が広がれば、当然、森林や草原、湿地帯など、生き物たちの生息地が失われていきます。
生息地は森や川、草原や湿地、海や湖などさまざまですが、森林については、3年ほどで日本の全国土分の森が失われているといわれます。
原因2:気候変動と異常気象の影響
地球の温暖化による気候変動は生き物にも大きな影響を与えています。
北極の氷が溶けることでシロクマなどの動物は生息地を失い、高山地帯などでは雪解けの洪水で命を失う生き物も少なくありません。
異常気象はあらゆる生き物の生存にも深刻な結果をもたらしているのです。
原因3:外来種の侵入と生態系の乱れ
日本にいなかった生物が外国からきて定着し、日本の生態系を乱している例も増えています。
ブラックバスはよく知られているもののひとつです。北米から持ち込まれたブラックバスは、日本の川などでも適応能力が高く、日本の魚やエビなどを食べて、生態系へ大きなダメージを与えています。
近年話題となったセアカゴケグモのように、船の荷物に紛れ込んできた外来種の例もありますが、大半は人間の行動が原因となっているといえるでしょう。また、2024~2025年現在にかけてはキョンによる農業被害も深刻です。気になる方は、下記の記事もご覧ください。
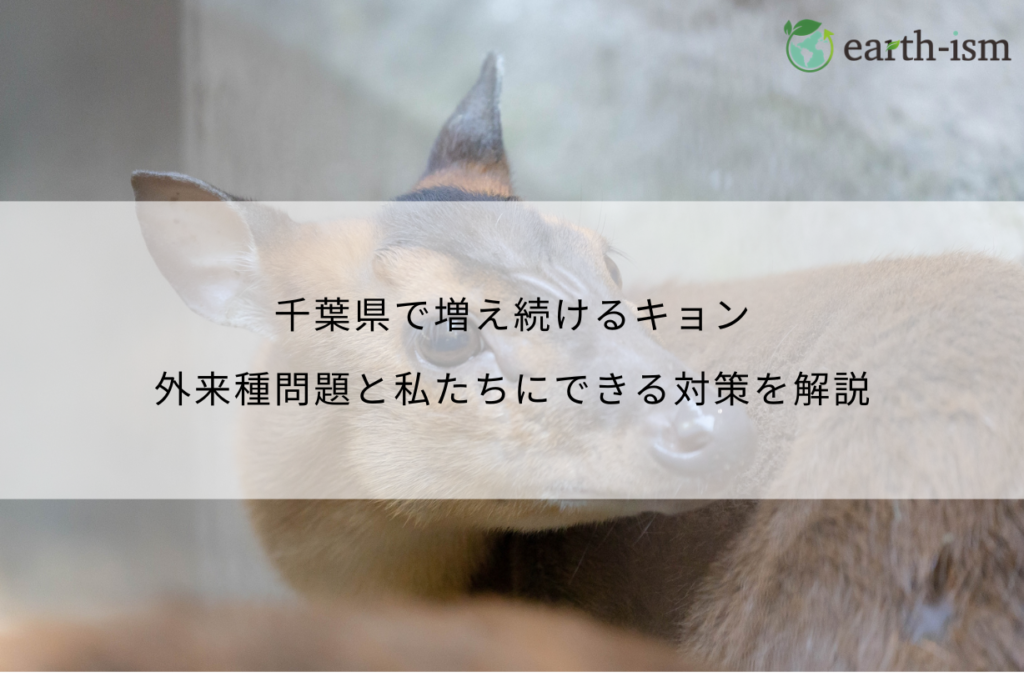
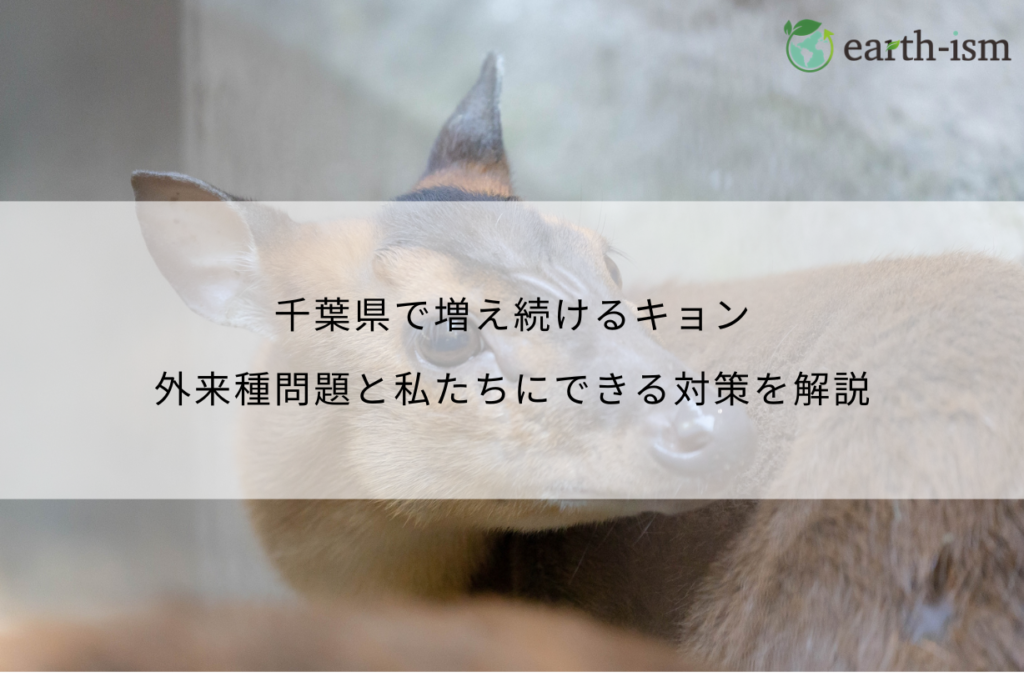
絶滅危惧種が「他人事ではない」理由


「絶滅危惧種」という言葉を聞くと、どこか遠い国の話と思うかもしれません。しかし、21世紀以降でも世界で14種の動物が絶滅しています。
身近に迫る絶滅の危機
日本人にとって絶滅の危機が「他人事ではない」のは、やはりウナギでしょう。
ウナギについては、2009年にヨーロッパウナギの取り引きが規制されています。EUは、日本で主に消費されているニホンウナギやアメリカウナギなど18種類のウナギも、ワシントン条約に加えるように提案しました。
EUの提案を採択するか否かの会議は、2025年11月から12月にかけて開催されます。採択されたとしても、すぐにウナギが食べられなくなるわけではなく、影響は限定的だとされますが、価格の上昇などにつながる可能性はあるといわれています。
最近絶滅した生き物たちのストーリー
前述した21世紀に絶滅した動物の中には、日本の生き物も含まれます。
その一例はニホンカワウソです。日本に広く生息していましたが、毛皮を目的とした人間による乱獲、高度成長期の生態系の破壊などにより、その数が減少。1964年に国の天然記念物に指定されたものの、2012年に絶滅が発表されました。
日本を代表する鳥であるトキも、2003年に絶滅。北海道から九州にかけて生息していたトキは、羽毛目的に乱獲されて絶滅寸前になります。1934年に国の天然記念物に指定され、1967年には佐渡トキ保護センターが設立されました。しかし、絶滅を防ぐことはできませんでした。
その後、中国から贈られたつがいで繁殖に成功し、順調に数を増やしていることは、知っている人も多いことでしょう。
急激に進む絶滅の背景とは?


ニホンカワウソにしてもトキにしても、絶滅の原因が人間のせいであると言われています。そもそもすべての生き物の絶滅の原因は、人間にあると言わざるを得ないでしょう。
後述するとおり、人間が生活の場所を広げることで動物や植物などの生息地は減少しています。人間による乱獲も深刻です。絶滅を防ぐための活動も行われていますが、現在でも、アフリカなどでは密猟が大きな問題となっています。
私たちにできる5つの行動
では私たちは、絶滅危惧種が増えていくことを、ただ見ているしかないのでしょうか?私たちにできることは何でしょう。
1.自然保護活動への参加
絶滅危惧種をテーマにしているかどうかにかかわらず、自然保護を目的とした活動はさまざまな場所で行われています。
まずは地元の活動について確認してみましょう。自然についての勉強会や観察会も行われているのではないでしょうか。
大人を対象とした地域ボランティアもあるはずです。専門的な内容も大切ですが、何よりも地元の自然について知ることが、自然保護活動の一歩となります。
2.絶滅危惧種について学び、広める
絶滅危惧種についての学びを深めることも大切です。先にあげた環境省のレッドリスト・レッドデータブックのサイトを見てみましょう。その数の多さに驚くはずです。
数年の間に、これほどの生き物が絶滅の危機に瀕していることに絶望的な気持ちになるかもしれません。一方、危機感を募らせている人は、世界中にたくさんいることも事実です。今は、インターネットで情報の入手が簡単にできますし、SNSでの発信により情報の共有や学びを広げることもできます。
一度のぞいてほしいのは、図書館などの子どものコーナー。動物の絶滅などについての書籍が数多く置かれています。要点がわかりやすいのでおすすめです。
3.環境に配慮した商品を選ぶ
近年は、SDGsの目標達成のため、社会的課題の解決を考慮したり、課題に取り組む企業や団体を応援しながら消費活動を行うことが求められています。そのために、さまざまな国際認証ラベルがあります。
FSC(Forest Stewardship Council)は、持続可能な森林管理を推進するための基準を設定していて、FSC認証は森林を持続させ、環境保全に関する厳格な基準を満たす製品に与えられます。
MSC(Marine Stewardship Council)認証は、その漁業版。将来の世代が、海の恩恵を受けられることを目的としています。これらのような認証ラベルに注意を払い、認証された商品を選ぶことも、絶滅危惧種を減らしていくことにつながっていきます。
4.ペット購入の際に絶滅危惧種を避ける
WWF(世界自然保護基金 World Wide Fund for Nature)によると、日本は犬や猫などの一般的なペット以外の動物、いわゆるエキゾチックアニマルの消費大国のひとつとされています。
2014年から2018年の間、1161匹の動物がワシントン条約の対象種として、日本税関に差し止められました。最も多いのは爬虫類で約7割を占めています。
ペットとして絶滅危惧種を飼わないのはもちろんのこと、その動物がどのように経路で流通しているのか、密輸ではないのか、などにも注意する必要があります。
5.寄付やクラウドファンディングで支援する
絶滅危惧種をはじめ、自然を守るために活動する団体はいろいろとあります。その団体に寄付をすることでも、自然保護の運動に参加することができます。代表的な団体を紹介しましょう。
1951年創立の自然保護NGO。その活動は多岐に渡り、多種多彩なイベント等も開催。
絶滅のおそれのある動物を守る「野生動物アドプト制度」などを展開。
現在29ヵ国に拠点を持ち、世界中のパートナーとグローバルな規模の自然保護を行う。
未来を変える「企業と個人」の取り組み事例


絶滅危惧種の問題を含めた、自然保護や環境問題に取り組む企業や個人について知ること、関わることも未来へとつながる行動です。
サステナビリティを重視する企業の取り組み例
日本ではユニクロの活動はよく知られている例のひとつでしょう。「服のチカラを、社会のチカラに。」という合言葉のもと、服のリユース・リサイクル、古着プロジェクトなどが行われています。服に再利用できないものは断熱材などに活用されています。
日清食品グループも環境戦略に積極的に取り組んでいます。食を通じて環境のためにできることのほか、プラスチック削減などのテーマを掲げ、サステナビリティマネジメントを企業の中心に据えています。
自治体・NPOとの連携プロジェクト紹介
都道府県や市町村は、生物多様性基本法により、生物多様性地域戦略の策定に努めることとされています。各自治体によっても、その地域のレッドリストに関連した取り組みが行われています。
NPO法人ツシマヤマネコを守る会、NPO法人シマフクロウ基金など、NPOの取り組みのほか、各地の大学による絶滅危惧種の保護に関する研究も盛んになってきています。
一人の行動が社会を変える
写真家が絶滅危惧種の動物を撮影し続け、注目される例も少なくありません。
ナショナルジオグラフィックのカメラマンが行った写真プロジェクト「フォト・アーク」は、動物の保護を支援する写真版「ノアの箱舟」として注目されました。
ボルネオ島の絶滅危惧種であるマレーグマを守るため、クラウドファンディングを立ち上げた東京農業大学の学生もいます。
まとめ|今日から始められる「一歩目」を選ぼう


冒頭で紹介したとおり、ウナギは絶滅危惧種です。動物園で見かけるなじみのある動物にも、絶滅危惧種となっているものが少なくありません。
まずは、どのような生き物が絶滅危惧種となっているかを知ることが大切です。その多さには、改めて驚かされるはずです。
そして、なぜ絶滅危惧種が増えているのかも前述のとおり。大きくは人間の生命活動のせいと言わざるを得ない、悲しい現状にあります。絶滅危惧種を増やさないためにできることは、自然環境を守ることにほかなりません。何をすればいいのか、何をしてはいけないのかは明らかといえるでしょう。
既にたくさんの人々、団体などが取り組みを始めています。自分でできることは何なのかを考え、確実に一歩を踏み出すときがきています。