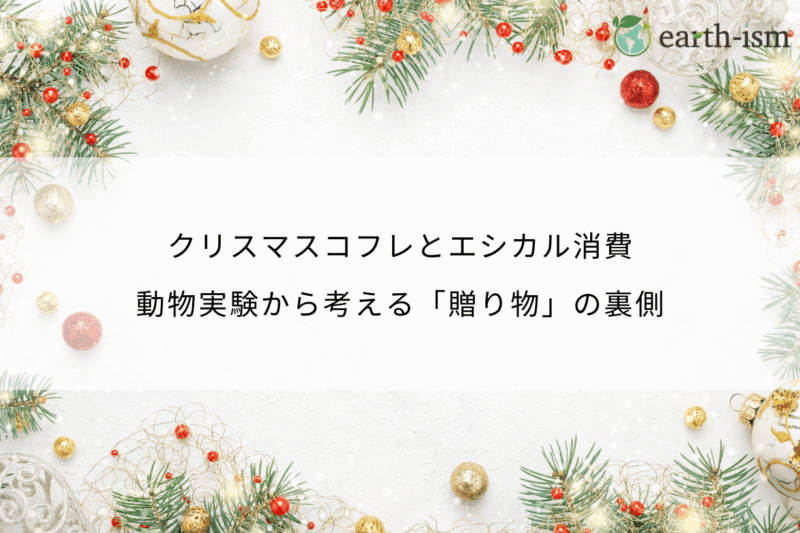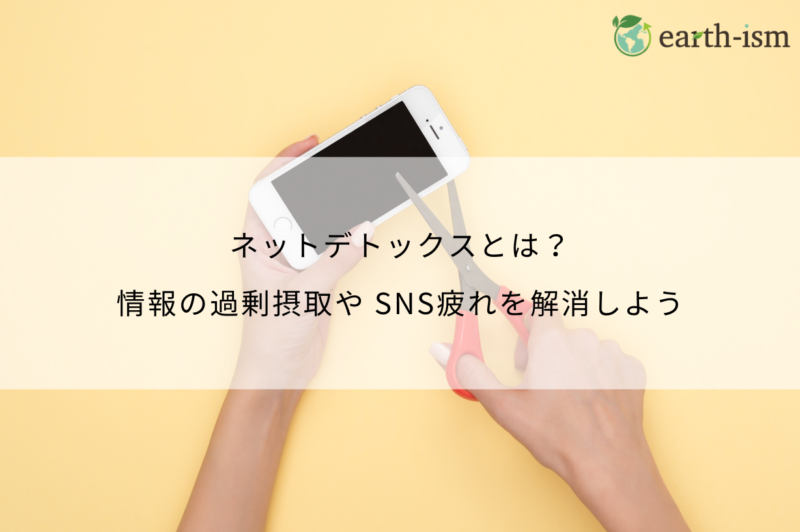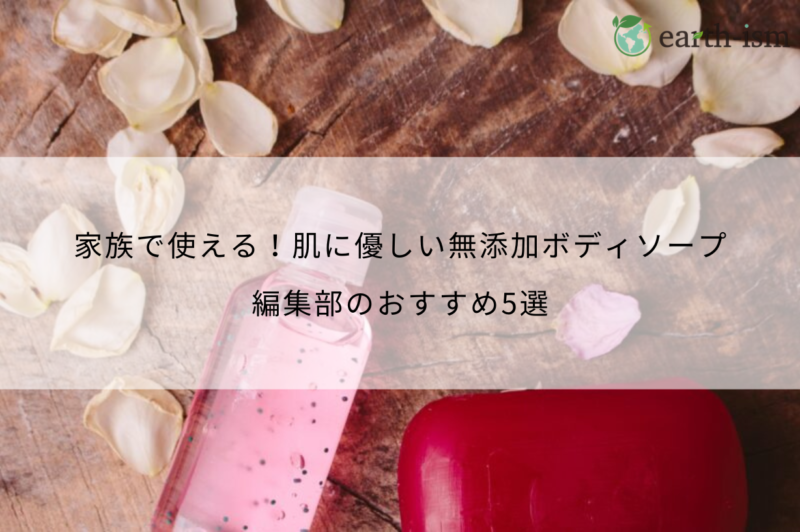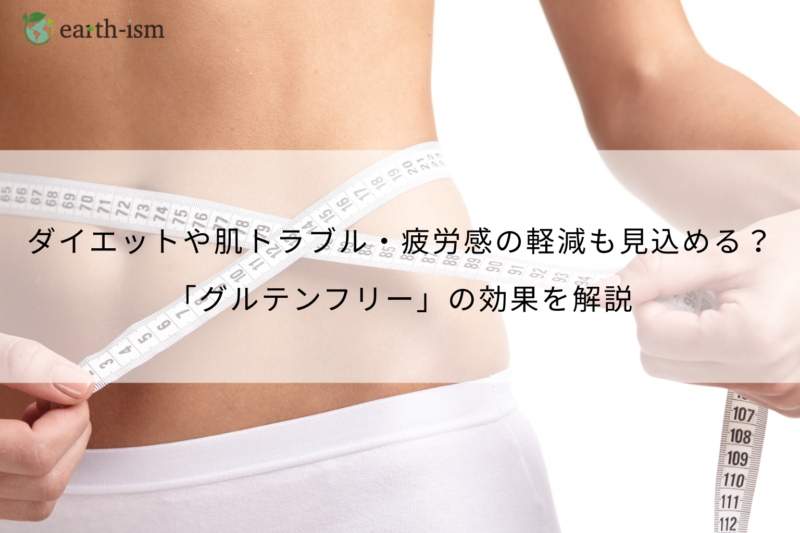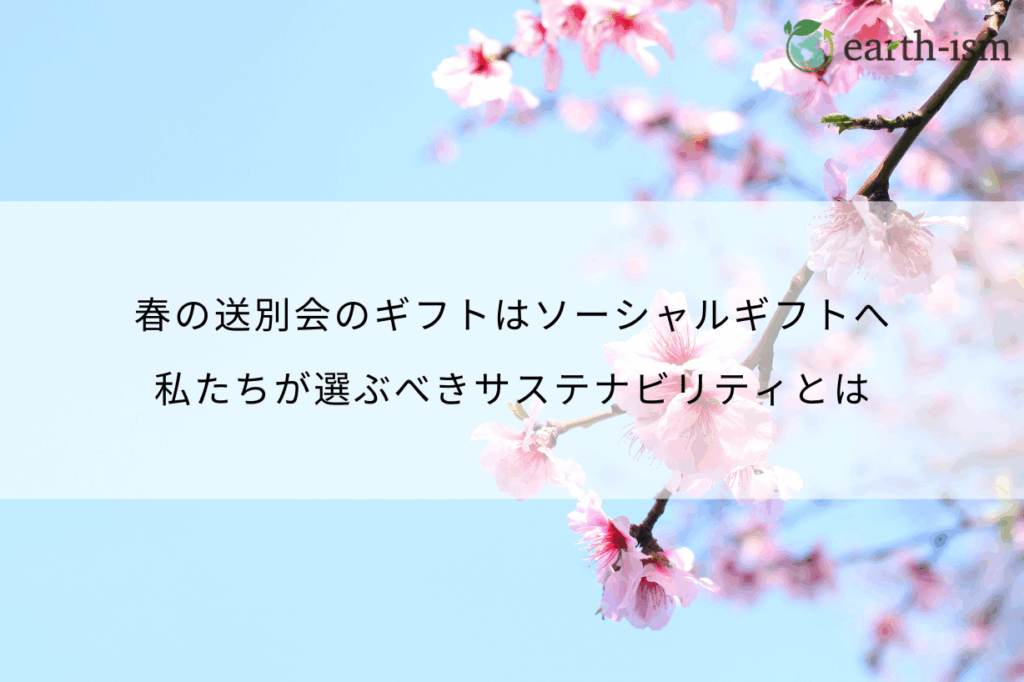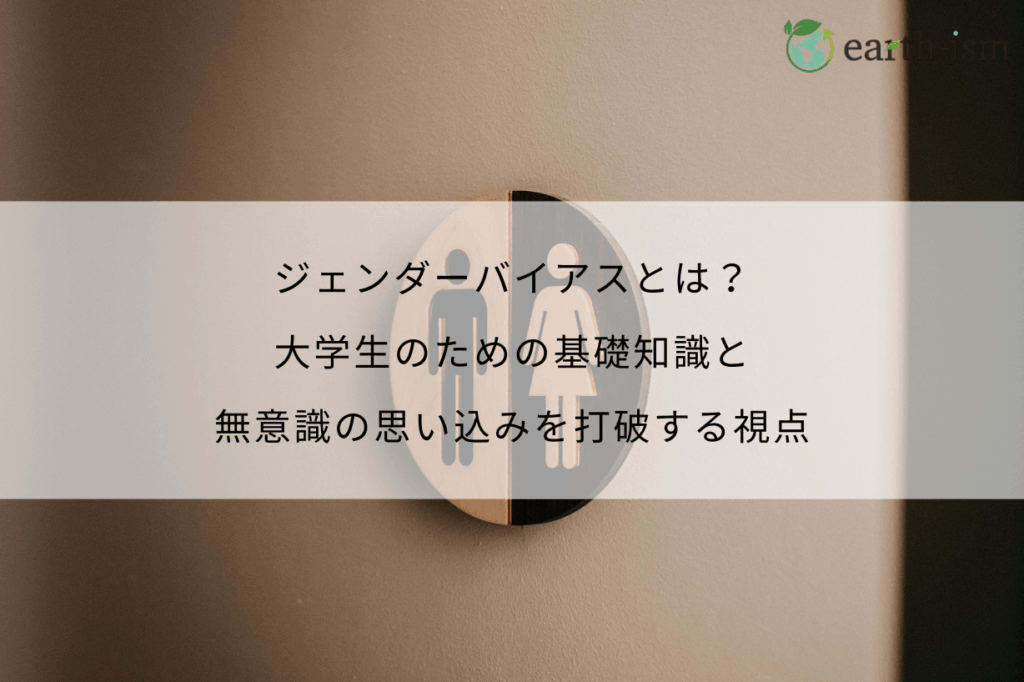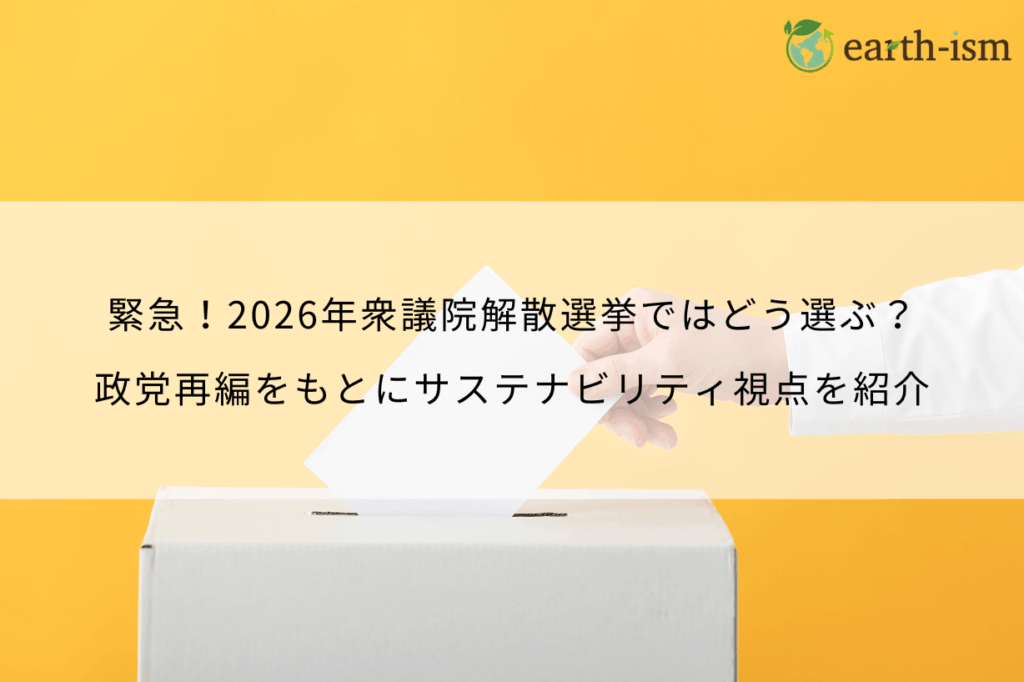化粧品カーボンフットプリントの日に考えるエシカルビューティ|肌にも地球にもやさしい美容


Contents
朝のスキンケア、仕事前のメイク、夜のクレンジング。わたしたちが毎日手にする化粧品は、「肌」を美しく整えるためのものですが、その裏側では「地球」にも少なからず影響を与えています。
最近注目を集めているのが「カーボンフットプリント(CFP)」という考え方。これまで見えにくかった化粧品のCO₂排出量を可視化しようとする動きが広がり始めています。
“化粧品カーボンフットプリントの日”は正式な記念日ではありませんが、SNSや業界関係者を中心に認知が広がり、消費者と企業が「見える化」を共有する日として機能しつつあります。
あなたが今手にしているその1本のコスメが、地球の未来にどんな影響を与えるのか、この記事を通して、少し立ち止まって考えてみませんか?


化粧品カーボンフットプリントの日とは?


11月1日は「化粧品カーボンフットプリントの日」。ちふれホールディングス株式会社が制定し、一般社団法人日本記念日協会によって認定・登録された記念日です。国民の祝日のような法的な記念日ではありませんが、サステナブルやエシカルを意識する人々のあいだで、啓発的な意味を持つ“シンボルデー”として徐々に浸透してきました。
背景には、近年のカーボンフットプリント(CFP)可視化への関心の高まりがあります。CFPとは、原材料の調達から製造・流通・使用・廃棄に至るまで、製品のライフサイクル全体で排出されるCO₂量を数値化する取り組みのこと。食品や日用品に続き、コスメ分野でも少しずつ導入され始めました。
また、これはSDGsの目標13「気候変動に具体的な対策を」や、目標12「つくる責任、つかう責任」とも直結しています。私たちが化粧品を「選ぶ」という行為は、単なる美容のためだけではなく、地球規模の課題解決につながる一歩でもあるのです。
化粧品は「環境破壊の一因」になっている


化粧品は顔を美しく彩る一方、環境破壊の一因にもなっています。その理由を紐解いていきましょう。
そもそもカーボンフットプリントとは?
カーボンフットプリントとは、商品やサービスが生み出され、使われ、廃棄されるまでの過程で排出するCO₂などの温室効果ガスをトータルで見える化する仕組みです。
化粧品の場合、単に「原材料が環境にやさしいかどうか」だけではなく、製造過程や輸送、使うときのエネルギーまでが影響します。
化粧品が排出する“意外なCO₂”
コスメのライフサイクルを詳しく分解してみると、原料調達から最終的な廃棄まで、実に6つもの段階で大量のCO₂が関わっていることが明らかになります。
原料の生産
化粧品の原料となる成分の生産段階から、既に大量のCO₂が排出されています。石油由来の合成成分であるシリコーンやパラベンなどの防腐剤は、石油の精製過程で多くのエネルギーを消費しています。
一方、「自然派」として人気の植物由来成分も決して環境負荷がゼロではありません。
アルガンオイルやシアバターなどの植物性オイルの生産には、広大な農地が必要で、そこには肥料の製造・散布、農機具の稼働、灌漑システムの運用など、多くの工程でCO₂が発生します。
さらに、希少な植物成分を求めて世界各地から原料を調達する際の輸送コストも無視できません。南米のアマゾンから調達される植物エキスや、ヒマラヤ産の薬草など、遠方からの原料ほど輸送によるCO₂排出量は増加します。
製造工程
化粧品の製造工程は、想像以上にエネルギー集約的な産業です。乳化、均質化、加熱、冷却、混合といった複数の工程を経て製品が完成しますが、これらの工程では大量の電力を消費します。
特に、クリームやローションなどのエマルジョン製品では、油分と水分を安定的に混合させるために高温での加熱処理が必要です。また、品質管理のための無菌環境維持や、一定温度での保管も継続的なエネルギー消費を伴います。
容器包装
容器包装の影響は、材質によって環境負荷が大きく異なり、選択する素材が環境への影響を左右します。
プラスチック容器は軽量で加工しやすい反面、石油依存度が高いです。特に、複雑な形状のコンパクトケースやポンプ式ボトルでは、製造時のエネルギー消費がさらに増加します。
ガラス容器は高級感があり、リサイクル性に優れていますが、何より重量があるため輸送時のCO₂排出量が増加します。一方で、適切にリサイクルされれば長期的な環境負荷は軽減されます。
輸送距離と方法
化粧品の輸送方法は、そのCO₂フットプリントに決定的な影響を与えます。輸送手段ごとのCO₂排出量を比較すると、その差は驚くほど大きいものです。
船舶輸送
- 1トンの荷物を1km運ぶときのCO₂排出量は 約10~15g
- 大量輸送に適しており、環境負荷が比較的低い
航空輸送
- 同条件で 約500~600gを排出
- 船便の 約40倍のCO₂排出量
また、国内輸送においてもトラック輸送が主流ですが、積載率や配送ルートの効率性によってCO₂排出量は大きく変わります。
近年注目されている「地産地消」の化粧品は、こうした輸送によるCO₂削減効果が期待できる一方で、小規模生産による製造効率の悪さというトレードオフも存在します。
消費者の使用
消費者による使用段階でのCO₂排出は、意外に見落とされがちですが、カーボントラストなどの報告から、実は製品全体のライフサイクルにおいて無視できない割合を占めています。
クレンジングや洗顔時のお湯の使用は、給湯のためのエネルギー消費に直結します。1回のクレンジングで平均2-3リットルのお湯を使用し、これだけで約0.5kgのCO₂が発生します。年間を通じて計算すると、一人当たり約180kgものCO₂がスキンケアによる給湯で排出されている計算になります。
ヘアケア製品の使用も同様で、シャンプー後のドライヤー使用時間が長いほどCO₂排出量は増加します。平均的なドライヤー(1200W)を10分間使用すると約0.12kgのCO₂が発生し、毎日使用すれば年間約44kgのCO₂排出となります。
さらに、使用頻度や使用量も重要な要素です。必要以上に多くの化粧品を使用したり、使い切る前に新しい製品を購入する習慣は、間接的にCO₂排出量を押し上げる要因となります。
廃棄
化粧品容器の廃棄段階では、処理方法によってCO₂排出量が大きく変わります。適切な分別とリサイクルが行われるかどうかが、環境負荷の決定的な分かれ道となります。
プラスチック容器をリサイクルした場合、新規製造と比較して約70%のCO₂削減効果がありますが、焼却処分された場合は1kg当たり約2.3kgのCO₂が発生します。しかし、複数の素材が組み合わされた化粧品容器(プラスチック本体にアルミラベル、ゴム製パッキンなど)は分離が困難で、結果的に焼却処分される場合が多いのが現実です。
ガラス容器は理論上は100%リサイクル可能ですが、色付きガラスや特殊加工されたガラスは分別の難しさから、実際のリサイクル率は60-70%程度にとどまっています。
また、中身が残った状態での廃棄は、内容物の焼却による追加的なCO₂発生だけでなく、有害物質の発生リスクも伴います。使い切ってから適切に分別廃棄することが、環境負荷軽減の重要なポイントとなります。
こうして見ると、1本の化粧品の裏側に“見えないCO₂”が存在することがわかります。
動物実験を禁止している企業も多い
さらにエシカルな観点では、「動物実験をしない」ことも欠かせません。ヨーロッパ連合では2013年に化粧品に関する動物実験が全面禁止となり、以降は原料・完成品ともに動物実験を伴う製品は市場に出せなくなりました。
こうした流れを受けて、日本企業でも自主的に動物実験を廃止する動きが進んでいます。たとえば、資生堂は2013年に動物実験を廃止し、代替法の開発や社外機関との連携を強化しています。ファンケルも創業当初から動物実験を行わない方針を掲げており、「アニマルフリー」の姿勢を一貫して示してきました。海外ブランドでは、LUSHやザ・ボディショップが早くから動物実験廃止を訴え、消費者に選択肢を提示してきた代表例です。
環境配慮と倫理的配慮は、どちらか一方だけでは不十分です。肌にやさしい成分を選ぶことと同じくらい、動物にも地球にもやさしい姿勢を選ぶことが、“未来の美しさ”を守るための新しいスタンダードになりつつあります。


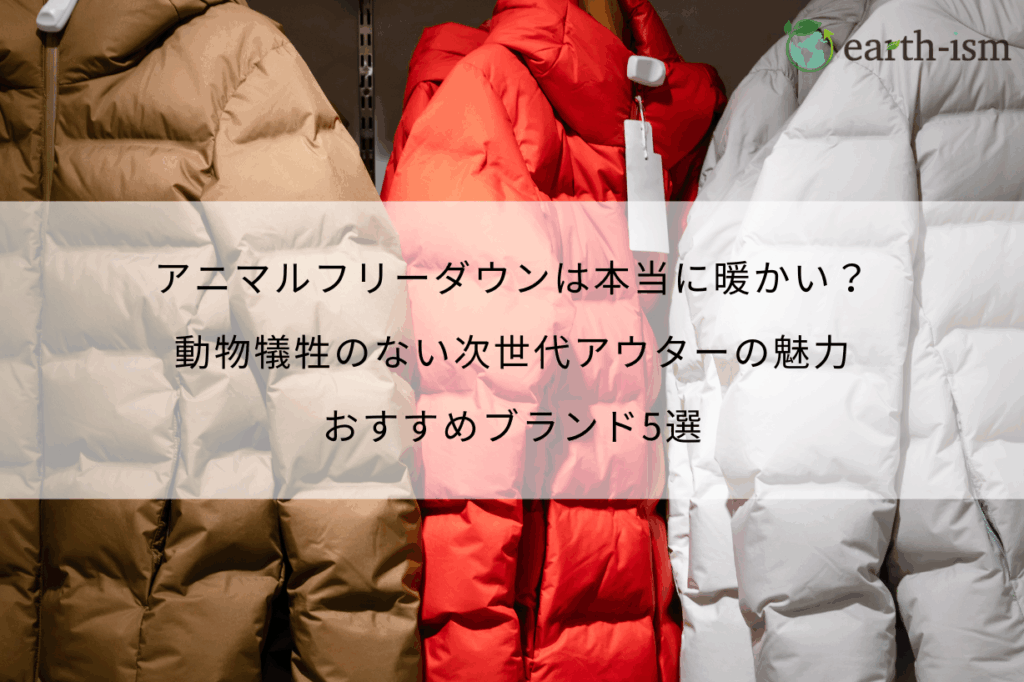
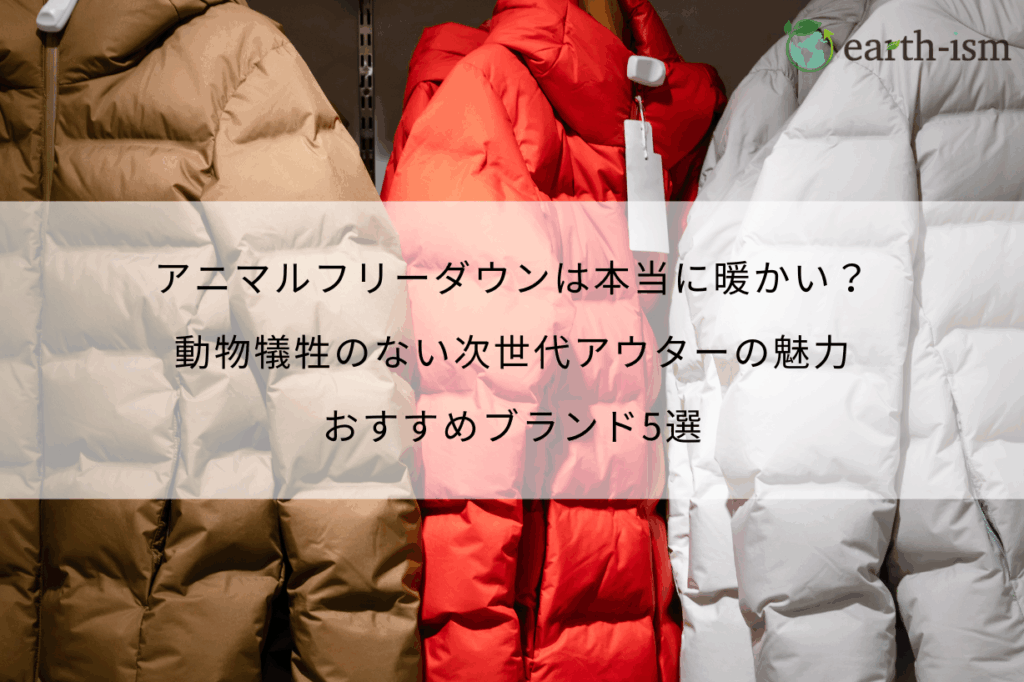
化粧品業界が取り組む脱炭素とエシカルの事例


ここでは、日本および世界の代表的な事例を紹介します。
事例1|資生堂「Sustainable Beauty Actions」
資生堂は「地球と共に美しく生きること」をテーマに、店舗での容器回収プログラム「ビューティーリサイクル」を展開しています。さらに一部製品ではLCA評価を導入し、カーボンオフセットも実施しています。
消費者が店舗に使用済み容器を持ち込むことで、資源循環に参加できる仕組みを構築している点は大きな特徴です。
事例2|LUSH「裸の真実」
LUSHは世界的に有名な“エシカルコスメ”の先駆者。シャンプーバーやバスボムなど容器レス製品を多数展開し、パッケージ由来のCO₂削減を実現しています。
さらに、原料は可能な限りフェアトレード&オーガニックにこだわり、消費者に「環境も人権も守る選択肢」を提示しています。
事例3|花王「みんなで減CO₂プロジェクト」
花王は「泡で出るボトル」の詰め替え文化を定着させ、プラスチック削減を牽引してきました。さらに商品ページにはCO₂削減量を明示し、透明性を高めています。2023年にはカーボンフットプリントの透明化に関して国際賞を受賞し、日本の企業として世界から高い評価を得ています。


私たちにできる、エシカルビューティの選択肢
では、実際に消費者である私たちができる行動にはどんなものがあるのでしょうか。
1. 詰め替え用・リフィルを選ぶ
同じブランドの化粧水や洗顔料を購入するとき、ボトルごと買うのではなくリフィルを選ぶだけで、最大70%ものCO₂削減につながるといわれています。詰め替え用はプラスチック使用量も少なく、ゴミの削減にも直結します。
特に毎日使うスキンケアやボディソープは、積み重ねると大きな差に。リフィル対応の商品を選ぶことで、「環境にやさしい行動をしている」という実感も得られます。ドラッグストアやオンラインショップでもリフィル商品は豊富に展開されているので、まずはお気に入りのブランドの“詰め替えパック”を探してみましょう。
2. パッケージに注目する
化粧品を選ぶとき、つい中身だけに目が行きがちですが、容器や箱の素材も環境に大きく影響しています。たとえば、FSC認証マークがついた紙箱は、森林資源を守るための管理基準をクリアした製品。再生PETボトルを使った容器なら、新たな石油資源の使用を減らすことができます。
ブランドの公式サイトや店頭の説明書きには、こうした「環境配慮マーク」や素材情報が記載されていることも多いです。購入前にラベルを少し確認する習慣を持つだけで、環境負荷の少ない商品を選ぶ力が自然と身についていきます。
3. 製造地・輸送方法をチェックする
同じ成分の化粧品でも、どこで作られ、どうやって運ばれてきたかによって排出されるCO₂は大きく変わります。特に空輸された輸入コスメは、船便や国内製品に比べて数十倍ものCO₂を排出することが知られています。
「Made in Japan」と書かれた製品は、輸送距離が短いため相対的に環境負荷が低くなる傾向があります。さらに最近は、地元産の植物や地域資源を原料にした“地産地消コスメ”も登場しています。地元の原料を使った製品を選ぶことは、地球環境だけでなく、地域の産業や雇用を支えることにもつながります。
4. 「使い切る」意識を持つ
環境への最大の負荷は「無駄」です。引き出しに眠ったままの未使用コスメは、製造や輸送に使われたエネルギーとCO₂を無駄にしているのと同じです。
買う前に「本当に必要か?」「今あるもので代用できないか?」と立ち止まって考えることが、最もシンプルで効果的なエシカル行動です。そして一度購入したら、最後の1滴まで使い切ることを意識しましょう。そうすれば、財布にもやさしく、地球にもやさしい美容が自然と実践できます。
5. 再生可能エネルギーで製造された製品を応援する
最近は、製造工場で再生可能エネルギーを導入しているブランドも増えています。太陽光や風力など、再生可能エネルギーで稼働する工場で作られたコスメを選ぶことは、消費者として直接「脱炭素」に貢献できる行為です。
公式サイトや商品ページには「再エネ使用」「カーボンニュートラル工場」といった表記がある場合があります。購入前にチェックしてみると、意外と身近なブランドが取り組んでいることに気づくはずです。環境配慮型のブランドを積極的に選ぶことは、企業に「持続可能な製品づくりを続けてほしい」という意思表示にもなります。
まとめ|キレイの先に、地球の未来を描こう
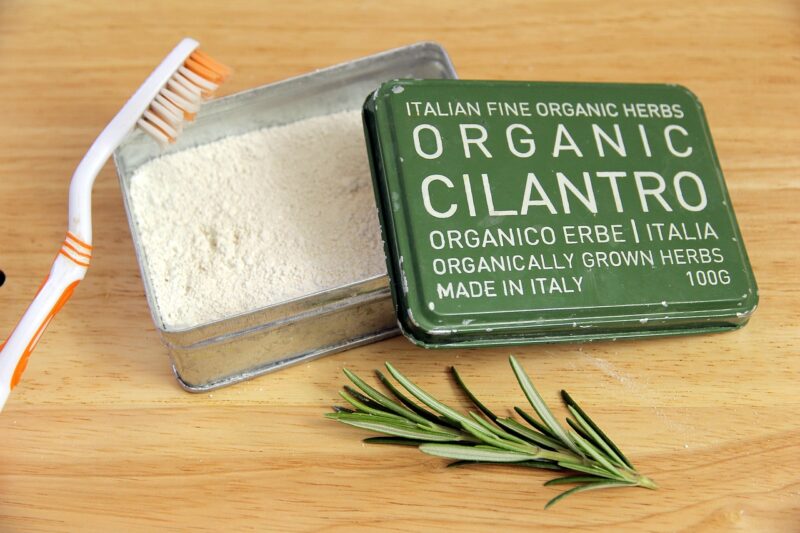
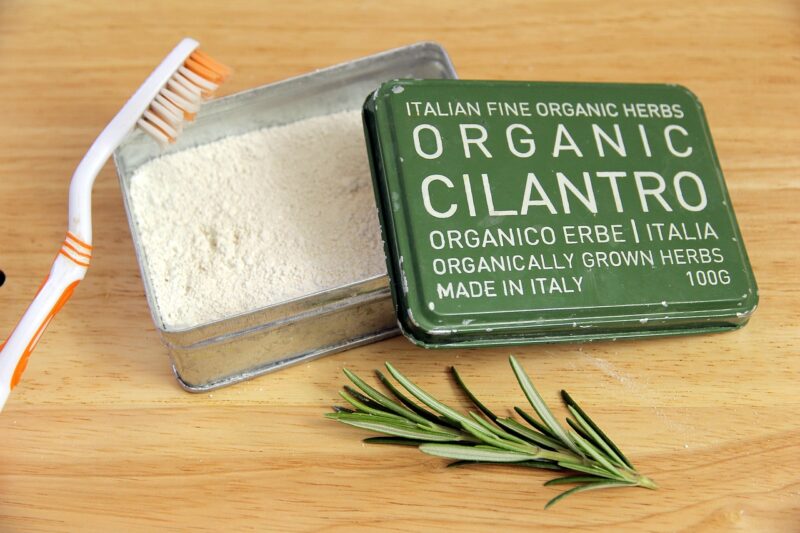
エシカルビューティは特別な選択ではなく、日々の小さな意識の積み重ねから始まります。化粧品カーボンフットプリントの日をきっかけに、自分の肌と同じくらい地球の未来を大切にする美容習慣を見直してみませんか。
「肌にいいものは、地球にもやさしい」という選択が当たり前になる世界を、私たち一人ひとりがつくっていけるのです。