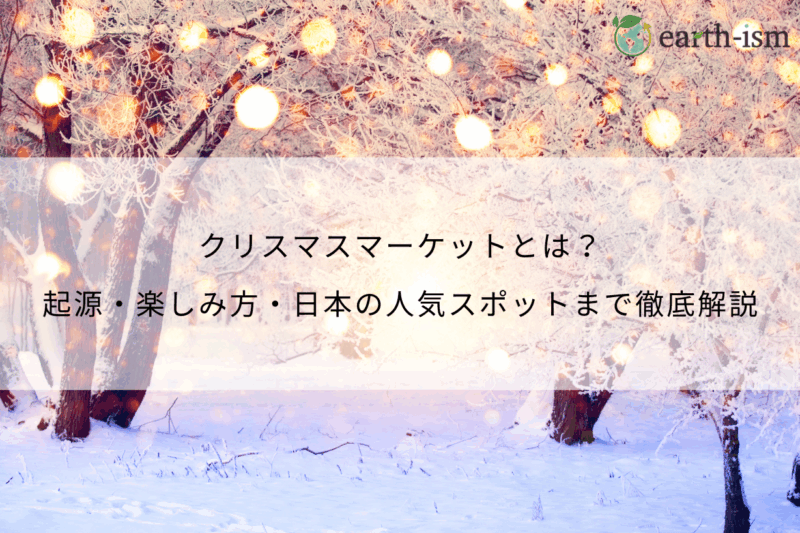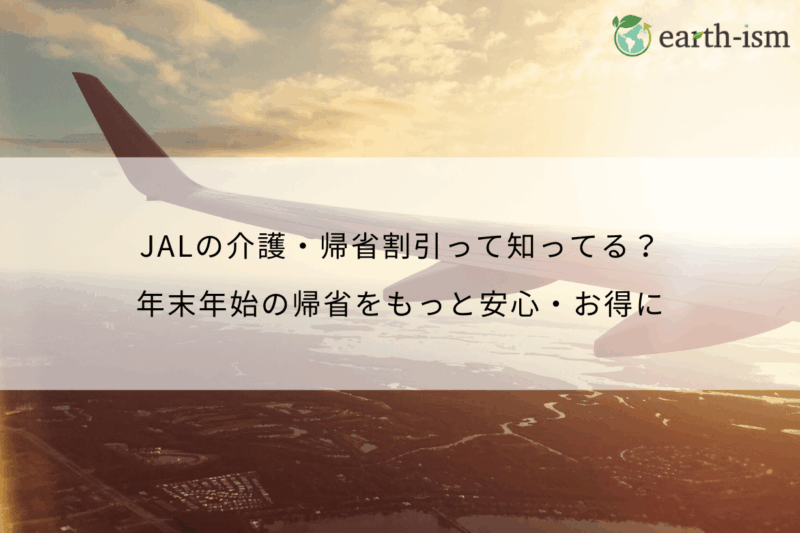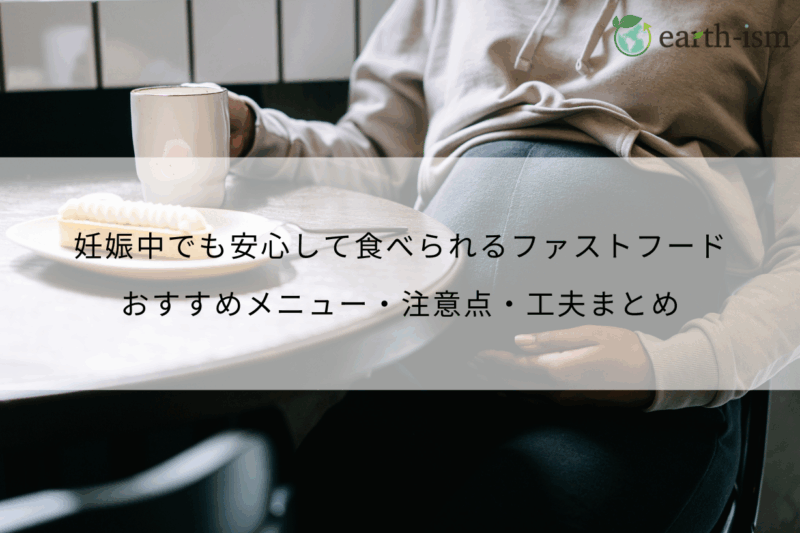【2025年版】ワーケーションとは?新しい働き方の意味・メリット・注意点を解説


Contents
コロナ禍を経て、リモートワークや在宅勤務がすっかり定着した今。「職場=オフィス」という前提は、すでに過去のものとなりつつあります。その中で注目を集めている新しい働き方が、“旅をしながら働く”というライフスタイル、ワーケーション(Workation)です。
「ワーケーションって、実際どうやるの?」「本当に仕事になるの?」
そんな疑問を抱きながらも、少しワクワクしてしまう──それがこの働き方の魅力でもあります。
本記事では、ワーケーションの意味や背景から、そのメリット・デメリット、具体的な導入方法やおすすめのエリア、実際に体験した人たちの声まで、これからワーケーションに挑戦してみたい人のために、リアルで役立つ情報をまとめました。
ワーケーションとは?|言葉の意味と背景


「ワーケーション(Workation)」とは、「Work(仕事)」と「Vacation(休暇)」を掛け合わせた造語で、観光地やリゾート地など日常とは異なる場所で、仕事と休暇を両立させる働き方を指します。
もともとは欧米を中心に広がった概念ですが、日本では2020年の新型コロナウイルスの影響によりリモートワークが一気に普及したことで、注目が集まるようになりました。
企業にとっては「人材の柔軟な働き方支援」や「地方との関係人口づくり」、個人にとっては「心身のリセット」や「新しい価値観との出会い」など、さまざまな可能性を秘めた働き方です。
また、近年は国や自治体も積極的にワーケーションの受け入れを進めており、補助金や専用施設の整備など、インフラ面でも徐々に整備が進んでいます。
ワーケーションは意味ない、と言われるけど本当?
SNSや職場で「ワーケーションって結局“遊び”じゃないの?」といった声を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。確かに、場所だけを変えて普段通りの業務をこなすだけでは、期待していたような変化や効果を感じにくいかもしれません。
しかし、重要なのは“どう活かすか”という視点です。目的や設計があいまいなまま導入すると、「意味がなかった」と感じるのは当然ともいえます。
たとえば、「集中できる環境で資料作成に専念する」「チームでの合宿形式でアイデアを出し合う」「心身を整えて次のフェーズに備える」など、自分なりの“意図”をもって取り組むことで、ワーケーションは一気に意味を持ち始めるのです。
言い換えれば、ワーケーションとは“ただの手段”。その手段を有効にできるかどうかは、自分自身の工夫と目的設定にかかっている──というわけです。
ワーケーションが普及しない理由|“理想”と“現実”のあいだで


ワーケーションは耳ざわりのよい言葉として注目されてきましたが、実際に制度化・活用されている企業はまだ少数派です。背景には、いくつかの現実的な課題が存在しています。
まず第一に、日本の企業文化の中では「仕事=会社でするもの」という価値観が根強く残っています。目の前にいない=働いていないのでは?という無意識の疑念が、上司や同僚の間に残っていることも珍しくありません。
また、制度として導入するには、労務管理・セキュリティ・評価体制といった法務・人事面での整備が必要です。特に中小企業では、リソース不足から踏み切れないケースも多いのが現状です。
さらに、社員側にも「楽しそうだけど、うちの職場では無理そう…」という心理的ハードルもあります。制度が整っても、組織全体のマインドセットが変わらなければ、活用は進みません。
ワーケーションのメリット|働きながら得られる“もうひとつの価値”
ワーケーションの最大の魅力は、単に「場所を変えて働ける」だけではありません。
新しい環境に身を置くことで、心身のリフレッシュや仕事の質の向上、価値観の転換といった、さまざまな効果が期待できるのです。
1. 心身のリフレッシュと生産性の向上
自然に囲まれた場所で働くことで、五感が刺激され、思考がクリアになる感覚を覚える人は少なくありません。都市の喧騒から離れた空間では、ストレス軽減や集中力アップに効果があるという研究もあります。特にクリエイティブな業務を担う人にとっては、刺激のある風景や音、空気が“仕事の原動力”になります。
2. ワークライフバランスの再設計
「9時から5時まで机に向かう」という型を離れ、自分の生活リズムや心地よいスタイルで働く時間を設計できるのもワーケーションの魅力です。仕事と余暇をうまく切り替えることで、心のゆとりが生まれ、結果的にパフォーマンスが安定するという声も上がっています。
3. 新たなつながりと学びのきっかけに
滞在先での人との出会いや地域文化との接点は、視野の広がりや人間関係の再構築にもつながります。「いつも同じメンバー、同じ空間」から一歩離れてみることで、思いがけない気づきが生まれることもあるでしょう。
ワーケーションのデメリット・注意点|甘くない現実もある


ワーケーションは魅力的な働き方ですが、誰にでも向いている万能なスタイルというわけではありません。理想と現実のギャップに戸惑う声も多く、事前にリスクや課題を知っておくことが成功のカギとなります。
1. 通信・作業環境の不安定さ
どんなに風景がよくても、Wi-Fiが不安定では仕事になりません。山間部や離島などでは、速度が遅い、接続が不安定、電源が確保できないといった問題が発生しがちです。Zoom会議やファイルのやりとりが多い業種では致命的な障害になることもあるため注意しましょう。
2. 「仕事」と「休暇」の境界が曖昧になる
旅先での開放感に流され、つい仕事の手が緩む人もいれば、逆に「常にメールをチェックしていて全然休めなかった」という人も。自己管理力やオンオフの切り替えが苦手な人には、逆に疲れる働き方になる可能性があります。
3. チームや上司との関係性への影響
物理的に離れていることで、急な対応や意思疎通が遅れることへの不安を感じる上司・同僚もいるかもしれません。とくにワーケーションが制度化されていない職場では、「遊んでいると思われないか?」といった心理的なハードルも存在します。
ワーケーションを成功させるコツ|準備・選び方・注意点をチェック
「ワーケーション=気ままな旅」と思われがちですが、成功のカギは“準備力”と“計画性”にあります。
快適で実りある滞在にするために、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。
1. 通信環境と作業スペースの確認は最優先!
まずチェックすべきは、Wi-Fiの速度と安定性。特にZoom会議や大容量データのやりとりがある人は、速度測定サイトなどで事前に調べておくと安心です。
加えて、作業に適したデスクや椅子があるかも要確認。ベッドの上で丸まって仕事……では、集中力が持続しにくくなってしまいます。
2. 仕事のスケジューリングを“ゆとり設計”に
普段通りに詰め込んだスケジュールだと、せっかくの環境を楽しむ余裕がなくなってしまいます。
移動日や到着初日はゆるめに設定し、早朝や夜の静かな時間を仕事タイムに充てるなど、場所に合わせた時間設計を心がけてみましょう。
3. 服装・持ち物・防災面もチェック!
自然の中でのワーケーションは、気温差や天候の急変も起こりやすいもの。
着脱しやすい服装や羽織もの、急な雨に備えた防水グッズ、そしてモバイルバッテリーや延長コードも必須アイテムです。
また、地域によっては防災意識も必要なので、避難場所の把握なども忘れずに。
ワーケーションにおすすめの場所・宿泊施設|国内の注目スポットは?


「どこでワーケーションするのがいいの?」という声にお応えして、初心者でも挑戦しやすく、仕事と休暇のバランスがとりやすい国内スポットをご紹介します。都市圏からアクセスしやすく、インフラやWi-Fi環境が整っている場所を中心にピックアップしました。
1. 長野・軽井沢|避暑地×集中空間の定番
首都圏から新幹線で1時間強。豊かな自然と涼しい気候が魅力の軽井沢は、“静けさの中でじっくり仕事をしたい人”にぴったりの場所です。 「NEST INN KARUIZAWA」や「星のや軽井沢」など、ワーケーションプランを用意した宿泊施設も多く、滞在型リモートワークにも対応しています。
2. 和歌山・白浜|海を眺めながらの“ととのう”時間
白浜町は、和歌山県が「ワーケーション先進地」として力を入れている地域。オーシャンビューのカフェやコワーキングスペース、温泉つき宿泊施設などが整備されており、“海に癒やされながら働きたい人”におすすめです。
IT企業のサテライトオフィスも集まっており、ビジネス拠点としての注目度も高まりつつあります。
3. 北海道・ニセコ|四季の自然を満喫しながら働ける
冬はスキー、夏はラフティングや登山が楽しめるニセコは、“アウトドア好きのリモートワーカー”に愛される地です。近年は外国人にも人気のエリアとしてインフラも充実しており、Wi-Fi完備のロッジや一棟貸しのヴィラも選択肢に。働いたあとに温泉で一息つく、そんな理想的なリズムが実現できますよ。
まとめ|“旅する働き方”は、人生の視点を変えてくれる


ワーケーションは、ただの「働きながらの旅行」ではありません。それは、自分の働き方や暮らし方を問い直す“選択のひとつ”なのです。
非日常の空間で仕事に向き合うことで、日々の思考パターンがほぐれたり、自分の内側に眠っていたアイデアや感情が顔を出してくることがあります。普段とは違う“空気”の中で過ごすことで、あなたの中の優先順位が変わるかもしれません。
もちろん、準備や環境調整は必要ですし、万能な働き方ではありません。けれど、ひとつのきっかけとして、今の自分を見つめる時間を持てるのは大きな財産になるはずです。
これからの時代、「働く」と「生きる」はもっと近づいていきます。だからこそ、自分自身にとっての“ちょうどいい距離感”を探す旅に、ワーケーションを取り入れてみましょう。