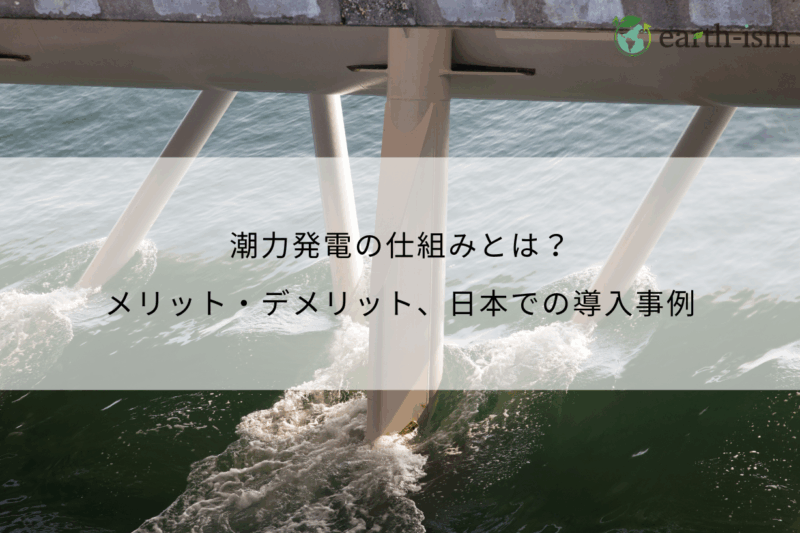拡大生産者責任(EPR)とは?仕組み・法制度・企業の対応まで徹底解説


Contents
「拡大生産者責任(EPR)」という言葉を、環境問題や法制度の文脈で目にする機会が増えてきました。これは、製品を製造・販売した企業が、使用後や廃棄時の処理まで責任を持つべきだという考え方に基づく制度です。
ごみ問題、資源枯渇、海洋プラスチック。こうした環境課題が深刻化する中で、単に「モノを売る」だけでは企業責任は果たせません。むしろ、「売ったあとに何が起こるか」にまで目を向ける姿勢こそが、これからの社会では問われていきます。
この記事では、EPRの基本概念から、日本と海外の制度の違い、どんな業界が影響を受けるのか、企業に求められる対応や事例まで、実務にもつながる視点でわかりやすく解説します。
拡大生産者責任(EPR)とは?|定義と基本的な考え方


まずは、拡大生産者責任の意味や背景、その考え方の根底にある哲学について、しっかり押さえておきましょう。ここを理解しておくことで、後の法制度や企業対応の話もすっと入ってきます。
「使ったあとも、作り手が責任を持つ」という制度設計
EPR(Extended Producer Responsibility)とは、製品の“ライフサイクル全体”に対して、製造者・販売者が責任を持つべきであるという原則を意味します。この概念は1990年代に欧州を中心に広まり、現在では国際的に認知された環境政策のひとつです。
従来、廃棄物は「消費者の責任」として処理されてきました。ですが、どのような素材を使い、リサイクルしやすい設計にするか、回収体制を整えるかといった要素は、製造段階での判断に大きく依存します。
つまり、「最後まで責任を持つことで、最初の選択が変わる」ことが、拡大生産者責任の本質です。


なぜ今、EPRが注目されているのか
近年、EPRが再び注目されている背景には、サーキュラーエコノミー(循環型経済)への移行があります。地球資源に限りがある中で、「作って、使って、捨てる」直線的な経済から、「回して、再利用して、価値を保つ」社会への転換が求められています。
この循環型経済を機能させるうえで、EPRは中核的な仕組みとなります。また、ESG投資やSDGsの浸透により、環境対応を怠る企業はリスクとして評価される時代にもなりました。
企業にとってEPRは、単なる法的義務ではなく、持続可能性への姿勢を示す戦略でもあるのです。


法制度としてのEPR|日本と世界の制度比較
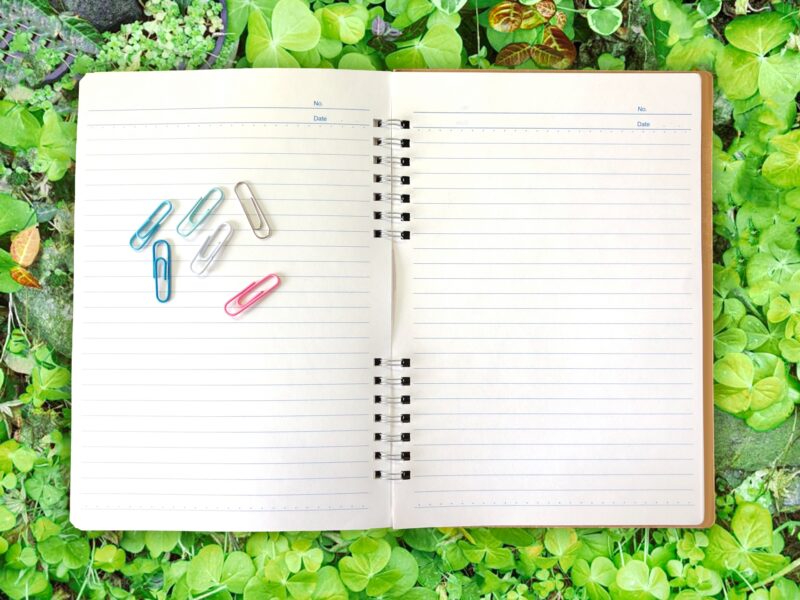
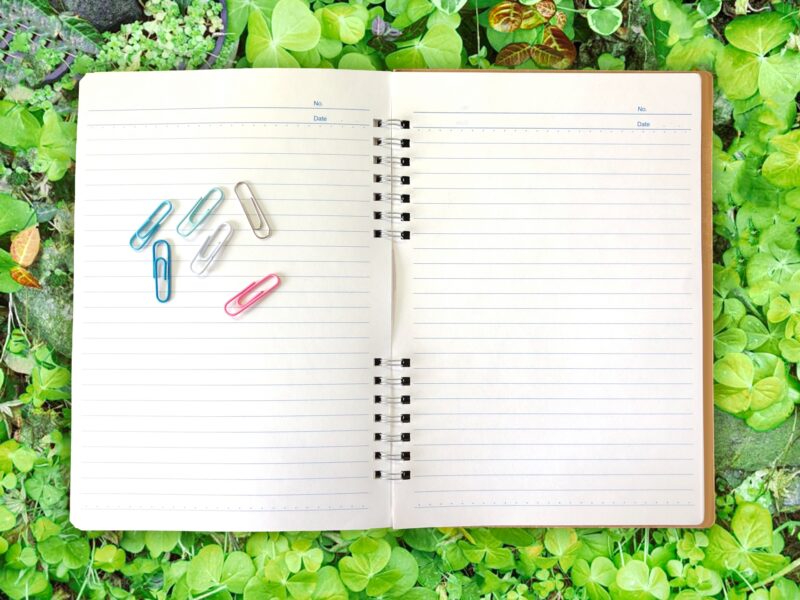
ここでは、日本国内におけるEPR制度の実態を確認した上で、EUやアメリカ、アジア諸国の動向と比較してみましょう。国際的な視野を持つことで、今後の日本企業に求められる対応のヒントが見えてきます。
日本における制度的位置づけ(家電リサイクル法、容器包装リサイクル法など)
日本では、拡大生産者責任の考え方がすでにいくつかの法律に組み込まれて制度化されています。代表的なものは以下の通りです。
- 家電リサイクル法(2001年施行)
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなどの特定家電について、製造業者がリサイクル費用を一部負担し、適正な回収・再資源化を進める法律です。 - 容器包装リサイクル法(1995年施行)
ペットボトルや紙パック、プラスチック容器など、製品を包む素材のリサイクル費用を、販売者や製造者が負担します。 - 小型家電リサイクル法(2013年施行)
携帯電話やゲーム機など、小型電子製品の回収・リサイクルを促進する仕組みです。市町村と民間業者の協力も特徴です。
これらの法律は、製造・販売した企業に対して“排出後の責任”を明確に課す制度として位置づけられ、EPRの実践例といえます。
EU・アメリカ・アジアの制度動向と比較
日本が「法制度化されたEPR」の先進国である一方、EUはさらに強固かつ包括的なアプローチを取っています。
特に注目すべきは、EUの「循環経済パッケージ(Circular Economy Package)」や「グリーンディール政策」です。これらの中で、EPRは単なる廃棄物管理ではなく、製品設計から回収・再資源化まで一貫した責任体制を求める要素として位置づけられています。
一方、アメリカでは州ごとに制度導入が進んでおり、カリフォルニア州などはEPRに基づく拡大包装回収法(EPR for Packaging)を検討中です。アジアでは韓国・台湾・中国などでも独自のEPR制度が整備されつつあります。
つまり、世界各国がそれぞれの事情に合わせたEPRの仕組みを構築し、国際的な標準化も進みつつあるのが現状です。
対象となる業界・製品|EPRが影響する領域とは?


ここでは、現在EPRの対象となっている主な業界や製品カテゴリー、そして今後規制の対象として注目されている分野について解説します。自社が関係している領域があるかどうかを確認するうえでも、重要な視点となるでしょう。
家電・自動車・容器包装・電子機器などの具体例
現在、EPR制度が特に活用されているのが、使用後の処理が困難だったり、環境負荷が高かったりする製品分野です。代表的なものは以下の通りです。
- 家電製品(テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコンなど):
日本では「家電リサイクル法」により、メーカーにリサイクル義務が課されています。 - 自動車:
使用済み自動車の再資源化を義務づける「自動車リサイクル法」により、エアバッグ・フロン類・シュレッダーダストの処理責任が発生。 - 容器包装類(ペットボトル、缶、プラ容器、紙パックなど):
リサイクル費用を製造業者が拠出することで、地方自治体の回収を支える仕組みが構築されています。 - 電子機器・電池:
資源の回収効率が低く、有害物質も含むため、EUの「WEEE指令」ではEPRを基盤とした厳格な回収・処理義務が存在します。
これらはすべて、製造段階から「その後の責任」まで含めて設計・流通を考えるべき分野です。
新たに規制が検討されている製品群(繊維・電池・プラスチック製品)
近年では、これまで制度の対象外とされてきた製品群にも、EPRの導入を求める声が高まっています。中でも注目されているのが以下の分野です。
- 繊維・衣料品:
アパレル産業の大量廃棄・大量生産構造が問題視されており、EUでは2025年までに衣料のリサイクル回収義務を導入予定。日本でもユニクロなどが自主的に回収を始めています。 - 使用済み電池・充電式電池:
EV普及に伴い、リチウムイオン電池の安全な回収・再利用体制が重要視されており、今後の規制強化が見込まれています。 - プラスチック製品全般:
マイクロプラスチック問題を受けて、使い捨てプラスチックだけでなく、製品型プラスチックへのEPR拡張も議論されています。
つまり、EPRの対象は今後ますます広がり、業界を問わず「自社製品の未来」を見直す必要性が高まっているのです。
企業に求められる対応|“義務”だけでなく“戦略”として捉えるには?


EPRは法的な“義務”として語られることが多いですが、実はそれだけではありません。EPRの枠組みを単なる負担と見るのではなく、サステナビリティ戦略の一環として活用する視点が、今の企業には求められています。
この章では、企業が実際に果たすべき対応の内容とともに、それをどのように企業価値の向上やESG経営に活かしていくかについて見ていきましょう。
リサイクル費用の負担・回収義務・表示制度
EPRに基づき、企業が求められる主な対応は以下の3つに分類されます。
- リサイクル費用の負担
製品の廃棄・再資源化にかかる費用を、一定の割合で製造業者・販売業者が拠出します。これは「費用負担型EPR」とも呼ばれ、容器包装リサイクル法などが該当します。 - 製品回収・引き取り義務
使用済み製品を自社または指定ルートで回収し、再資源化・適正処理を行う義務。家電リサイクル法のように「物理的責任型EPR」として制度化されているものもあります。 - 環境負荷に関する表示や設計対応
製品にリサイクルマークを付ける、分解しやすく設計するなど、使用後を見据えた製品設計・情報開示も義務化の対象です。
これらは、制度として整備されていなくても、業界ガイドラインや自主規制として求められるケースも増えており、全業種にとって無関係ではいられません。


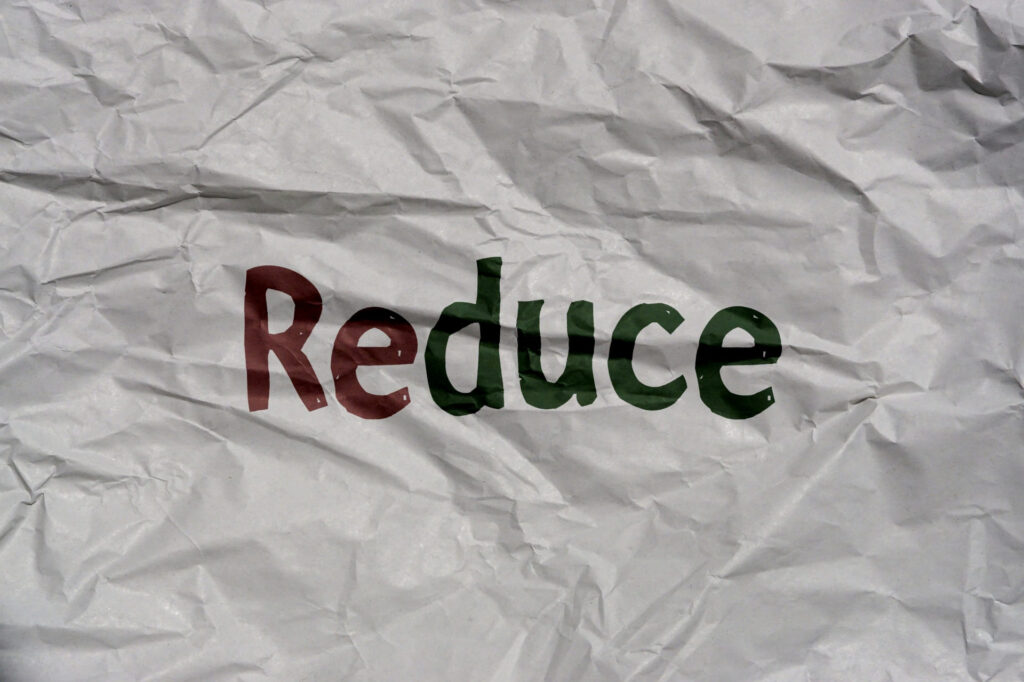
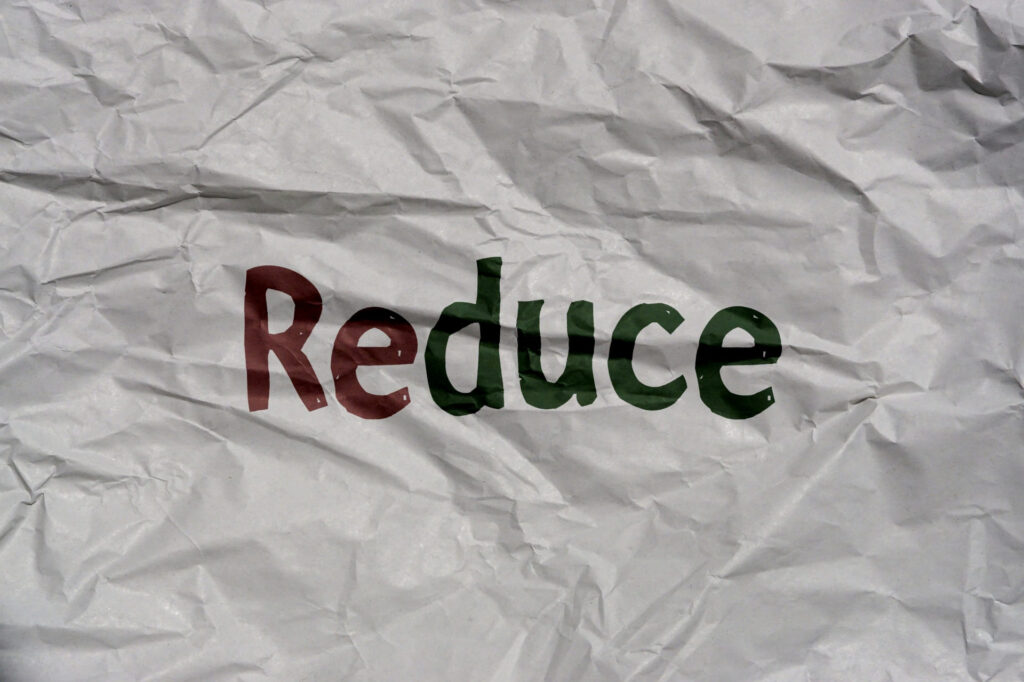
EPRを活用した企業ブランディング・CSR戦略
EPR対応は、単に義務を果たすことにとどまらず、企業価値の訴求にもつなげることができます。
たとえば、下記の例が挙げられます。
- 回収ボックスの設置やリサイクルキャンペーンによって顧客との接点を創出
- 製品の分解・再生工程を公開することで透明性の高い企業姿勢を打ち出し
- 環境ラベルを取得してサステナブルなブランドイメージを形成したりといった活用が可能
特にZ世代を中心とした消費者層は、「企業がどのように環境問題に取り組んでいるか」を重視しており、EPRへの積極的な対応が“選ばれる理由”になる時代に入りつつあります。
まとめ|“回す責任”が問われる時代に、企業はどう応えるか
拡大生産者責任(EPR)は、「作る責任」だけでなく「終わらせる責任」も含めて企業に問う仕組みです。廃棄物処理やリサイクルという言葉から連想される「面倒なコスト」ではなく、製品ライフサイクル全体をどうデザインするかという発想が、その本質にあります。
制度としてのEPRはすでに多くの国で整備が進んでおり、日本でも複数の法律に組み込まれています。今後はさらに、繊維製品やバッテリーなど、新しい分野への拡張も進むでしょう。企業は「待ちの姿勢」ではなく、「備え、活かす視点」を持つことが求められています。
そして、EPRはただの義務ではなく、サステナブルな企業ブランドを築くチャンスでもあります。
法令対応だけでなく、顧客や社会に対して「私たちは責任を果たす存在です」と伝える姿勢そのものが、次の信頼と選ばれる理由になるのです。