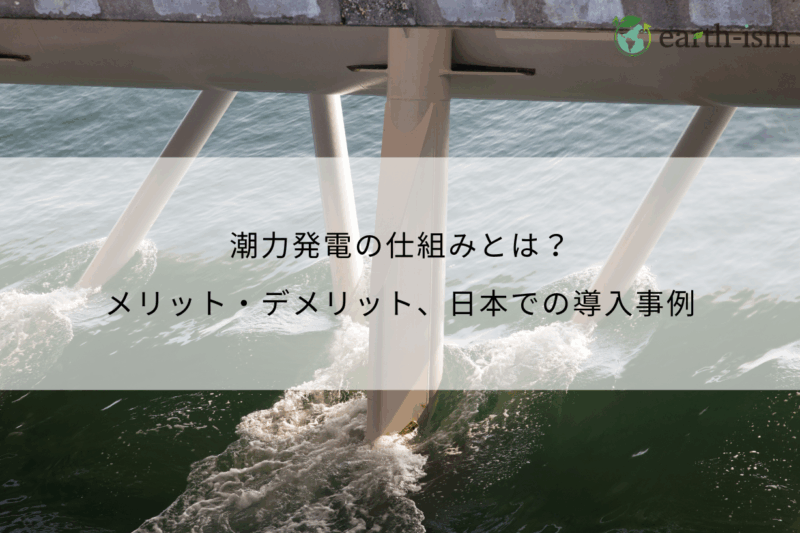カーボンニュートラルとは?環境省の目標・政策・補助金支援まとめ【2025年最新】
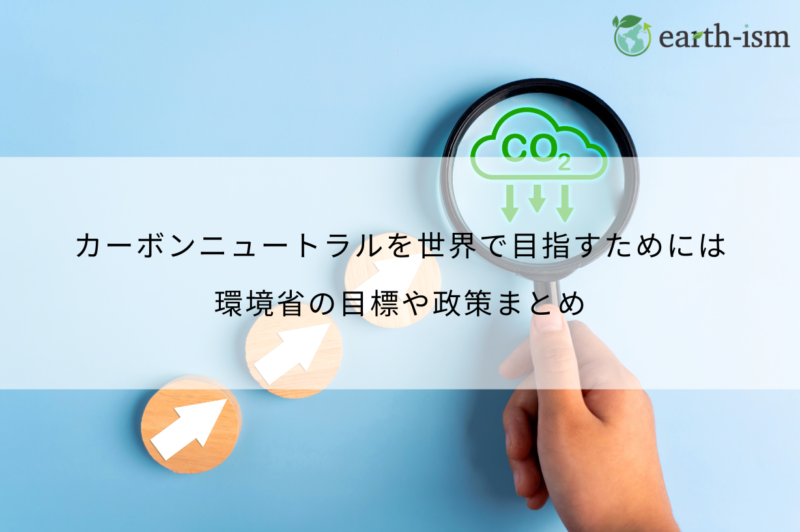
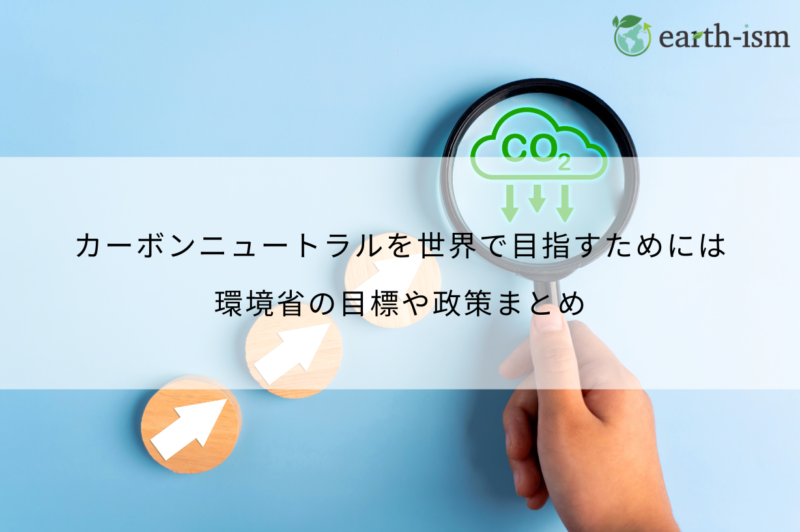
Contents
地球温暖化の問題に対し、カーボンニュートラルという言葉がごく当たり前に使われるようになっています。一般消費者レベルでは直接関係がないと思われるかもしれませんが、国や地域、会社では、より二酸化炭素削減に向けた社会を実現しようとしています。
この記事では、環境省をはじめとした日本の動向、会社や自治体への支援などについて、現在の状況を解説します。カーボンニュートラルへの動きはダイナミックなスピードで多彩に展開しています。その概要について見ていきましょう。


そもそもカーボンニュートラルとは?│脱炭素社会の基本概念


当然のように使われているカーボンニュートラルですが、そもそもどのような意味でしょうか。改めて確認していきましょう。
カーボンニュートラルの意味と背景
カーボンニュートラルの日本語訳は「炭素中立」。聞きなれない言葉ですが、カーボンは炭素のこと。ニュートラルは「中立」の意味ですから、カーボンニュートラルの直訳としては「炭素中立」となります。
カーボン、つまり炭素は自然界に広く分布する元素のひとつで、多くの有機化合物の構成要素となっています。一言でいえば生命の根源となる元素です。それほど重要なカーボンですが、カーボンを多く含む化石燃料を燃やすことで、大気中の二酸化炭素濃度が上昇し、温室効果によって地球温暖化が進んでいることが問題となっています。
二酸化炭素に代表されるのが温室効果ガスです。こでを全体としてゼロにするのが、カーボンニュートラルです。カーボンニュートラルを達成するためには、温室効果ガスの排出量の削減ならびに吸収を行わなければなりません。
世界の潮流と日本の動き
温室効果ガスによる気候変動問題の解決に向けて、2015年にパリ協定が採択されました。
その主な内容は、「世界的な平均気温上昇を工業化以前に比べて2度より低く保つことを目標とするとともに、1.5度に抑える努力を追求する」「主要排出国を含むすべての国が削減目標を5年ごとに提出、更新する」などが挙げられます。
この実現に向けて世界が取り組みを進めていて、「2050年カーボンニュートラル」という目標を掲げています。日本政府は2020年に、所信表明演説でカーボンニュートラル宣言を行い、2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするとしています。


環境省が掲げるカーボンニュートラルの目標


日本でカーボンニュートラルの問題などに中心となって活動しているのは環境省です。その活動概要は次のとおりです。
2050年までの中長期ビジョン
前述のとおり、2020年、日本は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにすることを宣言しました。その後2021年には、2030年度に温室効果ガスを2013年度から46%削減することを目標とし、さらに50%に向け挑戦することを表明しています。
さらに2013年度から比べ、2035年度には60%、2040年度には73%削減することを目指すとしています。
地域と企業の連携による“地域循環共生圏”
カーボンニュートラルの実現のために2018年に掲げられたのが地域循環共生圏です。
2050年までの目標を達成させるためには、国と地方の協力が欠かせません。「地域の多様な資源を最大限に活用しながら、環境・社会・経済の同時解決を目指す」のが、地域循環共生圏であると環境省は定義しています。
都市でも地方でも、カーボンニュートラルに対して多くの課題があることは共通しています。それぞれの地域が自ら課題を解決し、得意な分野で地域同士のネットワークをつくっていく。
そうすることで、地域も国全体も持続可能となっていく「自立・分散型社会」が地域循環共生圏であり、日本が目指す姿だとされています。
環境省が実施する主な政策・施策【2025年版】


続いて、より具体的な最新の政策などを見ていきましょう。
1.地域脱炭素ロードマップ
内閣官房長官を議長とする「国・地方脱炭素実現会議」が設置され、具体策を示すために策定されたのが、地域脱炭素ロードマップです。
これは地域を主役とし、「地域の魅力と質を向上させる地方創生に資する地域脱炭素の実現」を目指すもの。
再生エネルギーなどの地域資源を最大限に活用し、地域の経済活性化、地域課題の解決に貢献できるとしていて、ロードマップの概要には「地方からはじまる、次の時代への移行戦略」とうたわれています。
もちろん、さまざまな課題も想定されることから、国も人材、情報、資金の面から、積極的に支援を行うと記されています。
ロードマップでは、2030年までに少なくとも脱炭素先行地域を100ヵ所以上創出、地域の脱炭素モデルを全国に広げ、2050年を待たずに脱炭素達成を目指すとも明記されています。
2.グリーン成長戦略
カーボンニュートラル実現のためには、エネルギーや産業部門の構造転換、大胆なイノベーションの創出なども必要。そのため、関係省庁が連携して策定されたのが、グリーン成長戦略です。
この戦略では、成長が期待される14の重要分野について、実行計画が策定され、国として高い目標を掲げて、可能な限り具体的な見通しが示されています。
大まかな分野として、「エネルギー関連産業」「輸送・製造関連産業」「家庭・オフィス関連産業」、そして「企業の前向きな挑戦を後押しする政策ツール」があげられています。
例えば、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー、電気自動車などはすでに身近なものでしょう。そのほかの例については、環境省のサイトで確認可能です。
3.グリーンイノベーション基金
グリーン成長戦略の中の分野「企業の前向きな挑戦を後押しする政策ツール」の中の予算として含まれているのが、このグリーンイノベーション基金です。
経済産業省などが実施し、グリーン成長戦略であげられている重点分野に取り組む事業者や研究機関などを支援するもので、3兆円近い予算が計上されています。
その内容は、洋上風力発電の低コスト化、次世代型太陽電池の開発、CO2の分離回収等技術開発、次世代蓄電池・次世代モーターの開発、次世代航空機の開発など、まさに次の世代のイノベーションに関係するものばかりです。
補助金・支援制度の一覧│企業・自治体が使える国の制度


カーボンニュートラルをめぐる国の動向、政策などについて触れてきましたが、実際に自治体や企業が参加するには、どのような方法があるのでしょうか。いくつか例を見ていくことにしましょう。
脱炭素先行地域支援交付金
前述の地域脱炭素ロードマップで紹介したとおり、2030年までに100ヵ所以上創出することが目標とされている脱炭素先行地域。2025年5月9日現在、115市町村の88提案が選定されています。
脱炭素先行地域に選定されている地方公共団体などに対して、地域の脱炭素への移行を進めるために交付されるのが、この交付金です。
対象事業は専門的な分野も含まれますが、太陽光、風力、バイオマスなど、再エネ発電設備の導入は必須となっています。
中でも、住宅の屋根などに太陽光発電を設置する事業などは、脱炭素の基盤となる「重点対策」とされています。
意欲的に脱炭素の取り組みを行う地方公共団体などを支援することで、全国に脱炭素を速やかに広げる(環境省は「脱炭素ドミノ」という言葉を使っています)のが、この交付金の目的とされています。
エコアクション21
エコアクション21は、環境省が策定した日本独自の環境マネジメントシステムです。
カーボンニュートラルにより、マーケットは大きく変化。企業は、社会や取引先などからも、環境対策への取り組みが問われます。エコアクション21は、環境経営の認証・登録制度であり、企業価値を高めることができます。
具体的には、まず自社企業の環境対策を把握し、環境経営を実践。その取り組みを評価して、次の改善へと進みます。これらについて「環境経営レポート」を作成することで、環境に対しての取り組みだけではなく、透明性も保証されるわけです。
エコアクション21は、初めての申請でも対応しやすい内容で、中小企業でも容易に取り組める環境経営システムとして注目されています。
PPAモデル
カーボンニュートラルには太陽光発電の導入が効果的であることは周知のとおりです。
太陽光発電設備の導入には「自己所有」と「第三者所有」のふたつのパターンがありますが、第三者所有のモデルのひとつがPPA(Power Purchase Agreement 電力購入契約)です。
自己所有では、初期費用の確保やメンテナンス対応が必要ですが、第三者所有では、自治体の所有地に事業者が発電設備を設置、管理するため、初期費用やメンテナンスは不要となります。そのため自治体は太陽光発電設備導入が簡単に実施できます。
千葉市の事例では、自己所有の場合、2年間で太陽光発電設備の設置件数が18ヵ所だったのに対し、第三者所有の場合、3年間で118ヵ所となっています。
環境省の最新動向をキャッチするには?


2050年に向けた目標は紹介してきたとおりですが、国の政策などはつねにアップデートされています。
政策の更新スピードに注意
政策の根幹に大きな変化はないものの、細かな関連政策は流動的な面もあります。
現在は、第六次環境基本計画にそって政策が実施されていますが、当然、今後、第七次、第八次などとブラッシュアップされていきます。
省庁の事業計画などは、年度ごとに更新されますし、そのほかにも随時、最新情報が掲載されますから、環境省サイトなどをつねにチェックすることが大切です。
おすすめ情報源
さまざまな情報源がありますが、ここでは主なものをいくつか紹介しましょう。
- 環境省:基本となるサイト。報道発表や基本政策についても、こちらで確認することができます。
- 脱炭素ポータル:環境省サイトの注目キーワードに出ていますが、カーボンニュートラルに関して重要なサイトとなっています。
- 地域循環共生圏:地域循環共生圏についてまとめられたサイトです。
- 脱炭素地域づくり支援サイト:地域脱炭素について紹介しています。
自社や自治体でどう活用すべきか?


カーボンニュートラルについて、国の政策や関連情報について紹介してきましたが、これらを活用するにはどうしたらよいでしょうか。
自社の方向性の確認と制度の選択
国の政策は、世界の流れに準じたものであり、カーボンニュートラルの実現に向けた動きは、いまや常識となっています。
まずは、その流れの中で自分の会社あるいは自治体が、カーボンニュートラルに向けてどのような計画を立てるのか、つまりロードマップを描くのかが基本となります。
会社や自治体には、当然、それぞれの特徴、個性があります。国の政策、例えば「地域脱炭素ロードマップ」なども、地域の特性にそった取り組みを重視したものです。自社、自治体のカーボンニュートラルへの方向性を確認することが、ロードマップの策定には不可欠となります。
その上で、どのような解決策があるのか、どのような補助金制度を選べばよいのかなどの段階へ移ることとなります。
また会社の場合は、社のある自治体の動向を確認しておくことも必要です。特に脱炭素先行地域となっているか否かは、重要な要素になってきます。
環境経営は“義務”ではなく“信頼”
しかし、何よりも大切なのは、カーボンニュートラルなど環境問題への取り組みが、義務ではなく、取引先や社会の信頼の基本となっていることでしょう。
2050年に向けてカーボンニュートラルが進められていることは繰り返してきたとおりですが、エコアクション21の項目でも触れたように、企業経営はすでに大きく変化しています。
環境経営は企業の価値を高めるものですが、すでに当然の行動になっているといえます。
まとめ│“国家目標”に自分たちのアクションをどうつなぐか?


カーボンニュートラルに対する国の基本的な政策を見てきましたが、補助金や支援制度などについては、かなり細かな印象を受けるかもしれません。また冒頭で触れたとおり、個人とは少し距離があると感じられたかもしれません。
しかし、そもそもの問題は地球温暖化。カーボンニュートラルはそれを解決するための重要な取り組みのひとつです。つまり、根幹にあるのは地球の危機であり、人類の危機であるということなのです。
国が提示した目標に対して、ひとりひとりがどのような行動を取るのか、ということは一筋縄ではいかない問題かもしれません。ひとりひとり、そしてさまざまな会社や自治体が取るべきアクションは、それぞれ異なることでしょう。
earth-ismでは、地球の危機を解消するために取り組む企業を多く紹介しています。ぜひこちらのページも見てみてください。
それぞれがすべきことは、おのずと見えてくるはずです。環境の危機に瀕していて、時間も限られている点は、国も会社も個人も同じ。問題となっているのは、人類の未来のことなのです。ぜひ今日からカーボンニュートラルへの理解を深めていきましょう。