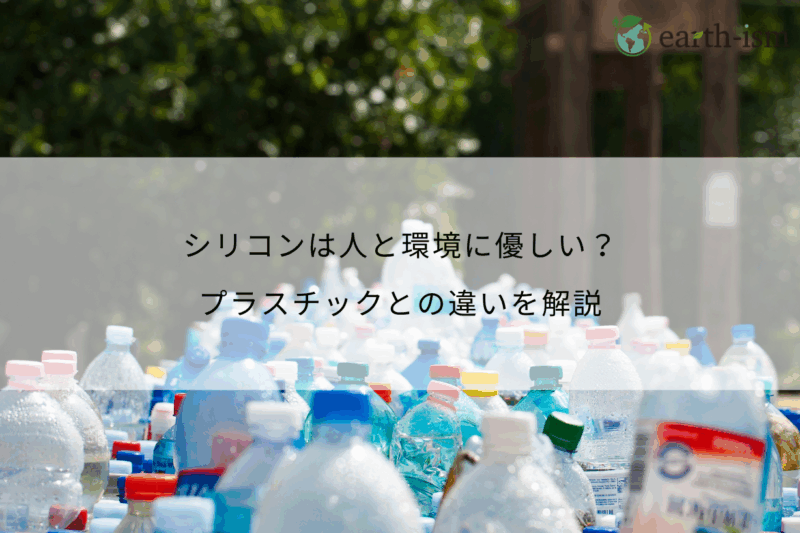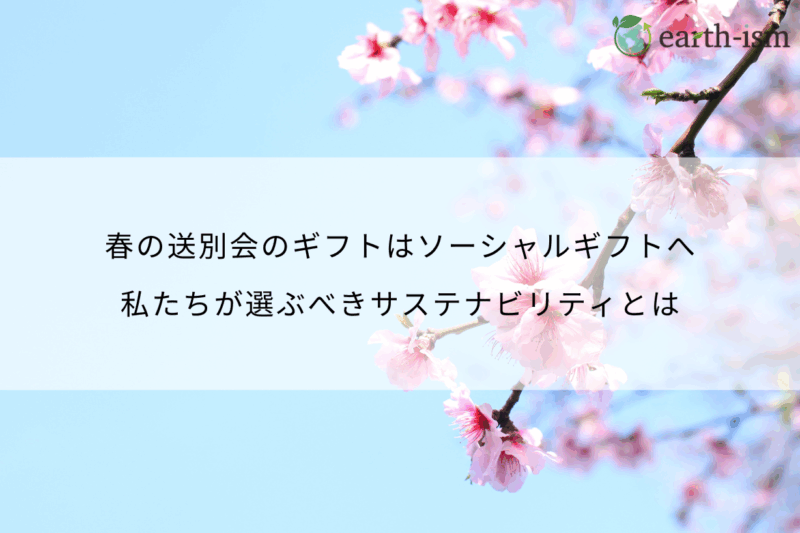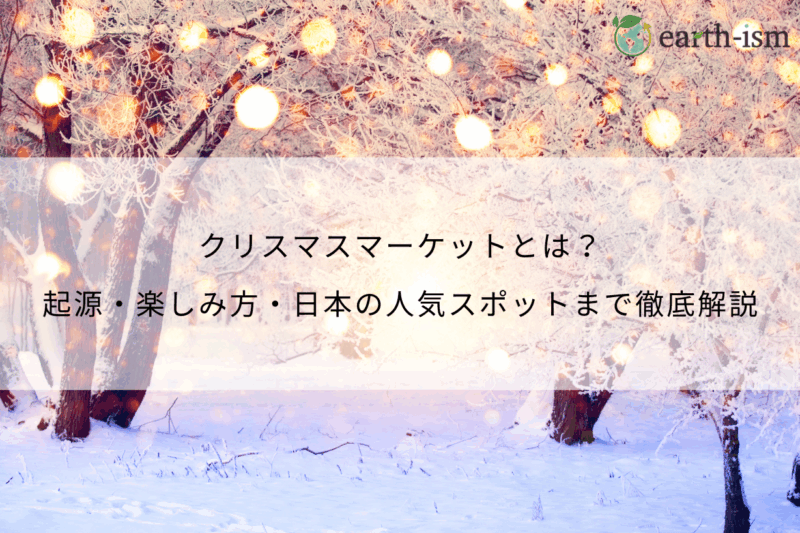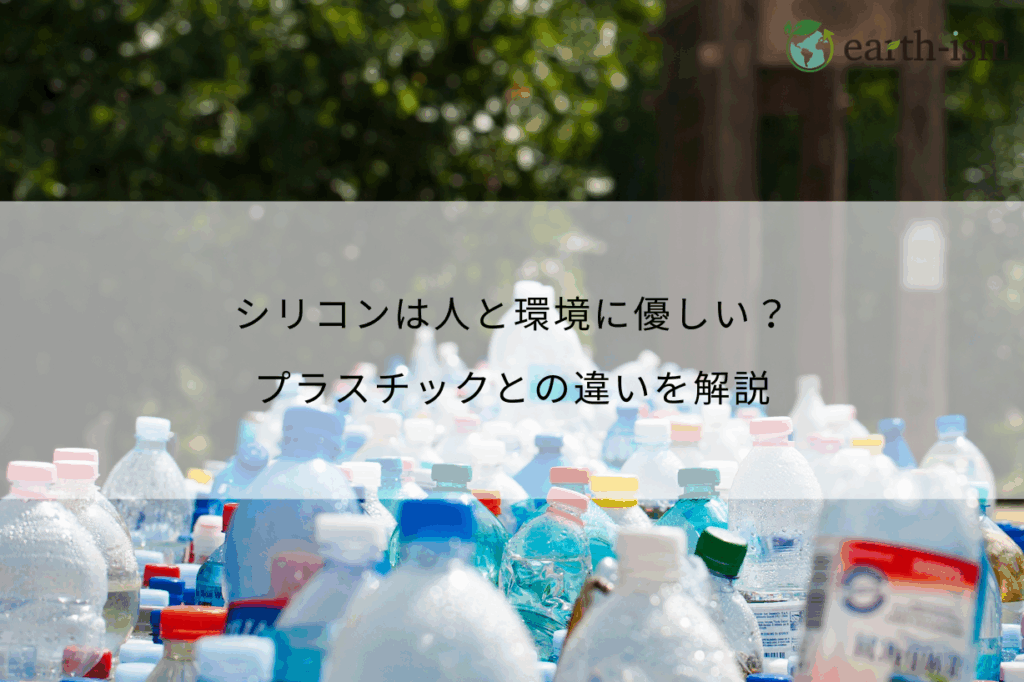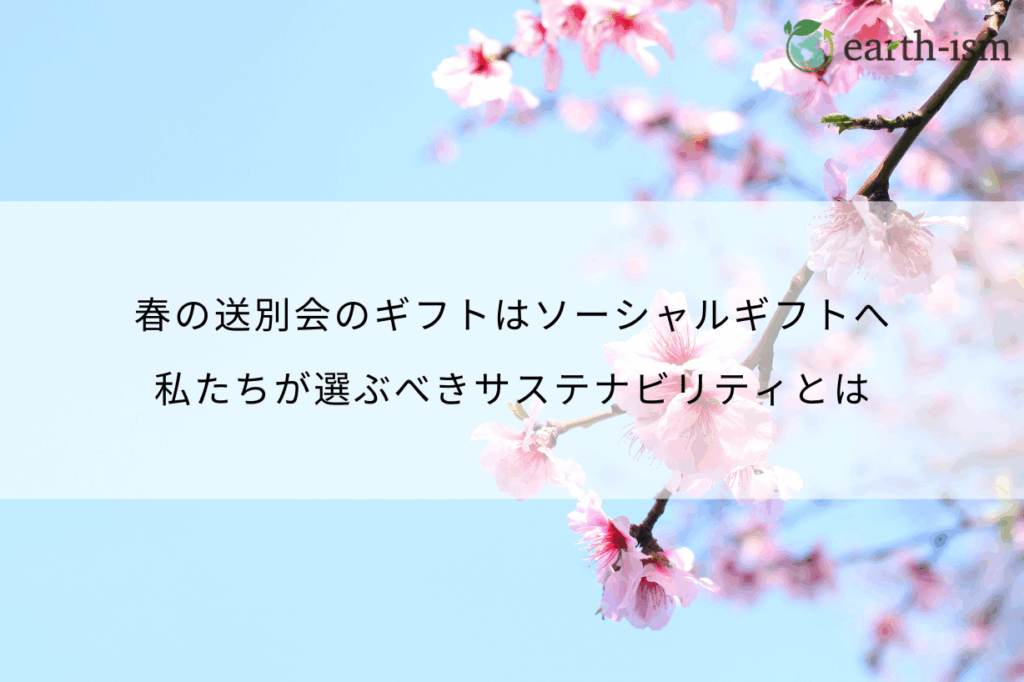歩くことが暮らしの中心の都市│「ウォーカブルシティ」とは?定義・事例・実現のヒントまで徹底解説
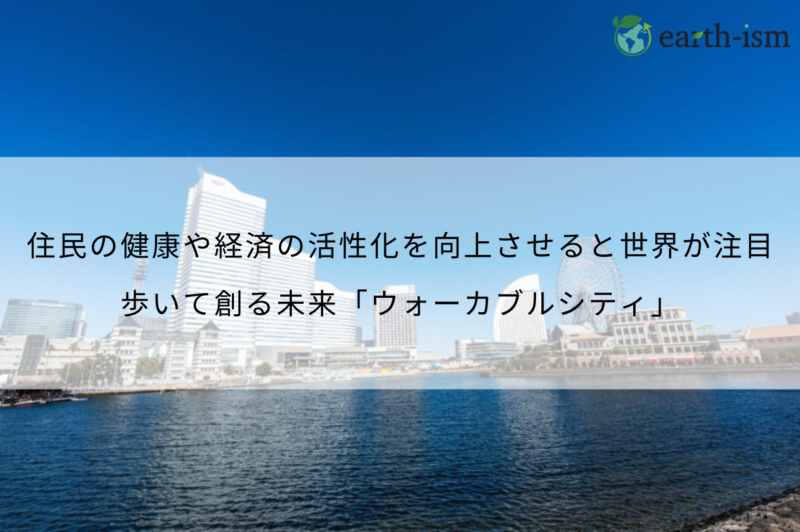
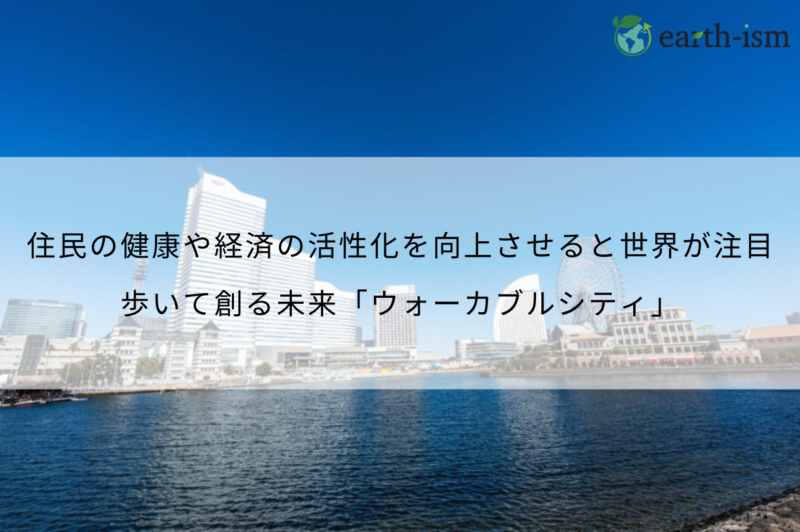
Contents
ウォーカブルシティという言葉を聞いたことはありますか?
ウォーカブルは「walkable」。walk+ableなので、「歩くことができる」という意味だと想像できます。つまり、ウォーカブルシティとは「歩くことができる街」となります。
では、「歩くことができる街」がテーマなのかというと、それだけではないようです。ここ数年、世界や日本の都市で急速に注目を集めているウォーカブルシティは、SDGsや世界の未来像などとともに議論されています。
それほど重要だと考えられているウォーカブルシティとは、いったい何なのか?その基本から、世界の事例、そして未来について解説していきましょう。
ウォーカブルシティとは?「歩ける街」以上の意味を持つ都市像


まずは、ウォーカブルシティの定義などについて見ていくことにしましょう。
車中心から人中心へ
日本では国土交通省の「ウォーカブルポータルサイト」が、ウォーカブルシティに関する国内の動向を紹介しています。
ウォーカブルポータルサイトの冒頭には「居心地が良く あるきたくなるまちへ」という言葉が掲げられています。
これまでの「車中心」から「人中心」の空間へと、都市を再構築することが、ウォーカブルシティの最も基本的な考え方となっています。ウォーカブルシティは、歩行者の安全や快適性を優先した思想といえます。
SDGsとの関係性
ウォーカブルシティはSDGsの目標11「住み続けられるまちづくりを」とも関係しています。
目標11では、2030年までに都市住民の数が現在の35億人から50億人に増えると予測される中で、都市化による課題に対処する重要性を掲げています。
過密、住宅不足、大気汚染など、さまざまな都市問題が深刻化していくことが予想できます。それらに対処するひとつの方法がウォーカブルシティの思想です。
身近な例をあげると、通勤、買い物、子育て、老後など、あらゆる世代にとって、利便性と豊かさを両立できるのがウォーカブルシティだといえます。
ウォーカブルな都市がもたらすメリット
このようにウォーカブルシティには、歩くことだけではなく、そのほかにも多くのメリットがあると考えられています。
生活者視点のメリット
まず思い浮かぶのは、歩く本人へのメリットです。
歩くことが習慣になれば、健康増進につながることは言うまでもありません。歩くことは、子どもでもお年寄りでも気軽に取り組むことができます。
歩くことが習慣になる、つまり車に頼らない日常が当たり前になれば、健康的な生活が送られるだけではなく、車にかかわるコストを気にすることもなくなります。この点でも、生活の質が向上しているといえるでしょう。
ウォーカブルシティでは歩く環境が重視されます。緑豊かな街並みになり、休息のためのベンチが設置されるなど、人にやさしい環境が創設されていきます。カフェなども充実するでしょうし、公共の空間も充実していくことでしょう。
社会・経済的なメリット
歩く人が増えるということは、人々が街中に滞在する時間が増加することも意味します。商店街などがにぎやかとなり、地域経済の活性化が期待されます。
車に依存しない街では、交通渋滞もなくなります。交通事故なども少なくなり、より安心して街を歩けるようになりますし、排気ガスが減少することで環境への負荷も軽減されます。
また都市の中で、歩きやすいエリアは、地下鉄移動が中心のエリアより、賃料が約75%高いとされます。不動産の価値が上昇するメリットもあるのです。
世界のウォーカブルシティ導入事例


実際のウォーカブルシティも紹介していきましょう。まずは世界の都市の例です。
コペンハーゲン(デンマーク)
1970年代から車道を減らし、歩行者空間を拡張してきたデンマークは、ウォーカブルシティの先駆けとして知られます。
有名なのは、市中心部にある全長1kmほどの歩行者専用道路「ストロイエ」。1962年の社会実験を経て、車用の道路が改造されました。現在、歩行者専用道路は、このストロイエの周辺にも広がっています。
同時に進められたのが、自転車を優遇する政策です。「世界一の自転車都市」とも呼ばれるコペンハーゲンでは、通学・通勤の交通手段の49%が自転車(コペンハーゲン市調べ。2018年)とされます。
市内の自転車インフラが整備されているだけではなく、列車やメトロ、バスへの自転車の持ち込みが許可されていて、無料となっています。
メルボルン(オーストラリア)
2011年から7年連続で「世界で最も住みやすい都市」に認定されたメルボルン。2017年には長期都市計画プラン「プラン・メルボルン2017-2050」を発表しています。
その中の構想のひとつが「15分都市」。徒歩15~20分以内にアクセス可能なところに、主要な施設やサービス、公共交通機関などを配して、利便性をよくするというものです。
そのため同市では、市内各所に歩行者センサーを設置し、歩行者の移動情報を収集してきました。このデータに基づいて、まちづくりが進められています。なお当然ながら、このセンサーでは個人情報は収集されません。
バルセロナ(スペイン)
400m四方の碁盤目状に整理された9つの街区をひとつの大きな街区(スーパーブロック)としてとらえ、その内部への車の侵入を抑制し、市民の快適な生活を実現する「スーパーブロック」計画を実施しているのはバルセロナです。
初期には、ある日突然、道路の通行方法を変更したため、市民からの反発が大きかった事例もあるようですが、その後は「市民の参加、対話型の都市プロジェクト」であることを重視し、スーパーブロックは市民が参画するまちづくりとして進められています。
スーパーブロック内の空間の活用方法は、近隣市民によって決定されるため、地域コミュニティは活発化。ハード面だけではなくソフト面でも取り組みが深まっているといわれます。
日本でも注目が高まる「歩ける都市づくり」
ウォーカブルシティは日本でも広がりを見せています。「ウォーカブルポータルサイト」によると、国内の「ウォーカブル推進都市」は2019年に207都市だったのが、2025年4月現在では390都市にまで増えています。
日本の先進事例
東京都の豊島区は、2023年に「いけぶくろウォーカブルCONCEPT BOOK」を策定。池袋駅の東口と西口をつないだほか、車道を交通規制してウォーカブル体験イベントも開催。再開発で歩行者空間の確保を進め、子育て世代からも好評を博しています。
石川県の金沢市では、2023年に「歩行者・自転車・公共交通優先のまちづくり」が策定されています。戦争の被害や大きな災害に見舞われていない同市は、約180kmの距離の街路が、江戸時代から変わらず残っているとのこと。歴史文化エリアを中心に、歩行者優先のまちづくりが進められています。
京都や奈良などの古都も、ウォーカブルシティを目指しています。京都盆地は山手線がすっぽり入るサイズで京都市はコンパクトシティとしての魅力をアピールしています。奈良も徒歩や自転車と公共交通のベストミックスを目指しています。いずれも、街を歩くことを中心とした観光体験が、古都のブランドに貢献する点が共通しています。
観光や地域振興への応用
京都や奈良の例だけではなく、街歩きが楽しいとその街への滞在時間は増えますし、消費行動も増えると考えられます。ウォーカブルシティが、観光にとっても重要な要素であることがわかります。
観光促進の側面が地域振興につながることは、当然のことといえるでしょう。歩くことは、それまで気づかなかった、もしくは過小評価していた地元の魅力を再発見できるひとつの方法でもあるのです。
ウォーカブルシティ実現に必要な施策・設計要素


では、ウォーカブルシティとはどのように実現できるものなのでしょうか。ここでは具体的なハード面について考えていきます。
都市計画のポイント
最も重要なことは安全性。歩道を広くすることで、ベビーカーや車椅子の人も通行しやすくなります。段差を極力少なくしたり、滑りにくい舗装にすることも必要です。
交通事故が起きやすい交差点を安全にすることも大切。歩行者のストレスを軽減するように、待ち時間を短縮するなど信号の最適化も考えなければなりません。ここでも、これまでの車中心から人中心へと発想を変える必要があります。
ベンチなどの休憩スペース、夏の日差しを和らげる並木道や街路樹も、歩行者の快適性を保つために整備したいものです。
利便性の点では公共交通機関との連携も必要。乗り換えのしやすさ、駅やバス停からのアクセスの良さは、誰もが気になるところでしょう。
最近は「ラストワンマイル」という言葉もよく聞かれます。流通や交通などの業界で使われる言葉ですが、最後の1マイル(約1.6km)という意味。
交通でもいくつかり例がありますが、都市部でも地方でも問題となっているのは、人口減少や高齢化などによる公共交通維持の難しさです。最後のあとちょっとした距離で交通アクセスがなくなり、利便性が悪くなってしまうという問題は、今後さらに深刻化することが考えられます。
都市の「設計」には、現在の日本が抱える根本的な問題も大きく関わっているわけです。
地域単位でできること
道路などのハード面だけではなく、地域で取り組めることもあります。ウォーカブルシティの魅力を知るためによく実施されるのは歩行者天国です。歩行者天国が定期的に行われることで、街を歩くことの楽しさや解放感がより実感することができます。
人が滞留しやすいオープンスペースも大切な場所となります。広場や公園のほかにも、問題となっている空き家をリノベーションするなどして活用することで「まちの居場所」が確保できます。
商店街の活性化も、人の行き来が多くなり、街歩きの楽しさの再発見につながるはずです。看板を工夫したり、街角にオブジェを設けたりするだけでも、街並みの景観が楽しくなり、活気がうまれることでしょう。街灯を整備すれば、通りを明るくするだけではなく、防犯対策にもなります。
生活者として「私たちにできること」
専門家や地域の人たちのほかに、個人でできることはないでしょうか。
自分のまちを観察してみよう
誰でも、いつでもできることは、自分のまちのウォーカブル度を自分の目や足で確かめることです。
「ここの段差、気になる」「この道、道幅が狭いのに車が多い」「ここから駅まで日陰がまったくないな」「この交差点、案内板がわかりにくい」など、改めて観察すると、いろいろな点に気がつくことでしょう。
そもそも、ふだんからそのような問題が気になっていたのではないでしょうか?「ここは、こうした方がいい」と感じたら、ぜひ市や町、区などに問題提起や提案をしてみましょう。
行政・不動産・地域活動とつながる
実は、その行動がウォーカブルシティの最も基本となる一歩。行政などと書くと大げさに思われるかもしれませんが、まちに暮らす人にとって暮らしやすいのがウォーカブルシティなのです。
「ウォーカブルポータルサイト」の関係で触れたように、ウォーカブルなまちづくりは日本でも急速に進んできています。市民参画型のまちづくりワークショップなども増えてきているので、参加してみることもおすすめです。
ウォーカブルシティの取り組みが、行政だけではなく、建物などの不動産の問題や地域社会の活動とも密接につながっていることが実感できるに違いありません。
自分が暮らすまちは、過ごしやすい方がいいに決まっていますし、街歩きが楽しい方がいいに決まっています。ウォーカブルシティの視点は、「まちは誰のものか」ということを考えさせてくれるのです。
まとめ|歩くことは、まちの文化をつくる


ウォーカブルシティの考えはアメリカで始まったといわれます。提唱者の一人とされる都市プランナー、ジェフ・スペックは著書『ウォーカブルシティ入門 10のステップでつくる歩きたくなるまちなか』(学芸出版社 2022)で歩行者に好まれるための4つの条件に触れています。
その4つとは「利便性が高い」「安全である」「快適である」「楽しい」。これまでに紹介してきたことの基本も、まさにこの4点となります。
さらに、ウォーカブルシティが単なる歩きやすい都市を目指しているのではなく、「人の時間と距離感」を大切にしていることも、理解していただけたことでしょう。
歩く速さでしか見えないこと、わからないことはたくさんあります。「歩くことがまちの魅力を育てる」というウォーカブルシティの考えが、超車社会のアメリカで始まったという歴史は、なにか象徴的ではないでしょうか。
歩くこと。歩いて、いろいろ気がつくことで、まちの未来は変わります。あなたの一歩が、ウォーカブルシティの未来を築いていくのです。