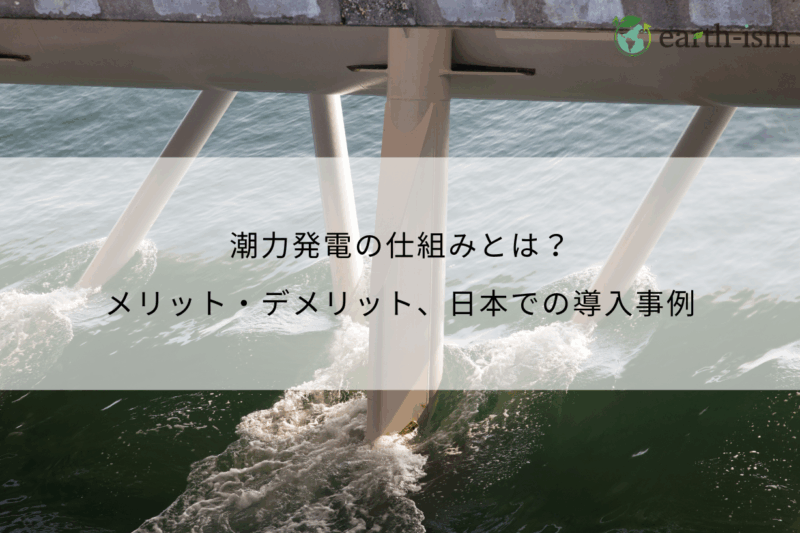大阪・関西万博2025の目玉とは?最新版で総ざらい|初めてでも外さない見どころ案内


Contents
4月13日の開幕から会期終盤へ。大阪・関西万博2025は、未来社会を「見て・触れて・考える」ための巨大な実験場として進化を続けています。
既にSNS上で多くの感想や批評が飛び交っていますが、そもそも情報が多すぎて「どこを見ればいい?」という声も少なくありません。
そこでこの記事では、最新の運営情報とともに、必見パビリオン/体験をわかりやすく整理してご案内します。まずは基本情報から押さえ、万博の最終局面を楽しみましょう。
大阪・関西万博2025とは?
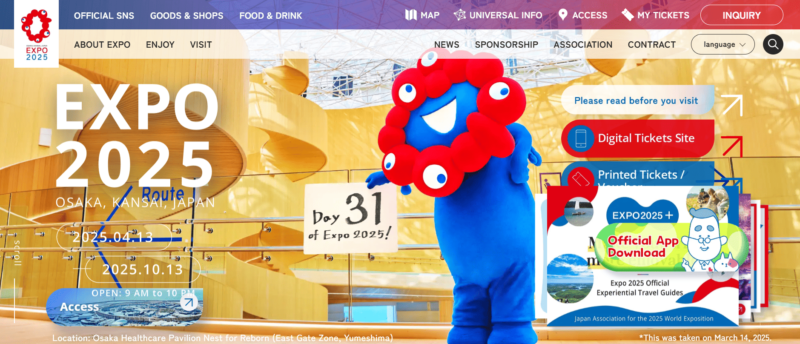
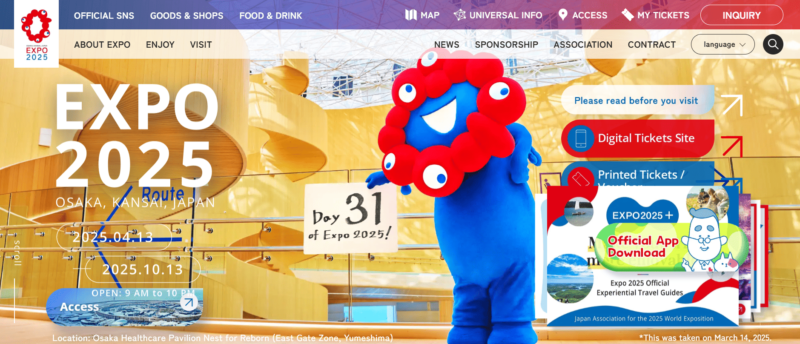
引用元:大阪・関西万博公式サイト
ところで、大阪・関西万博2025とは、いったいどのようなイベントなのでしょうか。改めて基本的なところから確認していきましょう。
開催期間、開催地(夢洲)・テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」
正式名称は、2025年日本国際博覧会。大阪・関西万博は略称です。開催期間は4月13日から10月13日までの184日間。開催地は大阪市臨海部に造られた夢洲(ゆめしま)です。
テーマは「いのち輝く未来社会のデザイン(Designing Future Society for Our Lives)」。「幸福な生き方とは何か」を正面から問う万博となります。
テーマである「いのち」を考える軸として、「Saving Lives(いのちを救う)」「Empowering Lives(いのちに力を与える)」「Connecting Lives(いのちをつなぐ)」の3つのサブテーマも掲げられています。
会期末が近づき、同日券の販売終了や最終プログラムに関する案内も更新されています。来場前は公式の「お知らせ」を必ず確認してください。
国家プロジェクトとしての位置づけと、経済効果への期待
今回の万博には、新型コロナが大きく影響しています。世界に甚大な被害を与えた新型コロナを乗り越えた先の、新たな時代に向けた国家プロジェクトが、大阪・関西万博なのです。
大阪・関西万博ではまず何よりも、新型コロナを経験した人類が、「いのち」という原点に立ち戻るという意味があります。
その上で、日本が国の成長戦略として位置付けているSociety5.0(AI、ロボテックス、ビッグデータ等の先端技術を活用して、さまざまな問題を解決する超スマート社会)の実現に向けた実証機会となっています。
経済効果は約2兆9182億円と予想されています(アジア太平洋研究所「アジア太平洋と関西~関西経済白書2022」より)。来場者数は約1810万人と想定されていて、人の動きが活発となって、経済効果が高まるものと期待されています。
【目玉1】「リング型」会場デザインと未来的な空間構成|歩くほどに広がる空と海と会場の眺め


引用元:大阪・関西万博公式サイト
今回の万博会場で一番の話題となっているのは「大屋根リング」でしょう。この会場のシンボルを中心に、会場の空間を見ていきましょう。
万博史上初の“空中回廊”「大屋根リング」
「大屋根リング」はすでにテレビなどのメディアで見たという人も多いでしょう。会場をぐるりと一周するこの建造物は、長さ約2km、高さ約12m、幅約30m。世界最大の木造建築物として、ギネス世界記録に認定されました。
階段のほか、4ヵ所のエスカレーターと6基のエレベーターが設置されていて、屋上にはスカイウォークと呼ばれる回廊があり、およそ30分かけて一周できるようになっています。また、雨や風、陽射しなどから逃れることができる空間としても利用できます。
世界最大の木造建築としてギネス世界記録に認定され、会場体験の象徴になりました。夜景と海風を受けながらの一周は、写真派・建築好きにとっても外せません。解体後の保存・再利用に向けた議論も始まっており、「万博の記憶」を次世代へどう残すかという視点でも注目を集めています。
360度、歩くだけでパビリオンを一望できる設計
「大屋根リング」の上からは会場が一望できます。東側にはリングの外側に東ゲートがあり、地下鉄の夢洲駅があります。日本館のほか、企業パビリオンが並んでいます。
時計と反対回りに歩いていくと、内側には海外のパビリオンが見えてきます。さらに進むと、西ゲートのある「西ゲートゾーン」。西ゲートの先には屋外型の展示イベント会場であるEXPOアリーナが建っています。
そして「大屋根リング」の南側部分があるのは海の上。内側にも水辺が広がり、外側には大阪湾が広がります。ダイナミックな風景の変化が楽しめるのも、「大屋根リング」の楽しみとなっています。
デジタル×自然が融合した都市空間の実験場
会場は、未来を先取りした「超スマート会場」にもなっています。AIによる情報提供アプリには、パビリオンや飲食店、会場エリアの混雑状況が表示され、施設やルートの案内などもしてくれるほか、おすすめのイベントやパビリオンの紹介などもしてくれます。
イベントなどでも、最先端の通信や映像装置を使った演出が見どころとなっています。精度の高い色の再現により臨場感あふれる映像を実現した大型LEDビジョン、全方向の映像体験が可能となったプロジェクションシステムなどは、今回の万博の見どころとなっています。
これらデジタルの技術が、会場南側の海などの自然と一体となって楽しめるのも、大きな魅力のひとつでしょう。
【目玉2】世界各国のパビリオン展示(参加国&企業のハイライト)


大阪・関西万博では、海外パビリオン162、国内パビリオン20と8人のプロデューサーによる8つの「シグネチャーパビリオン」を見学することができます。いくつかのパビリオンを簡単に紹介していきましょう。
サウジアラビア館
新しい未来を意味する「ネオム(NEOM)」と呼ばれるプロジェクトを掲げているのはサウジアラビア館です。
日本館に次ぐ2番目の広さを誇るパビリオンは、砂漠に石造りの白い建物がぎっしりと並ぶ砂漠の風景で、サウジアラビアの街に迷い込んだような感覚になります。
伝統的なサウジアラビアの文化が体感できますが、注目は「ネオム」。再生可能なエネルギーを100%利用する未来都市の姿は、石油というこれまでのサウジアラビアのイメージを一変させる内容となっています。
UAE館(アラブ首長国連邦パビリオン)
16mもの高さがあるナツメヤシ風の柱が90本立ち並ぶUAE館は、その光景だけでも話題となっています。このデザインは、日本の木工技術とUAEの伝統建築が融合して実現したものです。
また、文化体験プログラムも充実していて、UAEの伝統工芸(織物アル・サドゥ、椰子葉細工など)やエミラティ料理、伝統工芸のデモンストレーションも実施されています。
UAEパビリオンは、「Earth to Ether(大地から天空へ)」というタイトルを掲げ、地に根ざす伝統と未来への飛躍を共鳴させる展示空間を目指しています。五感に訴える演出と、文化・技術・未来の融合を見せる体験型展示が中心です。
UAE館のレストランでは、本格エミラティ料理が“BENTO BOX形式”で提供されており、現地の味覚を体験できる工夫があります。ラクダミルクを扱った飲み物もあったそうです。
フランス館・ドイツ館
ルイ・ヴィトン、ディオール、セリーヌなどのファッションブランドの展示が見られるのはフランス館ならでは。
館内では、デジタルアート、VR体験などを通じ、五感で楽しみながら、文化や科学技術に触れることができます。同時に、気候変動、社会的な多様性といったこれからの問題に向き合うフランスの姿がわかるように見どころは展開していきます。
ドイツ館は7つの円形の木造建築で構成された建物が特徴的。リサイクル可能な建材を使用していて、循環経済をテーマとした同館を象徴するパビリオンとなっています。
「サステナビリティ」「デジタル」「共創」にそった展示を行っていて、AIやIoTを活用した未来の社会、循環型生活など提案されています。
じっくりと問題と向き合う骨太の展示ですが、ここで活躍しているのが音声ナビゲーターの「サーキュラー」。光ったり話をしたりするかわいらしい人形のような「サーキュラー」はSNSなどで「かわいい」と話題になっています。
日本館
日本館は今回の万博のテーマである「いのち輝く未来社会のデザイン」を、開催国のショーケースとして具現化する役割を担っています。
会場内で最大のパビリオンとなる日本館の中心コンセプトは、「いのちと、いのちの、あいだに」。館内で出る生ゴミを微生物で分解し、バイオガス発電に変えるプロセスを追体験できる構成になっています。「ごみを食べる日本館」とも称されています。
この3エリアの見学は事前予約が必要。ふだんは見られないバイオガスプラントが見学できるツアーもあり、こちらも要予約となっています。ただし入館制度では、事前予約なし観覧可能な時間帯(9:30–10:30、19:30–20:30)があります。混雑が激しい時間帯は入場制限が実施される可能性もあるので注意が必要です。
そのほか、火星の石やはやぶさが持ち帰った砂も展示。藻に扮したハローキティのオブジェも見られます。
【目玉3】企業のパビリオンのインパクト
国内パビリオンの中には、さまざまな企業が展開している企業パビリオンがあります。こちらもそれぞれ個性的です。
パナソニックグループパビリオン


引用元:大阪・関西万博公式サイト
パナソニックグループパビリオンのメインは「ノモの国」。子どもたちのモノとココロを映し出す物語が五感で体験できる世界は、オリジナルアニメにもなっています。
子どもたちが参加できるイベントもいろいろと用意されているほか、ペロブスカイト太陽電池や微生物によるバイオライト、バクテリアによる食の未来などに関する展示もあります。
夜は、ゼロカーボン電力由来の水素で発電し、パビリオンがライトアップされます。
NTT Pavilion:都市のスマート化と5G/6Gの未来社会


引用元:大阪・関西万博公式サイト
次世代の情報通信の基盤となる「IOWN(アイオン Innovative Optical and Wireless Network)」を中心に、未来のネットワークについて展示しているのはNTT Pavilionです。
IOWNとは、現在の5Gの先6G時代の基盤。光ベースでの通信が確立されて、低消費電力、高品質・大容量通信などの性能が向上されるといいます。
電力効率は100倍、データ伝達容量は125倍になり、スマホは充電が不要になるといわれていますが、その世界はぜひNTT館で確かめてみたいものです。
各企業が「未来の日常生活」をリアルに再現
ほかにも、エネルギー、宇宙などをテーマに未来の世界を紹介した企業パビリオンが点在しています。どのパビリオンからも、もう間もなく実現しそうな未来の生活が感じられるのは興味深いところです。
一方、海洋プラスチックごみをゼロにしたり、未来のため植林をするなど、現代の問題について改めて考えさせられる展示もあります。
「笑いのチカラ」をテーマにしたよしもとwaraii myraii館があるのは大阪ならでは。どんな未来になっても「笑い」の大切さは変わらないことを実感できます。
【目玉4】個性光るシグネチャーパビリオン
生物学者の福岡伸一さん、放送作家の小山薫堂さんら8人のプロデューサーが手がけるシグネチャーパビリオンもそれぞれの個性が光る見どころとなっています。
「null2(ヌルヌル)」:AIアバターとの対話体験


引用元:null2公式サイト
メディアアーティストの落合陽一さんによる「null2」は、英語で「空(くう)」を表すnullがモチーフ。鏡のパビリオンが印象的ですが、来場者が自らの3Dアバターを生成し、そのアバターと対話できることが話題となっています。
このアバターは専用アプリとスマートフォンのカメラを使って2分ほどで立体的に作ることができるとのこと。
その後、アバターと対話を続けることで、言葉や考え方がデータとして蓄積されていき、より本人に近づいていきます。
【目玉5】食・持続可能性・体験型グルメ


未来の技術などがメインの万博ですが、もうひとつの楽しみは多彩なグルメです。
世界各国の未来フード、昆虫食・培養肉・プラントベースフードなど
海外のパビリオンの多くでは、その国のグルメも楽しめるほか、数多くのレストラン、カフェが会場内に設けられていて、定番のメニューからふだんは食べられないようなローカルフードなども楽しめます。さらに未来の食文化が体験できる革新的なメニューも用意されています。
昆虫食・培養肉・プラントベースなど、代替タンパクの実食体験が充実しています。日本の発酵文化と掛け合わせたメニューもあり、「伝統×科学」の再編集を体験できます。運営面ではリユース容器やマイボトル洗浄機などを導入し、会場全体でプラごみ削減や地産地消に取り組みます。食べ歩きも“学び”に変わるのが万博流です(詳細は来場者向け公式案内を参照)。
植物由来原料100%、あるいは大部分が植物由来原料の食品であるプラントベースフードが、ヨーグルト、ラーメン、スイートなどに応用されているメニューもあり、こちらも注目されています。


日本の伝統食×サイエンス
日本各地の伝統料理ももちろん味わうことができますが、発酵食品をテーマにしたカフェレストラン「Hasshoku」のように、日本の伝統的な発酵食品を現代の健康志向にあわせた古くて新しいメニューをそろえた店もあります。
前述のプラントベースフードの日本食、グルテンフリーのラーメンなど、伝統と科学が融合した料理に出合えるのも万博の楽しみとなっています。
日本食だけではなく世界各国の料理にも、「未来」と融合した新メニューが見つかるので、どれを味わうか迷ってしまうでしょう。
サステナブルな飲食体験
プラスチックの削減も万博の大きなテーマとなっています。会場ではプラスチックごみを出さないため、使い捨てをしないリユースカップや容器などが使用され、マイボトル洗浄機も設置されています。
また日本各地の食材の地産地消にこだわっているだけではなく、紙や電気なども地産地消を意識することで環境への負荷を軽減し、持続可能な社会を目指しています。
すべての点において重点が置かれているサステナブルの意識は、万博を訪れると自然に高まるはずです。




最新の注意点|運営アナウンスと衛生情報は必ずチェック
6月上旬、水域演出エリア「ウォータープラザ」の海水からレジオネラ属菌が指針値超で検出され、水上ショーが一時中断されました。既に謝罪と対策は公表済みで、再開や代替演出の最新情報は公式「お知らせ」で随時更新されています。来場前に最新の運営情報を確認してください。
また、公式デジタルチケットの販売は9月30日で終了、ゲート前の当日券は9月27日以降購入不可となっています。未使用券の取り扱いや入場枠の状況は直前に必ず公式でご確認ください。
【特集】「いのち」が動く、“芸術と科学”の融合展示
大阪・関西万博2025の会場では、「いのち輝く未来社会のデザイン」というテーマを象徴するように、最先端科学と人間の精神文化が交わる展示が数多く見られます。
その中でも特に注目を集めているのが、PASONAグループによる「動くミニ心臓」と、イタリア館に展示されているミケランジェロの彫刻《キリストの復活》です。
動くミニ心臓|科学が見せる“生命の鼓動”


PASONAグループのパビリオン「PASONA NATUREVERSE」で公開されている「動くミニ心臓(iPS心臓)」は、再生医療の最前線を体感できる展示です。
このミニ心臓は、人のiPS細胞から作られた心筋シートを立体的に組み上げたもので、直径約3センチ。透明な培養液の中で、1分間におよそ50回のペースで脈打ち続けています。まるで小さな生命が、ガラス越しに息づいているような光景です。
展示では、来場者が間近でその動きを観察できるようになっており、医療従事者だけでなく子どもや一般の来場者も“いのちが動く”瞬間を実感できます。
同館ではこの展示に加えて、AI医療・遠隔手術・マイクロロボットなど、次世代の医療技術も紹介されています。中でも、来場者が仮想空間で体験できる「未来のカテーテル手術シミュレーター」や、バイタルセンサー内蔵ベッドによる健康モニタリングなどは、医療とテクノロジーの融合を肌で感じられる仕掛けとして好評を博しています。
この「動くミニ心臓」は、単なる科学展示ではありません。「いのちはどこから生まれるのか」「命の境界はどこにあるのか」という哲学的な問いかけです。生物の“機能”としての鼓動が、見る者に“感情”としての鼓動を呼び起こすことが、大阪万博のテーマを象徴する展示といえるでしょう。
ミケランジェロ《キリストの復活》|芸術が刻む“いのちの再生”
イタリア館では、ルネサンスの巨匠ミケランジェロ・ブオナローティによる彫刻《キリストの復活(Resurrected Christ)》が展示されています。この作品は1514~1516年ごろに制作された大理石像で、高さは約2メートル。磔刑を経て復活したキリストの姿を描いたもので、イタリア・ラツィオ州のサン・ヴィンチェンツォ・マルティーレ教会に所蔵されている本作が、今回初めて日本で公開されました。
この展示は、イタリア館全体のテーマ「アートは人生を再生する(Art regenerates life)」を体現するものでもあります。会場には、ダ・ヴィンチやカラヴァッジョ、ファルネーゼ・アトラスといった作品も並び、ミケランジェロの登場によって“ルネサンス三大巨匠”が大阪に揃う構成となりました。
まとめ|大阪万博では「見る」を超えた体験が、未来への問いと記憶を生む


大阪・関西万博は、ハードの壮観さだけでなく、自分が関わることで完成する展示や、循環・包摂を実装する運営まで含めて“未来を体験する場”として成立しています。
ときに課題やトラブルも共有しながら、来場者とともにアップデートされるプロジェクトであることも、この万博のリアルです。会期は10月13日まで。あなたの1日が、未来社会への小さな実験になります。
新型コロナのことを思い出してみるのもいいかもしれません。万博という場所に集まることができ、未来の体験ができ、世界のグルメが楽しめるというのは、この上ない幸せだということがわかるのではないでしょうか。