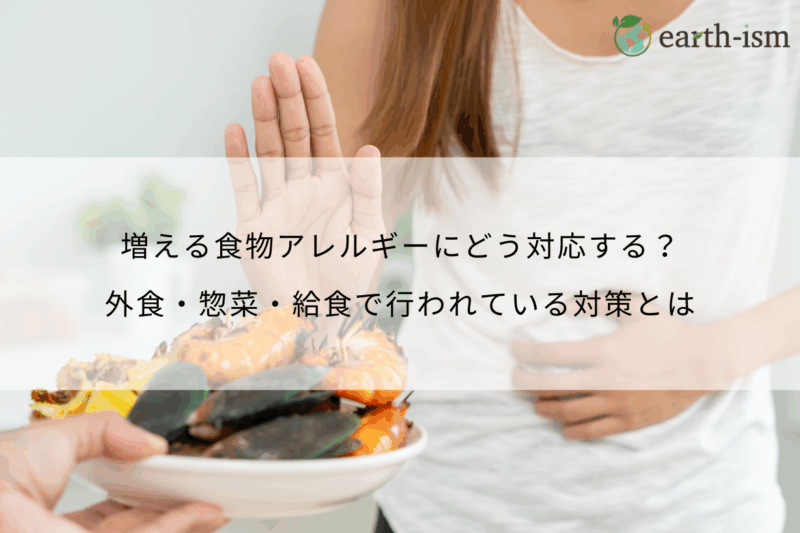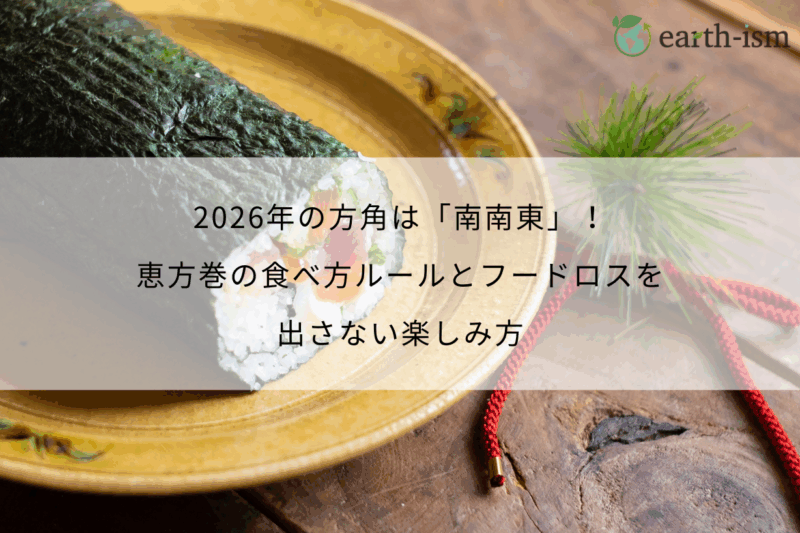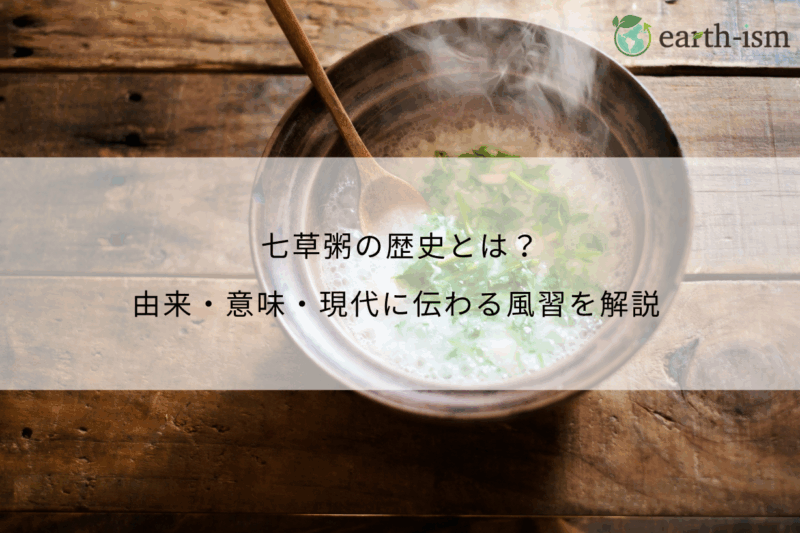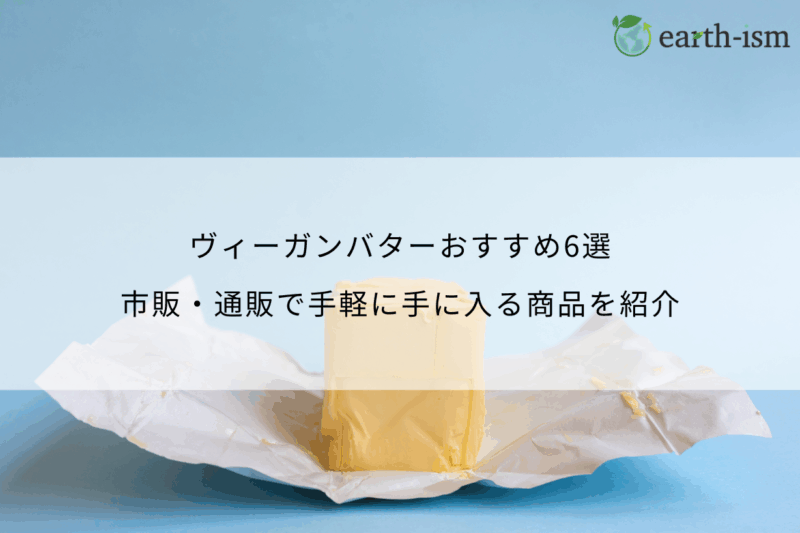日本の伝統的酒造りがユネスコの無形文化遺産に登録|日本の酒造りの何がすごいのか?


2024年12月にユネスコが、日本の「伝統的酒造り」を無形文化遺産に登録しました。
無形文化遺産は日本では2008年に能楽、人形浄瑠璃、歌舞伎が登録されたのが初めてで、それから23個目の登録です。
ユネスコの無形文化遺産の登録とは、グローバリゼーションの進展や社会の変容などにより、無形文化遺産に衰退や消滅などの脅威がもたらされるとの認識から、それらの保護を目的としています。
今回登録されたのは、日本酒ではなく日本の「伝統的酒造り」となっている点に注目する必要があります。それでは日本の酒造りは他のお酒と何が違うのか見ていきましょう。
アルコール発酵に必要な単糖類


基本的にお酒の作り方は、原料となる果物や穀物の成分から糖をつくり、その糖からアルコールが生成されます。
ワインの場合、ぶどうに含まれる成分がブドウ糖と果糖という糖類のなかでも単糖類がメインとなります。ぶどうを絞ったジュースに酵母を入れることで、そのままアルコール発酵できます。なお、ワインの場合、ぶどうに酵母が付着しており、この酵母で発酵をする場合と、培養した酵母を使う場合があります。
穀物を原料とする場合は、一手間が必要


一方、ビールやウィスキーなどの原料となる麦には糖がほとんどないため、デンプンがアルコールの元となります。デンプンは糖が複数連なったものなので、分けていけば糖になります。
そして、麦の中にはデンプンを麦芽糖という糖に分解する酵素があります。これは麦を発芽させて麦芽にさせる過程で増えていきます。ビールやウィスキーを造る過程では、まず麦を発芽させて麦芽にすることがスタートとなり、麦の中に麦芽糖を蓄えさせていきます。
そのため、麦芽をどの程度進めるかが重要になっていきます。早めに次の工程に進んでしまうとデンプンが多いままになってしまい、アルコール度数が低くなってしまいます。また、発芽を進めすぎてしまうと、せっかくできた麦芽糖をエネルギーとして消費しすぎてしまうため、こちらもアルコール度数が低くなってしまいます。
また、麦芽糖は二糖類と言って、糖が2つくっついた形をしているため、通常のアルコール発酵の酵母を使ってもアルコールにはなりません。ちょうど良いタイミングの麦芽と水を加えて麦汁を作り、そこにビールやウィスキーの酵母を入れることで二糖類の麦芽糖を単糖類に分割し、アルコール発酵が促されていきます。
日本酒の過程はさらに複雑に
さて、本題の日本酒ですが、原料はお米でデンプンがアルコールの元となります。しかし、麦のように発芽をさせるわけではなく、麹菌というカビの一種をつかってデンプンを単糖類に変換していきます。その過程が日本酒と同じ醸造酒であるワインやビールなどと比べると複雑になります。
まず、お米を研ぎます。研ぐ割合を「精米歩合」と言い、100%が何も研いでいない状態。50%は半分研いだ状態、20%にもなるとお米の中心の2割を残して、ほかの8割を削った状態を指します。お米は中心部の方がデンプンを多く含むため、削れば削るほど雑味の少ない澄んだ味わいとなります。
精米歩合の数値が小さいほど、お米を削っているため、製品としての日本酒の値段は高くなる傾向にあります。なお、大吟醸は精米歩合50%以下のものを指し、吟醸は精米歩合60%以下のものを指すので、同じ酒蔵の吟醸酒と大吟醸酒では大吟醸酒の方が値段が高くなります。
麦の場合、このような原料を加工する過程はありません。ワインの場合は、ぶどうの実を削ることはありませんが、糖度の高い房の下だけを使うようなことはあるようです。
麹をつくる
お米を研いで水に浸したあとに蒸していきますが、全てのお米を一度に蒸すことはしません。
一部のお米だけを蒸して、そこに麹菌を撒きます。麹菌はお米のデンプンを食べて糖にしながら、成長していきます。これには温度や湿度管理が重要になり、酒蔵には麹室(こうじむろ)という特別なスペースが用意されています。糖化したお米と成長した麹菌を「麹」と呼びます。
麹ができる頃に、残っているお米のまた一部を蒸していきます。そして蒸しあがったお米に、麹と水、さらに糖のアルコール発酵を促す酵母を入れていきます。こうすることで後から入れたお米のデンプンは麹によって糖に分解されつつ、酵母による糖のアルコール発酵が同時に進んでいきます。このように糖化とアルコール発酵を同時に行うのが、ワインやビールでは見られない日本酒ならではの特徴です。
まとめ|日本酒になるアルコール発酵も、多段階で進む


これでアルコール発酵が進んで日本酒ができると思うかもしれませんが、簡単ではありません。この後にも日本酒独特な工程があります。
第一段階のアルコール発酵が進んだものを「酛(もと)」と言いますが、この酛に麹と蒸した米、水をさらに入れて、発酵を進めていきます。そして、さらにもう一度、麹と蒸した米、水をいれて発酵を行なっていきます。このような多段階でアルコールを発酵させていくこともワインやビールでは見ることがない特徴です。安定して貯蔵できる米だからこそできる過程とも言えるでしょう。
このような複雑な過程を通して日本酒ができあがっていきます。そのため、原料のお米の種類、お米の精米歩合、麹の作り方、酵母の種類、各段階での発酵の進み具合など、できあがった日本酒の個性を決める要素は複数あります。
一言で「日本酒」と言っても、できあがるまでの過程が他の酒と比べて複雑で独特なのがお分かりいただけたでしょうか。このような背景から日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に選ばれることとなりました。日本酒を飲む時に、それぞれの個性の背景にある複雑なバックグラウンドに少しだけでも思い起こしてみてください。