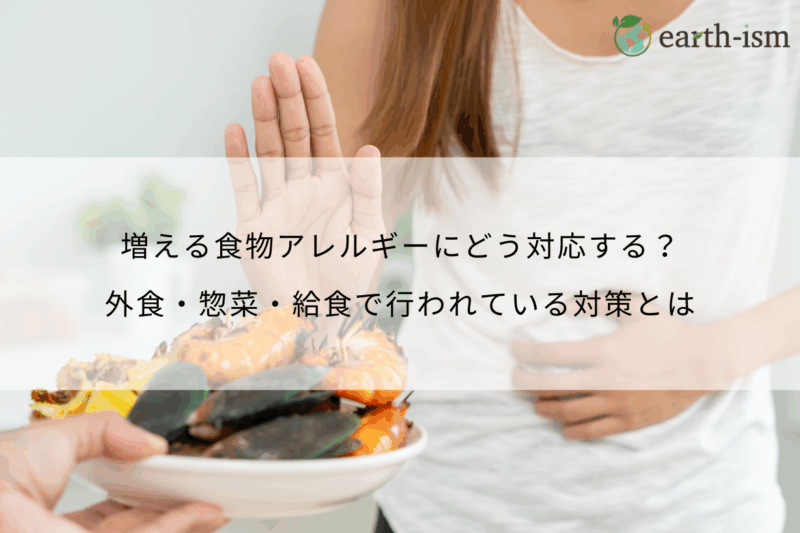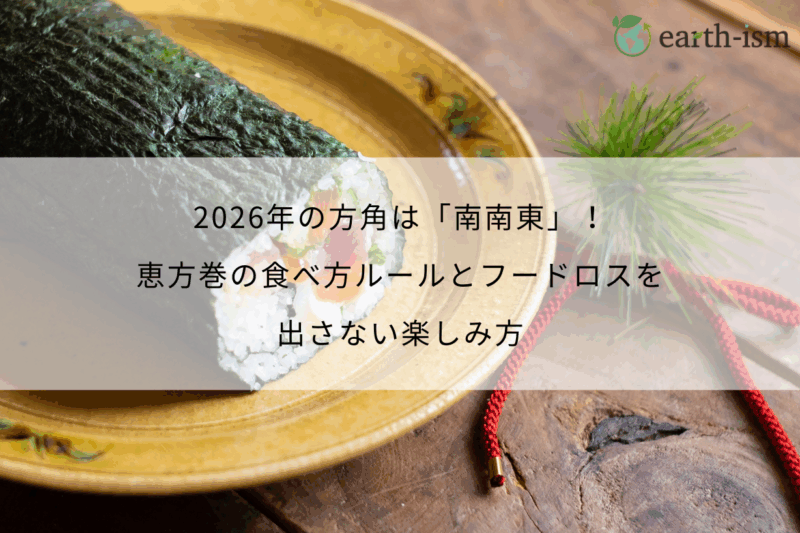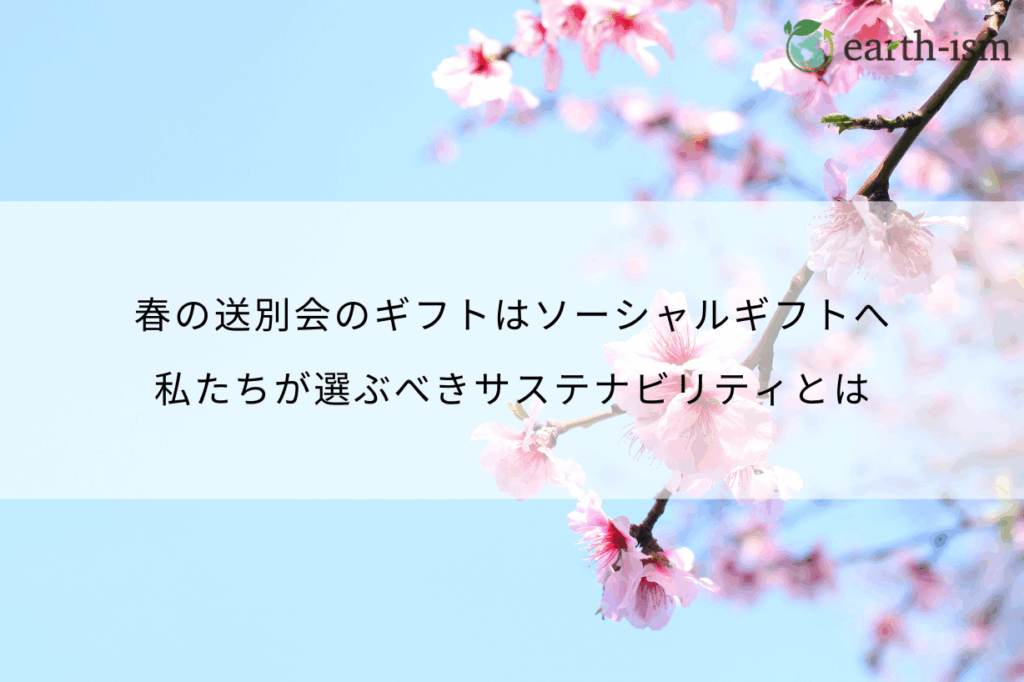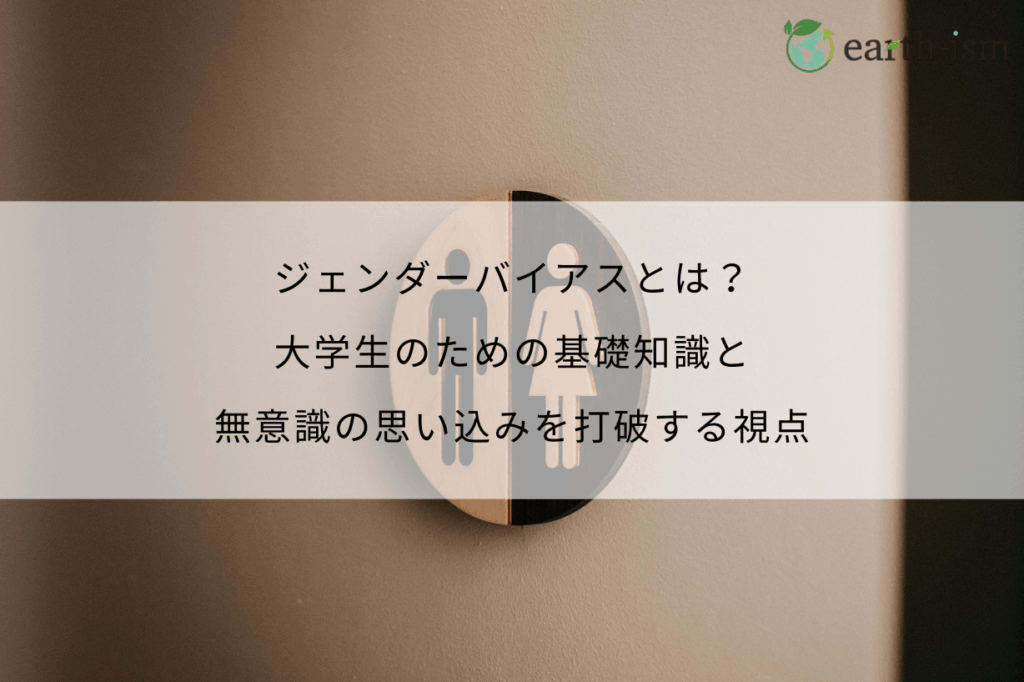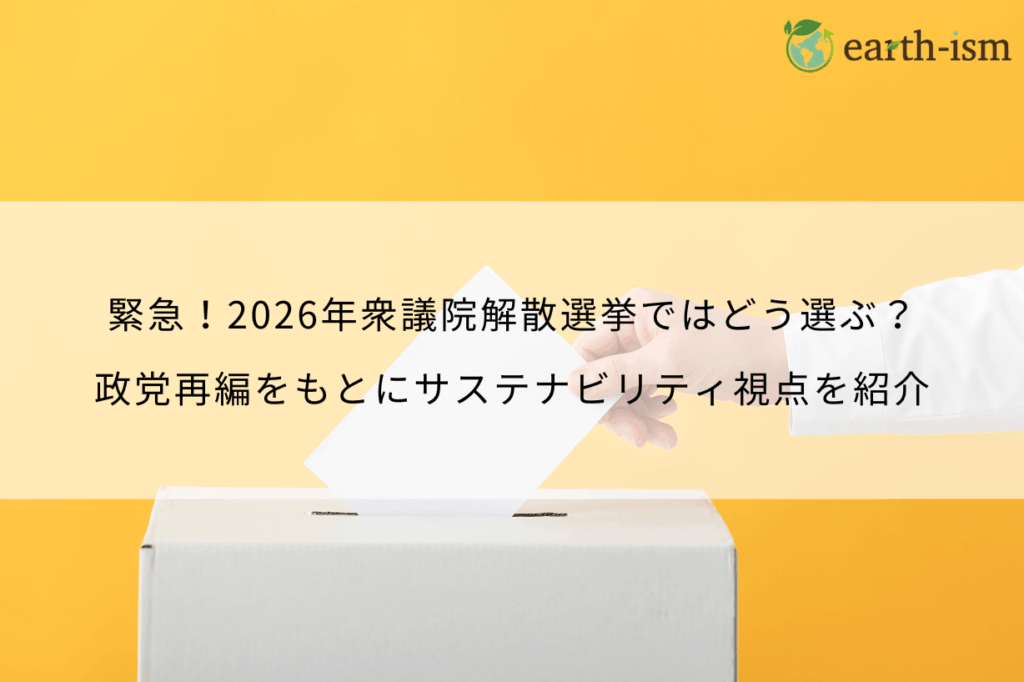オーガニック給食は悪なのか?持続可能な食糧供給について考察


Contents
2026年度から政府は小学校給食の無償化を決定し、中学校でも速やかな実施を目指しています。 東京都の23区では先行して2024年度からすべての区で無償化が実施されています。
この給食無償化の流れと並行して、オーガニック食材を取り入れる動きも広がっています。 東京都品川区は2024年2月、区内小中学校の給食で使用する全野菜を有機農産物(オーガニック)にすると発表しました。
背景には、給食の無償化によって「質が低下した」「おいしい給食を提供してほしい」という声に応える形で、食材の質を高めることによる付加価値の創出を目指す意図があるようです。


オーガニック(有機農業)の定義


オーガニック農業は近年注目を集めていますが、その定義や意義については様々な解釈があります。ここでは、オーガニック給食の概念と日本における有機農業の公的な定義について整理します。
オーガニック給食とは
オーガニック給食とは、有機農業で生産された食材を使用した給食のことを指します。推進派は主に次のような観点から支持しています。
- 化学合成農薬や化学肥料の使用を減らした食材を子どもたちに提供したい
- 栄養価が高く、風味豊かな食材を使用したい
- 環境負荷の少ない農業を支援したい
有機農業の公的定義
農林水産省による有機農業の定義は、「化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法」とされています。
日本で「有機」と表示するためには、有機JASマークの認証が必要で、以下の条件を満たさなければなりません。
- 周辺から使用禁止資材が飛来・流入しないよう必要な措置を講じている
- 種まきまたは植え付け前2年以上、化学肥料や化学合成農薬を使用していない
- 遺伝子組換え技術の利用や放射線照射を行っていない
これらの基準に適合していることを第三者機関が認証した農産物のみが「有機○○」と表示できます。現在、有機JAS認証を取得している農地は日本の全農地の約0.4%にあたる1万8800ヘクタール(令和4年度)にとどまっています。
農薬使用の役割と影響


農薬の使用は食料生産において重要な役割を果たしている一方で、その影響についても議論があります。ここでは農薬の規制状況とその使用がもたらす効果について検討します。
農薬の規制と安全性
農薬についての議論では、残留農薬の健康影響と食料安定供給における農薬の役割の両面から考える必要があります。
かつては高い毒性を持つ農薬や生態系に悪影響を与える農薬も使用されていましたが、現在の日本では法律により使用できる農薬の種類や残留基準が厳しく定められています。国内産・輸入品ともに検査が行われ、基準値を満たした食品のみが流通しています。
農薬使用のメリット
農薬使用の主要なメリットには以下のようなものがあります。
収量の安定と向上
農林水産省のデータによれば、稲作では1955年の10アール当たり収量335kgから2023年には533kgへと大幅に増加しました。この収量増加には、農薬による病害虫被害の軽減が大きく寄与しています。
品質の確保
農薬を使用しない場合、害虫による食害や形状不良などが発生しやすくなり、出荷できる割合が減少します。日本植物防疫協会の調査では、特にりんごなどの果樹類では農薬不使用により収量・品質に長期的な影響が現れることが報告されています。
科学的知見からの評価


有機農業と慣行農業の比較については、様々な観点から研究が行われています。ここでは栄養価の比較と環境への影響について科学的知見をもとに考察します。
栄養価の比較研究
有機栽培と慣行栽培で生産された農産物の栄養素については、国内の研究では有意な差は見られないという報告がある一方、海外では差があるとする研究もあります。日本食品科学工学会誌の調査では、両者の栄養成分に明確な優位性は認められないとしています。
これらの結果の違いには、栽培方法、土壌条件、気候などの要因が影響している可能性があり、現時点では栄養価における優劣を一概に断言することは難しいと考えられます。
環境への影響
有機農業は化学合成農薬や化学肥料の使用を減らすことで環境負荷の軽減を目指していますが、単位面積あたりの収量が低下する場合があります。
持続可能な食料生産の観点からは、環境保全と生産効率のバランスを考慮した農業システムの構築が課題となっています。
まとめ|持続可能な食料供給を考えてみよう


オーガニックと慣行農業のそれぞれの特性を理解した上で、将来の食料供給のあり方について考えることが重要です。農薬の使用は食料の安定供給と品質確保に重要な役割を果たしてきました。一方で、環境負荷の軽減や化学物質への慎重な姿勢も重要な視点です。
持続可能な食料システムを構築するには、オーガニック農業と慣行農業のバランス、地域の実情に合わせた適切な選択が必要でしょう。
給食へのオーガニック食材導入は、子どもたちの食育や環境教育の観点からも意義がありますが、コスト増や安定供給の課題もあります。オーガニック食材を選ぶ際には、有機JASマークなどの認証を確認し、科学的根拠に基づいた情報をもとに判断することが大切です。
食の安全と持続可能性、そして安定供給のバランスを取りながら、次世代のための最適な給食のあり方を社会全体で考えていくことが求められるでしょう。