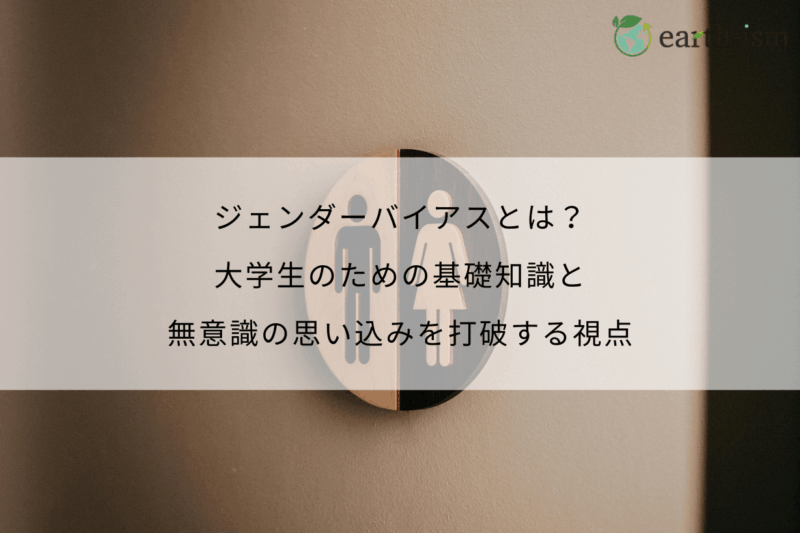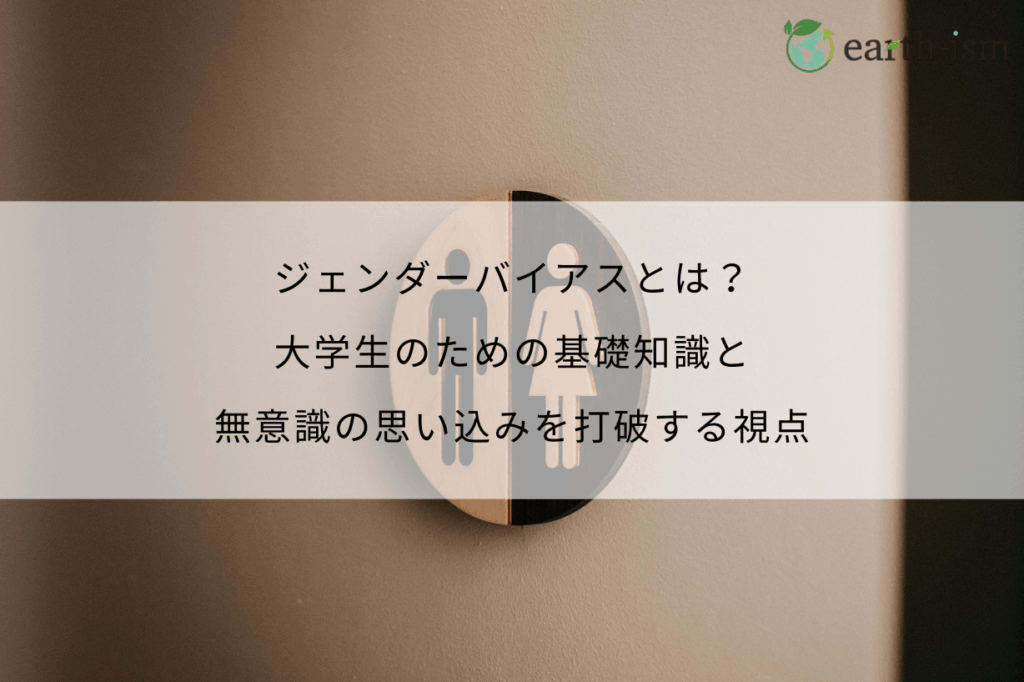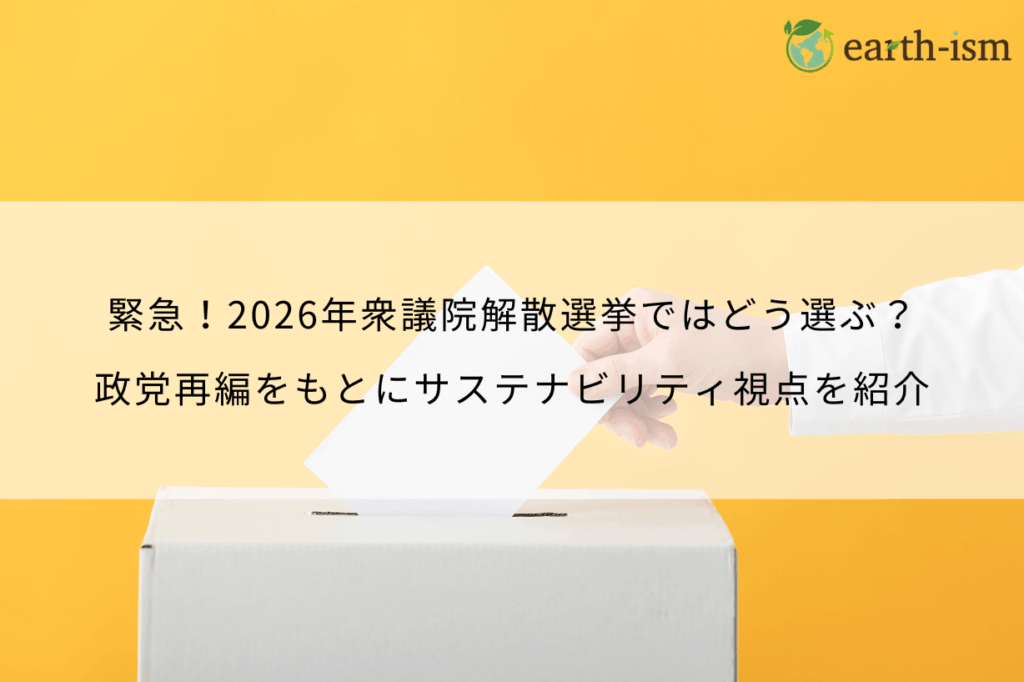Xジェンダーとは?意味や特徴・社会的課題などを分かりやすく解説
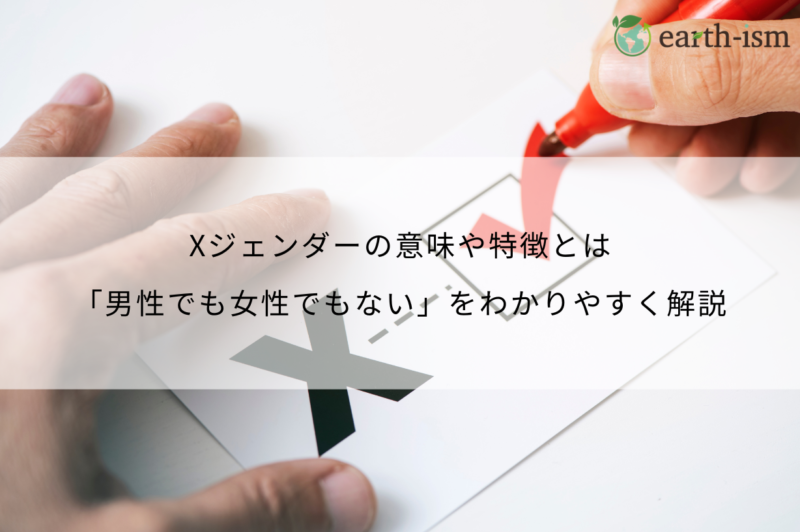
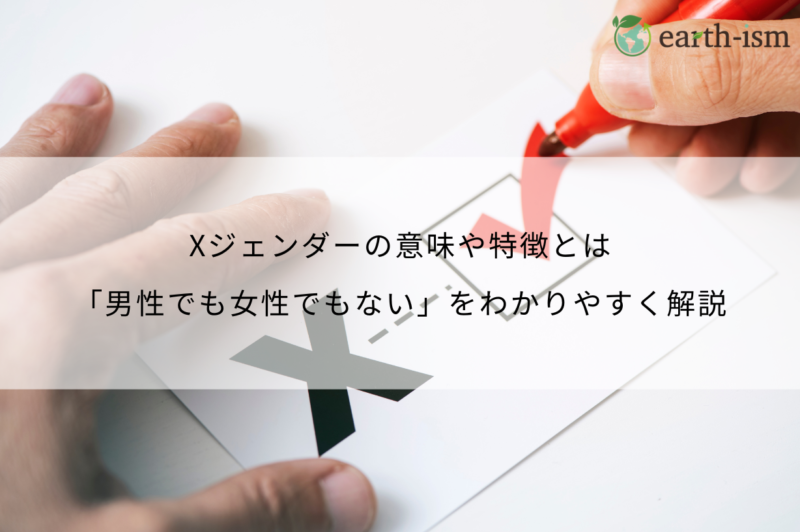
Contents
「Xジェンダー」という言葉を、最近よく見かけるようになったものの 「具体的にどういう意味?」「自分に当てはまるのかもしれない」「誰かに説明したいけど、うまく言葉にできない」と思っている方は多いのではないでしょうか。
Xジェンダーとは、性自認において「男性でも女性でもない」と感じる人々を指す言葉です。性の多様性が注目される現代において、性別を「男/女」という二択で捉えないXジェンダーという在り方は、多くの人にとって新しい視点を与えてくれます。
この記事では、Xジェンダーの定義や特徴だけでなく、ノンバイナリーやジェンダークィアといった関連用語、そしてXジェンダーの人々が直面している社会的課題まで、わかりやすく丁寧に解説します。
自分自身の性別について深く考えたい方も、身近な誰かを理解したい方も、Xジェンダーという多様な性のあり方を知ることは、誰もが“自分らしく生きられる社会”をつくる一歩になります。あなたの理解が誰かの安心や希望につながるので、ぜひ最後までお読みください。
Xジェンダーの特徴


Xジェンダーの特徴は、従来の男女二元論にとらわれない性別認識にあります。これは、自身を男性でも女性でもない、あるいはその両方、または全く別の性別として認識することを意味します。
| 一般的な性別認識 | Xジェンダーの性別認識 |
| 男性または女性のどちらか | 男性でも女性でもない/両方の感覚を持つ/まったく別の性だと感じる |
つまり、「男」「女」以外の性別を自認している人たちのことを指します。例えば、下記のような人たちはXジェンダーに当てはまるといえるでしょう。
- 自分はどちらの性にも当てはまらないと感じる
- 男性と女性、両方の感覚を持っている
- 時や気分によって、自分の性別の感覚が変わる
- 「中間」や「無性」など、独自の性別としてとらえている
このように、Xジェンダーはひとつの型にはまらない多様な性のあり方です。
性自認・見た目・恋愛対象は別の話
Xジェンダーを理解するうえで重要なのが、次の3つの言葉の違いです。
| 用語 | 内容 | 関係性 |
| 性自認 | 自分が「どんな性別の人間だ」と感じるか | Xジェンダーはここに当たる |
| 性的指向 | どんな性別の人に惹かれるか | 異性愛・同性愛・両性愛など |
| 身体的性 | 生まれつきの体の性別 | 男性・女性・インターセックスなど |
Xジェンダーは、性自認に関わる用語です。そのため、外見や恋愛対象と一致するとは限りません。
「流動的な性自認」もある
Xジェンダーの中には、「日によって性の感じ方が変わる」といった人もいます。これを「流動的(フルイド)な性自認」と呼ぶことがあります。
例えば下記のような具体例です。
- 月曜日は「どちらでもない」と感じる
- 木曜日は「ちょっと男性っぽい」
- 金曜日は「中性的にいたい」
このように、性の認識が一定ではなく変化することも、Xジェンダーの特徴の一つです。
Xジェンダーと関連する2つの用語
Xジェンダーを理解するうえで知っておきたい用語もあわせて紹介します。
ノンバイナリー(Non-binary)
「男女のどちらか」に収まらない性自認を持つ人々全体を指す包括的な用語です。Xジェンダーはこのノンバイナリーの一形態とされています。
ジェンダークィア(Genderqueer)
性別という枠組みにとらわれない、あるいはその枠組み自体に疑問を投げかける考え方や生き方を表す言葉です。性別の在り方そのものに対して自由で批評的なスタンスをとることが特徴です。
※日本では「エックスジェンダー」という表記も使われますが、意味は同じです。


Xジェンダーの4種類
ここでは、Xジェンダーの中でよく知られている4つのタイプを紹介します。どれかに当てはまる必要はなく、「自分の感覚に一番近い表現を使う」ことが大切です。
1.中性(ちゅうせい)
男性でも女性でもない、中間的な性別として自分を認識するタイプです。
- 「男らしさ」「女らしさ」どちらにも偏らない存在として自分をとらえている
- ファッションや言葉遣いも中性的なスタイルを好む人が多い
- 自分を“無性”とは違い、「ちょうど間」にいると感じている場合が多い
上記のような特徴が挙げられます。
2.両性(りょうせい)
男性的な感覚と女性的な感覚を両方持っていると感じるタイプです。
- 「どちらの性も自分の中にある」と考える
- 時期や気分によって、どちらかの性の感覚が強くなることもある
- 男性性・女性性をどちらも肯定して生きている
上記のような特徴が挙げられます。
3.無性(むせい)
自分には性別がない、または性別という概念にしっくりこないと感じるタイプです。
- 性別という枠組みに違和感がある
- 「男性でも女性でもない」だけでなく、「そもそも性別が必要?」と感じている
- 性に対して“距離”を置く傾向がある
上記のような特徴が挙げられます。
4.不定(ふてい)/流動型
性別の認識が日によって、状況によって変わるタイプです。
- 「自分の性別が一定していない」と感じる
- 周囲の環境や心理状態によって性の感じ方が変化する
- フルイド(fluid)=流動的とも呼ばれる
上記のような特徴が挙げられます。
Xジェンダーの人々が直面する社会的課題


社会の仕組みの多くは今もなお「男性」か「女性」のどちらかで成り立っています。この「男女二元制」が前提となっている社会の中で、Xジェンダーの人々はさまざまな困難や生きづらさに直面しています。
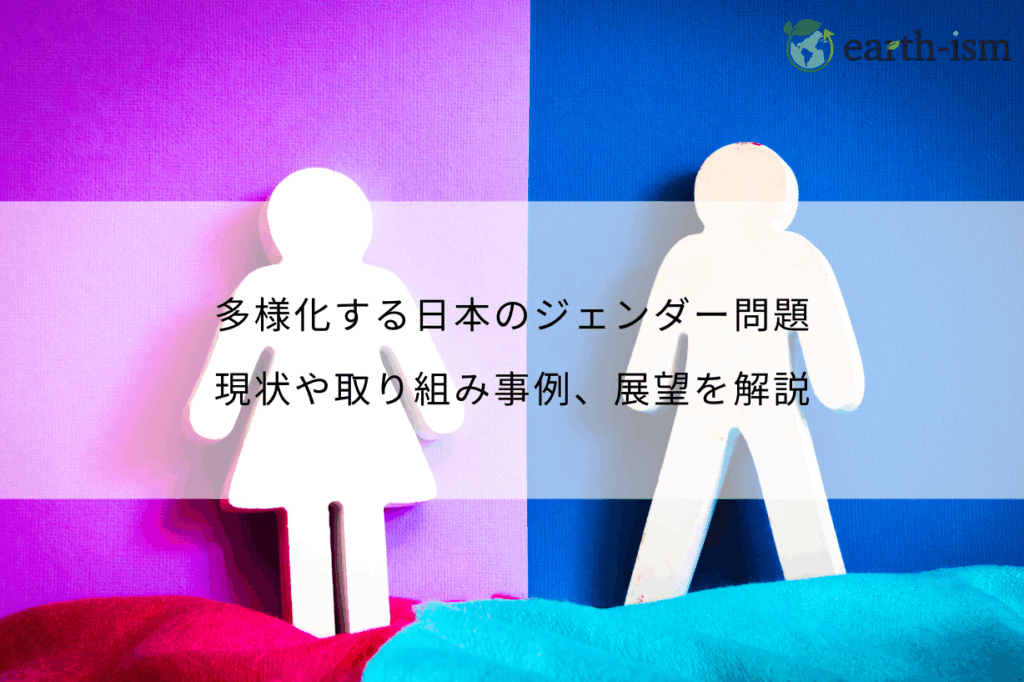
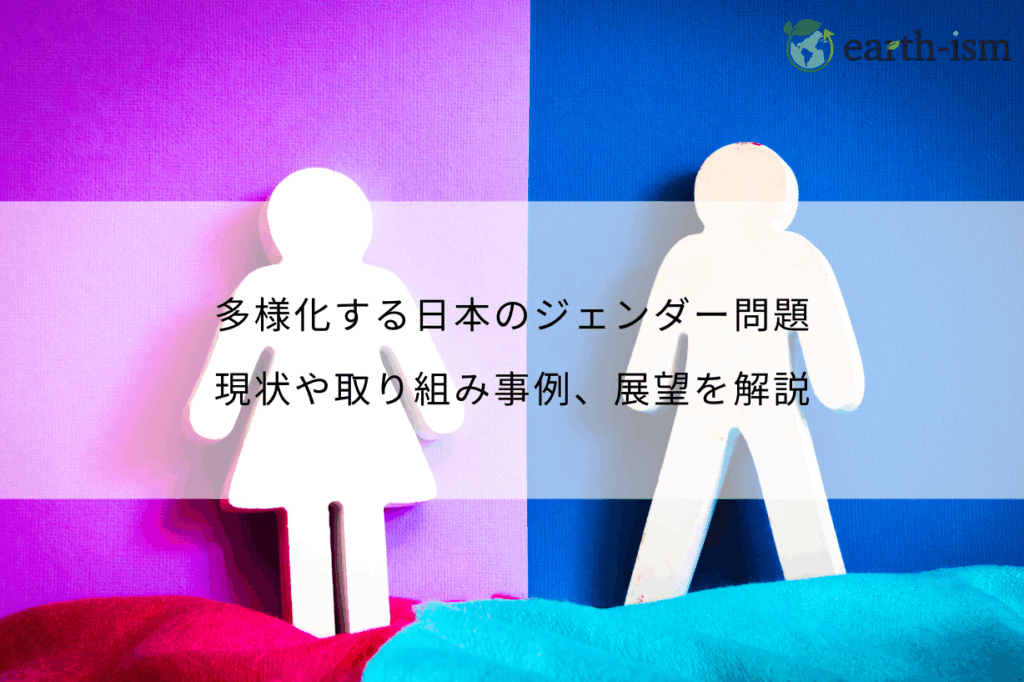
1. 公的制度に性別の選択肢がない
最も大きな課題のひとつは、「法的に認められていない」という現実です。日本を含む多くの国では、運転免許証・保険証・パスポートなどの公的書類に「男性」か「女性」しか選べないケースがほとんどです。
Xジェンダーの人にとって、自分の性別をどちらかに“仮置き”しなければならない場面が日常的にあり、そのたびに違和感や苦痛を抱えることになります。「存在を制度に否定されている」と感じることは、大きなストレスにつながります。
2. 学校や職場での制度・設備の壁
- トイレ・更衣室が男女別しかない
- 制服や服装規定に男女別ルールがある
- 呼び名や名簿が性別によって分けられる
- 人事書類や保険手続きに性別記入欄が必須
このような仕組みは、Xジェンダーの人にとって「自分に合った選択肢が存在しない」という現実を突きつけます。
中には、安心して使えるトイレがなく外出を控える人や、就職活動で不安を感じる人もいます。 「社会が自分の存在を想定していない」という感覚は、無力感や孤立感を強める原因となります。
3. 周囲からの無理解と偏見
Xジェンダーという言葉や考え方がまだ一般的ではないため、
- 「それってただのわがままじゃないの?」
- 「性別ってどっちかでしょ?」
- 「見た目は女なのに…?」
といった誤解や偏見にさらされることも少なくありません。
性自認を打ち明けた際に否定されたり、からかわれたりすることで、自分を表現すること自体が怖くなる人もいます。特に職場や学校といった日常生活の場では、無意識の差別(マイクロアグレッション)も大きな負担となります。
また、アメリカではトランプ政権下になったことによりLGBTQ+の人々への風当たりが強くなるなど、時代・環境の変化も激しいのが現状です。
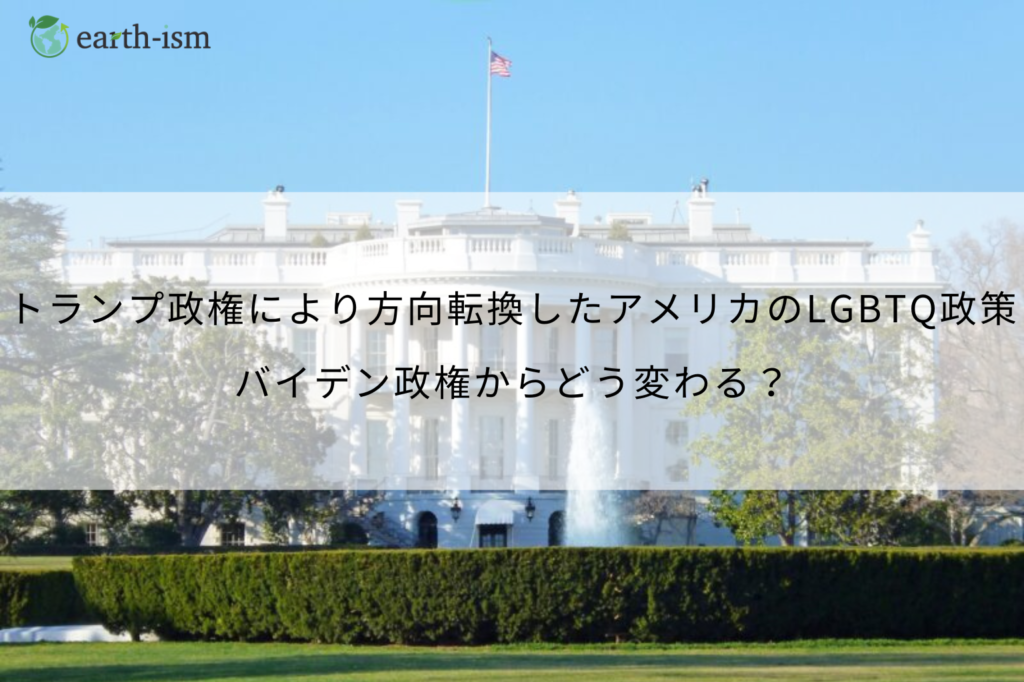
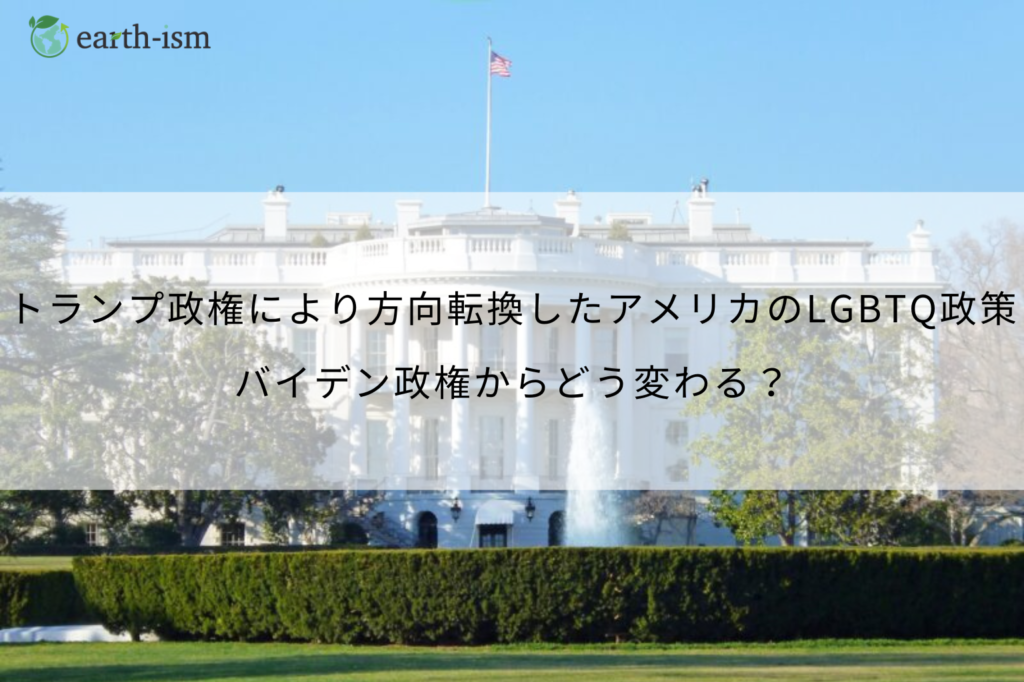
4. 「マイノリティストレス」による精神的負荷
こうした社会的課題の積み重ねは、「マイノリティストレス」と呼ばれる精神的なストレスを引き起こします。
- 自分を隠し続けなければならないこと
- 理解されないことへの諦めや孤独
- 将来に対する不安や恐怖
Xジェンダーであること自体が苦しいのではなく、社会の側が多様な性を受け入れる準備ができていないことが、苦しさを生んでいるのです。
Xジェンダーの人々に集まる声|「自認」と「行動」のバランスの取り方
Xジェンダーの「自認」が他者との共有空間に持ち込まれたとき、特に公共の場においては、複雑な課題が浮かび上がってきます。
性自認は自由。しかし公共の場は「共有空間」である
性自認はあくまで個人の内面的な認識であり、それ自体を否定することは誰にもできません。しかし、トイレや更衣室といった公共施設は「自分だけ」の空間ではなく、他者と安全・安心を共有する場です。
たとえば、自認が女性であっても、身体的特徴や見た目が男性的である場合に女子トイレを利用すると、他の利用者が強い不安や違和感を抱くことがあります。
社会的なマイノリティであるからこそ、「相手の安心感や信頼を尊重する姿勢」が、性の多様性そのものへの理解と受容につながるのです。
【事例】“女子トイレに入ったXジェンダー”への賛否
2022年、あるXジェンダーを自認する当事者が、身体的には男性であるにもかかわらず女性用トイレを利用し、そのことをSNS上で発信したことが大きな議論を呼びました。
当人は「女性として振る舞うことを求められたので女性トイレを使った」と主張しましたが、多くのユーザーが「自認だけで女性トイレを使うのは配慮が足りないのでは」と反応。
LGBTQ+コミュニティ内でも「共感できない」「運動全体への信頼を損なう」といった声が相次ぎました。
このような事例は、個人の行動が社会全体の理解度や信頼感に直結することを示しています。
公共施設側の対応と「第3の選択肢」の整備も課題
施設側にも課題があります。多くの建物では、いまだにトイレや更衣室が「男性用・女性用」の二択しかなく、Xジェンダーの人が安心して使える空間が不足しています。
ジェンダーフリートイレや個室トイレの整備、名前で呼ばず番号や記号で呼ぶ運用など、制度・設備面の柔軟な見直しも必要です。ただし、それらが整うまでの過渡期には、利用者側の配慮・自制・説明責任が強く求められるでしょう。
単に「誰が悪い」と悪者探しをするのではなく、あくまで時代の価値観に合わせ、周りの迷惑とならないような行動が求められます。
「性の自由」と「他者への配慮」は矛盾しない
大切なのは、性自認を尊重することと、他者の安心を大切にすることは決して矛盾しないという認識です。
- 「自分の性をどう認識するか」はその人の自由
- しかし「どこで、どう振る舞うか」は社会との関係の中で慎重に選ぶべき
それぞれが「私はこう感じる」を主張するだけではなく、「相手はどう感じるか」にも心を配ることが、多様性と共生を成立させるカギになります。
Xジェンダーへの理解を深めるために
Xジェンダーへの理解を深めるためには、まず多様な性のあり方について学ぶことが重要です。書籍やオンライン資料、専門家の講演などを通じて、性の多様性に関する知識を広げていきましょう。
Xジェンダーの人々の声に直接耳を傾けることも大切です。当事者の体験談や思いを知ることで、より具体的な理解が深まります。
また、自身の中にある性別に関する固定観念や偏見に気づき、それらを見直す努力も必要です。「男らしさ」「女らしさ」といった既成概念にとらわれず、個人の多様性を受け入れる姿勢が求められるでしょう。さらに、職場や学校、地域社会などで、すべての人が居心地よく過ごせるインクルーシブな環境づくりに貢献することも、重要な取り組みの一つです。
また、ジェンダーをモチーフとした映画を鑑賞することによって知識を得るのも一つの手です。下記の記事で詳しく解説しているので、併せてご覧ください。


まとめ
Xジェンダーの存在は、性別が単純な二元論では捉えきれないことを私たちに教えてくれます。一人ひとりの性自認を尊重し、誰もが自分らしく生きられる社会を目指すことが重要です。
Xジェンダーについて理解を深めることは、すべての人々にとってより包摂的な社会を作る第一歩となります。この知識を基に、私たち一人ひとりが自身の周りから変化を起こしていくことで、徐々に社会全体がより多様性を受け入れる方向に進んでいくでしょう。
性別やセクシュアリティは個人的なものであり、それぞれの自己認識が最も重要です。他者の性自認を尊重し、誰もが安心して自分らしく生きられる社会づくりに、共に取り組んでいきましょう。