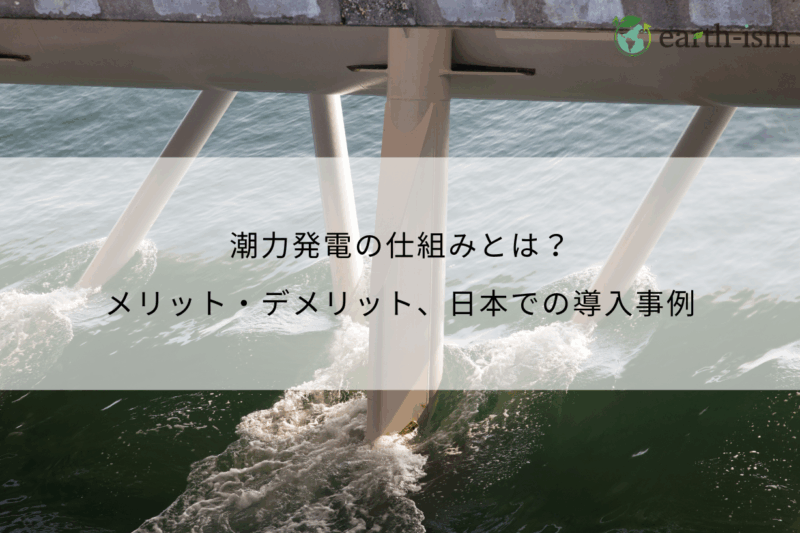スポーツ×SDGsの取り組み事例|代表的な企業や団体を徹底解説
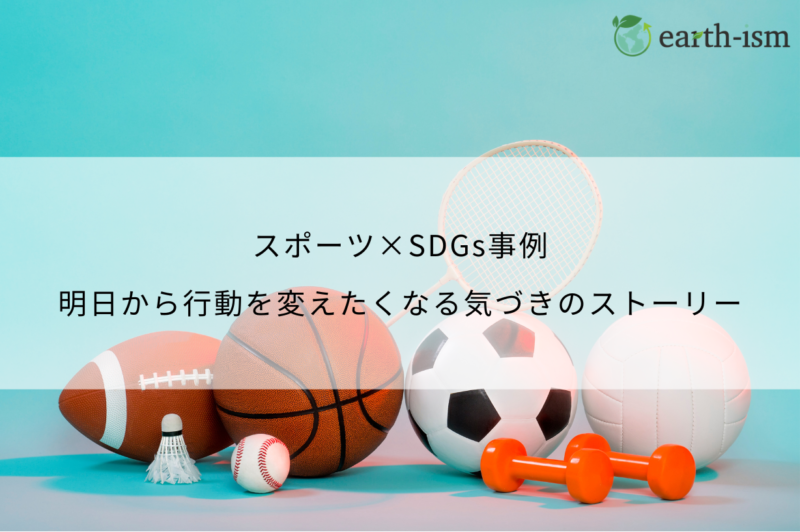
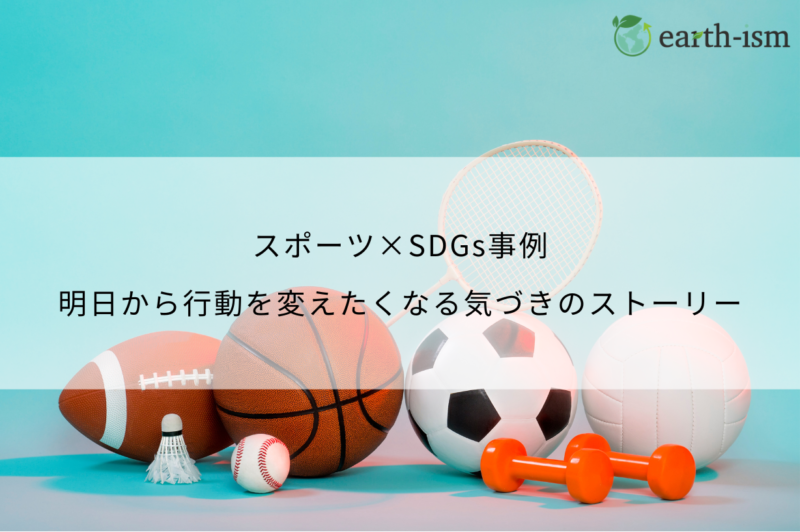
Contents
満員のスタジアムに響く歓声。ラストワンプレーで決まったゴールに、思わず隣の見知らぬ観客とハイタッチ。そんな瞬間、私たちは「スポーツの力」で心が動かされ、人と人がつながる感覚を体験しているのかもしれません。
しかし、その「スポーツを楽しめる日常」は、すべての人に等しく与えられているわけではありません。環境、貧困、紛争、性別や障がいといった壁が、誰かのスポーツとの出会いを遠ざけています。
そこで、注目したいのが「スポーツとSDGs(持続可能な開発目標)」の関係です。一見、別世界の話のように感じられるかもしれませんが、実はスポーツの中にはSDGsの理念が色濃く反映されている事例が数多くあります。
この記事では、「スポーツ×SDGs事例」を通じて、感動と気づきに満ちたストーリーをお届けします。そして、読んだあなたが明日からすぐにできるアクションも紹介していきます。
スポーツとSDGsが交わる理由


まずはスポーツSDGsの定義と、この2つが交わる理由について触れておきましょう。
SDGsとは?簡単におさらい
SDGsとは、国連が2015年に定めた「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」のこと。貧困や飢餓、教育、ジェンダー平等、気候変動、平和など、2030年までに達成すべき17の目標から成り立っています。
このSDGsの根底にあるのが、「誰一人取り残さない(Leave no one behind)」という理念。世界のどこにいても、誰であっても、尊厳ある人生を送れるように──それがこの目標群の核です。
驚くかもしれませんが、この17の目標の多くは、スポーツと深く結びついています。たとえば「健康と福祉(目標3)」「質の高い教育(目標4)」「ジェンダー平等(目標5)」「平和と公正(目標16)」などが挙げられます。
スポーツはただ身体を動かすだけでなく、教育、心の成長、社会参加など、あらゆる面で人を前進させる手段でもあるのです。
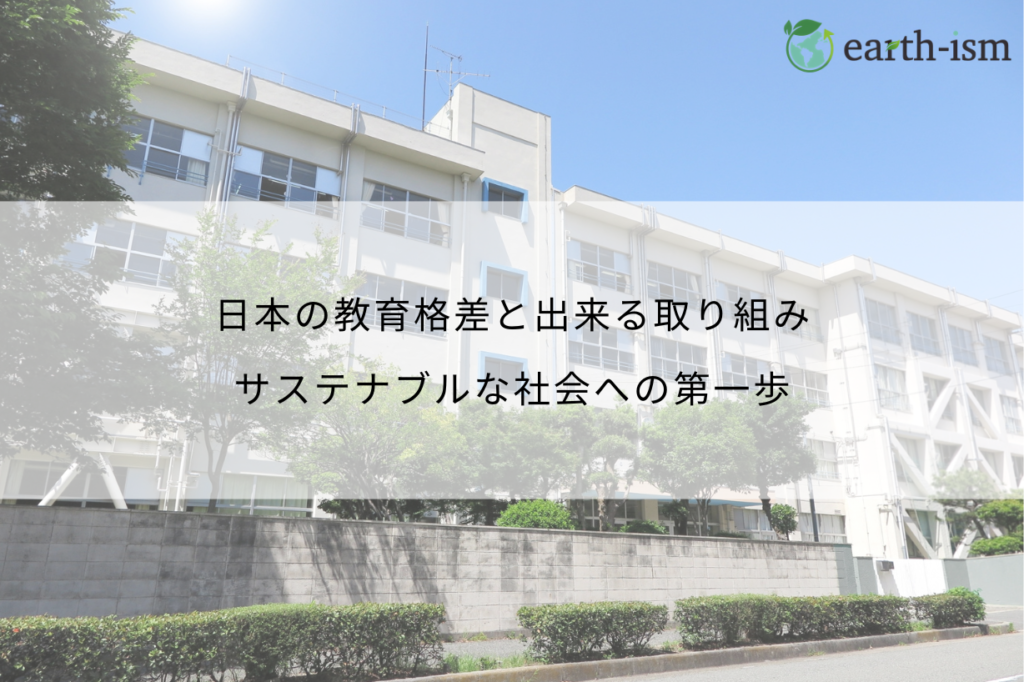
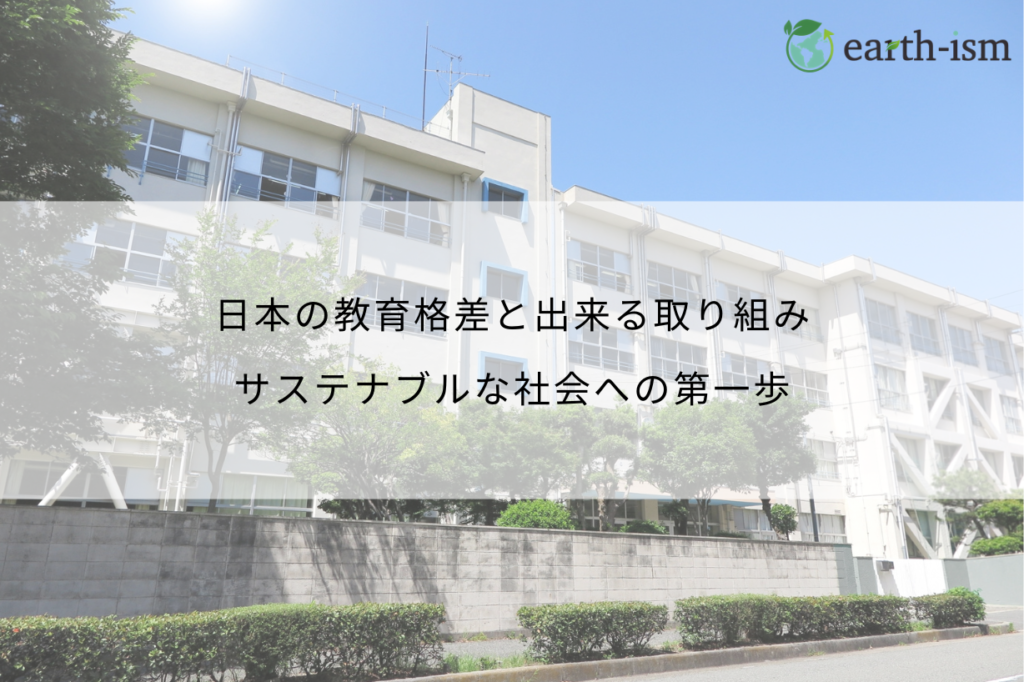
スポーツがもつ「社会変革の力」
スポーツは、国境、言語、宗教、立場を超えて人々をつなぐ「共通言語」です。ワールドカップやオリンピックで見られるように、全世界の注目が集まる舞台では、競技の枠を超えて「平和」や「共生」のメッセージが発信されることも少なくありません。
さらに、スポーツは個人の生活にも影響を与えます。自信、仲間との協力、目標に向かう努力──そうした心の成長は、学校や家庭では得られない「生きる力」を育みます。
だからこそ、スポーツには「社会を変える力」があるのです。近年では「環境配慮型スポーツ」や「インクルーシブなスポーツ」といった取り組みが広がりを見せ、SDGsとスポーツの融合がますます進んでいます。
国内外の「スポーツ×SDGs」注目事例
ここからは、実際に行われている「スポーツ×SDGs事例」を見ていきましょう。
1.Jリーグの「GREEN PROJECT」(日本)


Jリーグは2022年から「Jリーグ GREEN PROJECT」を本格始動させました。この取り組みでは、スタジアムのごみ分別の強化、再生可能エネルギーの活用、エコグッズの配布など、サステナブルなスタジアムの実現を目指しています。
具体的には、観客が使用するカップや容器に再利用素材を導入。試合会場ではリサイクルステーションを設置し、子ども向けにごみ分別のクイズ企画も行っています。まさに「楽しみながら学べるSDGs教育」と言えるでしょう。
このプロジェクトは、スポーツと社会貢献の融合を象徴する好例です。観客自身がSDGsの当事者となる体験が、「スポーツの場を使った行動変容」を促しています。
2.adidas「Made To Be Remade」(ドイツ発)


スポーツ用品の世界的ブランドadidasは、「Made To Be Remade」という再生可能ランニングシューズを開発。使用後は回収し、再び新しい靴にリサイクルする仕組みを導入しました。
これは単なる環境施策ではありません。靴の設計段階から「循環型デザイン」を追求し、スポーツの持続可能性を一から見直したのです。市民ランナーや学生アスリートにも広がりを見せ、フェアトレードスポーツ用品として注目を集めています。
この取り組みは、スポーツを楽しむことと環境保護が両立できるという「新しい常識」を私たちに示しています。
3.難民の希望に|IOCの「難民選手団」(国際)


国際オリンピック委員会(IOC)は、2016年リオ五輪から「難民選手団(Refugee Olympic Team)」を設置。故郷を追われた選手たちが、国や旗に関係なく「アスリート」として世界の舞台に立てるようにしたのです。
この選手団は、「スポーツと平和」の象徴として世界中から支持を集めています。競技だけでなく、その背後にある物語、つまり戦火を逃れ、過酷な状況でもトレーニングを続けた姿は、多くの人に「難民問題」を考えるきっかけを与えています。
スポーツが、声なき人々の「代弁者」になる。これこそスポーツとSDGsが交わる真価ではないでしょうか。
4.夏の甲子園と「つなぐ」SDGs(日本)


高校野球の聖地、夏の甲子園も近年ではSDGsに配慮した大会運営へと舵を切っています。
2024年大会では、プラスチック削減のため応援グッズやペットボトルの再利用促進、紙コップや弁当容器のリサイクル素材活用が行われました。また、会場内のごみ分別も積極的に促され、資源循環への意識が高まっています。環境保全プロジェクト「KOSHIEN“eco”Challenge」が設立されたことにより、企業も観客も巻き込んでエコなプロジェクトが推進されています。
さらに、障がい者観客席の整備や手話通訳ボランティアの導入など、包摂性を高める工夫も随所に見られます。朝日新聞社や高野連によるこれらの取り組みは、「誰もが野球を楽しめる環境」を目指す大きな一歩です。
注目したいのは、教育との連携です。出場校の中には、地域課題をSDGs学習として野球部活動とつなげる試みも始まっています。スポーツと教育、地域との協働──これらすべてが「未来につなぐ」実践なのです。
5.MIZUNO|スポーツ用品を「直して使う」という提案(日本)


MIZUNOは、野球をはじめとするダイヤモンドスポーツの分野で、道具を「使い捨てない」文化を育てています。たとえば、グローブやバットの修理を体験できるワークショップを各地で実施。子どもたちに「モノを大切に使う」意識を自然と伝えています。
また、ライフ&ヘルス事業では、ひざの負担を軽減する「ひざ誘導ソール」などを開発。高齢者やリハビリ中の人々にも歩く楽しさを届け、健康寿命の延伸にも貢献しています。
「長く使う」「誰もが動ける」。MIZUNOのSDGsは、スポーツを通じて生活全体を支える視点から動いています。
6.Bリーグ|バスケットボールから広がる「循環型社会」(日本)
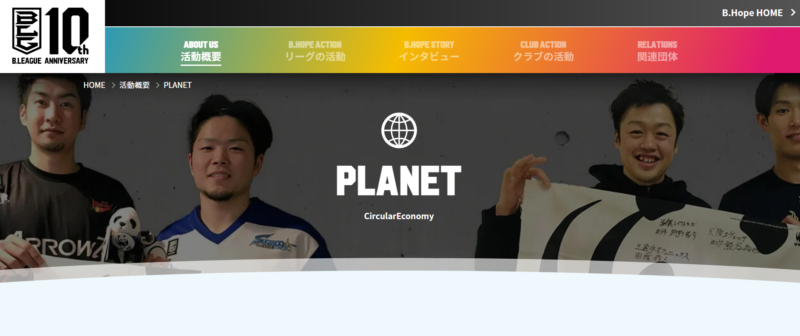
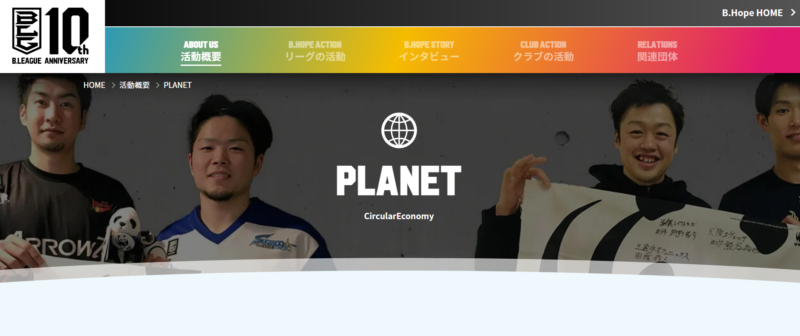
男子プロバスケットボールリーグのBリーグは、SDGsへの取り組みを「PEOPLE」「PEACE」「PLANET」の3つの柱で展開しています。
中でも注目は、「PLANET」の一環として行われているB.Hope Ecology Pass(エコパス)。これは、不要になった衣類を回収し、それを再生してバスケグッズに作り変えるというサーキュラーエコノミーの実践例です(2023年)。
このように、バスケットボールを起点にした資源循環の取り組みは、観客や地域を巻き込む形で展開されており、日常とスポーツの間に新しい接点を生み出しています。
7.西武ライオンズ|野球を通じて「地球にいいこと」(日本)


プロ野球・埼玉西武ライオンズは、「SAVE THE EARTH Lions GREEN UP!プロジェクト」のもと、スタジアムでのごみ分別の徹底、食品廃棄物のリサイクル、チャリティーオークションなど、持続可能な球場運営を実践していました(2023年シーズン)。
この活動は、野球観戦をただの娯楽にとどめず、楽しみながら環境について考える機会へと変えています。特にスタジアムに来るファミリー層や子どもたちにとって、「スポーツ×エコ」の学びの場になっているのが特長です。
「応援すること」が地球のためになる──そんな新しい観戦スタイルを提案しているのが、ライオンズの挑戦です。
私たちができる「スポーツ×SDGs」アクション


大きなプロジェクトを立ち上げなくても、私たち一人ひとりがスポーツを通じてSDGsに関われる方法はたくさんあります。
1. スポーツ観戦時のエコ意識
スポーツ観戦を楽しむときも、環境への配慮はできます。たとえばマイボトルやマイバッグの持参。ペットボトルやレジ袋を減らすだけで、ごみの削減につながります。最近はスタジアムに給水機が設置されていることも多く、マイボトルを活用しやすい環境が整ってきました。
ごみ分別にも積極的に参加しましょう。分別ステーションを利用するだけで、リサイクル率が大きく上がります。スタッフの案内がある場合は、それに従って行動するだけでも十分です。移動は公共交通機関で。CO₂排出を抑えるだけでなく、渋滞回避やエネルギー効率の面でもメリットがあります。
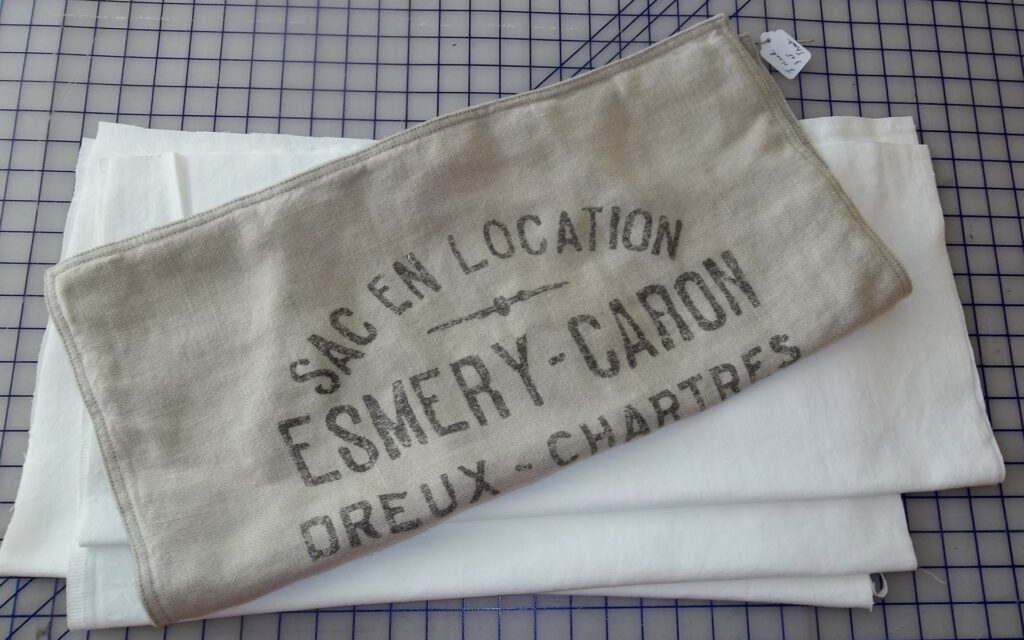
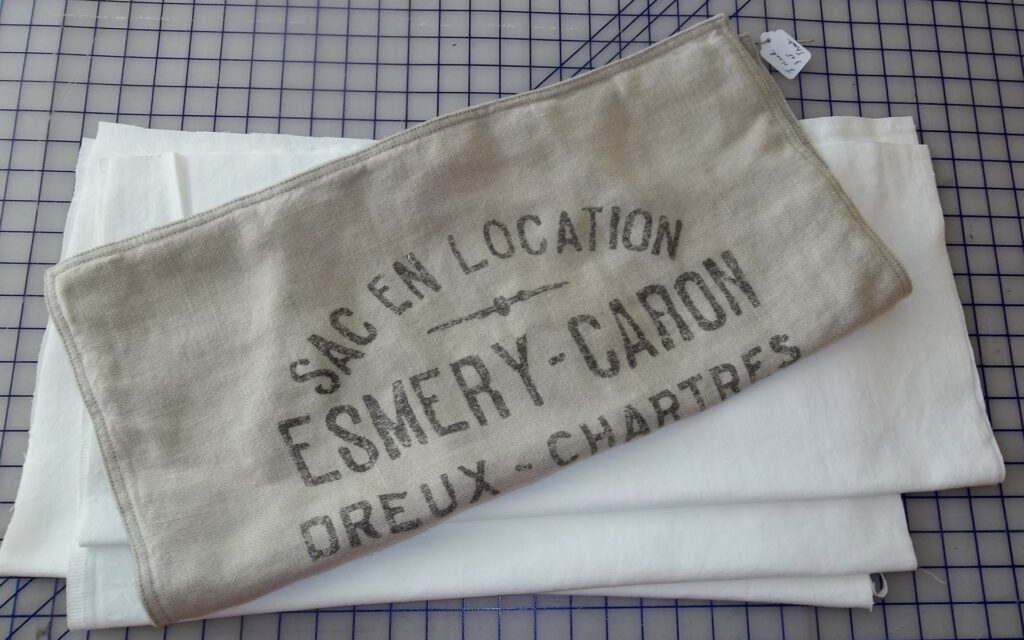
2. フェアトレード素材のウェアやシューズを選ぶ
スポーツを楽しむうえで欠かせないのが、ウェアやシューズといった道具選び。そのとき、フェアトレード素材や再生繊維を使用した製品を選ぶことで、環境保護や生産者の権利保護に貢献できます。
たとえば、adidasやNIKEなどの大手ブランドは、ペットボトル由来の再生ポリエステルやオーガニックコットンを使ったアイテムを展開しています。また、フェアトレード認証を受けた製品は、労働環境や適正価格の保証がなされているため、買うことで「応援の意思」を示せます。
日常的に使うものをサステナブルな選択に変えるだけで、スポーツと社会貢献がつながるのです。


3. 障がい者スポーツや地域イベントへの参加・支援
誰もが楽しめるスポーツ環境をつくることも、SDGsの大切なテーマです。
パラスポーツの大会や障がい者向けの地域イベントに観戦者として足を運んだり、ボランティアや運営支援を行ったりすることは、インクルーシブな社会づくりへの直接的なアクションになります。
たとえば、地域で開かれるユニファイドスポーツ(障がいのある人とない人が一緒にプレーする競技)に参加してみることで、新しいつながりや視点が得られるかもしれません。応援も立派な支援の一つです。
スポーツは「みんなのもの」という当たり前を支える側になることが、行動の第一歩です。
4. 子どもに向けたスポーツ教育や寄付
経済的な理由でスポーツに取り組めない子どもたちは世界中に多くいます。そんな子どもたちのためにできるのが、スポーツ教育を支援する活動や、中古用具の寄付です。
使わなくなったボールやスパイク、ユニフォームなども、開発途上国の学校やスポーツ団体では貴重な資源となります。NGO・NPOを通じて寄付する仕組みも整ってきており、手軽に参加できます。
また、国内でも困窮家庭の子どもたちが部活動を続けられるよう、寄付で支援する団体も増えています。
「誰もがスポーツにアクセスできる社会」を支えることは、次世代への大きな贈り物になります。
5. SNSでのシェア・情報拡散
「自分にできることは少ない」と感じたときこそ、知ったことを広める力が役立ちます。
たとえば、JリーグのGREEN PROJECTや難民選手団の話、環境に配慮したスポーツブランドの情報などをSNSでシェアすることで、「そんな取り組みがあるんだ」と気づく人が増えます。
いい活動を知り、共感し、誰かに伝える。その行動自体が、間接的にプロジェクトの後押しになります。
誰でも、どこにいても、今すぐできるSDGsアクションです。
SDGsスポーツ「プロギング」とは


SDGsのスポーツといえば「プロギング」が有名です。
プロギングはスウェーデン語の「plocka upp(拾う)」と英語の「jogging(走る)」を組み合わせた造語であり、2016年にスウェーデンアスリートのエリック・アルストロム氏が始めました。ランニングを「自己ベスト達成のためではなくゴミ拾いを行うためのもの」としたスポーツで、今では世界中で親しまれています。
「ポジティブな力で足元から世界を変える」がプロギングのスローガンです。
環境問題が取りざたされる際にはネガティブなワードで溢れがちですが、ジョギングを通してあくまで”楽しく”ゴミ拾いをすることによって、自分の力でも世界を少しずつ変えられることを発信しています。
社会貢献ができるだけではなく、身も心も健康になれる点が人気の理由といえるでしょう。


まとめ|走り出せば、未来はきっと変わる


スポーツには、ただの娯楽以上の価値があります。心を打ち、社会を動かし、世界を変える力があるのです。
SDGsと聞くと、どこか遠い問題のように感じるかもしれません。でも、次にボールを蹴るとき、バットを振るとき、観戦するその瞬間に、私たちは社会に参加しているのだと気づくことが大切です。
「この行動は、どんな未来につながっているだろう?」
そう問いかけることから、すべては始まります。スポーツとSDGsをつなげるのは、誰かの立派なプロジェクトだけではありません。私たち一人ひとりの選択こそが、「持続可能な未来」を走り出すエンジンになるのです。