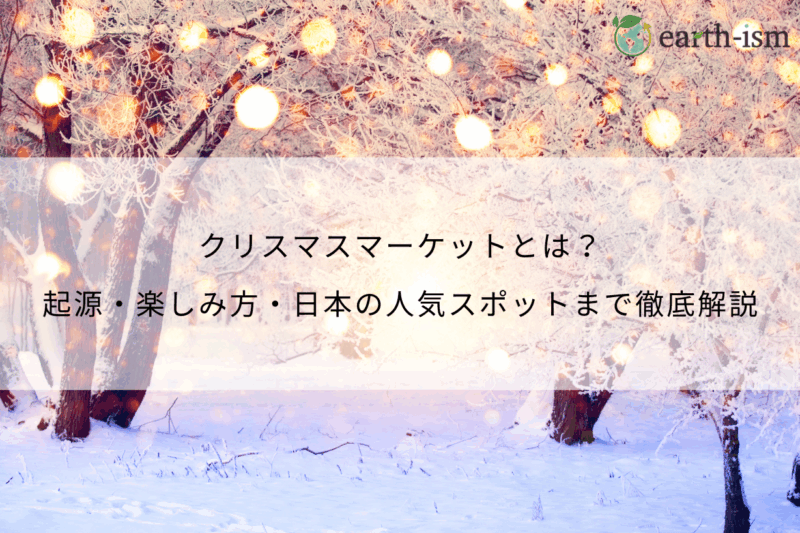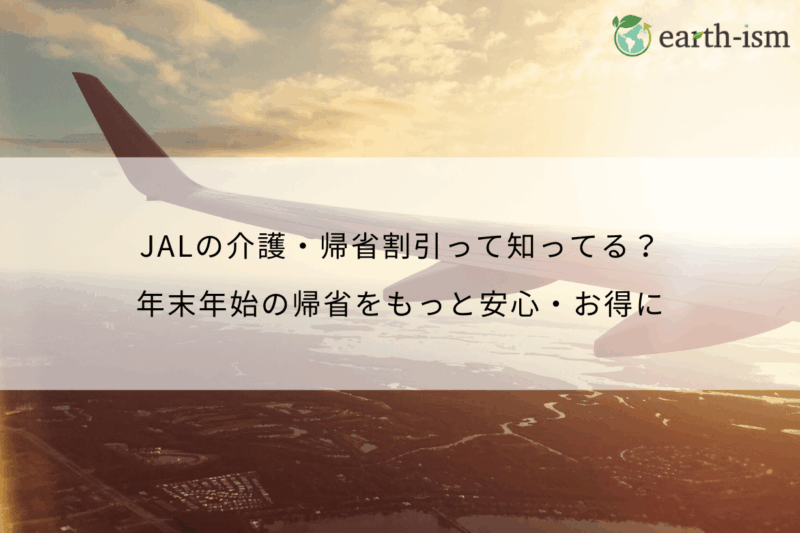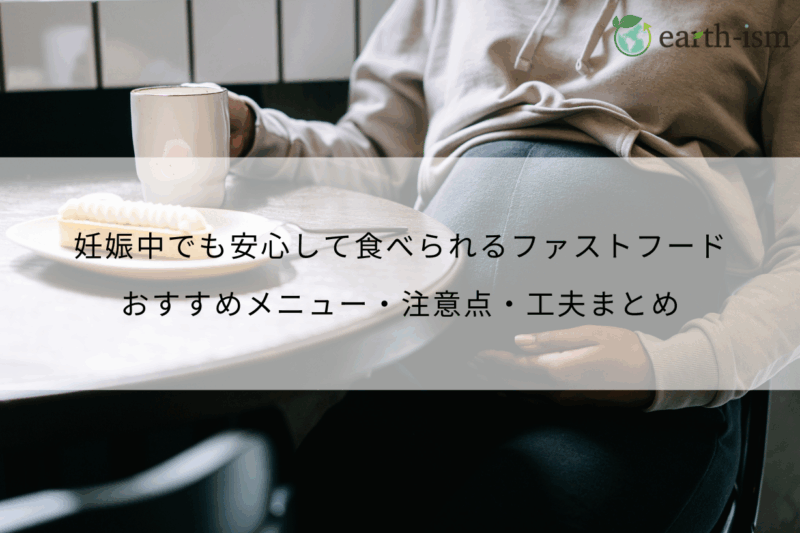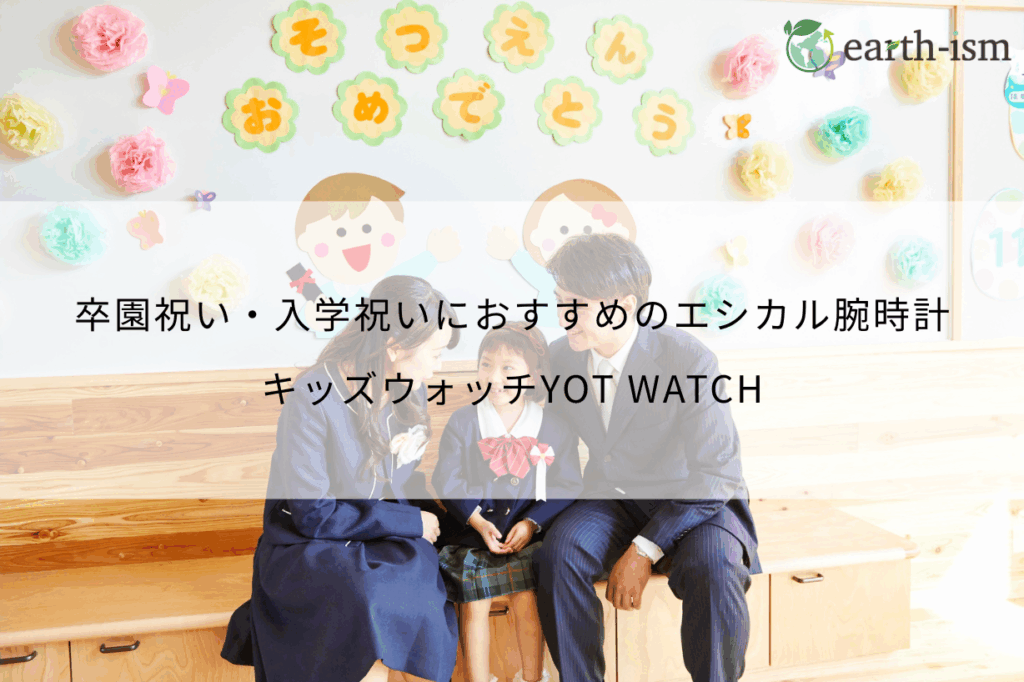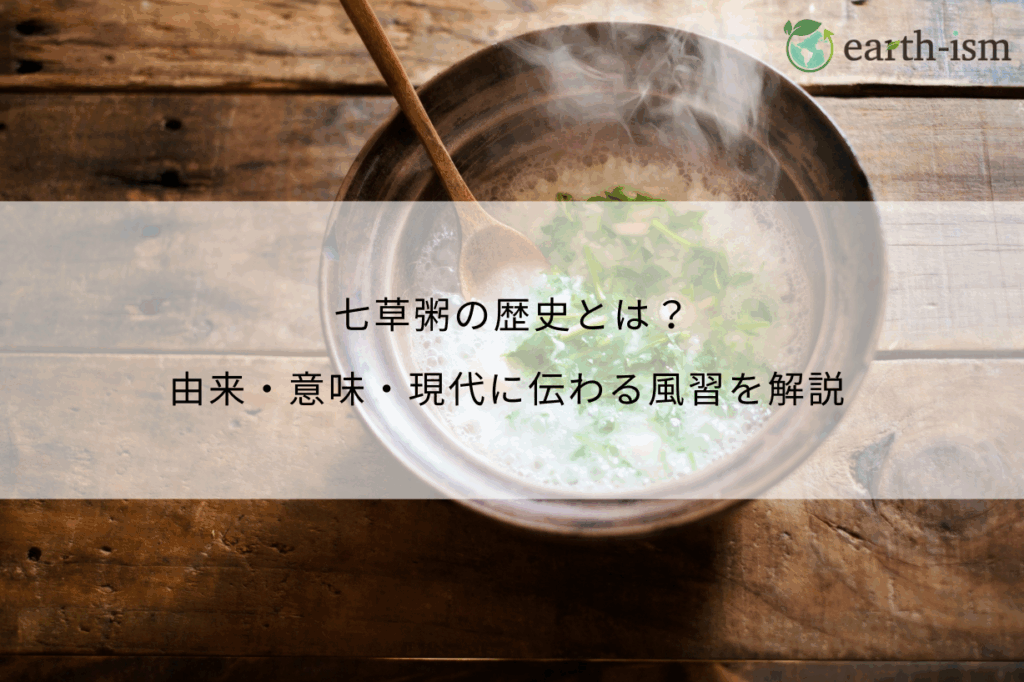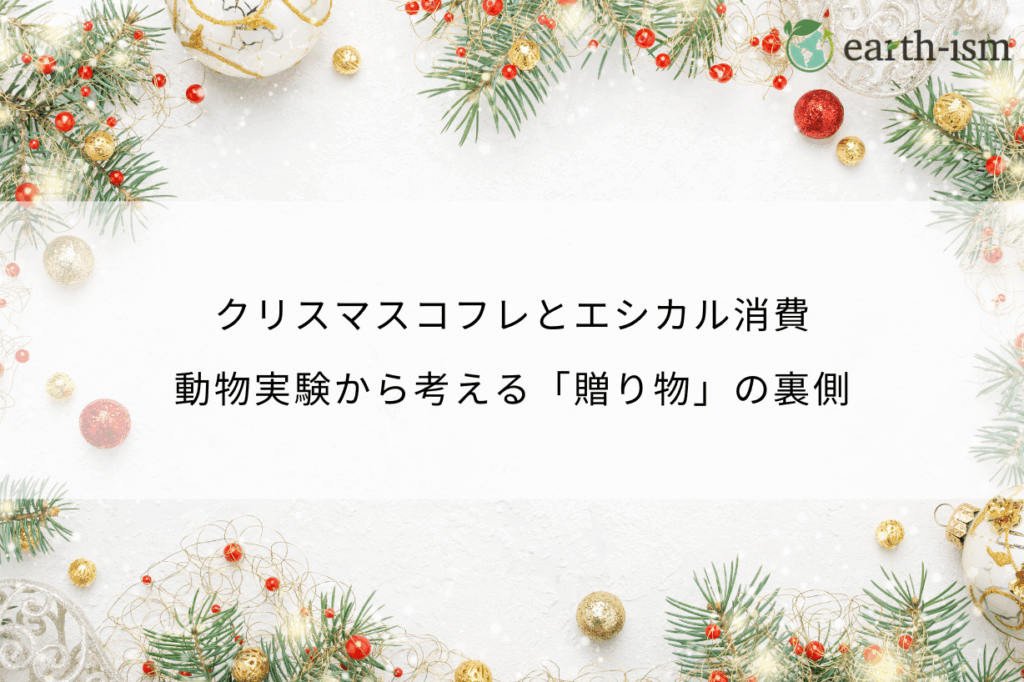アップサイクルに取り組む企業とは?企業での事例と取り組み方をわかりやすく解説


Contents
近年、SDGsやサステナブルという言葉が当たり前に聞かれるようになりました。その中でも「アップサイクル」という取り組みが注目を集めています。アップサイクルとは、ただのリサイクルとは違い、廃材や使われなくなったモノに新たな価値を与えて生まれ変わらせる考え方です。
多くの企業が廃棄物を減らすだけでなく、そこに付加価値をつけて製品化し、環境負荷を抑えながら新たなビジネスを創り出しています。
では、アップサイクルに取り組む企業は、どのように素材を集め、どんな形で製品やサービスに活かしているのでしょうか。また、自社で取り組みたいと考えたとき、どんな進め方があるのでしょうか。
この記事では、アップサイクルの意味と企業活動での位置づけ、国内外の具体的な事例、さらに自社で始める際のヒントまで、わかりやすく解説します。企業によるアップサイクルの理解を深め、エコな生活に役立てましょう。


そもそもアップサイクルとは?企業での意味と役割


そもそもアップサイクルとは何か、まずはその基本的な概念から解説します。
アップサイクルの定義と基本概念
アップサイクルとは、不要になったものや廃棄されるはずのものを、単なるリサイクルとは異なり、より価値の高い新しい製品として生まれ変わらせる取り組みのことです。企業が廃材や副産物を新しい製品やサービスに変えることで、資源を有効活用できるだけでなく、ブランド価値の向上にもつながります。
リサイクルとの違い
アップサイクルとリサイクルは、似て非なる概念です。
リサイクルは、使い終わったものを再び資源として利用することです。しかし、加工の過程で元の素材の品質や価値が低下してしまう「ダウンサイクル」となるケースも少なくありません。これに対してアップサイクルは、廃材に新たなアイデアや技術を加え、「より価値の高いもの」へと生まれ変わらせる点が最大の違いです。
単に資源を回すだけでなく、クリエイティブに価値を付加することが特徴です。
企業活動にアップサイクルを取り入れる意味
環境への配慮が求められる今、企業は廃棄物を減らすだけでなく、その素材を活かして新たな製品を生み出すアップサイクルで社会的責任を果たすことが期待されています。製造過程で出る端材や売れ残りを再活用することで、廃棄コスト削減にもつながります。
なぜ今、企業でアップサイクルが注目されているのか


それでは、なぜ今現在、企業がアップサイクルすることを求められているのでしょうか。その背景には、SDGsへの関心の高まりなど複数の要因があります。
SDGs・ESG投資との関係
アップサイクルは、国連のSDGs(持続可能な開発目標)の目標12「つくる責任 つかう責任」に深く関わります。また、投資家が企業の環境配慮を評価するESG投資の観点からも、廃棄物を価値ある資源として循環させる取り組みは高く評価されています。
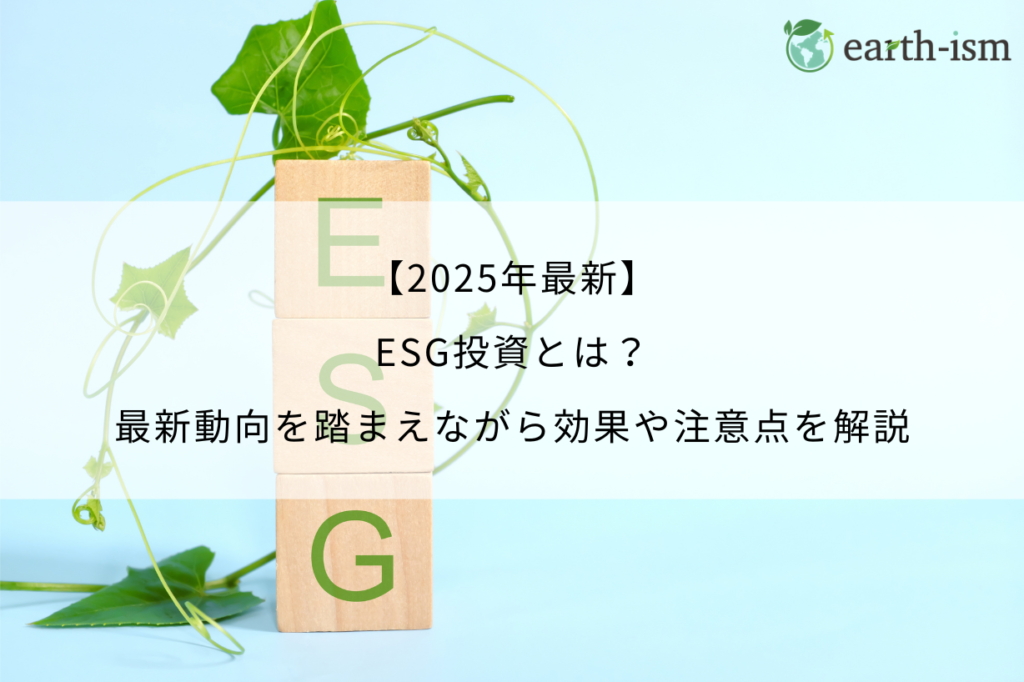
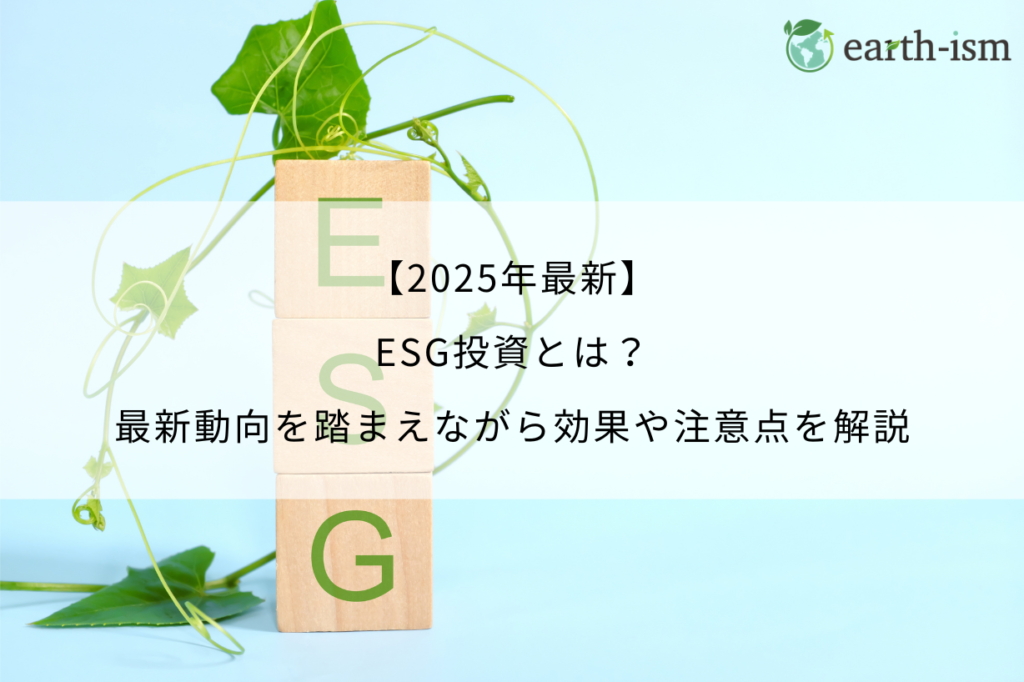
環境配慮型ビジネスへの消費者ニーズ
近年はZ世代を中心に「環境に優しい商品を選びたい」という意識が高まっています。アップサイクルはそのニーズに応える方法のひとつとして、多くのブランドが新商品やサービスの差別化に活用しています。


廃棄コスト削減・新たな収益化の可能性
廃材や副産物を有効活用することで、廃棄物の処理コストを抑えられるのはもちろん、付加価値の高い商品として販売することで新たな収益源になります。これまで「捨てるしかなかったもの」に新しい価値を与える発想が、アップサイクルの魅力です。
アップサイクルに取り組む企業の具体的事例【国内編】
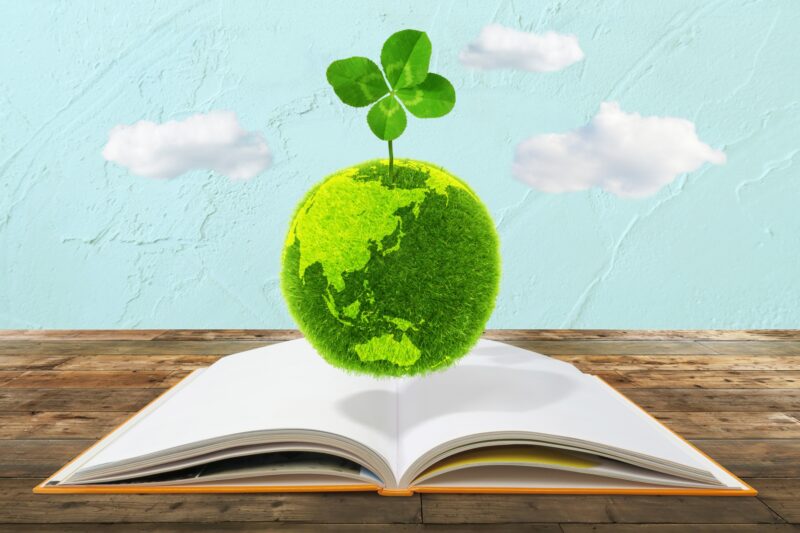
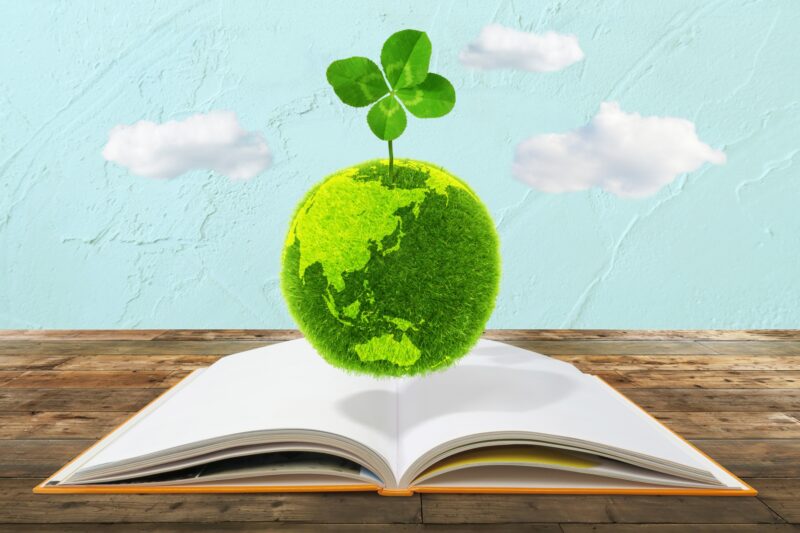
アップサイクルに積極的に取り組んでいる企業は国内でも数多くあります。特に素材の使用量が多いアパレルや建築、そして食品業界での注目事例をご紹介します。
アパレル・ファッションブランドの事例
衣料品業界では、古着や廃棄される布を再活用する事例が増えています。たとえば、JEPLANの「BRING」は不要な衣類を回収し、再資源化した糸で新しい服を作っています。また、大手ブランドでも、製造過程で出る端切れを小物やバッグにリメイクする取り組みが広がっています。
建築・インテリア業界の事例
建築現場や解体現場で発生する木材や古材を家具にアップサイクルする企業も増えています。古民家の梁や柱を活かしてテーブルやインテリア小物に作り変えることで、廃材に新しい命を吹き込んでいます。
食品ロスを減らすフードアップサイクル事例
食品業界でも、規格外野菜や副産物を活用したアップサイクル商品が増えています。果物の皮や野菜の切れ端を使ったジャム、ドライフルーツ、スナックなどが代表例です。食品ロス削減に取り組む企業として、フードアップサイクルは今後さらに拡大すると考えられています。
海外のアップサイクル企業の取り組み


日本とは異なり、海外では特にアップサイクルが進んでいます。以下で簡単に見ていきましょう。
欧米のブランド・スタートアップ
欧米ではアップサイクルはすでに多くの企業のブランド戦略に組み込まれています。Patagoniaは古着の回収と再生に積極的で、製品寿命を延ばす修理サービスも展開しています。また、TerraCycleは世界各地で回収した廃プラを再資源化し、日用品としてアップサイクルする仕組みを提供しています。
アジア発の地域密着型アップサイクル
アジアでも漁網や廃プラスチックをバッグやアクセサリーにアップサイクルするスタートアップが登場しています。海洋ゴミ問題をビジネスで解決する動きとして注目されています。
amu株式会社では、廃漁具由来マテリアルブランド「amuca®」で開発した廃漁具由来の生地やサングラスを2025年に展示したことで話題になりました。
企業でアップサイクルを取り入れるには?進め方とポイント


企業でアップサイクルを取り入れるにはハードルが高い、と思う方も多いでしょう。しかし、いくつかのポイントを押さえれば、エシカルな企業経営を推進できます。具体的にどう進めるべきか、見ていきましょう。
どの素材をアップサイクルできるか洗い出す
まずは、自社の製造工程やサービスの中で、廃棄されている素材や副産物をリストアップしてみましょう。普段は捨ててしまうものの中に、新たな価値の種が眠っています。
効果的な洗い出しを行うためには、製造現場のスタッフや廃棄物処理担当者へのヒアリングが欠かせません。日常的に廃棄されている材料の種類、量、発生タイミングを詳細に把握することで、アップサイクルの可能性を見極めることができます。
例えば、食品メーカーであれば規格外野菜や果物の皮、繊維メーカーであれば端切れや糸くず、金属加工業であれば削りカスや不良品などが対象となります。
自社独自の生産量に注意する
また、季節性や生産量の変動も考慮に入れる必要があります。安定的にアップサイクル事業を展開するためには、年間を通じて一定量の素材が確保できることが重要です。さらに、素材の品質や安全性についても事前に検証し、食品安全基準や化学物質規制などの法的要件をクリアできるかどうかも確認しておきましょう。
パートナー企業・仕入れ先をどう探すか
アップサイクルは自社だけで完結しにくいことも多いため、加工技術を持つ企業や協力工場とのパートナーシップが重要です。近年は、異業種とのコラボで新しい商品を開発する企業も増えています。
効果的なパートナー探しには、複数のアプローチが必要です。まず、業界団体や商工会議所などのネットワークを活用し、技術力のある中小企業や町工場との接点を作ることが重要です。これらの企業は独自の加工技術や設備を持っていることが多く、大企業では難しい柔軟な対応が期待できます。
また、大学や研究機関との産学連携も有効な手段です。材料工学や環境工学の研究者は、新しい加工技術や素材変換技術に関する豊富な知識を持っており、技術的な課題解決に大きく貢献してくれます。さらに、学生のアイデアやエネルギーを活用することで、従来にない革新的なアップサイクル手法を開発できる可能性もあります。
ブランド価値としての発信が重要
アップサイクルは単なる素材再利用にとどまらず、企業の「ストーリー」として伝えることが大切です。
現代の消費者は、商品の機能や価格だけでなく、その背景にある企業の価値観や社会貢献への取り組みを重視する傾向が強まっています。アップサイクルの取り組みを効果的に発信することで、ブランドイメージの向上や顧客ロイヤルティの向上につながります。
ストーリーテリングにおいては、「なぜアップサイクルに取り組むのか」という企業の想いや使命感を明確に伝えることが重要です。環境保護への貢献、地域社会との協働、新しい価値創造への挑戦など、企業独自の動機や目標を具体的なエピソードとともに語ることで、消費者の共感を得ることができます。
アップサイクル企業を選ぶ・応援する視点


一方で、消費者としてアップサイクル企業を応援する際には、以下のポイントが重要です。
取り組みの透明性
どのように素材を回収し、どの工程でアップサイクルしているのかが公開されている企業は、信頼性が高いと言えます。認証や第三者評価も参考になります。
真にアップサイクルに取り組んでいる企業は、プロセスの詳細を積極的に公開しています。具体的には、廃棄物の種類と回収方法、加工技術の詳細、最終製品までの工程数、関わる人員や企業名、環境負荷の削減効果などを数値やグラフで明示している企業が信頼できます。
また、第三者機関による認証も重要な判断材料となります。GRS(Global Recycled Standard)、GOTS(Global Organic Textile Standard)、Cradle to Cradle認証、FSC認証などの国際的な認証マークが付いている商品は、厳格な基準をクリアしている証拠です。
持続性のある仕組み
一時的なキャンペーンではなく、継続的に廃棄物削減に取り組んでいるかを確認しましょう。供給元や製造ラインの安定性も重要です。
持続可能なアップサイクル事業には、安定した素材供給体制が不可欠です。優良な企業は、複数の廃棄物供給源を確保し、季節変動や供給量の変化にも対応できる柔軟な仕組みを構築しています。また、素材の品質管理体制も整備されており、一定の品質基準を維持した商品を継続的に提供できる体制が整っています。
事業の継続性を判断するポイントとして、企業の設立年数や事業規模、従業員数の推移も参考になります。長期間にわたってアップサイクル事業を継続している企業は、ノウハウの蓄積があり、市場の変化にも対応できる可能性が高いです。
地域や産業を巻き込む広がり
地域の人々や産業と連携して、循環型の仕組みを作っている企業は、アップサイクルの意義をさらに高めています。地域課題の解決にもつながる点が注目されています。
真に優れたアップサイクル企業は、単独で活動するのではなく、地域のエコシステム全体を巻き込んだ循環型の仕組みを構築しています。例えば、地元農家から規格外野菜を調達し、地域の工場で加工し、地元の販売店で売るといった地産地消型のモデルは、輸送コストの削減だけでなく地域経済の活性化にも貢献します。
また、教育機関との連携も重要な要素です。小中学校での環境教育プログラムの提供、大学との共同研究、職業訓練校での技術指導などを通じて、次世代の人材育成や環境意識の向上に貢献している企業は、社会的価値の高い活動を行っていると評価できます。
earth-ism編集部おすすめのアップサイクルに取り組む企業の例|株式会社Ay


株式会社Ayは、群馬県桐生市の伝統的な絹織物「伊勢崎銘仙」を活用し、アップサイクルによって新たな価値を生み出す事業を展開しています。
着物文化を継承しつつ、廃棄物や環境負荷を抑えた持続可能な製造モデルを構築。地域経済との連携にも力を入れ、地元職人・産業との協働を通じて地場の活性化に寄与しています。こうした活動は、脱炭素やコスト削減にもつながり、CSR(企業の社会的責任)視点から「環境」「文化」「社会」を統合的に重視する姿勢が見られます。
詳しくは下記の記事で説明しているので、合わせてご覧ください。


まとめ|アップサイクル企業の動きを知り、自社でも小さく始めよう


アップサイクルは、大企業だけの取り組みではありません。中小企業でも、廃材を活かした新商品開発や、地元の異業種との連携など、小さな一歩から始められます。
消費者としても、アップサイクル製品を選ぶことが企業の背中を押す力になります。私たち一人ひとりが、資源を循環させる新しい価値を応援し、広げていきましょう。