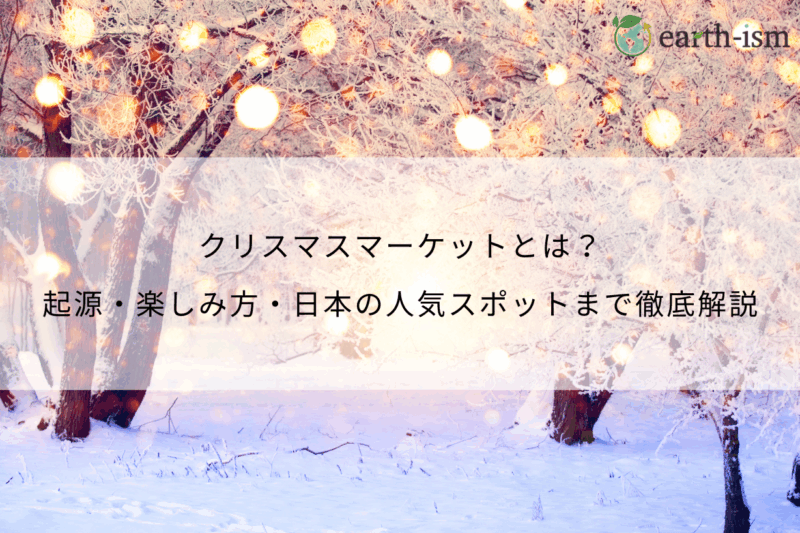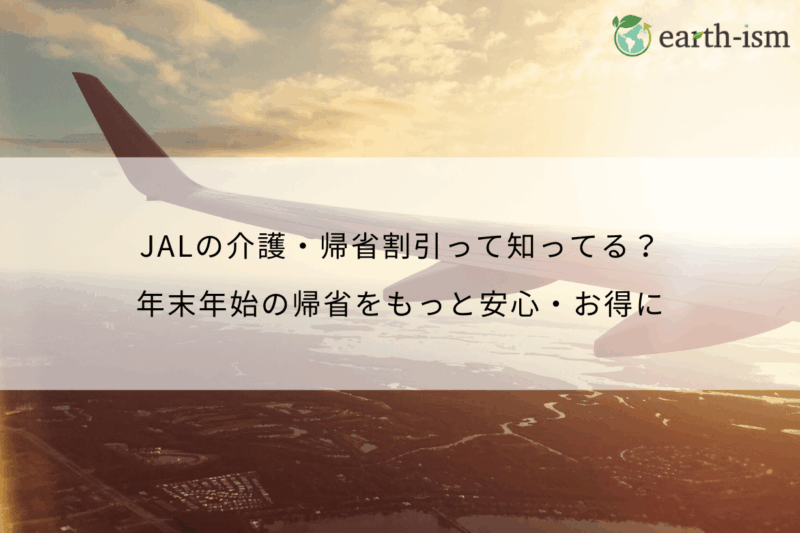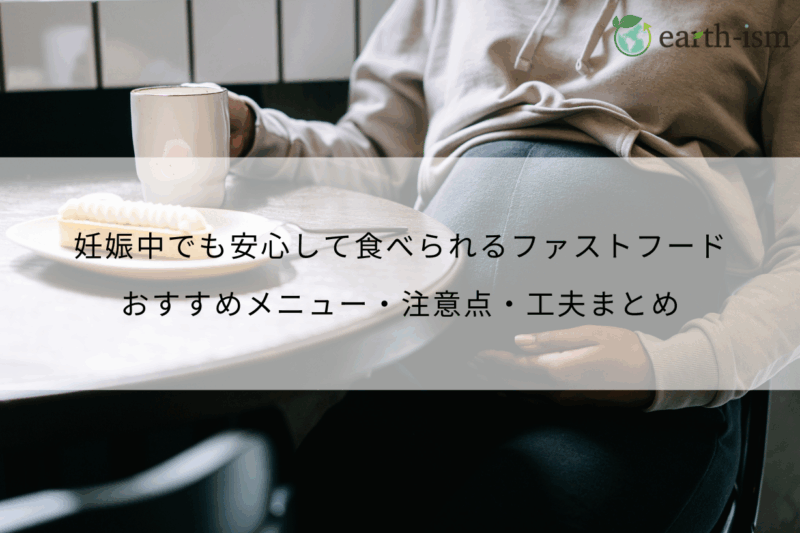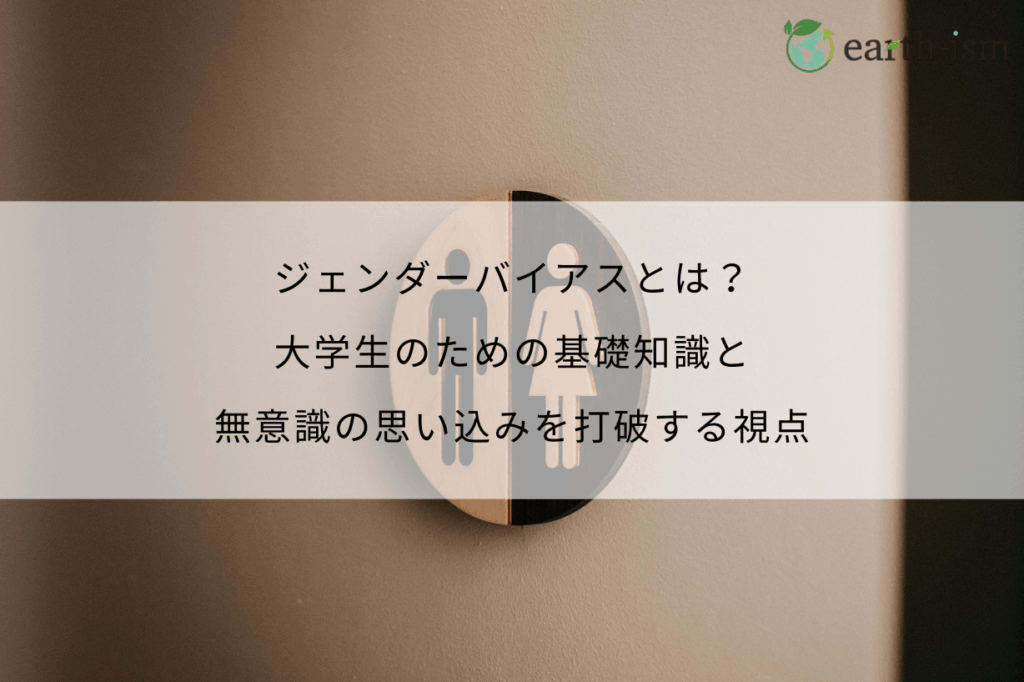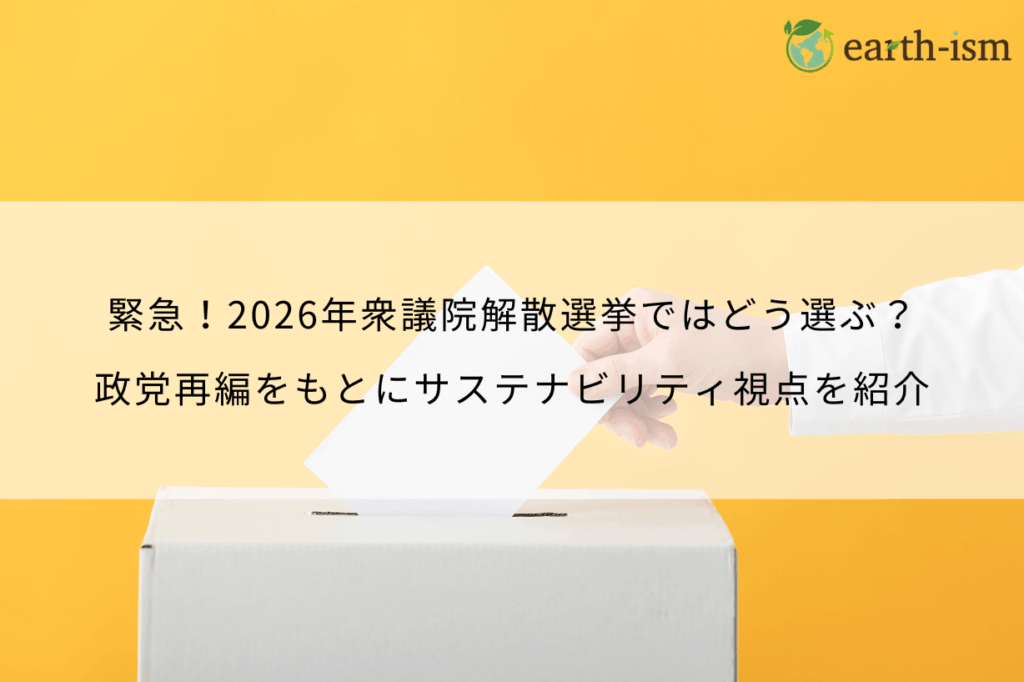今年のお月見は何をする?海外と日本の最新お月見事情を調査してみた
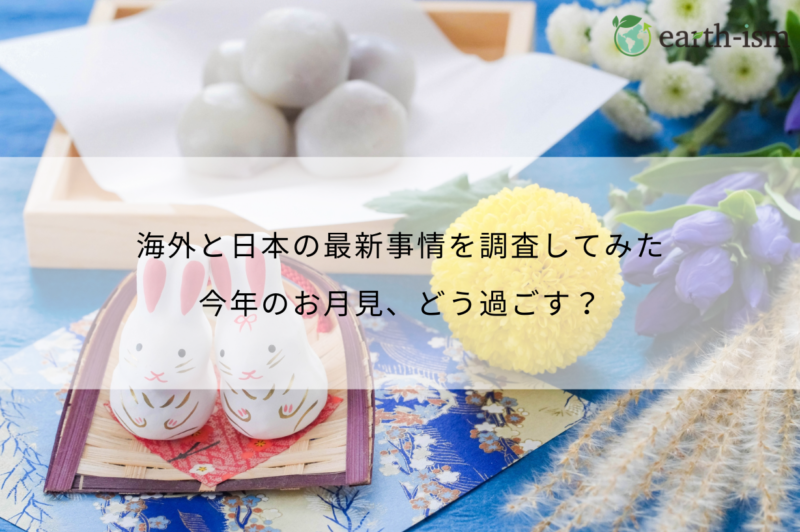
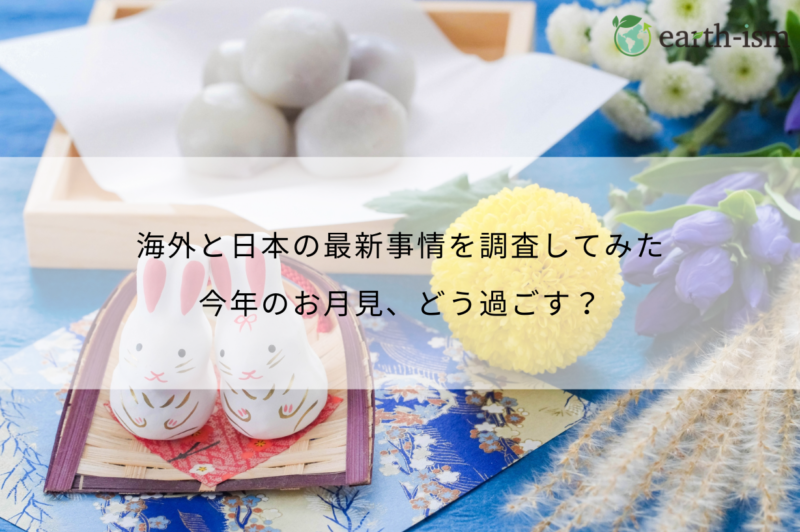
澄んだ夜空にぽっかり浮かぶ満月を眺める「お月見」は、日本人にとって秋を彩る風物詩です。しかし近年は、月見バーガーやSNS映えする月見スイーツなど、伝統の楽しみ方に加えて現代ならではのスタイルも増えています。
さらに海外にも、国ごとにちょっとユニークな月見文化があるのをご存じでしょうか?
この記事では、日本と海外の月見事情を比べながら、今年のお月見をもっと楽しむための情報をお届けします。中秋の名月や月見バーガーなどの言葉で毎年お月見シーズンを思い出す、という方は、ぜひ最後までお読みください。
そもそもお月見とは?由来と意味


お月見の深い起源について、改めて考える機会は少ないかもしれません。そこで、ここではお月見の歴史について解説します。
お月見の起源と歴史
お月見は、平安時代に中国から伝わった「中秋節」がもとになったとされています。当時の貴族たちは、秋の澄んだ夜空に浮かぶ月を愛で、酒宴や詩歌を楽しんだそうです。その後、庶民の間にも広がり、収穫への感謝や五穀豊穣を願う行事として根付いていきました。
いつお月見をするの?2025年の中秋の名月はいつ?
お月見といえば「十五夜」とも呼ばれる中秋の名月の日に行われます。2025年の中秋の名月は9月6日です。この日は旧暦8月15日にあたり、例年9月中旬から10月上旬に訪れます。満月とは必ずしも同じ日とは限らず、少しずれる年もあります。月の公転周期が一定ではないためです。
お月見に欠かせないススキやお団子の意味
お月見といえば、ススキとお団子をお供えする風習が有名です。ススキは稲穂に見立てられ、秋の収穫を象徴します。お団子は月に見立てられ、感謝の気持ちと魔除けの意味が込められています。地域によっては里芋を供えるところもあり、「芋名月」と呼ばれることもあります。
海外ではお月見って何をするの?


ところで、海外にも日本のようにお月見文化はあるのでしょうか。日本のお月見は中国起源ということもあり、アジア地域には類似の月を祝う文化が見られます。一方、欧米では日本やアジアとは異なる形で月が文化や伝承に深く関わっています。
以下で詳しく解説します。
中国の中秋節と月餅の話
日本のお月見のルーツともいえる中国の「中秋節」は、家族が集まって月を愛でながら月餅を食べる大切な行事です。月餅には月のように丸い形に「家族円満」の意味が込められており、親しい人への贈り物としても重宝されています。近年では、伝統的な味に加えてアイスクリーム月餅やチョコレート月餅など、進化系も人気です。
韓国の秋夕(チュソク)の過ごし方
韓国の秋夕(チュソク)は日本のお盆に近い位置づけで、祖先を敬い、家族で集まって過ごす一大イベントです。収穫を祝う意味もあり、「ソンピョン」という米粉のお餅を作ってお供えし、親戚一同で月を眺めながら食事を楽しみます。夜には伝統的な踊りや地域のお祭りも開かれる地域があります。
欧米での月にまつわる風習やイベント
満月が特別な意味を持つ風習やイベントは存在します。例えば、満月の夜に夜通し音楽やダンスを楽しむ「フルムーンパーティー」などが有名です。特にタイのパンガン島で開かれるフルムーンパーティーは、世界中から若者が集まる人気イベントです。また、ハロウィンやイースターでも月は神秘の象徴として語られています。
日本と海外の月見文化を比べてみよう


同じ「月」を見ていても、国や地域によって楽しみ方や込められた意味はさまざまです。日本と海外の月見文化を比べると、意外な共通点や違いが見えてきます。
月を「静かに愛でる」日本、「集いと縁起」の中国・韓国
日本のお月見は、秋の収穫を祝いつつ、静かに月を眺める行事として発展してきました。静寂の中で月を見て心を落ち着けるスタイルが特徴です。
一方で、中国の中秋節や韓国の秋夕は、家族や親族が集まってごちそうを分かち合う「団らん行事」としての色が濃く、にぎやかに過ごすのが一般的です。
「団子」と「月餅」「ソンピョン」というように、丸い食べ物を用意して「満ちる・円満」を祈るのは共通点と言えます。
欧米では神秘と伝承の象徴
欧米では「月そのものを祝う日」は少ないものの、満月は占いや魔術、ハロウィンなどの文化に深く関わっています。
たとえば、狼男の伝説は満月の夜に変身するとされ、ハロウィンも満月と結びつけられることがあります。ケルト由来の伝承では、月は死者の世界とつながる扉とも考えられてきました。
このように、欧米では「月を見る」というより「月が物語を生む」という側面が強いのが特徴です。
ちょっとした豆知識|世界の満月の呼び名
欧米には満月に季節ごとの呼び名があります。たとえば9月の満月は「ハーベストムーン(収穫月)」と呼ばれ、農耕の節目を知らせる役割がありました。
こうした季節の月名は日本ではあまり知られていませんが、古くから月と農業が切り離せなかった世界共通の名残です。
最近のお月見の楽しみ方


2025年現在では、平安時代のように団子を食べながら歌を詠む、といったことはあまり見られません。最近ではどのような楽しみ方があるのか、以下で見ていきます。
月見バーガーで気軽にお月見気分
近年のお月見シーズンの風物詩といえば、ファストフード各社が出す「月見バーガー」です。2025年も各チェーンから新作が登場予定で、卵を月に見立てたバーガーが人気を集めています。家族でテイクアウトして、自宅のベランダで月を眺めながら食べるだけでも立派なお月見になります。
マクドナルドの「月見バーガー」は1991年から続く定番商品で、毎年微妙にレシピを変えながら進化を続けています。モスバーガーでは「月見フォカッチャ」、ロッテリアでは「月見リブサンド」など、各チェーンが独自の月見メニューを展開しており、食べ比べを楽しむファンも多くいます。
また、コンビニエンスストアでも月見をテーマにしたサンドイッチやおにぎりが登場し、より手軽にお月見気分を味わえるようになりました。
SNSでは各社の月見バーガーを食べ比べて投稿する「月見バーガー巡り」も話題となっており、若い世代を中心に新しいお月見の楽しみ方として定着しています。家族みんなで異なるブランドの月見バーガーを購入し、味の違いを楽しみながら月を眺めるのも現代らしいお月見スタイルです。
家でお団子以外に楽しめるスイーツやアレンジレシピ


お団子が苦手な人や子どもが喜ぶものを作りたい場合は、月見プリンや月見パンケーキなどもおすすめです。黄身をお月様に見立てた「月見オムライス」などのアレンジレシピもSNSで話題です。夜空をイメージした青いゼリーや星形クッキーを添えれば、テーブルの上でお月見気分を盛り上げられます。
近年特に人気なのが「月見スイーツ」の手作りです。卵黄を使った月見プリンは、カスタードの優しい甘さが子どもにも大人にも好評で、上にきな粉をかけることで和風の味わいも楽しめます。また、パンケーキの上に黄身を乗せた「月見パンケーキ」は、見た目のインパクトと美味しさで家族みんなが喜ぶメニューです。
料理系では、月見うどんや月見そばの進化版として、月見ラーメンや月見カレーなども人気があります。クリームチーズやマスカルポーネを使った洋風の月見スイーツも増えており、従来の和風にとらわれない自由な発想でお月見を楽しむ家庭が増えています。
YouTubeやInstagramでは、簡単にできる月見レシピの動画が多数投稿されており、料理初心者でも気軽にチャレンジできる環境が整っています。
ベランダや公園でのミニピクニックお月見
遠出をしなくても、ベランダや近所の公園でレジャーシートを広げてお月見を楽しむ人が増えています。温かいお茶とお菓子を用意し、夜風に当たりながら月を眺めるだけで、日常から少し離れた贅沢な時間を味わえます。
このスタイルは特にコロナ禍以降に人気が高まり、「おうちキャンプ」や「ベランピング」の延長として楽しまれています。マンションのベランダでも、LEDキャンドルやランタンを置くことで雰囲気を演出でき、近所迷惑を考慮しながら音楽を小さく流すなどの工夫で特別感を演出する家庭も多くあります。
公園でのお月見では、虫よけスプレーや防寒具の準備も重要です。また、近年では月の観察に適した双眼鏡や小型望遠鏡を持参して、月の表面のクレーターを観察したり、周辺の星座を確認したりする「天体観測付きお月見」も人気があります。
子どもと一緒に月の満ち欠けや宇宙について学ぶ良い機会としても活用されており、教育的側面も重視されています。
SNSで楽しむ!月の写真を撮ってシェア
最近はスマホで簡単に月の写真を撮れる時代です。SNSでは「#お月見フォト」で検索すると、美しい月やお団子の写真がたくさん投稿されています。今年は自分で撮った月の写真を家族や友人とシェアするのも楽しい過ごし方です。
スマートフォンのカメラ性能向上により、以前は一眼レフでないと難しかった月の撮影も手軽にできるようになりました。iPhone 15 ProやGoogle Pixel 8 Proなどの最新機種では、ナイトモードや超望遠レンズを使って月の表面の模様まで鮮明に撮影できます。
撮影のコツとしては、三脚やスマホスタンドを使って手ぶれを防ぐこと、月だけでなく建物や樹木とのシルエットも一緒に撮ることで構図に変化をつけることなどが挙げられます。
また、タイムラプス機能を使って月の動きを記録したり、連続写真で月の満ち欠けの変化を表現したりする創意工夫も見られます。
まとめ|今年は自分らしいお月見を楽しもう


お月見には、決まった形も正解もありません。静かに月を愛でるのも、家族でにぎやかにお団子を囲むのも、月見バーガーを片手に空を見上げるのも立派なお月見です。
海外を見れば、月は集いの象徴であったり、物語を生む神秘の存在であったりと、国ごとにさまざまな形で私たちの暮らしに寄り添っています。
今年はほんの少し目線を変えて、自分や家族にぴったりのスタイルで月を楽しんでみませんか?小さな工夫ひとつで、同じ月もきっと特別な思い出になるでしょう。