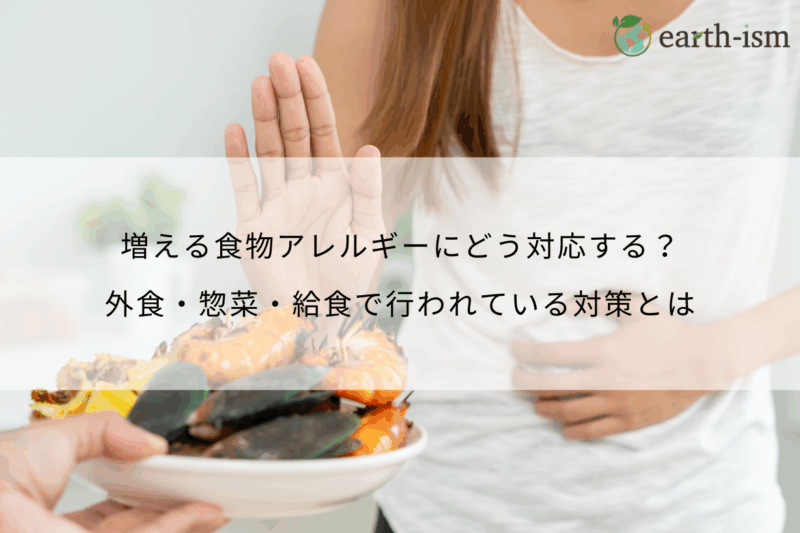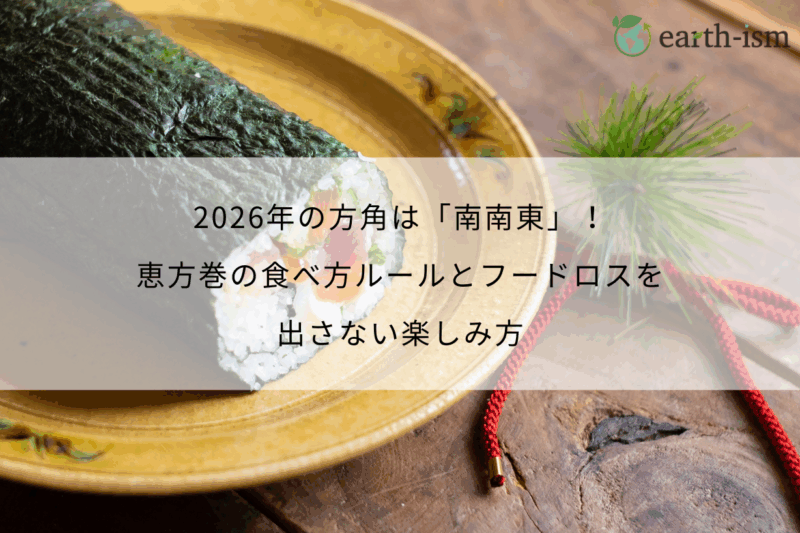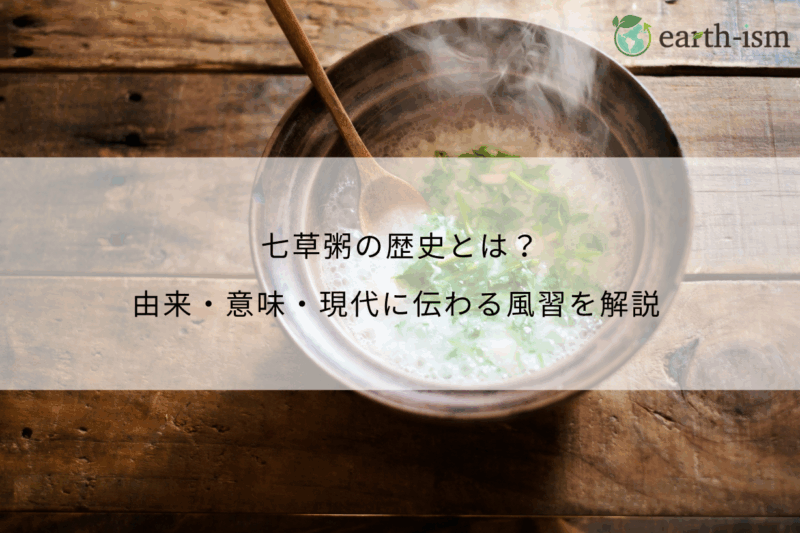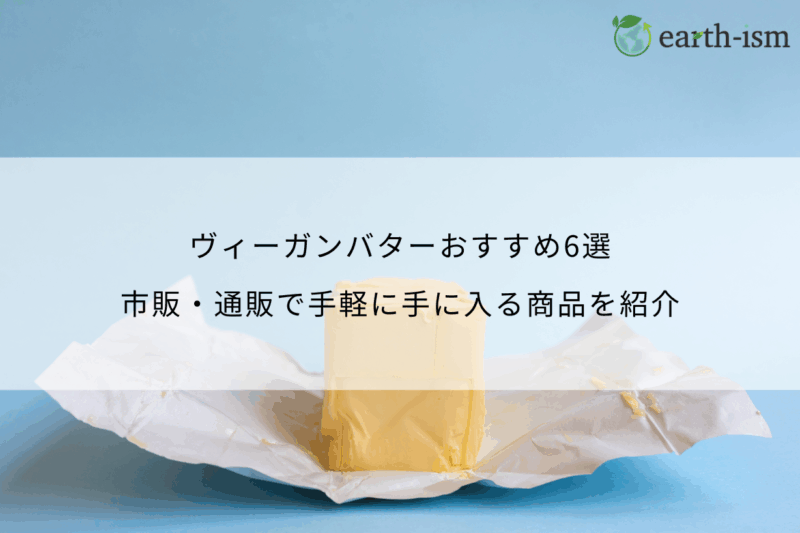フードレスキューとは?私たちの日常から始める「もったいない」の救出


Contents
フードレスキューとは、まだ食べられるのに廃棄されてしまう食品を活用し、食材や料理を「救う」取り組みのことです。
日本では年間500万トン以上の食品ロスが発生しており、家庭や飲食店、スーパーなど身近な場所で起きています。こうした問題に対して、アプリやサービスを通じて消費者が直接参加できる仕組みが広がりつつあります。
日常生活の延長で取り組めるうえに、節約や新しい食との出会いにつながるのが魅力です。この記事では、フードレスキューの基本から最新サービス、家庭でできる工夫までを整理し、今すぐ実践できる方法をご紹介します。
日本で広がる食品ロスとフードレスキューの必要性


日本では年間472万トン(2022年度推計)の食品ロスが発生しています。農林水産省「食品ロスの発生量(令和4年度推計値)」によれば、そのうち家庭からは236万トン、事業者からは279万トンと、家庭と外食・小売の双方で大量の食品が廃棄されています。これは国民一人あたりに換算すると、毎日お茶碗一杯分のごはんを捨てている計算になります。
こうした背景から、まだ食べられるのに捨てられてしまう食品を消費者とつなぐ「フードレスキュー」の仕組みが注目されています。
飲食店やスーパーの余剰食品をアプリで購入したり、地域のイベントを通じてシェアしたりする取り組みが増えており、食品ロスを減らすだけでなく、暮らしに役立つ新しい習慣として広がりつつあります。
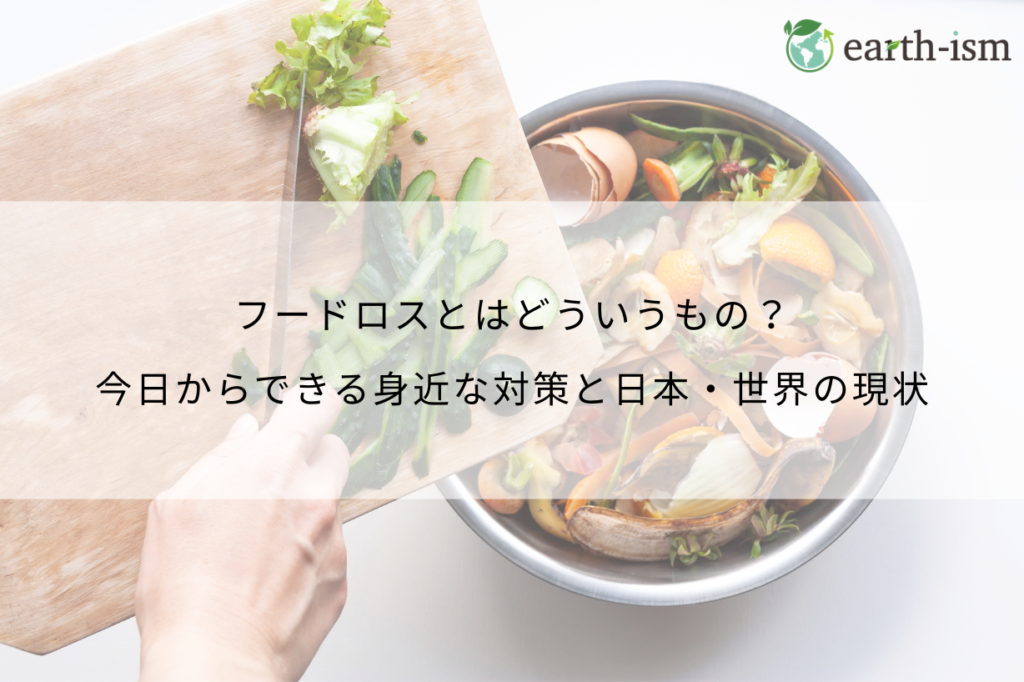
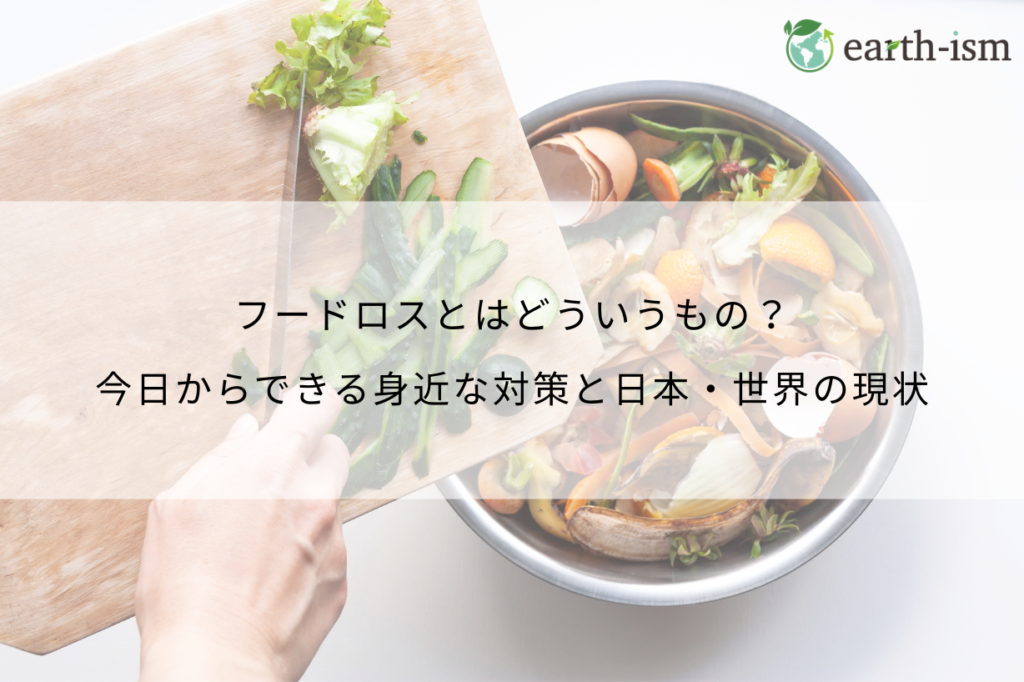
フードレスキューという考え方


「何となくだけど、安いものを選んで買っているという風に見られたら恥ずかしい」「お金がない人みたいなイメージを植えつけられたら嫌だ」というように、割引された食品を購入することに抵抗を感じている方もいるのではないでしょうか。
しかし、このときに「フードレスキュー」という言葉を知っていれば、安いから買うのではなく社会をより良くするために買うというポジティブな意識に変わります。これによって抵抗を感じることも少なくなるはずです。
アプリで気軽に参加できるフードレスキュー
フードレスキューを実践する手段として、スマートフォンのアプリを活用する人が増えています。代表的なサービスが「TABETE」です。TABETEは飲食店やベーカリー、スーパーで売れ残ってしまった商品を、通常よりお得な価格で購入できるアプリです。ユーザーは近隣の店舗を検索して気軽にレスキューに参加でき、店舗にとっては廃棄削減につながる仕組みになっています。
TABETEは2024年10月時点で利用者数が110万人を突破し、掲載店舗数は全国で2,880店舗以上に拡大しています。単に食品ロスを減らすだけでなく、初めて訪れるお店との出会いや、食費の節約になる点も魅力です。
このほかにも、地域ごとに食品をシェアする「ごちめし」、スーパーの割引商品を通知する「クラダシ」など、さまざまなサービスが広がっています。いずれも“買い物ついでに社会貢献ができる”仕組みとして注目を集めています。
レスキューデリと呼ばれる国内の取り組み
「レスキューデリ」は、東京駅改札内のエキナカ商業施設「グランスタ」などのエキナカ店舗の営業終了後に、まだ食べられる食品を駅で働く従業員の食事に活用する取り組みです。
フードシェアリングサービスである「TABETE(タベテ)」を運営するコークッキングによる実証実験として、エキナカ店舗の課題として存在していたフードロスを大きく変えようという目的のもと行われました。
1か月の実験の結果として1,700セット販売され、約1トンのフードロスが削減できたとのことです。
フードレスキュー®というマークで活動へ積極的に参加もできる


フードレスキュー®は、博報堂が生み出した食品ロス削減のためのアクションワード&ロゴのことです。このワードとロゴは無料で自由に使うことができ、生産・加工・流通・消費の流れに携わる企業や自治体に対して使用が推奨されています。
子供から大人まで親しみやすさを感じられるデザインのフードレスキュー®を使うことで、企業側も消費者側もフードロスに対する危機感をカジュアルに強めることができます。
家庭でできるフードレスキューの工夫
フードレスキューは特別な活動ではなく、家庭の中でも実践できます。農林水産省の調査によると、食品ロスの約半分は家庭から発生しており、その主な理由は「食べ残し」「傷み」「期限切れ」です。こうした原因を少し意識するだけで、日々の暮らしの中で食品ロスを大きく減らすことができます。
たとえば、冷蔵庫の中を定期的に確認し、賞味期限が近い食品を優先的に使うこと。まとめて調理して冷凍保存すること。野菜の皮や芯をスープに活用することも有効です。家庭での小さな工夫が積み重なることで、食品ロス削減だけでなく、家計の節約にもつながります。
さらに、値引きされた商品を前向きに選ぶことも「レスキュー」のひとつです。見た目や鮮度には問題がなくても、売り切れなければ廃棄される運命にある食品を積極的に購入することは、フードレスキューの実践になります。


世界に広がるフードレスキューの事例


フードレスキューの動きは、日本だけでなく世界各地で広がっています。代表的な事例のひとつが、ニューヨークの「City Harvest」です。City Harvestは1982年に設立された非営利団体で、飲食店やスーパーから余剰食品を回収し、必要としている人々に届けています。2023年レポートによれば、年間で約45,000トンの食品をレスキューし、300万人以上に食事を提供しています。
オーストラリアでも「Love Food Hate Waste」という国をあげたキャンペーンが展開されています。消費者への啓発活動を中心に、保存方法や調理の工夫を発信し、家庭から出る食品ロス削減を目的としています。さらに、事業者や行政と連携した「Food Rescue Sector Action Plan」では、業界全体での廃棄削減を推進しています。
こうした海外の取り組みはいずれも「消費者・事業者・行政の三位一体」で進められている点が特徴です。日本のフードレスキュー活動もアプリや地域プロジェクトにとどまらず、社会全体での仕組みづくりへと発展していく可能性があります。
賞味期限切れ ・販売期限切れの商品の廃棄問題もある


食品を取り扱う小売や飲食業では、販売期限や消費期限が厳しく設定されています。とくにコンビニやスーパーでは、製造から数時間~数日のうちに販売できなければ廃棄となる商品が多く存在します。
この背景には、日本独自の「3分の1ルール」と呼ばれる商慣習があります。製造日から消費期限までの期間を「製造→出荷→販売」の3つに分け、出荷や販売の段階でそれぞれ期限の3分の1以内でなければ取引しないというルールです。本来は安全性を確保する目的で始まったものですが、結果的に「まだ食べられる食品」が大量に廃棄される要因となっています。
一方で、企業による改善の動きも始まっています。ローソンでは、販売期限が近いデザートや弁当を割引価格で販売する実証実験を行い、食品ロス削減と消費者メリットの両立を図りました。また、セブン‐イレブンやファミリーマートでも、販売期限の近い商品を値引き販売する取り組みを順次拡大しており、消費者の「レスキュー意識」と企業の「廃棄削減ニーズ」が結びつきつつあります。
販売期限切れによる廃棄問題は依然として大きな課題ですが、企業と消費者が一緒に取り組める仕組みが少しずつ整い始めているのが現状です。
ちなみに、賞味期限切れになった製品を購入できる格安のサイトもあります。節約したい、またはフードロス対策に興味があるという方はぜひご覧ください。
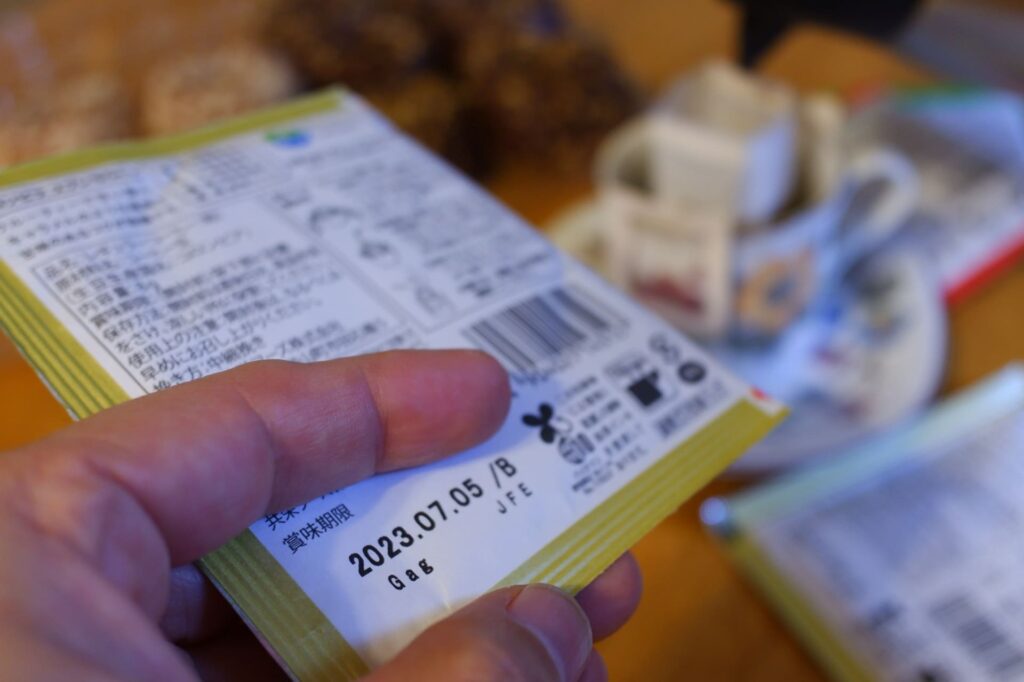
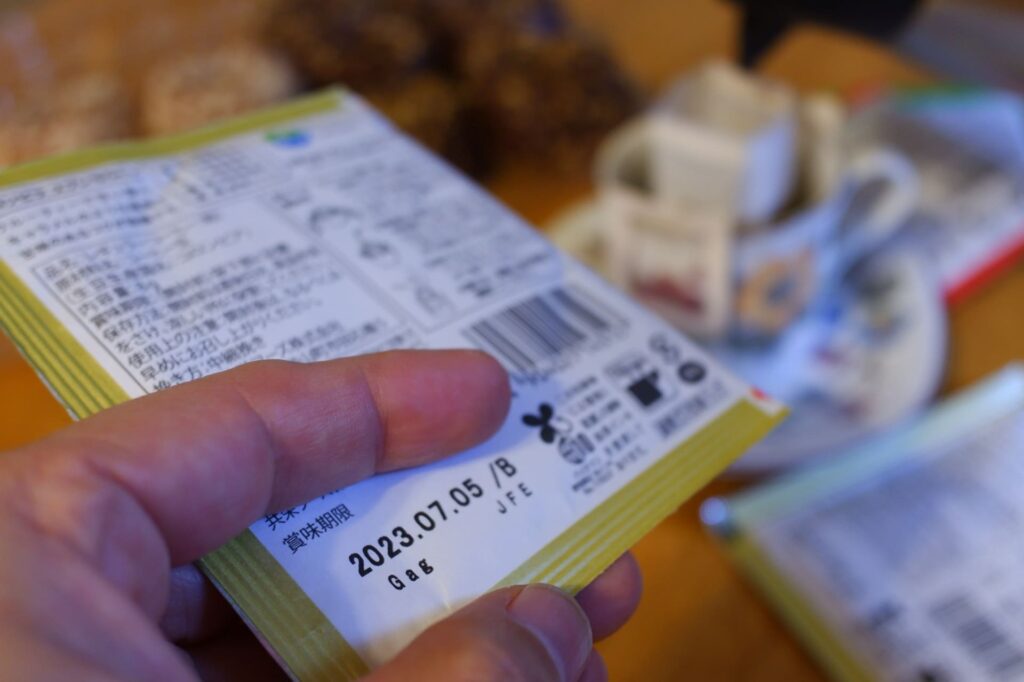
まとめ|小さな選択が未来を変えるフードレスキュー


日本では年間523万トンもの食品ロスが発生しており、その背景には家庭での食べ残しや、販売期限を過ぎた商品廃棄といった身近な課題があります。こうした問題を解決する動きが「フードレスキュー」です。アプリを使って余剰食品をレスキューしたり、家庭で食材を使い切る工夫をしたりと、生活の延長線上で取り組めるのが特徴です。
さらに、海外では「City Harvest」や「Love Food Hate Waste」といった大規模な取り組みも広がっており、日本でも企業や行政が改善に向けた動きを強めています。消費者である私たちが値引き商品を前向きに選んだり、アプリを活用して余剰食品を買い支えたりすることは、食品ロス削減につながる立派なアクションです。
フードレスキューは、環境にも家計にも優しい新しいライフスタイルといえます。今日の買い物から、ひとつのレスキューを始めてみませんか。