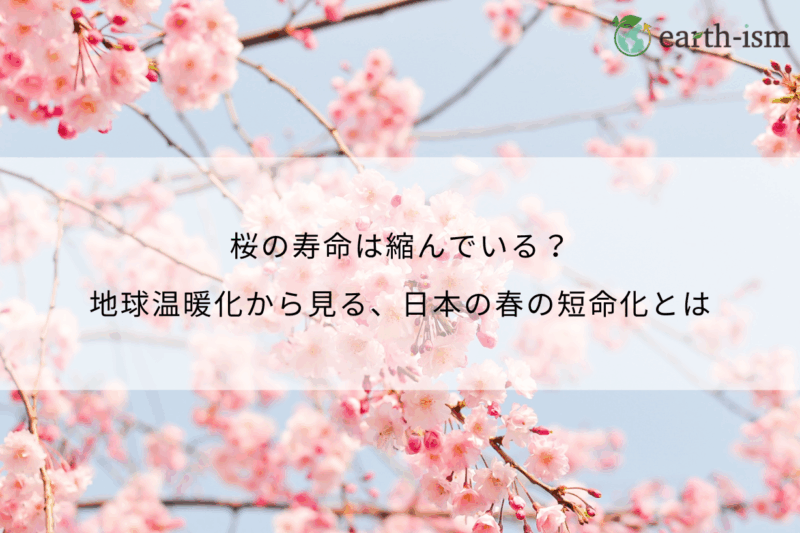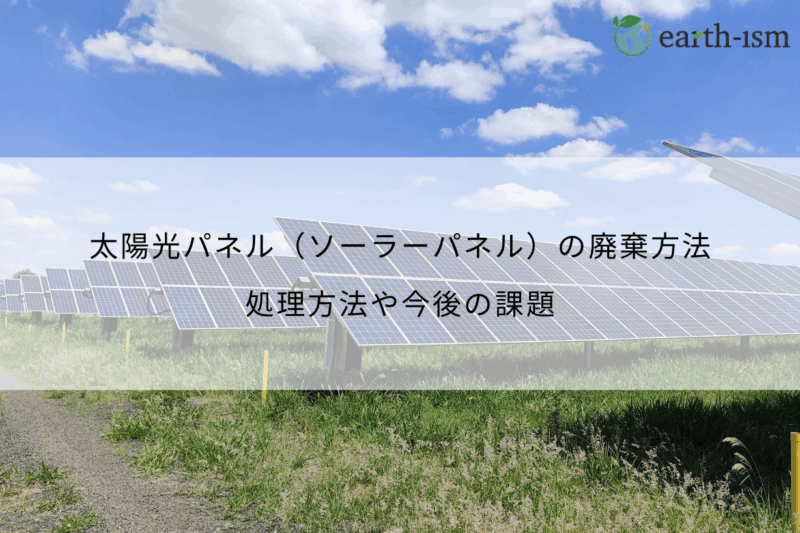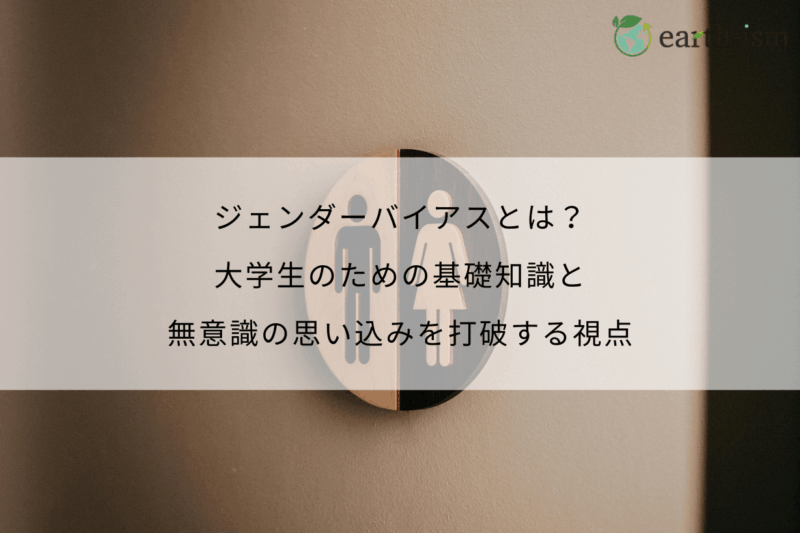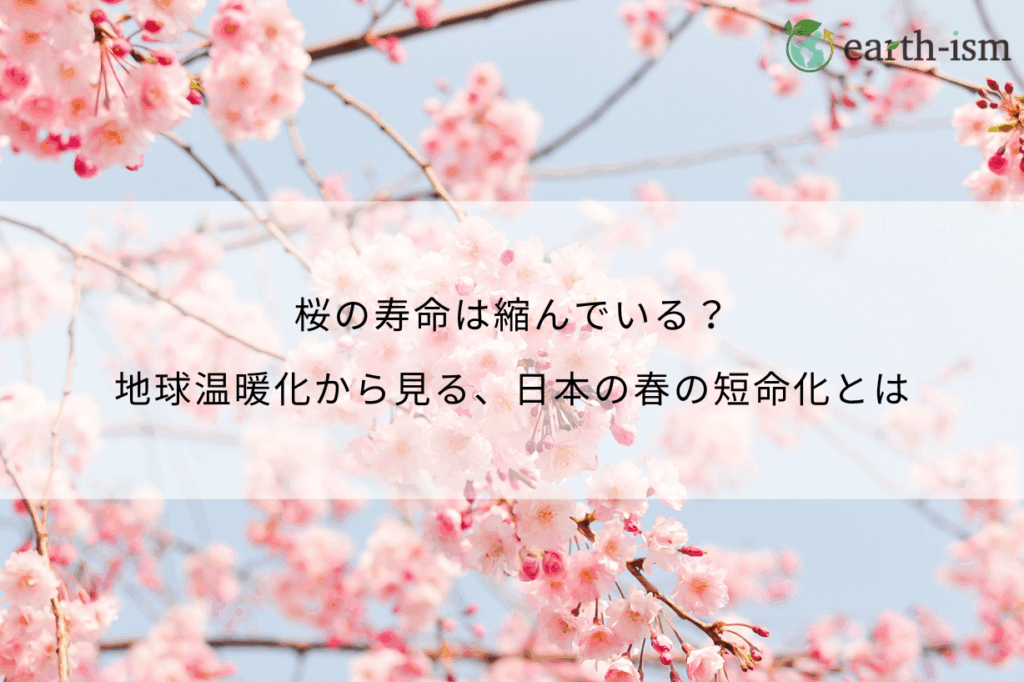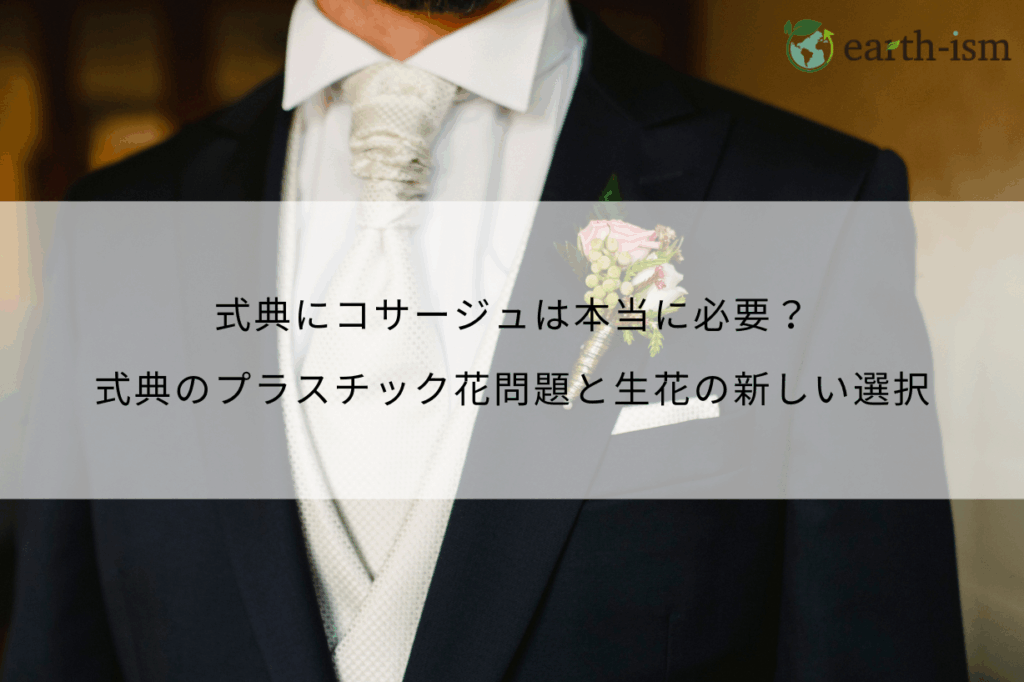「夫婦別姓になぜこだわる人がいる?」のかが分からない方へ|理由や歴史視点から徹底考察


Contents
夫婦別姓を巡る議論は、長年にわたって日本社会の中で続けられてきました。夫婦別姓という言葉を聞いて、「なぜそこまでこだわるのか」と首をかしげる方も多いのではないでしょうか。実際、SNSなどでもそうした声をよく目にします。
しかし、この問題の本質を理解するためには、歴史的背景や現代社会における個人のアイデンティティの問題まで、幅広い視点での考察が必要です。この記事では夫婦別姓によるメリットやデメリットなどの観点に触れながら、日本における夫婦別姓への意見についてのリアルを深掘りします。
そもそも夫婦別姓制度とは


夫婦別姓制度とは、結婚後も夫婦がそれぞれの姓を維持できる制度を指します。現在の日本では、民法の規定により、夫婦はどちらか一方の姓を選択する必要があり、多くの場合、女性が改姓するケースが一般的です。
しかし、夫婦別姓制度では改姓の必要がなく、個人のアイデンティティや職業上の実績を尊重できる点が大きな特徴です。また、国際結婚や多様な家族のあり方が広がる中で、選択肢を増やす意義も議論されています。
この制度の導入は、ジェンダー平等や個人の権利を重視する観点から支持を集めていますが、一方で家族の一体感が損なわれるのではないかという懸念や、戸籍制度への影響を指摘する声もあります。


世界的には夫婦別姓を認めている国が多い中、日本では選択制導入の是非を巡る議論が続いており、今後の法改正が注目されています。
夫婦別姓は日本を覗いた多くの国々では選択制として導入されることが多く、それぞれの家庭が自由に選べる点が重要なポイントとされています。
名前はアイデンティティと強く関係するため、夫婦別姓を望む人もいる


名前は個人のアイデンティティを形成する重要な要素です。長年使い続けてきた名前を結婚を機に変えなければならない状況は、人生の連続性に影響を与えることがあります。
名前の変更が自己認識や社会的な繋がりに与える影響は、決して軽視できるものではありません。実際、前章で述べたように、日本では選択的夫婦別姓を求める声が増えています。
改姓によってそれが断ち切られることへの違和感は、単なる「こだわり」ではなく、自己存在の本質に関わる問題なのです。
選択的夫婦別姓が求められる背景


選択的夫婦別姓を求める声は、単なるライフスタイルの選択ではなく、個人の尊厳や実務的な課題に深く根ざしています。以下では、選択的夫婦別姓を希望する理由の背景を探ります。
人格権としての氏名権が重要視されている
国連の「市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)」や「女性差別撤廃条約」では、名前を含む個人の権利を保護することが求められています。
多くの国では、夫婦が結婚後も別姓を維持する選択肢が法的に認められていますが、日本はその選択肢がない数少ない国の1つです。これは国際的な人権基準に対する疑問を生じさせています。
アイデンティティに影響を与えてしまう
長年使い続けた名前を突然変更することは、アイデンティティの一部を失う感覚を伴います。特に職場や地域コミュニティで名前を重要な個性として認識されている場合、その影響は大きいといえます。
手続きの煩雑さなど、実務上の課題がある
改姓に伴い、運転免許証や銀行口座、クレジットカード、保険、パスポート、SNSアカウントなど、多岐にわたる名義変更手続きが必要です。これに費やされる時間や労力は膨大であり、特に仕事や育児で忙しい人にとっては大きな負担となります。
さらには、キャリアにも影響を与える可能性があります。名前は個人のキャリアの一貫性に直結する場合があり、例えば研究者や弁護士、医師など、名前が実績の証明となる職業では、改姓によって過去の実績や信頼が途切れることがあります。
学術論文やビジネス上の契約書において旧姓を証明する手間が生じることもあるでしょう。
ジェンダー平等の視点からの批判も根強い
改姓を求められるのは多くの場合、女性です。2023年の男女共同参画局の調査では、結婚後に改姓した女性は約94%に上る一方、男性が改姓する割合は6%に過ぎません。この不均衡は、男女平等の観点から見ても改善が求められる点です。
また、ダイバーシティの観点からも見逃せません。同姓を強制する現行制度では、別姓を希望する夫婦や、夫婦のどちらかが外国籍の場合など、多様な生き方を尊重する余地がないのです。選択肢のない制度は、個々人の価値観やライフスタイルを無視する結果となっています。
韓国など海外諸国の事例も


世界の多くの国では、結婚後も姓を選択できる制度が一般的です。例えば、欧米諸国や韓国では夫婦別姓が法的に認められており、日本の現状が例外的であることが際立ちます。
こうした国際的な動きも、選択的夫婦別姓を求める議論を後押ししています。
韓国の場合
韓国では、法律上、結婚後も夫婦がそれぞれの姓を保持することが原則です。これは韓国社会における「家門」の概念に起因します。韓国では伝統的に、姓は先祖代々受け継がれるものとされ、結婚後も姓を変える慣習がありません。
そのため、結婚によって夫婦が別姓であることは日常的なことであり、特に議論の対象になることもありません。
アメリカ、イギリスなどの欧米諸国の場合
アメリカでは、結婚後に改姓するかどうかは完全に個人の選択に委ねられています。旧姓を保持したり、夫婦が新しい姓を共同で選んだりするケースも一般的です。
イギリスでも、結婚後に改姓するかどうかは法的な義務ではなく選択肢の1つです。近年では、女性の社会進出に伴い、旧姓を保持する女性や、夫婦がダブルバレル(両者の姓をつなげる形)を選択するケースが増えています。
夫婦別姓に反対する人の声には「一体感が失われる」などがある


夫婦別姓への反対意見では、「家族の絆が弱まる」「子どもに悪影響がある」といった主張が頻繁に聞かれます。
しかし、これらの主張の多くは科学的根拠に欠け、むしろ個人的な価値観や思い込みに基づいています。
反対の根底には、良い言葉ではありませんが、ジェンダー平等という概念そのものへの抵抗が潜んでいると考えられます。夫婦別姓は、単なる名前の問題ではなく、「家族のあり方」や「男女の役割」といった、より根本的な価値観の変革を象徴しているからです。
明治以降に制度化された家父長制的な家族観を「日本の伝統」として捉え、それを守ろうとする意識が強く働いています。
この層にとって夫婦別姓は、従来の秩序への挑戦として受け止められています。また、夫婦別姓反対の背景には、急速に変化する社会への漠然とした不安があります。
「女性は結婚後に夫の姓を名乗り、家庭を支えるべき」という価値観は、単なる因習ではなく、ある種の社会秩序の象徴として機能しているのです。
このように、夫婦別姓に反対する背景には、単なる家族観の違いだけでなく、社会全体の価値観やジェンダー平等に対する根深い意識の差が横たわっていると言えるでしょう。
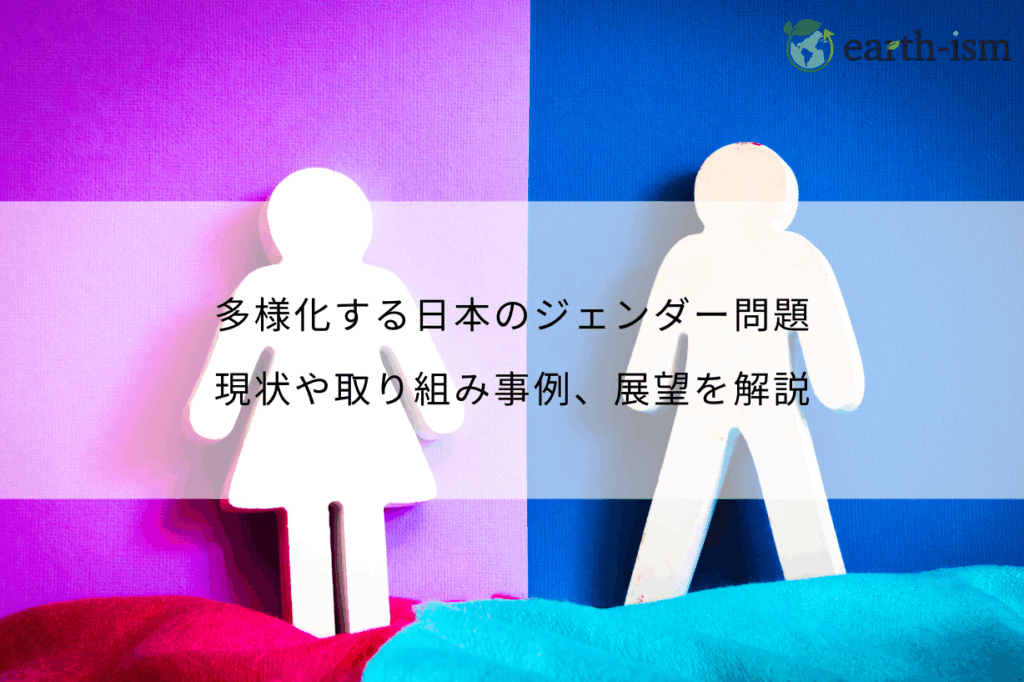
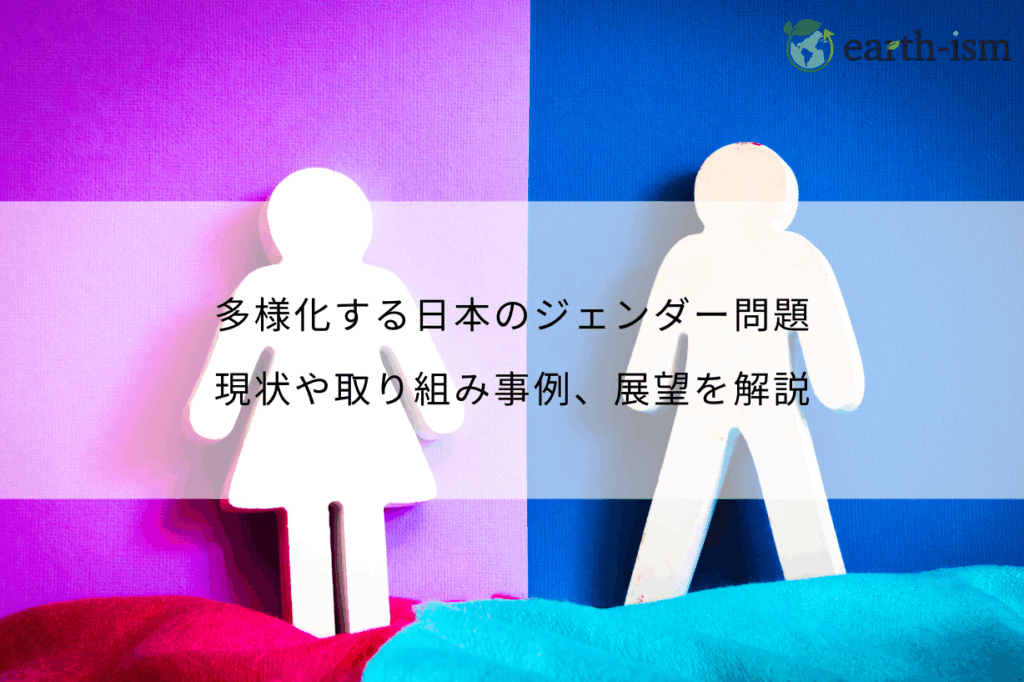


日本における夫婦別姓にまつわる法整備の進み具合は?


法務省は平成3年から夫婦別姓にまつわる検討を進め、平成8年と平成22年に改正法案を準備しました。しかし、国民の意見が分かれていることなどから、いずれも国会提出には至らなかったのが現実です。結論から言えば法整備は依然として進んでいない現状にあります。
令和3年に実施された「家族の法制に関する世論調査」では、「夫婦同姓制度を維持すべき」との回答が27.0%、「同姓制度を維持しつつ旧姓の通称使用に関する法制度を設けるべき」が42.2%、「選択的夫婦別姓制度を導入すべき」が28.9%という結果が出ています。
また、夫婦同姓制度の合憲性が争われた裁判において、最高裁判所は平成27年と令和3年の二度にわたり、現行制度は憲法に違反しないと判断しました。
ただし、これらの判決では、選択的夫婦別姓制度の導入については「国会で論ぜられ、判断されるべき事柄」と述べられています。
このように、日本における夫婦別姓の現状は、法制度上は夫婦同姓が義務付けられているものの、社会の多様化や個人の権利意識の高まりに伴い、選択的夫婦別姓制度の導入に関する議論が続けられています。
これからの夫婦別姓制度はどうなる?


「なぜこだわるのか」という問いは、むしろ「なぜ改姓を強制されなければならないのか」という問いに置き換えられるべきかもしれません。
選択的夫婦別姓は、多様な生き方を認め合う社会への重要なステップとなるはずです。2024年の世論調査では、「制度に賛成だが、自分は夫婦同姓がいい」「制度に賛成で、夫婦別姓がいい」と答えた「賛成派」が計65.0%という結果になっています。
「こだわり」は、時として社会を前進させる原動力となります。夫婦別姓への「こだわり」は、個人の尊厳と実践的な必要性の両面から生まれた、現代社会における重要な問題提起ではあります。
しかし、日本の戸籍制度は、家族単位で管理されるため、夫婦別姓を導入すると戸籍の管理や記載方法を変更する必要が出てきます。この変更が制度全体に与える影響を懸念する声がSNS上で多く見られることは事実です。
実際に2025年に入ってから、選択的夫婦別姓制度の導入をめぐって、石破総理大臣は議論の頻度を高めたいとしています。一方で、自民党内には根強い慎重論も見られるため、今後の動向に注目しなければなりません。
まとめ


夫婦別姓への「こだわり」は、単なる名前の問題ではありません。それは、個人のアイデンティティ、職業生活における実務的な必要性、そして何より個人の尊厳に関わる重要な人権課題です。
一方で、反対意見の背景には、急速な社会変化への不安や伝統的価値観の保持という心理が存在します。
夫婦別姓を巡る議論は、私たちに重要な問いを投げかけています。私たち一人一人が真摯に向き合い、早急に選択的夫婦別姓の取り決めをするのではなく、政治・経済、また文化を含めた慎重な対話を重ねていく必要があるでしょう。