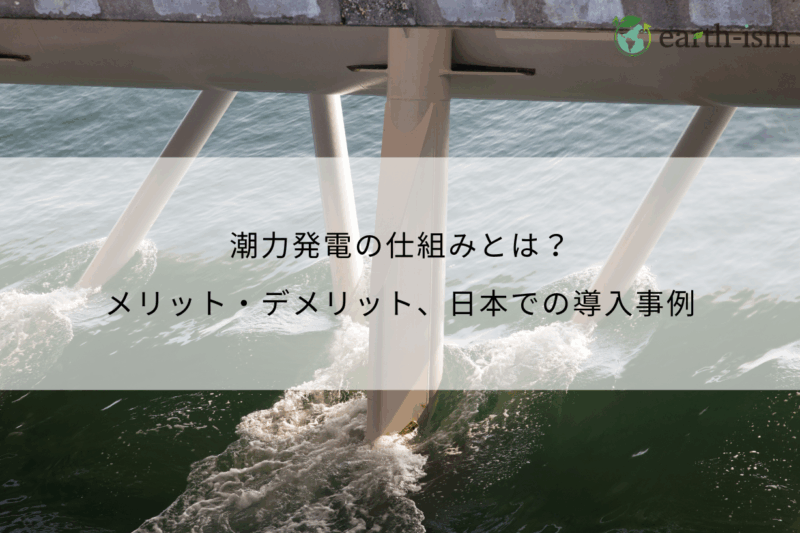【中学生向け】ダイバーシティとは?身近な例や企業の取り組み、賛否についても解説


Contents
「ダイバーシティ」という言葉を、ニュースや学校で聞いたことはありませんか?
なんとなく「多様性」に関する言葉だとわかっても、「実際にどんな意味で、私たちの生活にどう関わるの?」と感じる方は多いはずです。
ダイバーシティとは、年齢・性別・国籍・価値観など、さまざまな違いを持つ人々が互いを認め合い、それぞれの個性を活かし合う考え方のこと。今や企業や学校、地域社会で重要視される概念となっています。
この記事では、ダイバーシティの基本的な意味から、私たちの身近にある具体例、そして企業や社会での取り組み事例まで、初心者の方にもわかりやすく解説します。
ダイバーシティを正しく理解することで、あなたも周りの人との違いを新たな価値として捉え、より豊かな人間関係や将来のキャリアに活かすヒントが見つかるでしょう。
ダイバーシティの意味とは?


ダイバーシティ(Diversity)は、日本語で「多様性」を意味する言葉です。私たち人間は、それぞれが異なる性別、国籍、文化、性格、価値観、考え方を持っています。ダイバーシティは、これらの違いを否定するのではなく、積極的に受け入れ、それぞれの個性や特徴を尊重しながら共存することを大切にする考え方です。
この概念は、単に「違いを認める」だけではなく、違いを価値として捉えるところに本質があります。たとえば、多様な背景を持つ人々が集まることで、新しい視点やアイデアが生まれ、より豊かな社会や組織をつくることができます。
また、ダイバーシティは、人種、宗教、障がい、性的指向など、あらゆる違いを包括する広い意味を持ち、すべての人が自分らしく生きられる環境を目指すものでもあります。
なぜダイバーシティが重要なの?


ダイバーシティが大切である理由は多岐にわたります。
1. 創造性とイノベーションを生み出す
異なる背景を持つ人々が集まることで、問題に対するアプローチの幅が広がり、新しいアイデアや解決策が生まれやすくなります。同じような経験や考え方の人だけでは気づけない視点や発想を得ることができるのです。
中学校での具体例としては以下のとおりです。
- 文化祭の企画会議では、男女や異なる部活の生徒が集まることで、多くのクラスメイトが楽しめる企画が生まれる
- 生徒会の議論では、学年や得意分野が違う生徒の意見を聞くことで、学校全体のためになる解決策が見つかる
- グループ学習では、理系が得意な人・文系が得意な人・運動が得意な人が協力することで、一人では解決できない課題をクリアできる
2. 社会的公平性を実現する
ダイバーシティを重視することは、性別・人種・年齢・出身地などの違いによる差別をなくし、すべての人が自分の能力を発揮できる社会を作ることにつながります。これは個人の幸福だけでなく、社会全体の発展にも貢献します。
社会への影響としては以下のとおりです。
- 能力や努力で正当に評価される公正な社会の実現
- 多様な人材が活躍することで、組織や社会全体の力が向上
- 差別のない環境により、すべての人が安心して生活できる社会の構築
現在の中学校では、女子生徒会長や外国出身のクラスメイトが活躍し、男女共同参画や国際理解教育が進んでいます。また、様々な特技を持つ生徒がそれぞれの分野でリーダーシップを発揮する環境が整ってきています。
3. 多様化する市場に対応する
現代社会では、顧客の年齢・国籍・価値観が多様化しています。組織内に様々な背景を持つ人がいなければ、これらの多様なニーズを理解し、適切なサービスや商品を提供することが困難になります。
中学校での対応例では以下のようなものが挙げられるでしょう。
- 1年生から3年生まで、すべての学年が参加しやすい学校行事の企画
- 海外から転校してきた生徒も馴染みやすい学級運営
- 運動が苦手な生徒も活躍できる体育祭の種目設計
- 障がいのあるクラスメイトも一緒に参加できる授業や活動の工夫
多くの中学校では、生徒の多様な意見を取り入れることで、いじめの早期発見システムや、全校生徒が楽しめる新しい学校行事を生み出すなど、学校生活の質を向上させています。
4. リスクを予防し、より良い判断を可能にする
同じような考え方の人ばかりが集まると、「集団思考」という現象が起こり、重要な問題を見落としたり、間違った判断をしてしまうリスクが高まります。多様な視点があることで、様々な角度から物事を検討し、より適切な決定ができるようになります。
リスク軽減の効果は以下のとおりです。
- 異なる経験を持つ人々による多角的な問題分析
- 意思決定の際の盲点や見落としの早期発見
- 変化する環境への柔軟で迅速な対応
多様なメンバーがいる組織は、予期しない問題にも対応しやすく、長期的に安定した成長を続けることができます。
身近なダイバーシティの例にはどのようなものがある?


意外と身近なところに、ダイバーシティは集まっています。例えば、下記の例が挙げられるでしょう。
学校でのダイバーシティ
学校では、いろいろな個性を持ったクラスメイトが集まっており、それぞれが得意なことや苦手なことを持っているのは自然なことです。クラスにはさまざまな趣味や考え方を持つ友達がいます。それぞれが異なる興味や意見を持つことで、互いに新しい発見や視点を共有し合うことができているのではないでしょうか。
また、国籍が異なる友達がいる場合、その友達を通じて違う文化や言葉を学べる機会が生まれます。これにより、自分とは異なる世界観を理解し、多様な価値観を受け入れる力を養うことができます。
さらに、特別支援学級の生徒と一緒に活動する場面では、自分とは異なる考え方やアプローチに触れることができ、これまで気づかなかった視点を得るきっかけになるでしょう。このように、多様性に触れる経験は、学校生活をより豊かで刺激的なものにし、互いを尊重し合う姿勢を育む大切な学びとなります。
家庭でのダイバーシティ
家庭でも、家族の中で役割や考え方が異なることがあります。例えば、親が家事を分担していたり、兄弟がそれぞれ違う夢を持っていたりするのも、ダイバーシティの一例です。
家庭における性別役割分業などの旧来からの文化は、今は見直されつつあります。男女共同参画社会になるにつれて「分業は時代遅れ」などの言説も広まっており、父親・母親、また子どもにわたり、一家揃って家事や仕事を行う、という価値観が一般的になることが臨まれている傾向にあるのも事実です。


SNSでのダイバーシティ
SNSは、世界中の人と簡単につながれる便利な場所です。しかし、その中には目に見えない「闇」が潜んでいます。10代にとって身近な問題の一つが、ルッキズム(外見至上主義)です。SNSでの「いいね」やフォロワー数は、しばしば外見に大きく左右されることがあり、特定の美的基準が繰り返し強調されることで、自分の容姿に自信を失う人も少なくありません。
たとえば、完璧に加工された写真や「美しい」とされる人ばかりが注目されることで、「こうでなければいけない」というプレッシャーが生まれます。その結果、容姿が理由でコメント欄に心ない言葉を投げかけられたり、自分を隠そうと過剰な加工をしてしまう人もいます。
「可愛くない」「太ってる」「肌が汚い」といった言葉は、何気なく発されたとしても、受け取った側には深い傷を残します。
また、文化や価値観の違いを理由にした偏見も少なくありません。こうした環境では、自分らしさを表現することが難しくなり、多様性が失われてしまいます。何を発信し、何を支持するのかを考えることが大切です。自分らしくいることを大切にしながら、他人の「違い」もリスペクトしましょう。
企業や団体が取り組むダイバーシティ


身近なことだけではなく、企業など社会においてもダイバーシティへの取り組みが見られます。
トヨタ自動車
たとえば、トヨタ自動車は、多様なバックグラウンドを持つ社員を積極的に採用するだけでなく、その多様性が生かされる職場環境を整備するための施策を行っています。
トヨタでは、社員一人ひとりが能力を最大限に発揮できるよう、研修やメンタリング制度を充実させ、多様な視点から新しいアイデアを生み出す文化を育んでいます。また、女性リーダーの育成や、障がい者雇用の促進に特化した取り組みを通じて、誰もが活躍できる職場作りを進めています。
ファーストリテイリング(ユニクロ)
ファーストリテイリングも、ダイバーシティ推進の成功事例として知られています。障がいを持つ人々を積極的に雇用するだけでなく、店舗や職場環境を工夫し、彼らが安心して働ける環境を整えています。
障がいを持つ社員向けに業務を分かりやすく整理するマニュアルを用意し、必要に応じて個別のサポートを行っています。これにより、障がい者雇用率を法律で定められた水準以上に達成し、多様性を活かした経営を実現しています。
Googleもダイバーシティの取り組みで知られています。Googleでは、社員の文化的背景や性別の違いを積極的に受け入れ、多様なチームでプロジェクトを進めることを推奨しています。同社は、ダイバーシティから生まれる創造性を競争優位性とし、従業員研修や多様性に関するデータ収集を行いながら、継続的な改善を図っています。
企業はなぜダイバーシティに取り組むのか?
企業がこうしたダイバーシティに注力する背景には重要な理由があります。
まず、多様な意見や視点を取り入れることで、従来にはなかった斬新で魅力的な商品やサービスを生み出すことが可能になります。また、ダイバーシティを重視した取り組みは、社会に貢献する姿勢として評価され、企業のブランドイメージ向上にもつながります。
さらには、経済的なメリットもあるのです。多くの国や自治体では、ダイバーシティに関連する取り組みを支援するための政策を実施しているのをご存知でしょうか。たとえば、障がい者雇用を促進する企業には雇用助成金が支給される場合があり、これを活用することで企業は雇用コストを軽減しつつ社会的責任を果たすことができます。
また、ジェンダー平等や多文化共生に関連するプロジェクトを実施する企業には、特定の基金やプログラムを通じて資金が提供されることもあります。これらの支援は、ダイバーシティを推進する動機となり得ますが、単に経済的な理由だけでなく、企業の社会的責任(CSR)やブランド価値向上にも結びついています。
企業がダイバーシティを「軽視しすぎる」と起こる危険性
ただし、助成金や補助金を目的とした取り組みが形だけのものになってしまうと、長期的な効果や信頼性が失われるリスクもあります。
そのため、多くの企業は助成金を活用しつつ、ダイバーシティを本質的に推進する姿勢を見せることが求められています。助成金は、ダイバーシティを始めるきっかけとして有効ですが、継続的な成果を生むためには、企業文化として根付かせることが重要です。
最近では企業の不祥事はSNSですぐに拡散されるため、うわべだけのダイバーシティ推進、と謳っている企業は、のちのち信頼を失うリスクが否めません。
earth-ismでご紹介している企業(CSRに取り組む企業)では、こうした「うわべだけ」ではない取り組みを行っています。ぜひCSRページをご覧ください。
「超ダイバーシティボランティア!」プロジェクト
「超ダイバーシティボランティア!」は、高齢者と子ども、さらには障がいのある方を含めた多様な世代と背景が一堂に会する交流型ボランティア活動です。ハンズオン東京が開催しており、「コミュニティのニーズに合ったボランティア活動の場を提供することにより、社会へ貢献し、ボランティアリズムを浸透させ、リーダーを育成することをミッション」としています。
単なる支援ではなく、助け合いながら互いに学び、尊重し合う場を提供し、未来を担う子どもたちに豊かな感性を植え付ける教育的プログラムともいえます。
ダイバーシティ推進には賛否両論もある
以下では、ダイバーシティ推進の賛成議論と期待される効果について解説します。ダイバーシティを推進する流れに日本はなっていますが、それにもSNSなどで賛否が寄せられているため、昨今の潮流を理解しておきましょう。
賛成の声
まず、以下は賛成の声を上げる立場の方からの意見です。
女性管理職・政治参画が推進されるから
政治・行政の分野でも、女性管理職比率向上や女性の参画を促す政策が進展しています。2025年7月の自由民主党「J‑ファイル」では、女性活躍推進法の改正にも言及し、ハラスメント対策とともに行政分野での多様性拡大を目指す方針が示されています。
社会的正義と公平が実現されるから
ダイバーシティは単なる経済施策ではなく、公平性や誰もが参加できる社会づくりという理念的側面も持ちます。内閣府によると、ジェンダーギャップ指数において日本は2024年で146カ国中118位と非常に低く、改善に向けた取り組みが注目されています 。
ダイバーシティ促進に対する反対・懸念の声
ダイバーシティ促進に対する反対・懸念の声は以下のとおりです。
無意識の偏見やバイアスが継続されるから
アンコンシャス・バイアス(無意識の偏見)が根強いままだと、「形だけの多様性」に終わり、本来の目的が達成できないケースがあります。
コミュニケーションや評価制度が混迷するから
さまざまな価値観が混在すると、職場内での衝突や意思疎通の難化、評価方法の複雑化などが生じやすく、成果を上げるまでに時間やコストがかかるという懸念があります。
成果実感の乏しさ、制度の形骸化につながるから
企業の多くが「イノベーションによる価値創造」ではなく、「雇用や社会的責任」のためにダイバーシティを実施しているに過ぎず、制度が形骸化しているという批判もあります。
日本の政治的潮流とダイバーシティ
現在、日本では女性の政治参画や行政分野での多様化に注目が集まっています。政府の施策としては、女性活躍推進法の改正や職場環境の改善、ハラスメント対策強化などが進められており、官民を挙げた取り組みが増えています。
一方、世界的な潮流としては、2025年にアメリカでトランプ政権再任後、DE&I(多様性・公平性・包括性)への見直しや縮小の「バックラッシュ」が報じられています。マクドナルドやディズニー、メタなどが方針を転換し始めており、「行き過ぎたポリティカル・コレクトネス」に対する反発が背景にあります。こうした国際的な流れも、日本の議論に影響を与えつつあります。
また、日本では極端な推進や偏重を避け、「中庸」な姿勢を保つことが重要視されるようになっています。多様性と公平性のバランスをとるための中庸なアプローチが求められており、単なる数値目標に終わらない取り組みが期待されていると言われています。
ダイバーシティを意識した未来の社会


ダイバーシティは、特別な努力が必要なものではなく、日常の中で小さな行動から実現できるものです。
たとえば、クラスメイトや友達の違いを認め、それぞれの個性を尊重することが大切です。見た目や性格、趣味が自分と違う人に対しても、偏見を持たずに話をしてみると、新しい発見や学びがあるかもしれません。
また、自分の意見に固執せず、他の人の考え方を取り入れる姿勢を持つことで、視野が広がり、より深い理解につながります。これらの行動を積み重ねることで、ダイバーシティを身近なものとして体感することができるのです。
まとめ


未来の社会において、ダイバーシティはさらに重要な役割を果たすと考えられています。仕事や学びの場では、多様な視点やアイデアが新しい可能性を生み出す源となるでしょう。また、すべての人が自分らしく生きられる社会を築くことが、より豊かな未来を実現する鍵となります。そのためには、一人ひとりの行動が大切です。
小さなことでも、相手を尊重する姿勢や違いを受け入れる心を持つことが、未来の社会をより良い方向へ導く力になるのです。あなたの行動が、ダイバーシティが当たり前の社会をつくる大きな一歩となります。