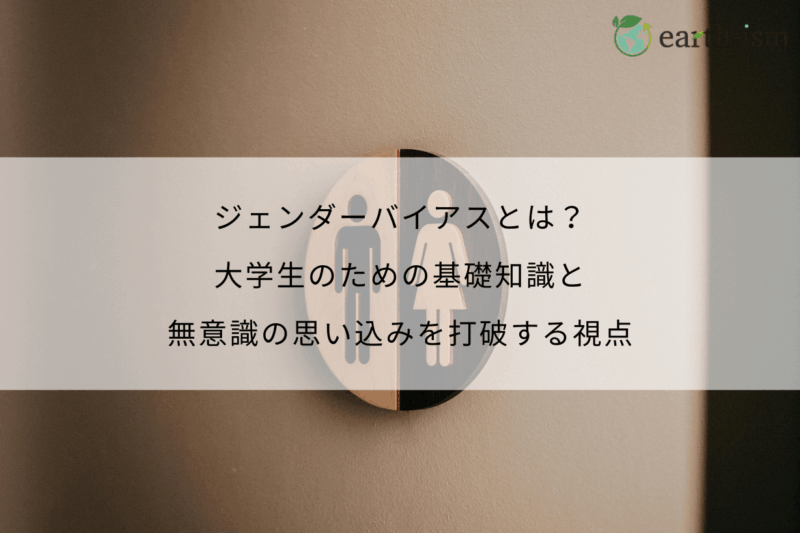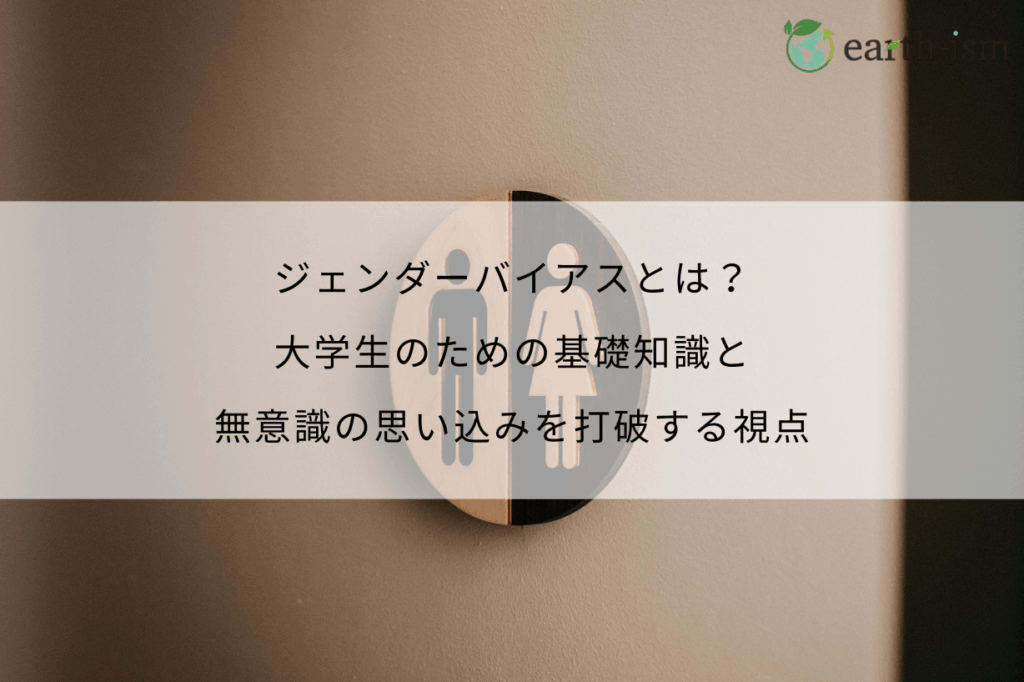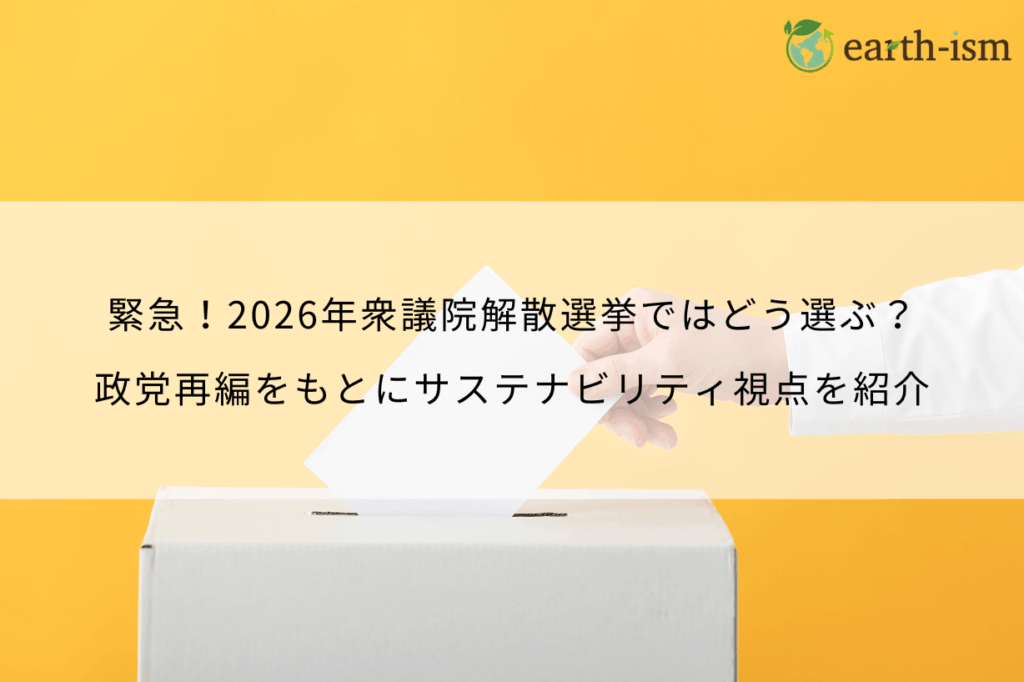【2025年最新版】STEAM教育を楽しく!おすすめ教材10選|家庭・学校で今すぐ使おう
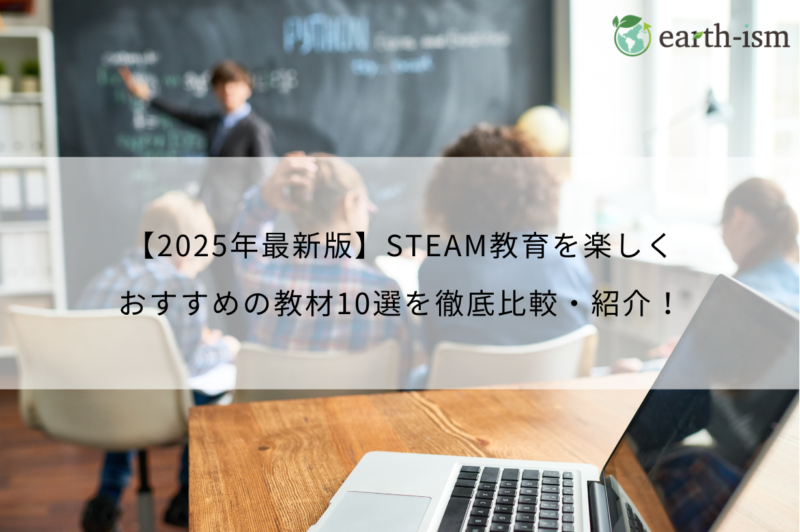
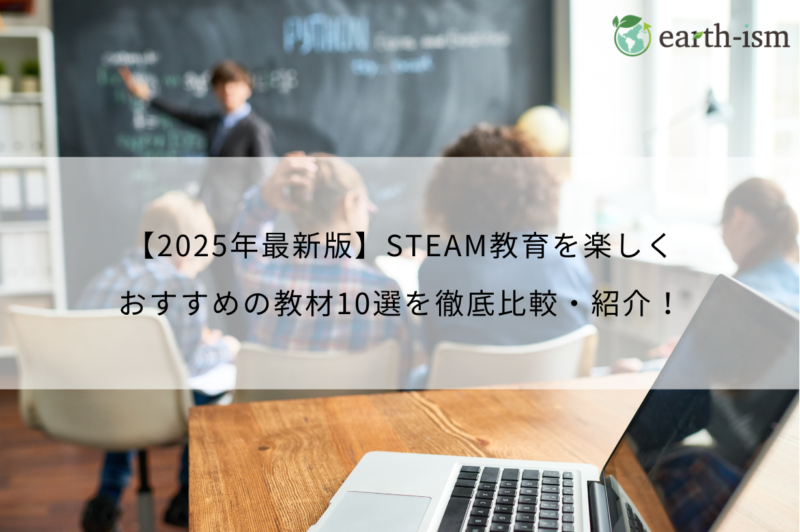
Contents
- STEAM教育ってなに?基礎知識を徹底解説
- 今すぐ使える!おすすめSTEAM教材10選【2025年版】
- 1. Cubetto(キュベット)|3歳から始めるプログラミング
- 2. VisCuit(ビスケット)|お絵かき感覚でプログラミング
- 3. Ozobot(オゾボット)|紙とペンでロボットプログラミング
- 4. LEGO® Education SPIKE™(レゴ・スパイク)|創造性×論理思考
- 5. micro:bit(マイクロビット)|本格プログラミングへの入門
- 6. IchigoJam(イチゴジャム)|日本発の手のひらパソコン
- 7. Artecブロック ロボット教材|日本の学校現場で圧倒的シェア
- 8. littleBits(リトルビッツ)|磁石で繋ぐ電子工作
- 9. Scratch(スクラッチ)|世界標準のビジュアルプログラミング
- 10. Think!Think!(シンクシンク)|思考力を鍛えるパズルアプリ
- STEAM教材選びの完全ガイド|失敗しない選び方
- まとめ|学びは「好奇心」から始まる
「これってどうなっているんだろう?」「自分でも作ってみたい!」 そんな子ども達の好奇心を育むのが、今話題の「STEAM教育」です。
科学やテクノロジー、芸術といった多様な分野を横断的に学ぶことは、答えのない時代を柔軟に生き抜く力を育みます。文部科学省も「Society 5.0に向けた人材育成」として積極的に推進しており、全国の小中高校でも導入が加速しています。
とはいっても「実際にどんな教材を使えば良いの?」「費用対効果は?」と迷う保護者や教育者の方も多いのではないでしょうか?
この記事では、教育現場での豊富な導入実績を持つSTEAM教育向け教材を10個厳選してご紹介します。各教材の特徴、対象年齢、価格帯、活用事例まで詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
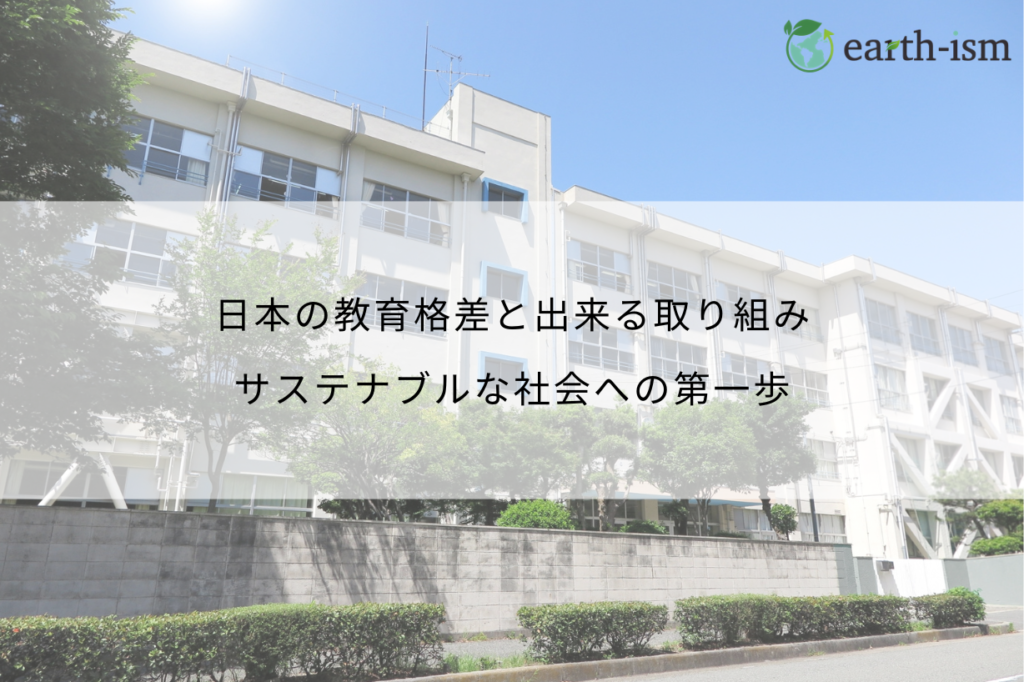
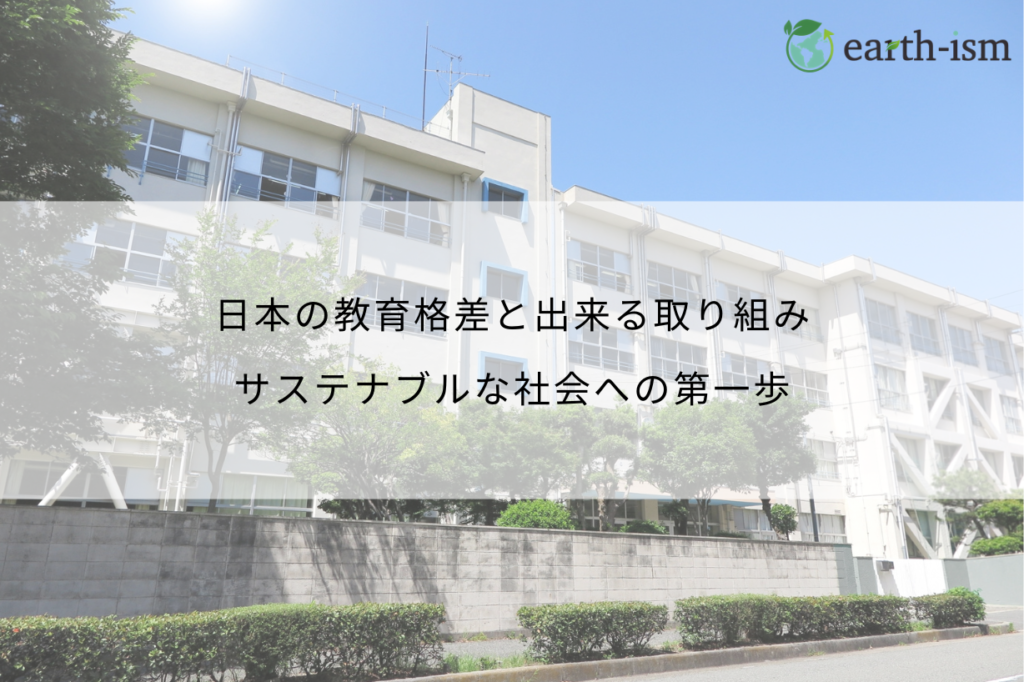
STEAM教育ってなに?基礎知識を徹底解説


まずは、STEAM教育の詳細を簡単に説明します。
STEAM教育の定義と背景
STEAM(スティーム)教育とは、Science(科学)・Technology(技術)・Engineering(工学)・Arts(芸術・教養)・Mathematics(数学)の頭文字から名付けられた教育アプローチです。Georgette(ジョーゼット)Yakman が2006年前後に枠組み化を行いました。
もともとはSTEM教育として、アメリカで理系人材育成のために始まりました。その後、創造性や表現力の重要性が認識され、Arts(芸術・教養)が加わってSTEAM教育として発展。2006年にアメリカの技術科教師ジョーゼット・ヤークマン氏によって体系化されました。
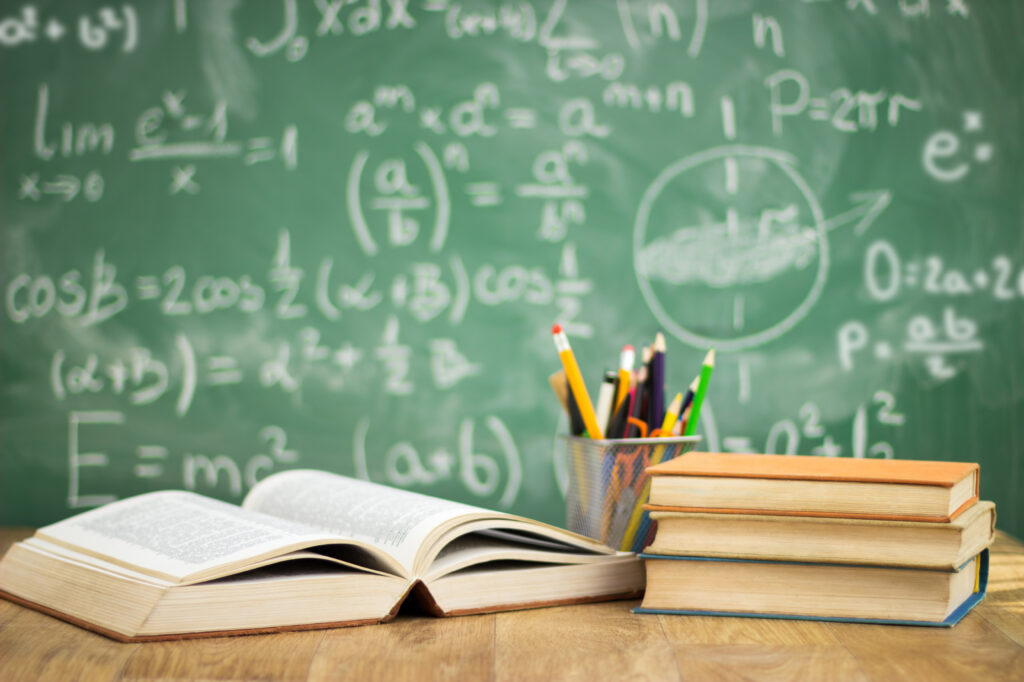
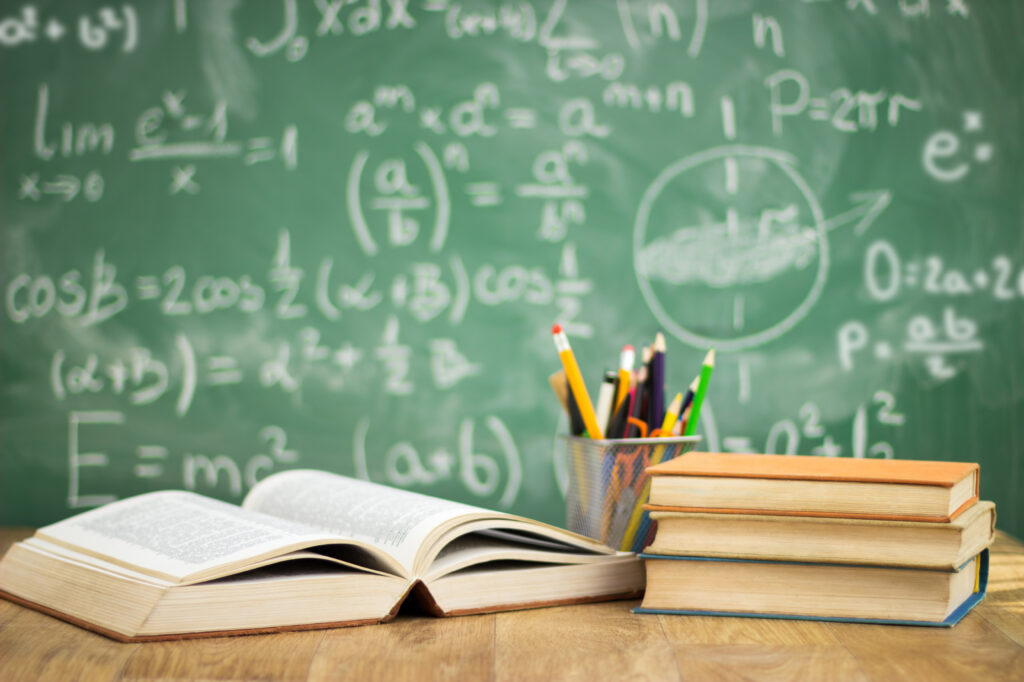
なぜ今STEAM教育が注目されるのか
現代は、AIやIoT、ビッグデータといったテクノロジーが急速に進化し、社会構造が根本的に変化しています。
このような社会においては、状況の変化に柔軟に対応し、自ら考えて行動できる力を持った人材が必要とされています。従来の暗記中心の学習では対応できない、複雑な課題を解決する能力が求められているのです。
日本でのSTEAM教育の現状
文部科学省は2020年度から小学校でプログラミング教育を必修化。さらに2025年の大学入学共通テストでは新科目「情報Ⅰ」の出題が始まりました。政府はSociety 5.0の実現に向け、STEAM型の資質・能力育成を方針として示し、STEAMライブラリーなどの施策も進めています。
企業連携も活発です。MicrosoftはMakeCodeを通じて教材・カリキュラムを提供し、Sonyは学校向けロボット教材KOOVを展開。Googleは長年CS Firstなどを提供してきました(CS Firstは2025年6月で提供終了)。
今すぐ使える!おすすめSTEAM教材10選【2025年版】


それでは、教育現場で高い評価を得ているSTEAM教材を、対象年齢順にご紹介していきます。
1. Cubetto(キュベット)|3歳から始めるプログラミング
対象年齢:3~9歳向け
価格帯:約3万円〜
学習分野:プログラミング的思考、論理思考
キュベットはイギリスで開発された幼児向けプログラミング教材です。画面やキーボードを一切使わず、木製のロボットと操作ボードを使って学習します。
特徴とメリット
- デジタルデトックスしながらプログラミング学習が可能
- 直感的な操作で3歳からでも理解できる設計
- モンテッソーリ教育との親和性が高い
全国の保育園・幼稚園で導入が進んでおり、子どもたちが「順次処理」「繰り返し」「条件分岐」といったプログラミングの基本概念を自然に身につけています。
2. VisCuit(ビスケット)|お絵かき感覚でプログラミング
対象年齢:4歳〜
価格帯:無料(アプリ)
学習分野:創造性、プログラミング的思考、表現力
ビスケットは、文字を使わず自分で描いた絵のみでプログラミングが可能なため、読み書きができない小さな子どもでも楽しめるのが最大の特徴です。
特徴とメリット
- 完全無料で利用可能
- パソコン、タブレット、スマートフォン対応
- 「メガネ」という直感的なツールでプログラミング
絵を描く創造性とプログラミング的思考を同時に育成できるため、文系・理系の枠を超えた学習が可能です。
3. Ozobot(オゾボット)|紙とペンでロボットプログラミング
対象年齢:5歳〜
価格帯:約1万円〜
学習分野:プログラミング、色彩認識、空間認識
アメリカ生まれのオゾボットは、直径2.5cmの超小型プログラミングロボットです。紙とペンだけでプログラミングが可能で、初期投資を抑えながら本格的なプログラミング学習ができます。
特徴とメリット
- 設定不要で即座に学習開始可能
- 黒・赤・緑・青の4色でコマンドを指定
- アナログとデジタルの融合学習
- 複数台を使ったグループ学習にも最適
4. LEGO® Education SPIKE™(レゴ・スパイク)|創造性×論理思考
対象年齢:6歳〜
価格帯:3万円〜6万円
学習分野:工学、プログラミング、問題解決、協働学習
レゴエデュケーションが提供するSPIKEシリーズは、レゴブロックにセンサーとモーターを組み合わせてロボットを作り、プログラミングで動かす総合的なSTEAM教材です。
ラインナップ
- SPIKEベーシック:小学校低・中学年向け(6〜10歳)
- SPIKEプライム:小学校高学年〜高校生向け(10〜18歳)
特徴とメリット
- レゴの創造性とプログラミング学習の融合
- 豊富な学習プログラムと教員向けサポート
- 国際ロボット競技会「FLL(FIRST LEGO League)」推奨・適合
- チームワークと問題解決能力を同時育成
組み立て段階でエンジニアリング思考を、プログラミング段階でコンピュテーショナル思考を育成。さらに、作品発表を通じてプレゼンテーション能力も向上します。
5. micro:bit(マイクロビット)|本格プログラミングへの入門
対象年齢:8歳〜
価格帯:2,000〜3,000円前後
学習分野:プログラミング、電子工作、IoT、データサイエンス
マイクロビットはイギリスのBBCが主導して開発した手のひらサイズのマイコンボードです。日本上陸以来、教育現場で急速に普及しています。
搭載機能
- 25個のLEDディスプレイ
- 2つのプログラマブルボタン
- 加速度センサー、磁力センサー
- 温度センサー、光センサー
- Bluetooth通信機能
特徴とメリット
- 圧倒的なコストパフォーマンス
- ブロック型プログラミングからテキストプログラミングまで対応
- 豊富な拡張パーツでIoTシステム構築も可能
- 世界85+カ国以上で教育利用
工作品を光らせたり、温度や加速度を測定したり、無線通信でデータを送受信したりと、幅広い学習が可能です。中学校技術科の授業でも積極的に活用されています。
6. IchigoJam(イチゴジャム)|日本発の手のひらパソコン
対象年齢:8歳〜
価格帯:約2,000円〜
学習分野:プログラミング、コンピューターサイエンス
イチゴジャムは「こどもパソコン」とも呼ばれる、日本で開発された手のひらサイズのマイコンです。初心者向けプログラミング言語BASIC(ベーシック)を現代的にアレンジして学習できます。
特徴とメリット
- 電源を入れれば即座にプログラミング開始
- インターネット接続不要の安全設計
- 半田付けキットでものづくり体験も可能
学習効果 BASICプログラミングを通じて、コンピューターの基本的な仕組みから学べるため、より深いコンピューターサイエンスの理解につながります。
7. Artecブロック ロボット教材|日本の学校現場で圧倒的シェア
対象年齢:8歳〜18歳
価格帯:1万円〜5万円
学習分野:ロボティクス、プログラミング、メカニクス
株式会社アーテックが開発したプログラミング学習教材シリーズです。独自のArtecブロックを使ってロボットを組み立て、専用ソフトウェアでプログラミングします。
特徴とメリット
- 組み立てやすい独自のブロック設計
- 初心者から上級者まで段階的に学習可能
- 豊富な指導案と教員研修プログラム
コース展開
- はじめてのロボットプログラミングキット:小学生向け
- エジソンアカデミー:小学校高学年〜中学生向け
- エキスパートコース:高校生〜大学生向け
8. littleBits(リトルビッツ)|磁石で繋ぐ電子工作
対象年齢:8歳〜
価格帯:約1万円〜
学習分野:電子工学、回路設計、創造性
リトルビッツは、磁石で簡単に接続できる電子パーツを使って電気回路や仕組みを学べる教材です。専門知識がなくても直感的に電子工作を楽しめます。
特徴とメリット
- 磁石による簡単確実な接続
- 色分けされたモジュールで視覚的に理解しやすい
- MITメディアラボ発のイノベーティブな設計
- アート作品制作にも活用可能
学習効果 電子回路の基礎から応用まで、段階的に学習できます。特に「なぜ動くのか?」という原理理解に優れています。
9. Scratch(スクラッチ)|世界標準のビジュアルプログラミング
対象年齢:8歳〜
価格帯:無料
学習分野:プログラミング、ゲーム制作、アニメーション、音楽制作
MITメディアラボが開発したScratchは、世界で最も使われているビジュアルプログラミング環境です。ブロックを組み合わせるだけで本格的なプログラムを作成できます。
特徴とメリット
- 完全無料で利用可能
- 世界中のユーザーと作品を共有できるコミュニティ機能
- 小学校プログラミング教育の事実上の標準
- ゲーム、アニメーション、音楽など幅広い創作が可能
最新バージョンの機能
- 外部拡張等でAI学習も扱える
- マイクロビットとの連携
- 多言語対応(40言語以上)
10. Think!Think!(シンクシンク)|思考力を鍛えるパズルアプリ
対象年齢:4歳〜10歳
価格帯:無料〜月額1,980円
学習分野:思考力、空間認識力、論理的思考
シンクシンクは、空間認識力や論理的思考を鍛える思考力育成に特化したデジタル教材です。ゲーム感覚で楽しみながら、算数・数学の土台となる思考力を育成します。
収録内容
- 120種類以上の多様なパズル
- 25,000問以上の豊富な問題数
- 年齢・能力に応じた個別最適化システム
特徴とメリット
- 1日10分の時間制限で集中力維持と依存防止を両立
- カンボジア・インドでの大規模実証実験で学習効果を科学的に証明
- Google Play Awards受賞の高品質アプリ
- 保護者向けの詳細な学習レポート機能
継続利用により、学力や認知指標で統計的改善が見られています。
STEAM教材選びの完全ガイド|失敗しない選び方
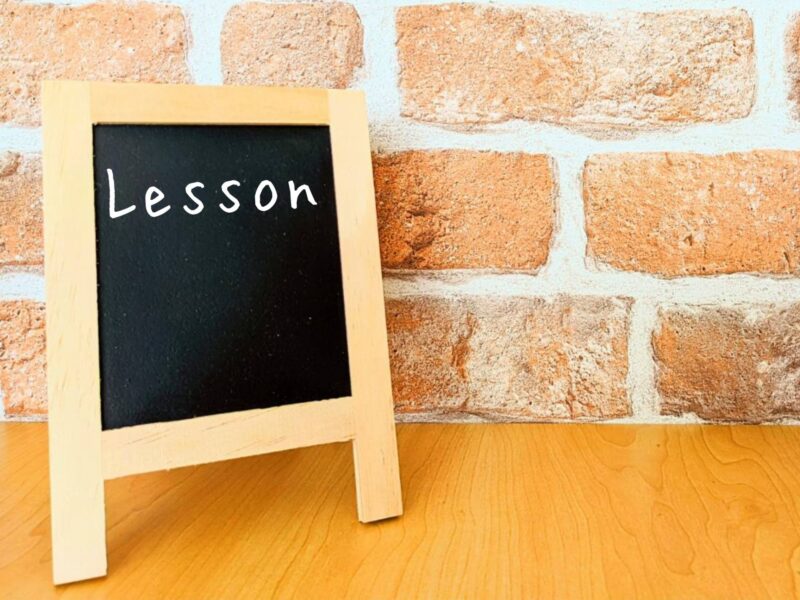
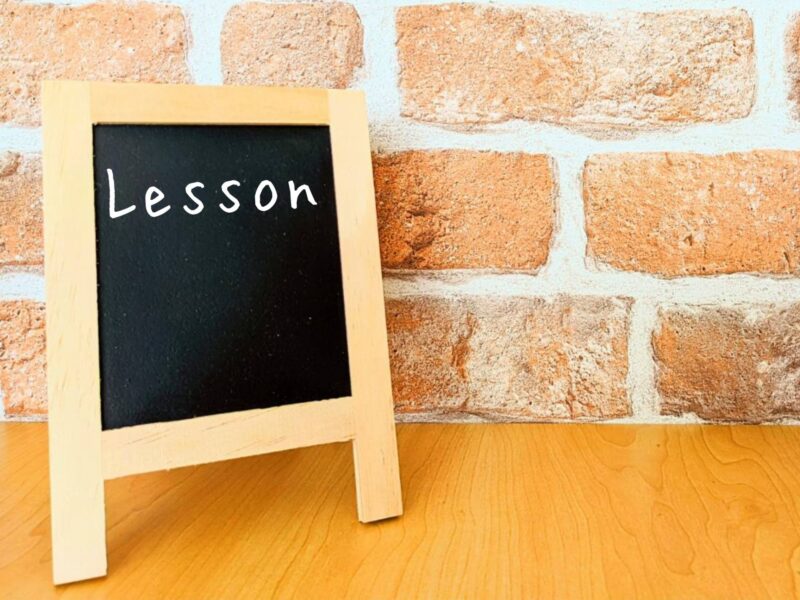
| 年齢層 | 重視すべきポイント | おすすめ教材 |
|---|---|---|
| 3-6歳 | 直感性、安全性、遊び要素 | Cubetto, VisCuit |
| 6-9歳 | 創造性、基礎概念理解 | Ozobot, LEGO SPIKE Basic, Scratch Jr |
| 9-12歳 | 論理思考、問題解決能力 | micro:bit, LEGO SPIKE Prime, Scratch |
| 12歳以上 | 実践的スキル、将来性 | IchigoJam, Python, Arduino |
STEAM教材を選ぶ際は、まず子どもの年齢と発達段階を最重要ポイントとして考慮する必要があります。年齢に適さない教材を選んでしまうと、子どもが挫折してしまったり、逆に物足りなさを感じてしまったりする可能性があります。
学習目的別の選び方
初めてのプログラミング体験を重視する場合は、Ozobot、Cubetto、VisCuitといった直感的に操作できる教材がおすすめです。これらの教材は、コンピューターの画面や複雑なインターフェースに慣れ親しんでいない子どもでも、すぐに操作を覚えることができます。
特にOzobotは紙とペンという身近なツールを使うため、「プログラミングって難しそう」という先入観を持つことなく学習をスタートできます。
予算別の選び方
予算1万円未満での効果的な学習
限られた予算でも、質の高いSTEAM教育は十分に実現可能です。micro:bitは約2,000円という低価格でありながら、本格的なプログラミング学習からIoT体験まで幅広くカバーできる優秀な教材です。参考書を1-2冊追加しても合計5,000円程度で、中学生レベルのプログラミング学習が可能になります。
予算1-3万円での本格的な学習環境構築
この価格帯では、より実践的で拡張性のある教材を選択できます。Ozobotに拡張パックを組み合わせることで、基本的な紙ペンプログラミングから、より高度なデジタルプログラミングまで段階的に学習を進められます。特に小学生にとっては、アナログとデジタルの両方を体験できる貴重な学習機会となります。
予算3-5万円での高品質な学習体験
この価格帯になると、学校現場でも使用されているプロフェッショナルレベルの教材を選択できます。LEGO SPIKE Basicは、世界中の教育現場で実績を積んでいる信頼性の高い教材で、創造性とプログラミング学習を高次元で融合させることができます。
予算5万円以上での最高水準の学習環境
十分な予算がある場合は、LEGO SPIKE Primeのような最高レベルの教材を選択できます。この教材は高校生レベルまで対応しており、本格的なロボティクス学習から競技会への参加まで幅広い活用が可能です。将来的にエンジニアリング分野への進学を考えている学生には、特に価値の高い投資となるでしょう。
まとめ|学びは「好奇心」から始まる
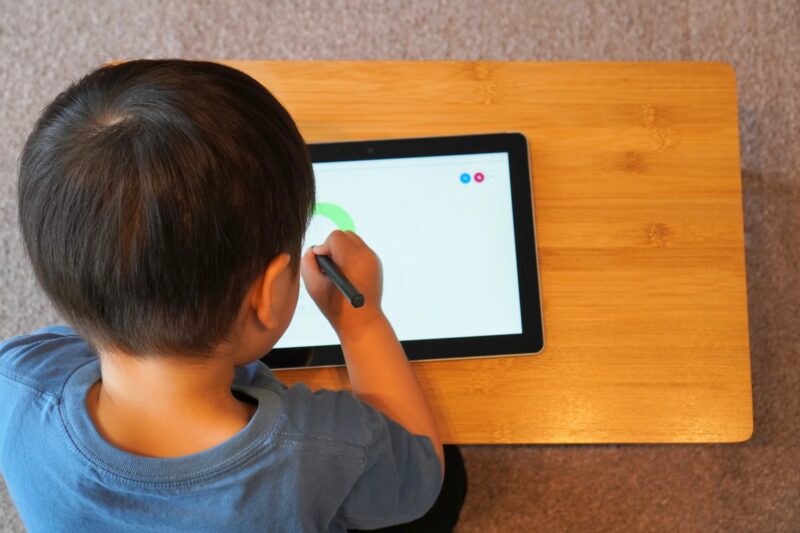
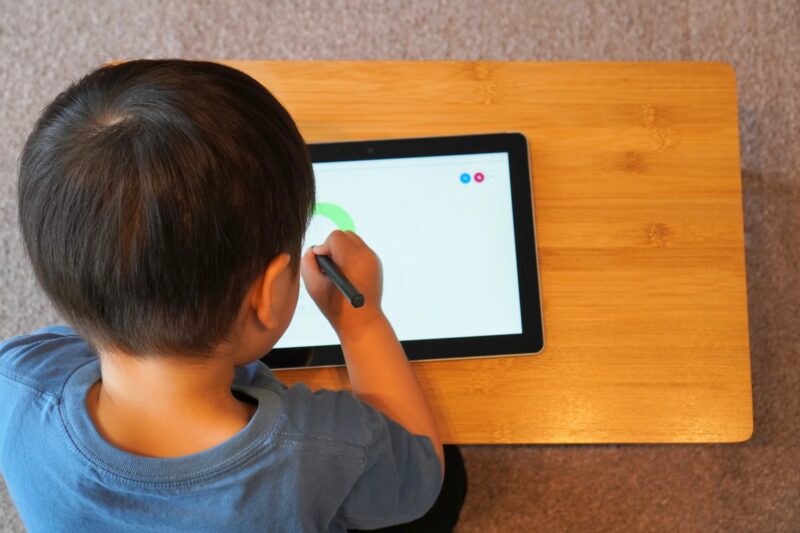
子どもの「知りたい!」「やってみたい!」というワクワクする気持ちこそが、学びの最も大切な原動力です。その好奇心を大切に育て、将来への可能性を広げる手段として、STEAM教育は極めて有効なアプローチといえます。
2025年現在、デジタル化がさらに加速し、AI技術も日常生活に浸透しています。このような時代だからこそ、単なる技術習得にとどまらず、創造性と論理性、芸術性と科学性を併せ持った総合的な能力を育成することが重要です。
本記事で紹介した10の教材は、いずれも世界中の教育現場で高い評価を得ている実績のあるものばかりです。子どもの年齢、興味、予算に合わせて最適な教材を選び、ぜひSTEAM教育の第一歩を踏み出してください。
変化の激しい21世紀を生き抜く力を育てるために、STEAM教育への取り組みは今後ますます重要になることでしょう。一人ひとりの子どもが持つ無限の可能性を信じ、適切な学習環境を提供することで、次世代の大人を育てていきましょう。