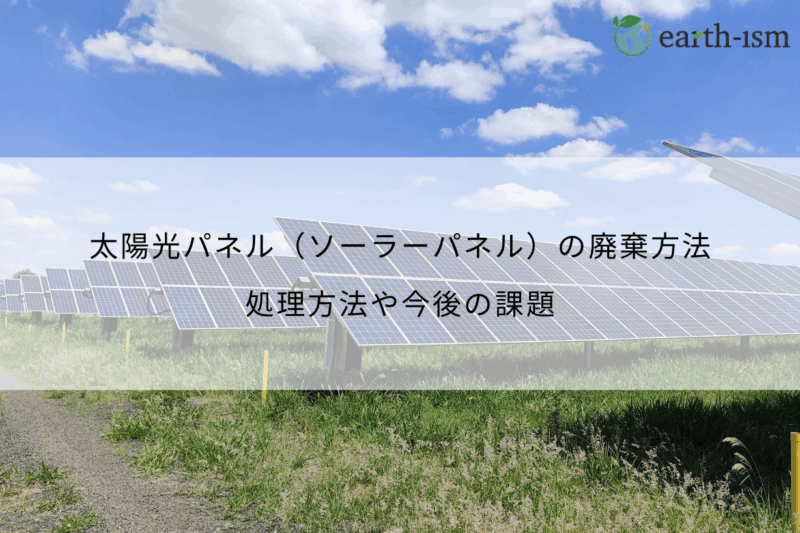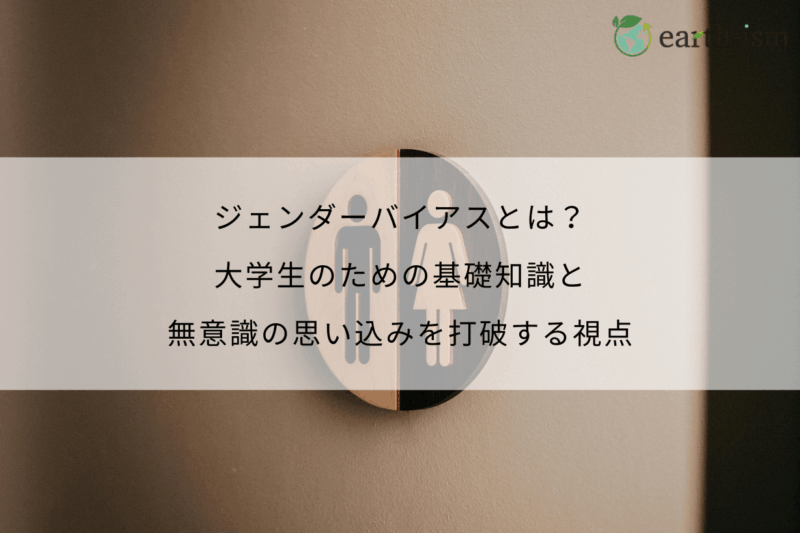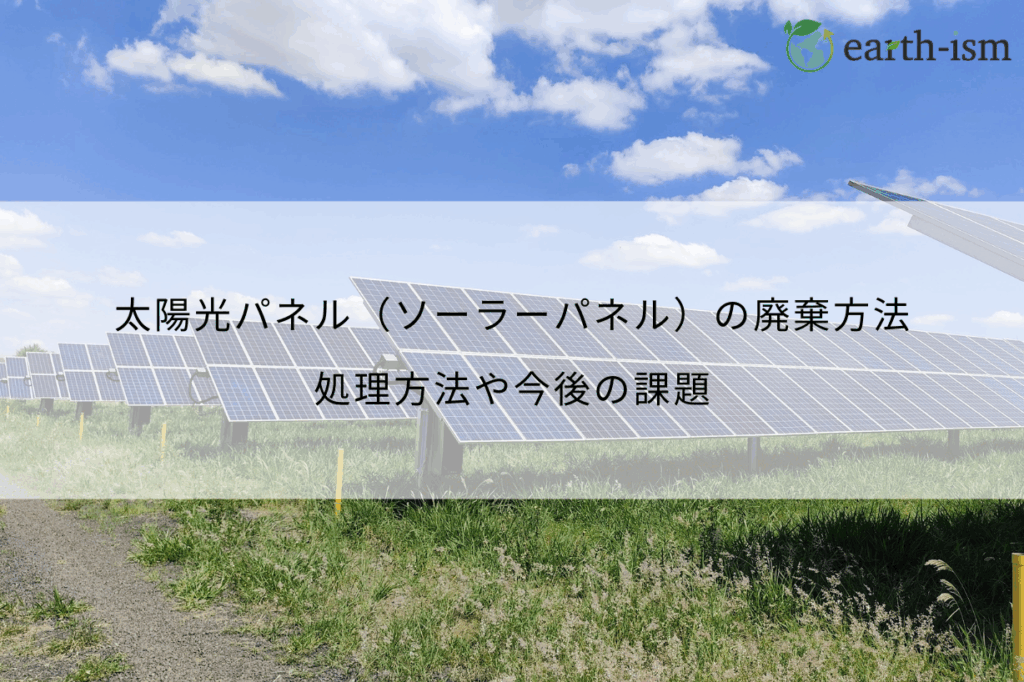教育はいつから「ぜいたく品」になったのか|子育て世代が抱える構造的な貧困を分析
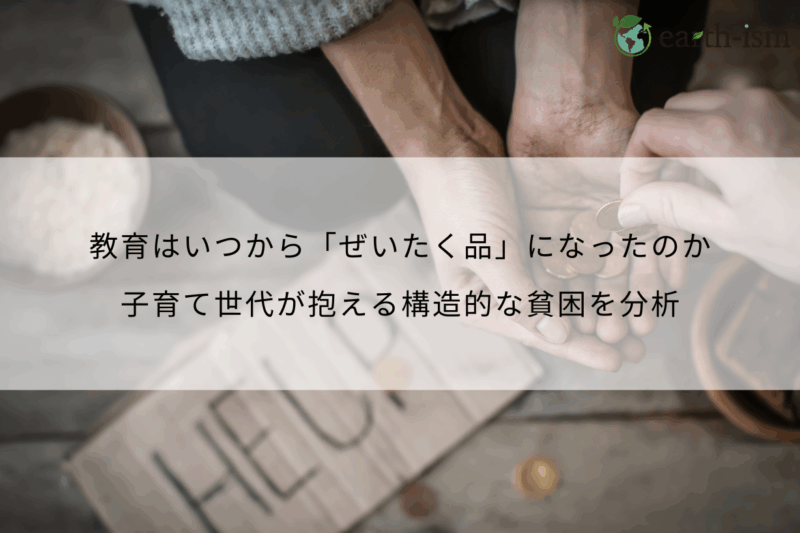
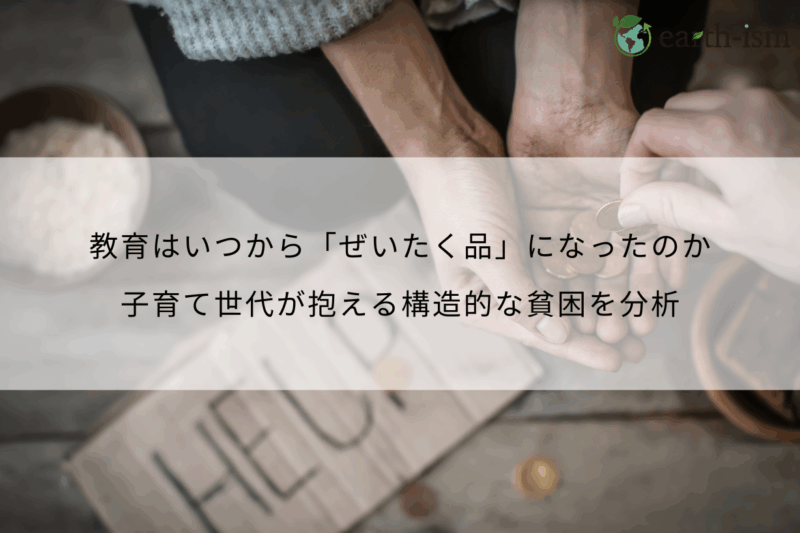
Contents
「教育費を払うために、自分の老後を削る」
もし、この言葉に少しでも胸がざわつくなら。あるいは、すでにその現実の渦中にいるのなら。この記事は目の前のあなたのためにあります。子どもの未来を思って払うお金が、自分の老後を奪っていくという矛盾を、私たちはいつまで抱え続ければ良いのでしょうか。
個々の家庭の「やりくり」や「自己責任」の問題ではありません。私たち子育て世代が直面しているのは、個人の努力ではどうにもならない「構造的な貧困」であり、国家レベルで設計されたシステムのエラーなのです。
この記事では、なぜ日本において教育が「未来への投資」ではなく「家計を圧迫するコスト」と化してしまったのか、その構造をデータと共に解き明かしていきます。


教育費の“インフレ”が止まらない


私たちの親世代が知っている「教育費」と私たちが今直面している「教育費」は、もはや別物です。定期的に取られているデータは家計の実感を冷徹に裏付けています。
注目すべきは、他の物価と比べた教育費の異常な上昇率です。
1975年(昭和50年)、国立大学の授業料は年間3万6,000円でした。消費者物価指数(2020年基準)で見ると、1975年の物価は現在の約半分(指数49.0)です。仮に物価スライドだけなら、授業料は7万円程度になっています。
しかし、現在の国立大学授業料の標準額は53万5,800円。実に14.9倍にも高騰しているうえに、2025年11月現在ではこの価格よりも高騰する可能性も示唆されているようです。この間、消費者物価全体は約2倍の上昇に過ぎません。
所得が伸びない中、教育費だけが異次元のインフレを起こしているという所得と教育費の伸び率の差こそが、家計に襲いかかる闇の正体といえるのではないでしょうか。
大学費用だけではありません。文部科学省の「子供の学習費調査」(令和5年度)によれば、公立中学校に通う生徒の「学校外活動費(塾や習い事など)」は、年間平均で356,061円に達します。子どもが二人いれば、それだけで年間70万円を超える支出です。これは学習費総額の65.6%を占め、依然として公教育費の2倍以上を私費(塾代など)が占める異常な構造を示しているといえます。
決して「贅沢」とは呼べません。なぜなら受験戦争が激化し、学校の授業だけでは内申点や学力競争に対応しきれない現実がある以上、多くの家庭にとって塾は「任意」ではなく「ほぼ必須」のコストとなっているためです。
私たちは、この制御不能なコスト上昇を「教育費インフレ」と呼び、社会問題として認識する必要があります。
なぜ日本は「教育=私費」という異常を許容するのか


「教育費インフレ」の根本原因は、極めてシンプル。「日本は、教育を“国の投資”ではなく“家庭の私費”と捉えすぎている」のです。
財務省の資料でもたびたび引用されるように、日本の公教育(初等教育から高等教育まで)に対する公的支出の対GDP比は、OECD(経済協力開発機構)諸国の中で長年、最低水準にあります。(2020年時点でOECD平均5.1%に対し、日本は4.0%など)。
国が未来への投資を怠ってきた。そのツケが、そっくりそのまま「親の責任」という名の請求書として、各家庭に回されているのです。「子どもの教育は親が責任を持つべきだ」という価値観は、一見、美しい「家族の絆」のように聞こえます。しかし、それは十分な所得の伸びと安定雇用があった時代の名残に過ぎません。
実質賃金が30年間ほぼ横ばいであるこの国で、その価値観だけを維持することは、もはや「美徳」ではなく「呪縛」です。私たちは、教育費負担が「家計」の問題ではなく、国の「社会設計」の問題であるという現実に、目を向ける必要があるのではないでしょうか。
実際に、筆者も子どもの頃は田舎で過ごしていたからか、「大学に行くのは贅沢」「高等教育を受けるのは金持ちだけ」といった発言をよく聞いてきました。都市と地方の地域格差もあるかもしれませんが、教育の機会は均等にされるべきものであるのに、富裕層・中間層と貧困層の間には大きな壁があるでしょう。
“中間層の崖”——支援からこぼれ落ちる家族たち
社会問題として「貧困」が語られるとき、スポットライトが当たるのは主に「住民税非課税世帯」です。もちろん、その層へのセーフティネットは不可欠です。しかし今、日本で最も深刻な悲鳴を上げているのは、そこではありません。
年収600万円から900万円。いわゆる「中間層」と呼ばれる世帯こそが、あらゆる支援の網からこぼれ落ち、教育費という名の重石(おもし)によって沈みかけています。
この構造を象徴するのが、複雑怪奇な「支援制度の所得制限」です。たとえば児童手当。2024年10月から所得制限が撤廃され、支給期間も高校生まで延長されました。大きな前進ですが、基本的な支給額(月額1万円など)が年間数十万円の塾代や将来の大学費用にどれだけ影響するでしょうか。
加えて、下記の問題もあります。
- 高校授業料無償化(就学支援金):年収約910万円未満の世帯が対象
- 大学授業料無償化(高等教育の修学支援新制度):これが最も深刻な「崖」。満額支援の対象は「住民税非課税世帯」。支援が受けられる上限も、多子世帯や私立理系などの例外を除けば、年収約600万円程度まで。
つまり、年収600万円から900万円の世帯は「大学無償化の対象外」であるものの「高校無償化は対象」であり、「児童手当はもらえる」という、制度の狭間にいます。彼らは「支援を必要としない裕福な層」では決してなく、「支援を打ち切られることで、教育費負担が最も重くのしかかる層」なのです。
【シミュレーション:世帯年収800万円(手取り月収45万円)の家計】
夫婦共働き(正社員とパート)で世帯年収800万円。手取りは約620万円(月平均45万円+ボーナス)と仮定します。
- 手取り月収:45万円
- 住居費(ローン):12万円
- 生活費・光熱費・通信費:15万円
- 子ども2人(公立中・公立小)の学校関連費・習い事:4万円
- 中学生の塾代(平均):3万円
- 小学生の塾・習い事代:2万円
この時点で残りは9万円です。ここから食費や雑費、保険料を支払うと、手元に残るのは3〜4万円。この3〜4万円から、年間100万円以上(二人分の大学費用。私立文系なら一人年間120万円、理系なら160万円)を貯蓄して同時に自分たちの老後資金(一人2000万円?)を貯めなければならないとなると、至難の業と言わざるを得ません。
「中間層の崖」の現実です。貯蓄などできるはずがなく、ただただ家計が疲弊していく。社会設計の欠陥が、この層を意図的に貧困へと追い込んでいるのです。
“年収の壁”が世帯収入の最大化を阻む


「中間層が苦しいなら、もっと働けばいい」と言うのは簡単です。しかし、そこにも構造的な罠が仕掛けられています。
「年収の壁」です。
子育て中の女性(あるいは男性)がパートタイムで働き、家計を助けようとするとき、必ずこの壁にぶつかります。
- 106万円の壁:従業員101人以上の企業などで、週20時間以上働く場合。社会保険(厚生年金・健康保険)への加入が義務化され、年間約15〜16万円の保険料負担が発生。手取りが減る「働き損」が起こります。
- 130万円の壁:企業の規模に関わらず、年収が130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険料(年間30万円以上)を支払う必要が生じます。
「週にあと3時間だけ多く働けたら、子どもの塾代が払える。でも、それを超えると130万円の壁にぶつかって、手取りが20万円近く減ってしまう。だから働けないんです」といった悩みは、多くのパートタイム労働者が抱えるリアルなジレンマです。この制度は、労働者の「就労調整(働き控え)」を強烈に誘発しています。
国の施策としては「キャリアアップ助成金」などで壁を超えやすくしようとしていますが、問題の本質はそこではありません。
本質は、「夫がフルタイムで働き、妻が家事・育児をしながら扶養の範囲内で働く」という「昭和モデルの家族制度」を前提とした税・社会保障制度が、令和の今もなお温存されていることです。この歪なシステムが、女性の経済的自立を阻害するだけでなく、世帯収入の最大化を妨げ、結果として教育への投資を妨げているのです。
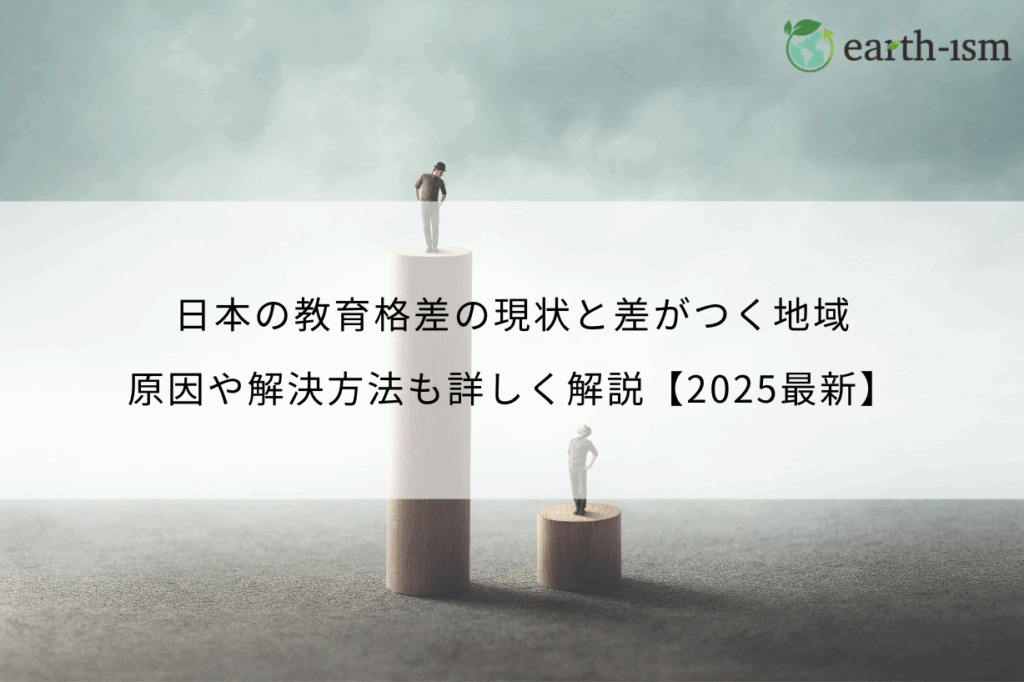
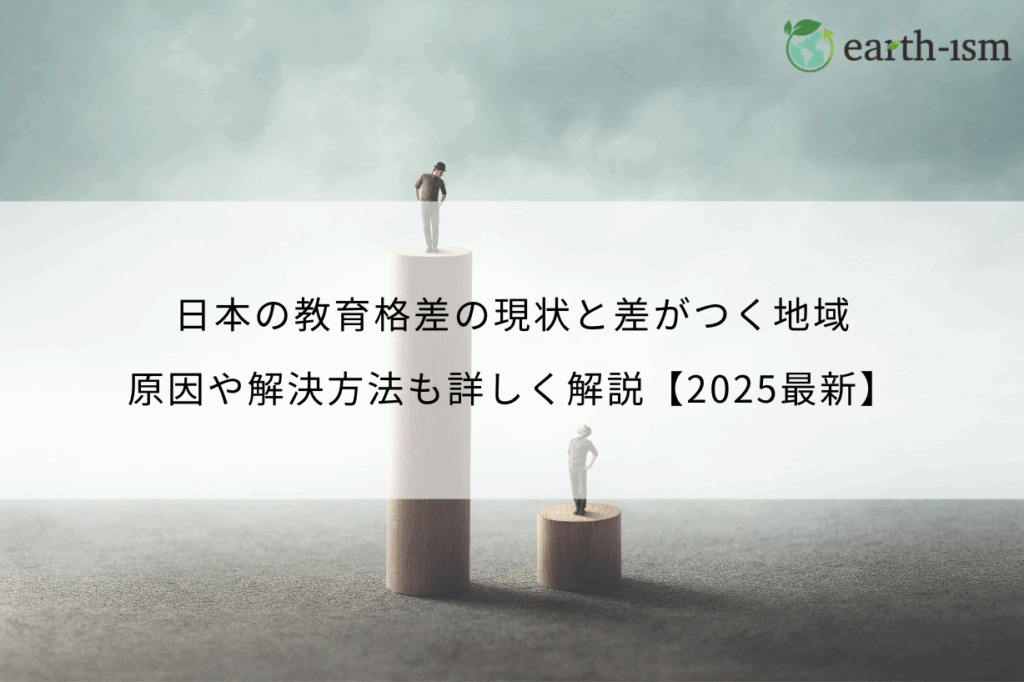
教育費が「老後不安」に直結するメカニズム
冒頭の言葉に戻りましょう。「教育費を払うために、自分の老後を削る」。これは比喩ではありません。
金融広報中央委員会の「家計の金融行動に関する世論調査(令和5年)」によると、二人以上世帯(子育て世代の中心である30代・40代)の金融資産保有額の「中央値」(データを順番に並べた真ん中の値)は、衝撃的な低さです。
- 30代世帯の中央値:150万円
- 40代世帯の中央値:220万円
上記が現実です。半数の世帯は、これ以下の貯蓄しか持っていません。この貯蓄額で、どうやって子ども一人あたり1000万円とも言われる大学費用(入学金・授業料・生活費)を捻出し、同時に「老後2000万円問題」に備えようというのでしょうか。
結果、親世代は究極の選択を迫られます。
- 老後資金(iDeCoやNISA)を諦め、すべてを教育費に回す
- 教育費のために貯蓄を取り崩し、学資保険を解約し、最後は教育ローン(親の借金)に手を出す
- 子どもに奨学金(子の借金)という名の負債を背負わせる
どれを選んでも、誰かの未来が削られます。特に「1」と「2」は、教育費の支払いが終わる頃(50代後半〜60代)には親が貯蓄ゼロになっていることを意味し、「老後の貧困」を予約する行為に他なりません。
教育費の私費負担の重さとは、すなわち「子どもの未来」と「親の老後」を天秤にかける非人道的なシステムなのです。
教育は「課金ゲーム」か「未来への投資」か


私たちはいつから、子どもの未来を「課金ゲーム」のように捉えなければならなくなったのでしょうか。
親の所得が、そのまま子の学力を決める。
そんな残酷な現実が、データによって繰り返し証明されています。年収が高いほど良い教育環境(塾、習い事、体験活動)を「買う」ことができる。その結果、学力に差がつく。
「教育を受ける権利」は、日本国憲法第26条で保障された基本的人権のはずでした。しかし、その実態は「教育を買う力」に置き換わってしまっています。
「お金がなければ奨学金がある」という反論もあるでしょう。しかし、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金の主流は「貸与型(=借金)」です。多くの若者が、大学卒業と同時に平均300万円を超える負債を背負います。これは「支援」ではなく「未来への足枷」です。
一方で、世界に目を向けてみましょう。
ドイツでは、2014年までに全州で国立大学の授業料が原則無償化されました。一度は有料化の動きもありましたが、「教育は社会の公的投資である」という哲学に基づき、世論がそれを覆したのです。フランスや北欧諸国も同様に、高等教育までの公的負担を原則としています。
もちろん、無償化には質の維持という課題もあります。しかし、彼らは「教育が格差の再生産装置になってはならない」という一点において、国家としての強い意志を持っています。
翻って日本はどうか。「受益者負担」の名の下に教育を私費化し続けた結果、教育は「階層を流動化させる梯子」ではなく、「階層を固定化する壁」として機能してしまっているのです。
持続可能な社会のために、今すぐ何をすべきか
私たちは、子育てを「リスク」にしすぎています。教育は各家庭が切り詰めて行う「消費」や「コスト」ではありません。社会全体で行うべき「未来への投資」です。子ども一人ひとりの可能性を最大限に引き出すことこそが、少子高齢化が進むこの国にとって最も確実で、最もリターンの大きい投資であるはずです。
とはいえ、壁や課題だけを言っていても問題は解決しません。どうすればいいのでしょうか。小手先の「支援金」では、この構造的貧困は解決しません。必要なのは、社会のOS自体を入れ替える覚悟です。
1. 教育への公的支出を、OECD平均まで引き上げる
財源論(「お金がない」)は、優先順位の問題に過ぎません。未来への投資を最優先事項とする政治的決断が必要です。まずは高等教育の授業料負担の大幅な軽減と、給付型奨学金の抜本的拡充が急務といえます。
2. 「年収の壁」の抜本的見直しと、第3号被保険者制度の抜本的見直し
「働き控え」を生む歪な制度は見直しが図られるべき時かもしれません。誰もが働きたいだけ働き、その対価が正当に家計に反映されるシステムへ移行する道もあると考えられるでしょう。
3. 支援の「所得制限」のあり方を問い直す
「支援が必要な層」の定義が、現代の教育費インフレの実態と乖離しているといえます。特に負担の重い「中間層」に対し、支援が届くような制度設計、例えば大学費用の支援対象を年収900万円程度まで引き上げるなどが必要です。
「子を育てる社会」を、「子を削る社会」にしてはいけません。
まとめ|教育を「コスト」にしないために


教育とは未来への希望のはずでした。それを“支払い能力”で測る国のままでは、少子高齢化も進んでいる昨今、持続可能な未来を語ることは難しいでしょう。
「構造的な貧困」は確実に次の世代に受け継がれます。「教育費は家計の問題」という呪縛から解き放たれ、「教育は社会全体の投資である」という常識を取り戻すことが、今後の課題といえるのではないでしょうか。
よくある質問(FAQ)
Q:なぜ今の時代の教育費は、親世代の頃より高く感じるのでしょうか?
A:単なる実感ではなく、データとして教育費が異常な高騰(インフレ)を起こしているからです。例えば、国立大学の授業料は1975年から現在までに約14.9倍に上昇していますが、消費者物価指数は約2倍の上昇に留まっています。所得が伸びない中で教育費だけが突出して上がっているため、家計への負担が相対的に激増しています。
Q:教育費負担における「中間層の崖」とは何ですか?
A:世帯年収が約600万円から900万円の中間層が、各種支援制度の所得制限によって支援対象から外れ、最も家計が困窮する現象を指します。住民税非課税世帯などの低所得層へのセーフティネットはあるものの、中間層は「自力で高額な教育費を全額負担」しなければならず、貯蓄が困難な状況に追い込まれています。
Q:パート主婦(夫)が直面する「年収の壁」が教育費にどう影響しますか?
A:106万円や130万円の壁を越えると社会保険料などの負担が発生し、手取りが減る「働き損」が生じます。教育費を稼ぐために労働時間を増やしたくても、制度上の歪みによって就労調整(働き控え)を余儀なくされ、世帯収入の最大化が阻まれることで、結果的に教育資金の準備を難しくしています。
Q:教育費を優先することで、老後の生活にはどのようなリスクがありますか?
A:教育費を捻出するためにiDeCoやNISAなどの老後資金の積み立てを諦めたり、貯蓄を取り崩したりすることで、「老後貧困」を招くリスクが高いです。30代・40代の金融資産保有額の中央値は150万〜220万円と低く、大学費用と老後資金(2,000万円問題)を同時に解決することは、現在の日本の構造では至難の業となっています。
Q:日本の教育に対する公的支出は、海外と比べてどうなっていますか?
A:日本の公教育に対する公的支出の対GDP比は、OECD諸国の中で長年最低水準(2020年時点で日本4.0%、OECD平均5.1%)にあります。欧州諸国(ドイツやフランスなど)では「教育は社会の公的投資」という考えから大学授業料が原則無償の国も多いですが、日本は「教育は家庭の私費」という考えが強く、各家庭の自己責任に委ねられているのが現状です。