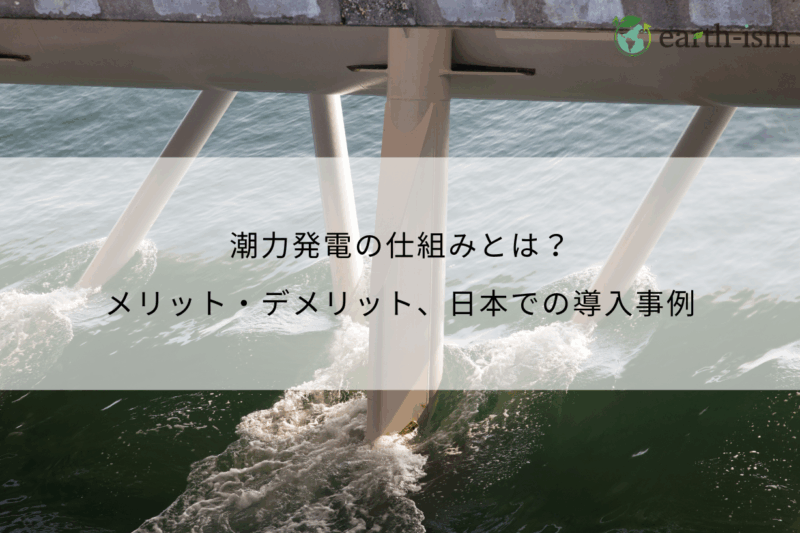少子高齢化の中で、若者ができることは「構造を疑うこと」|高齢者を支えるのは本当に“若者の役目”か?
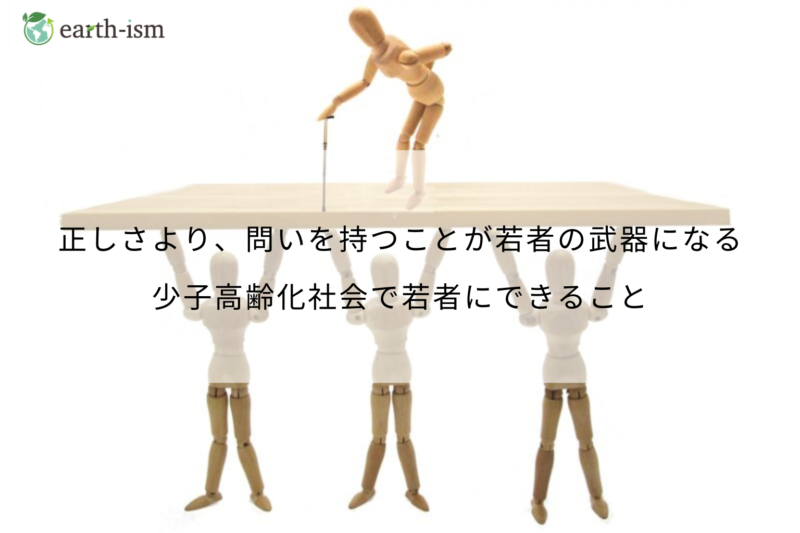
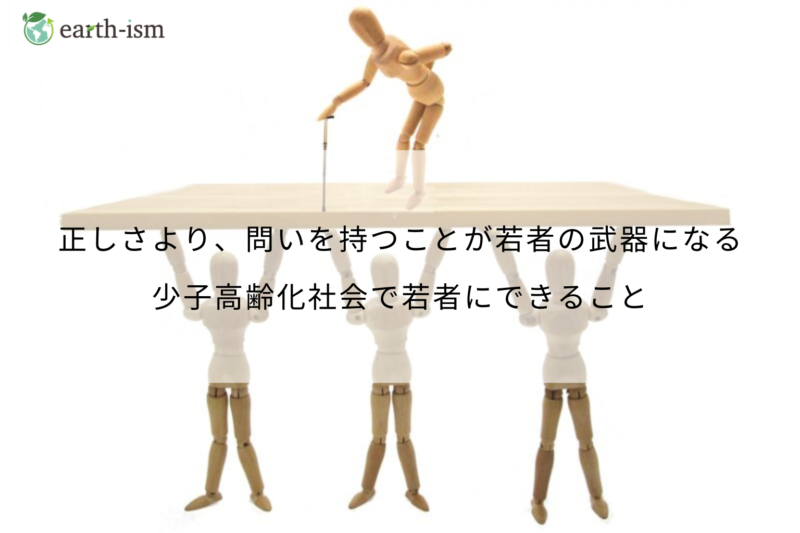
Contents
日本において「少子高齢化」は避けて通れないテーマのひとつです。人口は減少を続け、2040年には全人口の約35%が65歳以上になると見込まれています。
この現実を前に、私たち若い世代は「支える側」という枠組みだけでなく、自分たちの生き方や社会のあり方をどう描き直せるかを考える必要があります。少子高齢化が進む社会で、私たちは何を選び、どんな未来をつくれるのでしょうか。一緒に考えてみましょう。
少子高齢化という「現象」が語られるとき、何が見落とされているか


まずは少子高齢化という社会問題を考えたときに、見落とされやすい点について見ていきましょう。
数字だけでは語れない「構造」の話
少子高齢化というと、子どもの数が減り高齢者が増えていく単なる数字の変化と思われがちですが、その背景にはさまざまな社会的構造が関わっています。
例えば、価値観の多様化により子どもを産まない選択や非婚化・晩婚化が進んでいることが挙げられます。他にも、女性の社会進出が進む傍ら、子育て支援が不十分であることや不安定雇用・低賃金による経済的な不安感も少子高齢化の要因です。


高齢化率・出生率だけでなく、「どこにお金が流れているか」を見る
少子高齢化問題を考えるとき、高齢化率や出生率だけでなく、資金の流れを知ることも大切です。今後も変わらず少子高齢化が進んだ場合、若者1人に対し高齢者1人を支える「肩車社会」が2060年頃に訪れると考えられています。
年金、医療費、介護費などの社会保障費は年々増え続け、現役世代の負担はさらに大きくなっていきます。
年齢別の投票率・政治的影響力の格差
日本では、若者に比べて高齢者のほうが投票率が高くなっています。
令和6年10月に行われた第50回衆議院議員総選挙における投票者の投票率を年代別で見てみると、20歳代が34.62%、30歳代が45.66%だった一方で、60歳代は68.02%、70歳代以上は60.42%でした。
この結果からも分かるように、高齢者のほうが若者よりも政治的な影響力が高いといえるでしょう。高齢者の割合が増え続けると、有権者に占める高齢層の比率も上がり、政策も彼らの意見が反映されやすくなります。
「世代間対立」は誰が得するのか?政治・メディアの“分断装置”
少子高齢化が進む中で、年金や医療など社会保障の負担をめぐって、「高齢者ばかり優遇されている」「若者ばかり負担が大きい」といった世代間の不平等感や対立の声が上がることがあります。
こうした分断を、政治や一部のメディアが「対立構造」として取り上げることで、感情を刺激し注目を集めやすくなるのも事実です。ときに、世代間の溝を強調することで票を集めたり、視聴率やクリックを稼ぐ材料とされることもあります。
しかし、世代間対立そのものでは少子高齢化という構造的な問題は解決できません。若者と高齢者は相反する存在ではなく、本来は同じ社会を循環する一員です。
世代を分断して誰かを責めるだけではなく、雇用・教育・子育て支援・税制など、仕組みそのものをどう見直し、より持続可能な形に転換していけるかが問われています。
「貢献しなきゃ」というプレッシャーが、若者から思考を奪っている


「社会に貢献しなければならない」「高齢者を支えていくのは若者だ」という価値観はいまだ根強いですが、それが若者のプレッシャーになっている可能性があります。
役に立たないと意味がない?
「人の役に立てない自分には価値がない」という考え方は、誰かを支えようとする善意を、時に自分自身をすり減らす鎖に変えてしまいます。
もちろん、誰かの役に立つことは素晴らしいことです。しかし、役に立つことを目的にしてしまうと、相手からの評価でしか自分を測れなくなります。誰かに必要とされることよりも、自分自身をどう扱うかが、何より大切です。
「若者が支えるしかない」構図の不自然さ
近年、「ヤングケアラー」という言葉が示すように、家族の介護や世話を若い世代が背負い込むケースが増えています。少子高齢化の進む社会で、若者だけが無理に負担を背負い続ける構造は、本来とてもいびつなものです。
「若者が支えるしかない」という考え方は、社会全体の責任を個人に押し付けているにすぎません。
一部の人が背負うのではなく、制度と仕組みを整えて社会全体で支え合う視点が必要です。
「貢献」の前に、自分の人生の主導権を取り戻す
私たちはつい「何かの役に立たなきゃ」と焦ってしまいがちです。でも本当に大切なのは、他人に貢献する前に自分の心を満たし、自分の暮らしや選択を自分の意思で決められることです。
誰かに人生を委ねるのではなく、自分で選んだ道を歩む力を取り戻す。「貢献」よりも先に、自分の人生の主導権をしっかりと握ることこそが、社会を変える最初の一歩になるはずです。
若者ができる「行動」は、社会に馴染むことではなく変えること


少子高齢化のなか、社会の一員として若者ができる行動について見ていきましょう。
投票と政治参加
先述の通り、日本では若者の投票率が低い傾向にあります。自分1人の票では何も変わらないと思うのではなく、積極的に政治に参加していきましょう。
若者の利害を代弁してくれる政党や候補がないか、各政党の政策について調べてみるのもマストです。政治への参加が、より良い未来に繋がるという意識を持つことが大切です。
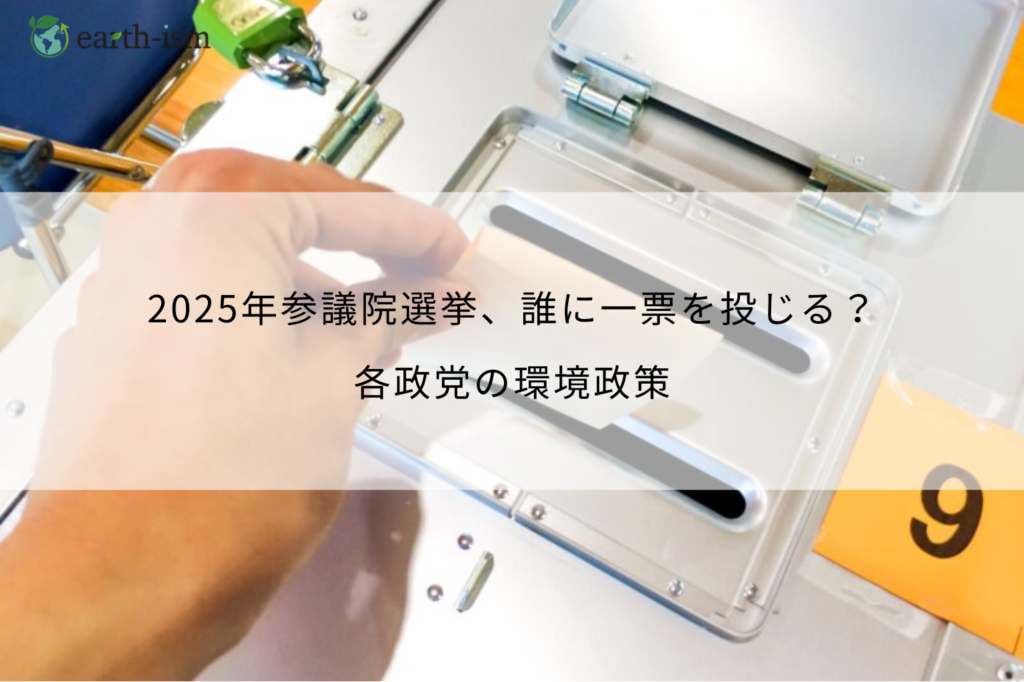
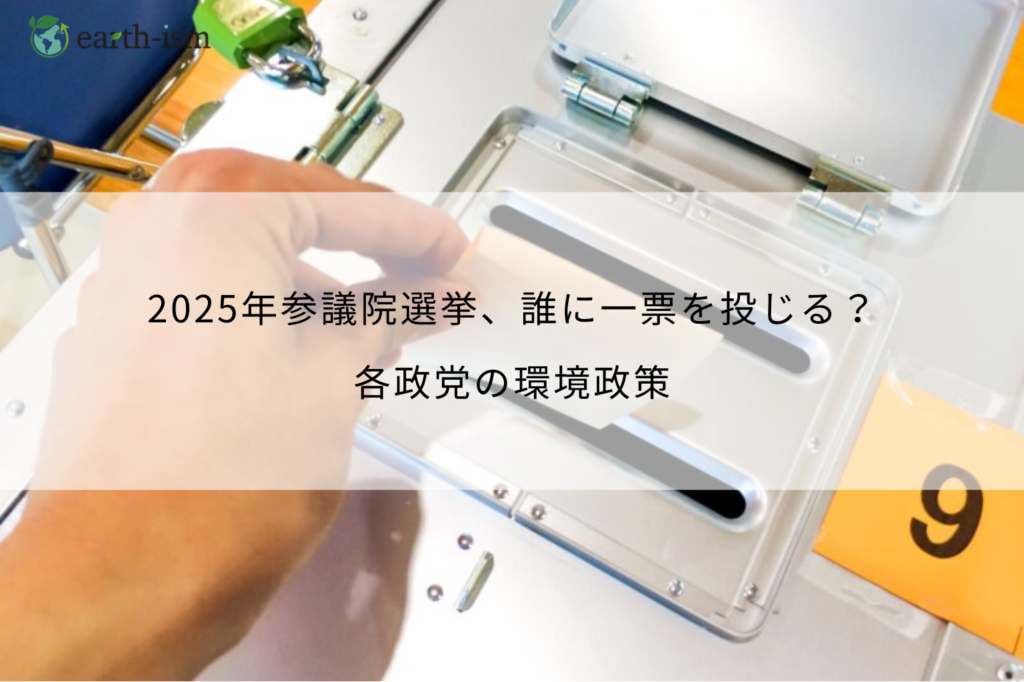
消費と労働の再定義
少子高齢化は、労働人口の減少や経済成長の鈍化を招きます。そのようななかで、働き手にとって仕事しやすい環境を作っていくことは重要なポイントになります。
長時間労働などのブラックな環境に異議を唱えることも、立派な社会変革の1つです。
「支え合い」は“命令”ではなく“選択”として成り立つ
ボランティアや地域活動についても、誰かに命令されてやるのではなく、自分の意思で選択することに意味があります。
高齢者支援に関しても「する」「しない」のどちらかではなく「どうすれば良いか?」という視点を持って多角的に考えてみましょう。
無力じゃない|構造を知れば「私にもできること」はある


若者は決して無力ではありません。より良い社会の実現のために「できること」を見つけ実践していきましょう。
SNS・発信・学び合いの力
少子高齢化は、他人事ではなく自分たちの問題です。現在は、SNSを活用すれば簡単に同世代と意見交換することができます。
新たな気づきを得ることで、自分1人の力では社会は変えられないという無力感から希望を見出せるかもしれません。互いに学び合い、分かち合うことで、より多様で自由な社会づくりを目指していきましょう。
小さな選択の集合体が、「社会の形」を変えていく
たとえ1つのアクションは小さいものでも、日々の選択が社会の形を変えていきます。エシカルブランドを選ぶこともその一例です。
環境や労働問題に配慮されたブランドの商品をチョイスすることは、持続可能な社会に向け良い影響を及ぼすでしょう。
また、少子高齢化において「子育てしやすい社会」の実現は重要なことですが、それと同時にさまざまなライフスタイルを認め合い「産まなくても尊重される社会」を目指していくことも大事なことです。


まとめ|正しさより、問いを持つことが若者の武器になる


私たちは生きていく以上、社会の仕組みや誰かの期待と無縁ではいられません。だからこそ、未来を誰かに委ねるのではなく、「自分で考える力」を絶やさずに磨いていくことが、若者にとっての何よりの武器になります。
社会のあり方に問いを投げかけ続ける姿勢は、正しさを一方的に信じるよりも、ずっと遠くまで私たちを運んでくれます。他人の声に縛られすぎることなく、自分の心の声を信じ、自分の足で選び取る道を歩んでいきましょう。