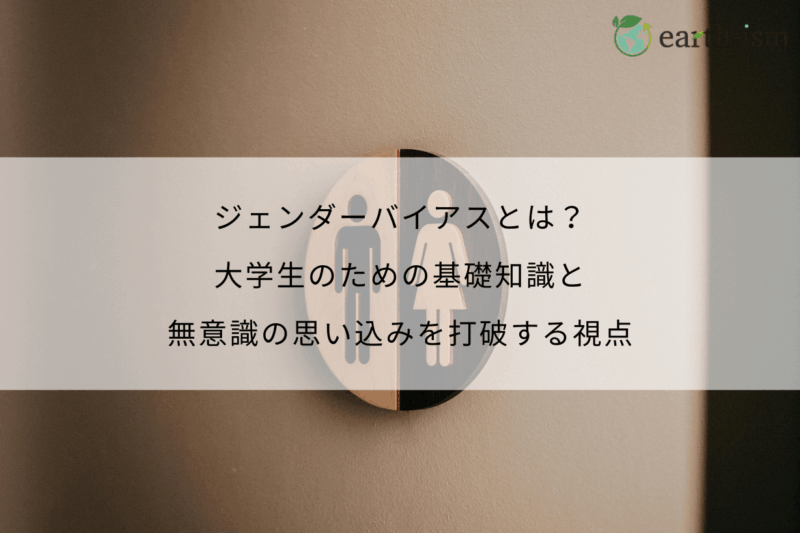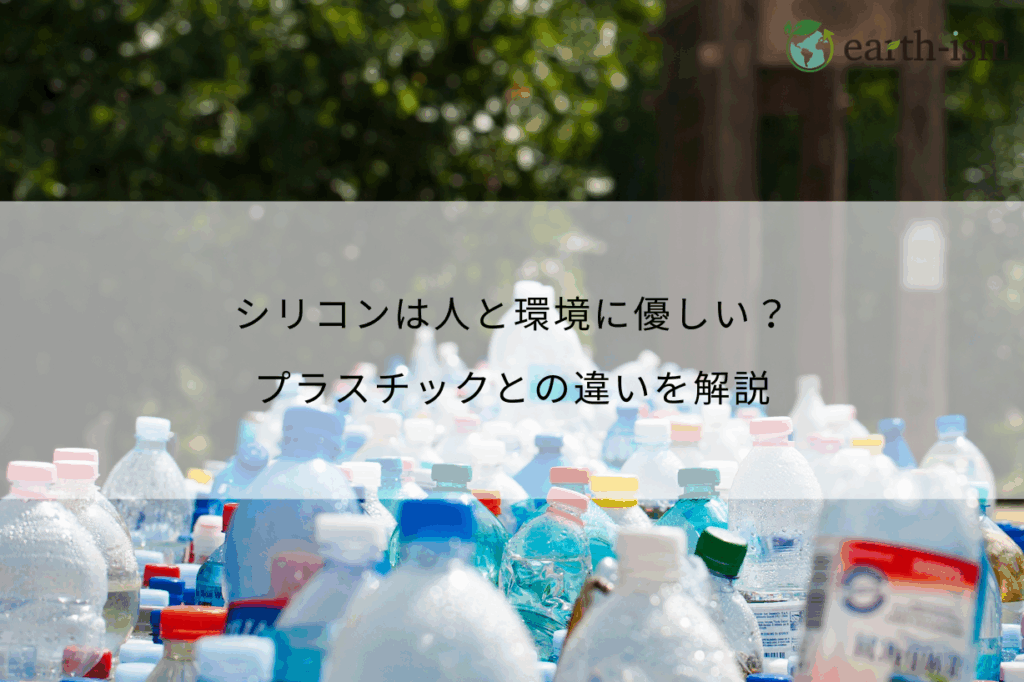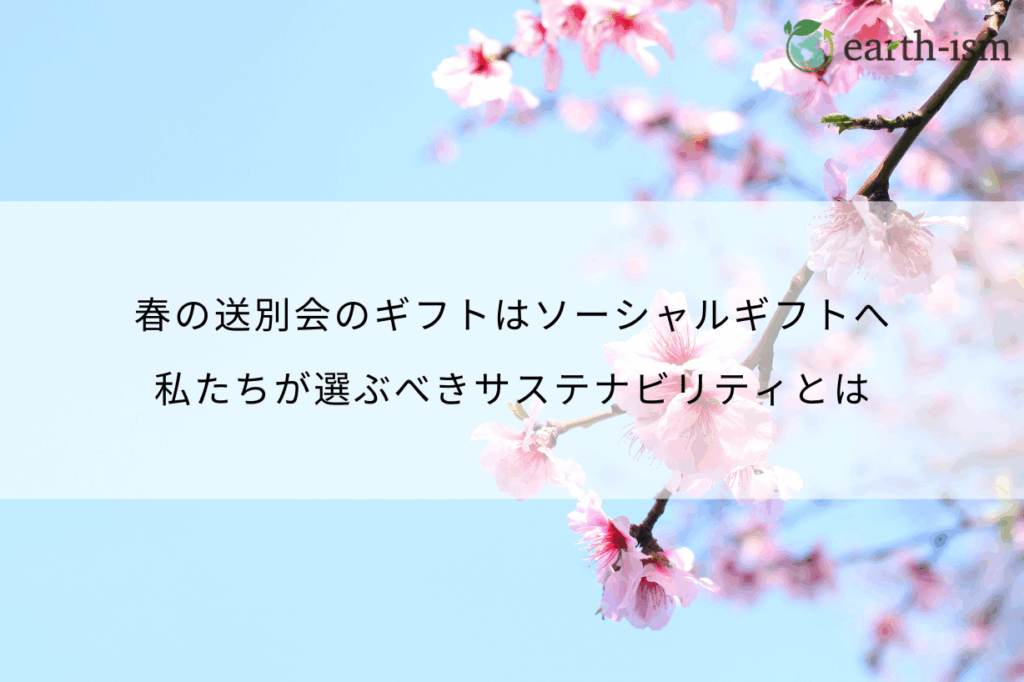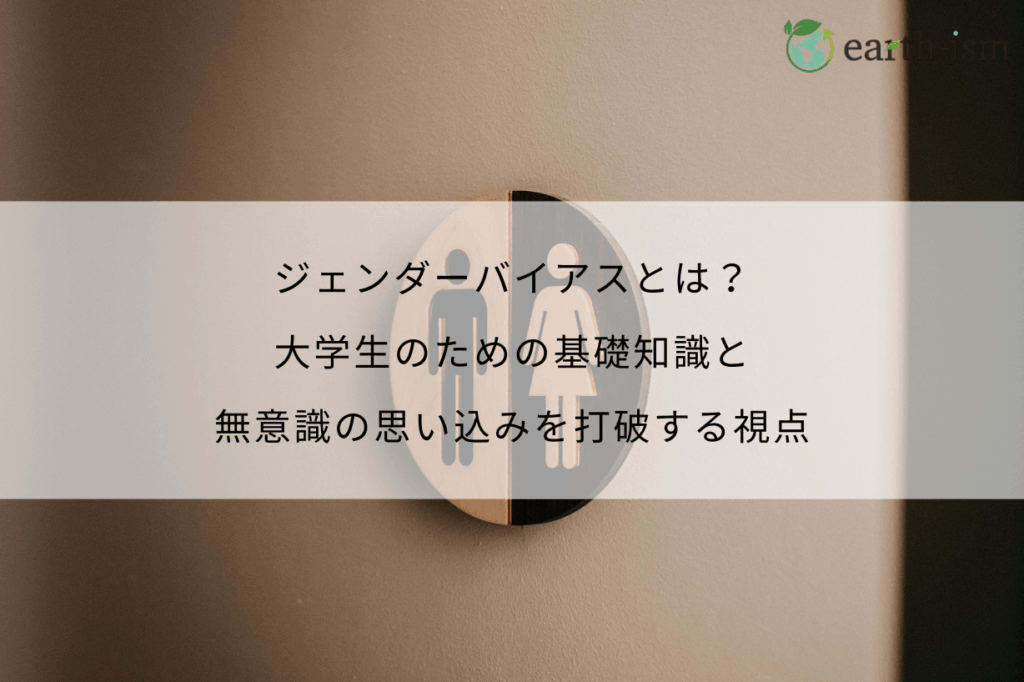ハラールフードとは?日本で配慮する必要性や課題を考えよう


Contents
訪日観光客の増加や外国人労働者の受け入れ拡大に伴い、日本国内でも宗教的配慮が求められる場面が増えています。一部の空港や宿泊施設では、礼拝スペース(Prayer Room)の設置や、メッカの方角を示す「キブラ」の案内が見られるようになりました。
特に最近では、ムスリム(イスラム教徒)の訪日観光客や在日ムスリムが増加していることから、イスラム教で食べることが許されている「ハラールフード」への関心も高まっています。これに伴いハラールフードを提供する飲食店や学校が増える一方、給食などではさまざまな課題が浮上しています。
本記事では日本国内におけるハラールフードに対する取り組みや、その必要性や課題について解説していきます。なぜ今、ハラールフードが注目されているのか、何が問題なのか、一緒に考えてみませんか。


増加する訪日ムスリムと、日本が抱える悩み


早稲田大学名誉教授・店田廣文教授が行った2024年の調査では、日本に住む外国人ムスリムの人口が約29万人と推計されており、2010年の約10万人と比べると約3倍に増加しています。また、日本政府観光局「日本の観光統計データ」によると、インドネシアやマレーシア、シンガポールといったムスリム人口の多い国からの訪日観光客も年々増えています。
一方、訪日ムスリムが抱える悩みには、「礼拝できる場所が見つからない」などのお祈りに関することのほかに、「食事を選ぶのが難しい」「安心して食事ができるレストランが見つからない」といった飲食に関することが挙げられています。
このような状況を踏まえ、日本ではムスリムにも安心して食事を食べてもらえるように、食事に配慮する企業や自治体が増えています。
ハラールフードとは


イスラム教では、日々の服装や食事といった生活に関わるすべてに戒律があります。
例えば、女性がスカーフのようなもので髪を覆っているのをよく見かけますが、それも戒律に由来している慣習です。食事では神によって許された食品や料理(ハラール)と、神によって禁じられたもの(ハラーム)に区別でき、ハラールな食品や料理はハラールフード、ハラール料理と呼ばれることもあります。
具体的には以下のように分けられます。
◇ハラールな食品の例
- 野菜
- 果物
- 穀物(米・小麦など)
- 豆類
- 魚介類
- 海草類
- 牛乳
- 卵
- イスラム法に則って処理がされた食肉
◇ハラームな食品の例
- 豚肉
- ゼラチンなどの豚由来の成分、豚が含まれた餌を食べた家畜類、豚に触れた食品もNG
- アルコール
- 手指消毒用のアルコールや、味噌や醤油などに含まれる自然醸造のアルコールもNGと考える人もいます
- 血液
- イスラム法に則って処理がされていない食肉
そのため、ムスリムが安心して食事を楽しむには、食材や調理方法において宗教的な配慮が求められます。特に、豚肉やアルコールを避けること、調理器具や食材がハラームな食品と混ざらないよう注意することが重要です。
日本国内におけるハラールフードの対応


このような状況を踏まえ、日本国内では以下のようなハラールフードへの対応がなされています。
認証制度
ムスリムが安心して食品を選べるよう、2012年にNPO法人日本ハラール協会が国内初の認証制度を開始しました。この制度では、製造や加工の過程を確認し、ハラーム(イスラムで禁じられているもの)が含まれていないかを検査しています。食品に限らず、化粧品や医薬品、屠畜場なども認証の対象です。
飲食店
ハラール対応の飲食店は東京や大阪などの都心部を中心に徐々に増えており、ムスリムやベジタリアン向けのレストラン検索サイト「Halal Gourmet Japan」には、2025年1月現在、700件以上の飲食店が掲載されています。また、近年ではレストランだけでなくハラール対応のベーカリー、スイーツショップなども話題になっています。
学校給食
2024年9月には茨城県の2つの町で、ムスリムの生徒が食べられるハラールフードの給食を初めて提供されました。いつもはお弁当を持参するムスリムの子ども達も、この日は他の生徒と同じ給食を味わえたそうです。
また、東京都にはハラールに対応した給食を提供している保育園もあります。2016年には上智大学でハラールフード専門の学食がオープンしました。
これらの対応により、ムスリムが安心して利用できる商品や食事が明確になり、日本でより快適に生活できるようになります。しかし、これらには「やりすぎではないか」といった声もあるのは事実です。
ハラールフードに対応する必要性と抱える課題


このようにハラールフードに対応する企業や学校、自治体が増えている理由のひとつとして、イスラム諸国の人口は増加しており、その市場は拡大していることが考えられます。ハラールフードに対応することはビジネス拡大につながる可能性があるからです。
また、ハラールフードに対応することでイスラム文化や宗教的背景への理解が深まり、多様な文化や宗教を持つ人々との共生がしやすくなると考えられています。その結果、観光業や地域の活性化にもつながるのではないかというのが自治体が考えていることと推察されます。
ハラールフード対応が抱える課題


一方で、ハラールフードに対応することによって、特に調理や製造の現場でさまざまな問題が発生しています。
調理設備の専用化、専用の調達が必要
ハラールフード対応には、専用の調理設備や食材の調達が必要です。豚肉やアルコールなどのハラーム食材に使用した食器や器具を共有することができません。
また、使用する肉はイスラム法に則った屠殺方法で処理されていることが求められるため、専用の業者から調達する必要があります。新たに調理設備や器具を整えたり、製造プロセスを見直したりする必要があり、人材や設備に関するコストが増加する可能性があります。
宗教への理解が必要
ハラールフードへの対応は、ヴィーガンやアレルギー対応とは異なり、「特定の食材を使わなければよい」という単純なものではありません。肉などは所定の手続きで処理する必要があり、通常の食事とは別に調理するとなれば、人的な手間がかかります。
なぜ日本でムスリムの食事に対応しないといけないのかという不満も上がりやすくなります。また、調理者や製造に関わる人がハラールの概念やムスリム文化について十分に理解していないと、間違ったハラール料理を提供し社会問題につながってしまう可能性もあります。
このように、ハラールフードに対応するには現場で多くの課題が残されています。宗教や異文化を理解することは、簡単そうに見えますが、実際には多くの努力と配慮が必要です。多様性とは何か、共生とは何か、今後も社会全体で考えていくべき重要なテーマです。
まとめ
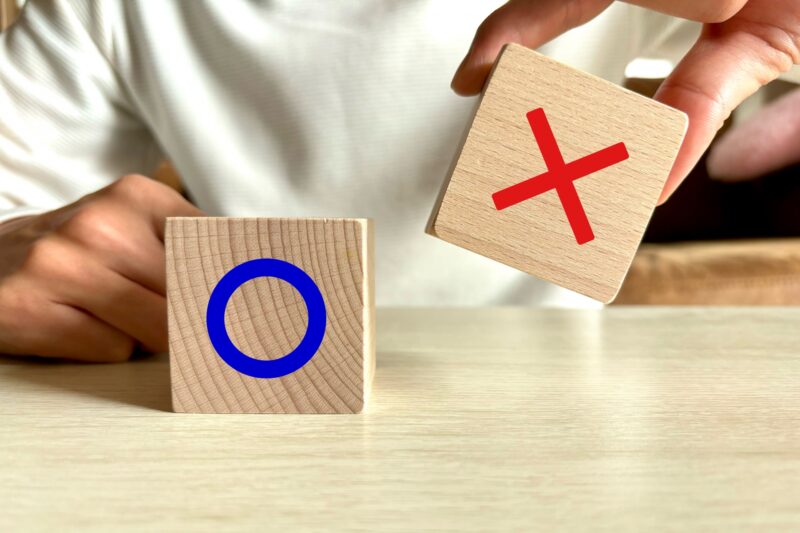
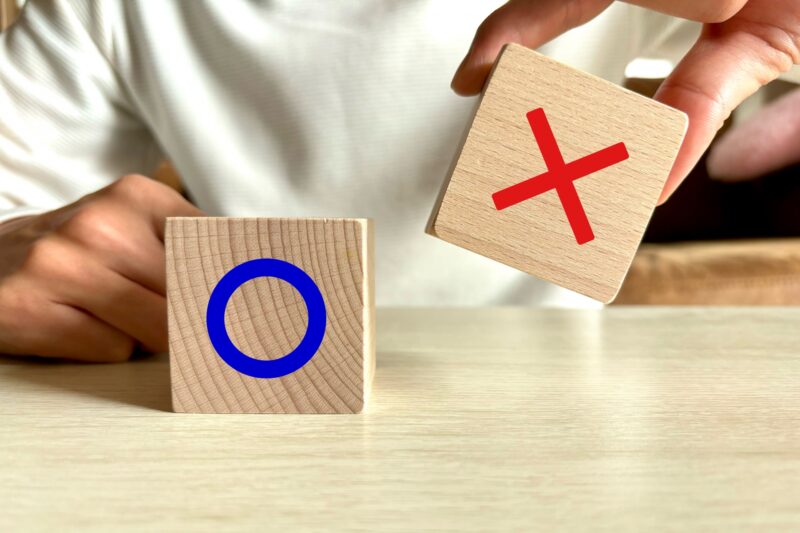
今回は日本国内でのハラールフードへの対応の現状と、その課題について解説しました。特に給食などの公共施設における食事提供の現場では、ハラールフードをどのように受け入れ、どの程度まで対応すべきなのか、多くの模索が続いています。
異文化理解には単なる配慮だけではなく、共に考え、行動を伴うことが求められます。あなたもこの機会に、一緒に考えてみませんか?