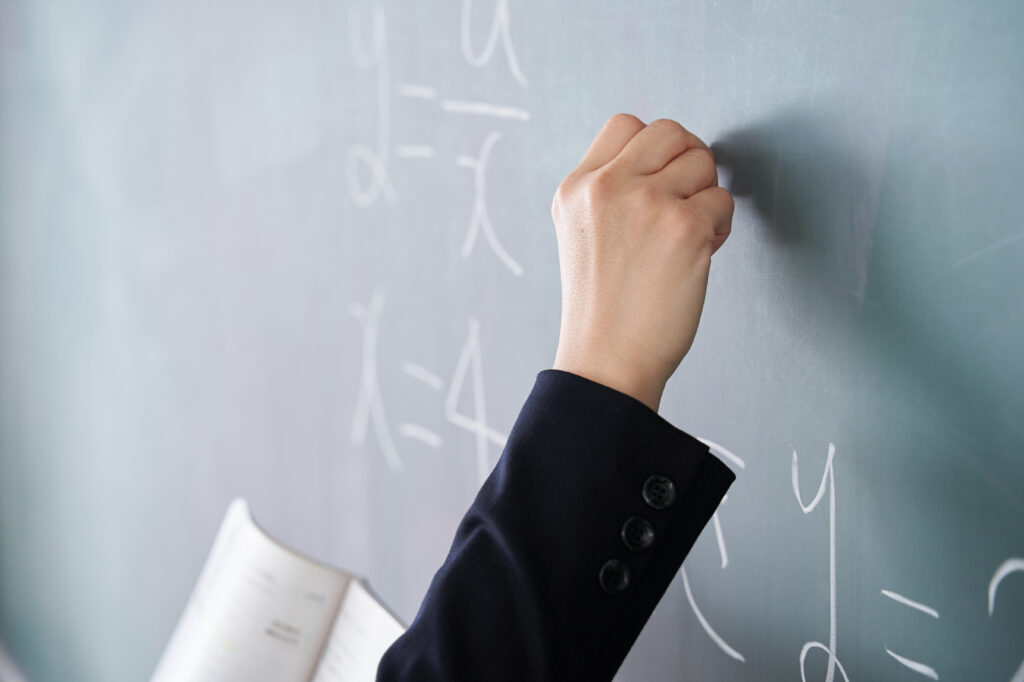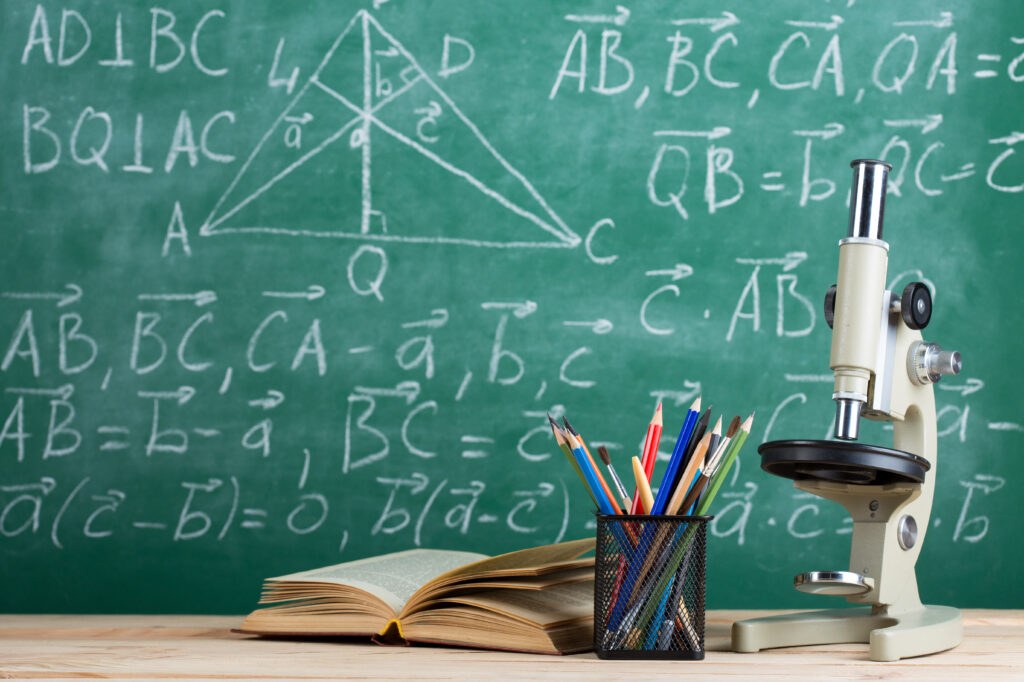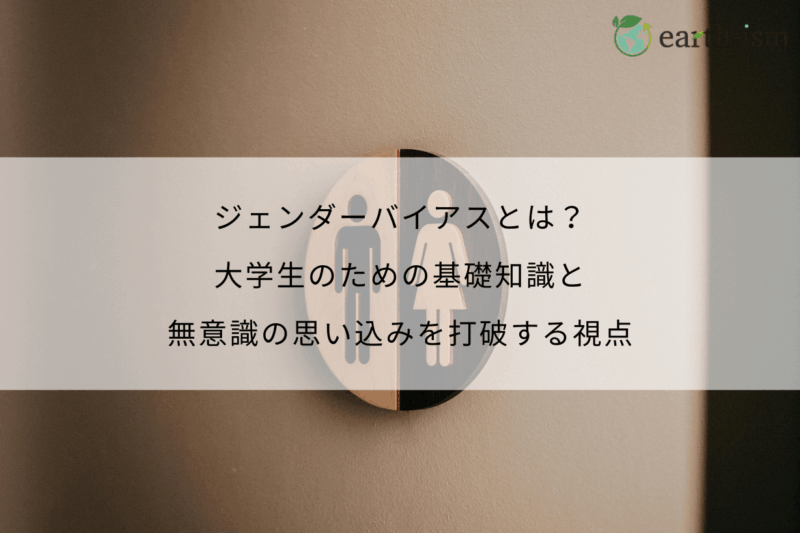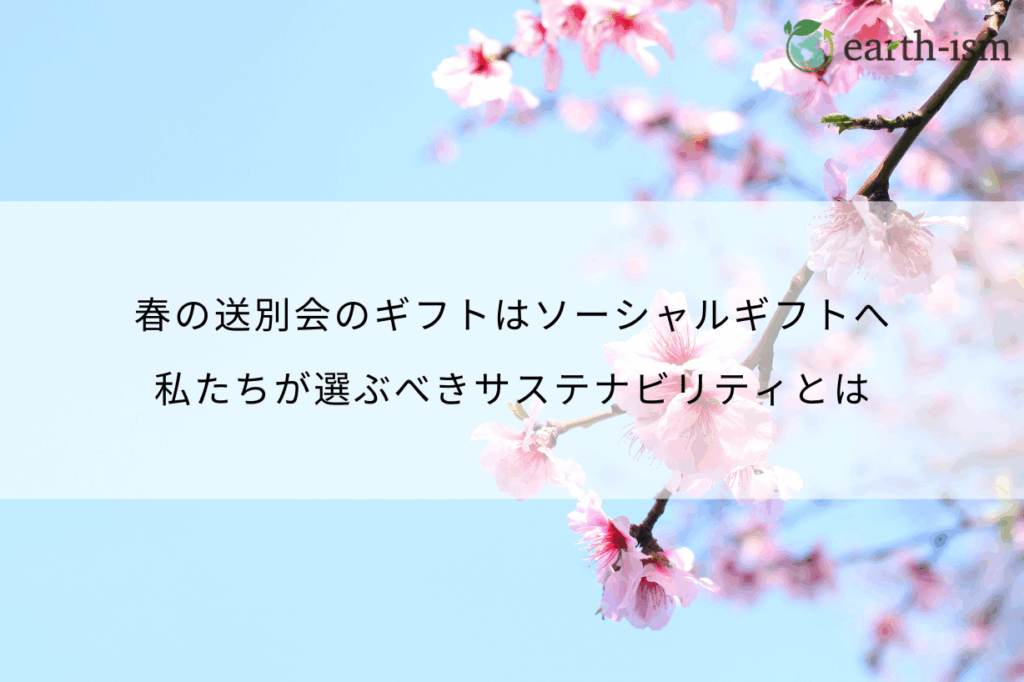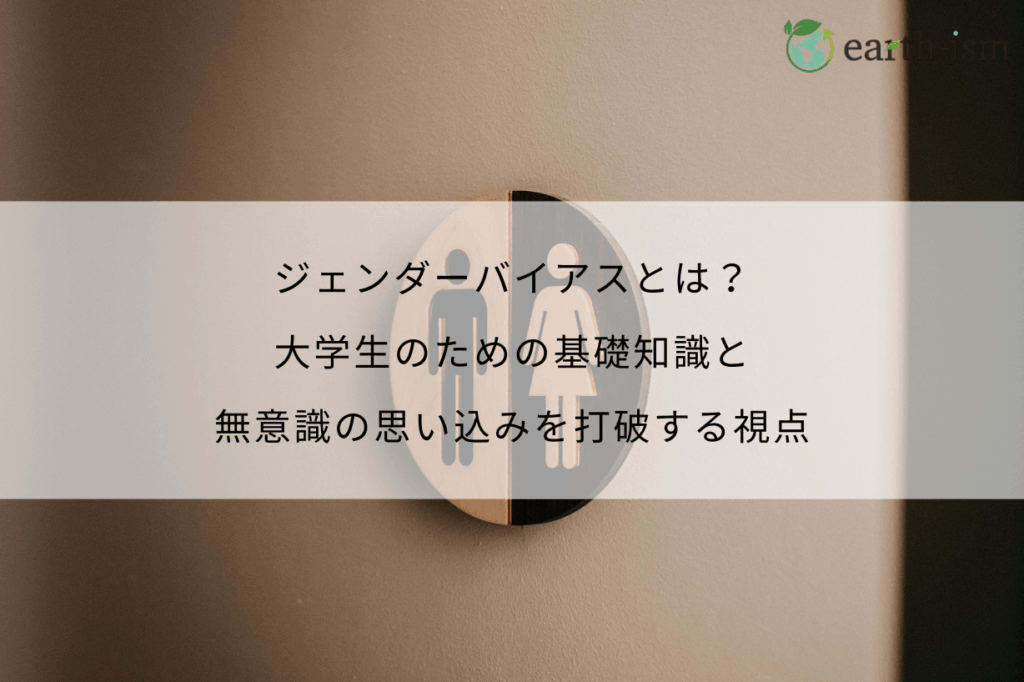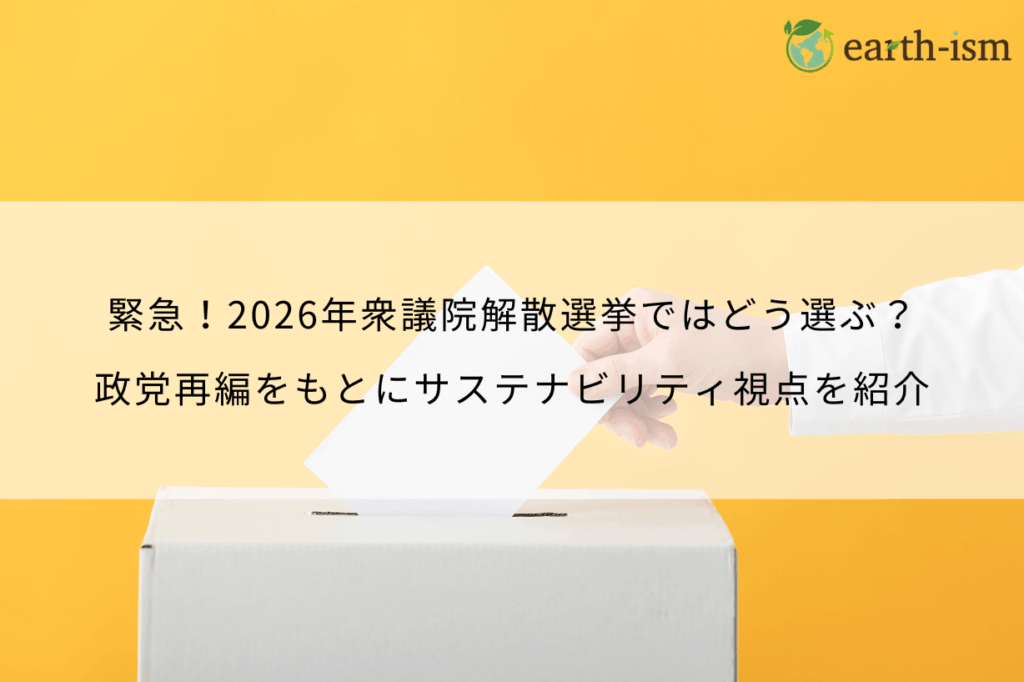給特法の改正とは?変わる教員の働き方と、私たちにできること
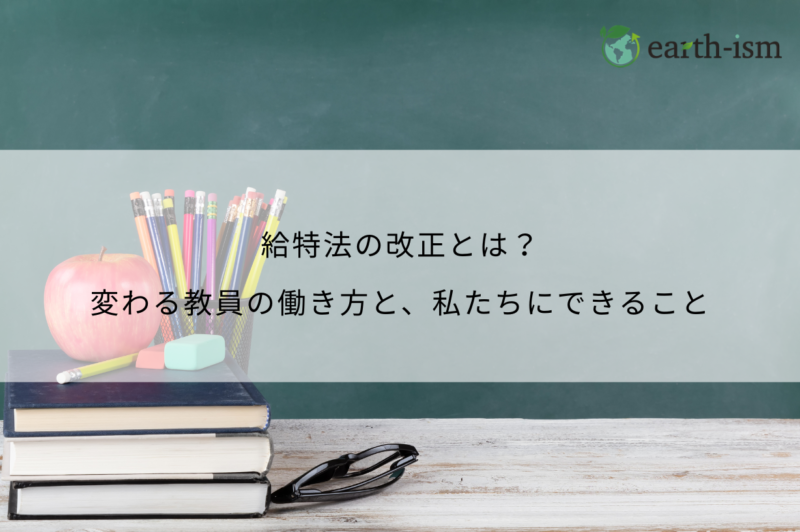
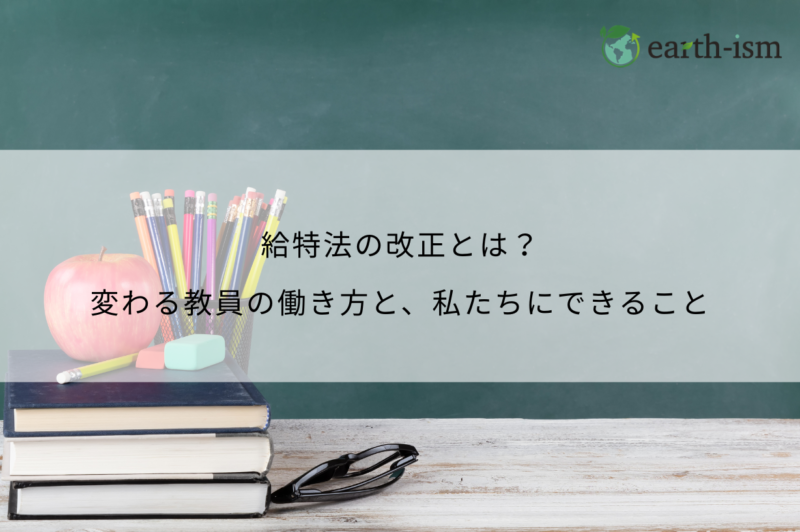
Contents
運動会の翌日も、日曜日の部活動のあとも、先生たちは変わらず教室に立ち続けています。「先生っていつ休んでるの?」という素朴な疑問の裏には、長年見過ごされてきた“教員の働き方問題”があります。
その根底にあるのが、「給特法(きゅうとくほう)」と呼ばれる法律。教員に残業代を支払わない仕組みを定めたこの法律が、50年ぶりに見直されようとしています。教職という尊い仕事が、過重労働によって支えられてはいないか。
この記事では、給特法の基本から、今後の改正動向、そして私たちにできるアクションまでをやさしく解説していきます。
給特法とは?簡単にわかる基礎知識
はじめに、給特法の正式名称とその内容について見ていきましょう。
正式名称と内容
給特法とは「公立学校の教職員の給与等に関する特別措置法」の略称です。
1971年に制定されたこの法律は、教員の勤務実態にあわせた特例的な給与制度を定めています。
特徴的なのは、時間外勤務手当(いわゆる残業代)を支払わずに、代わりに「教職調整額」として月給の4%を一律で支給するという仕組みです。
これは、教員の勤務が時間で計測しにくいという特性を理由に、残業の実態にかかわらず固定額で手当を支給する制度です。
なぜ制定されたのか?当時の背景
制定当時の背景には、教員の業務が多岐にわたり、労働時間の管理が難しいという課題がありました。
授業に加えて学級運営、部活動、保護者対応と、教員の仕事は多岐にわたります。そのすべてを労働時間としてカウントすることは困難だとされ、4%の手当で包括的に処理する仕組みが採られたのです。しかし、当時と比べて現代の学校現場は大きく様変わりしています。
給特法の問題点とは?いま改正が求められる理由
現在、給特法には複数の問題点が指摘されています。なぜいま、この法律が見直されようとしているのか。その背景をひもときます。
現実の業務量に見合っていない「4%」
文部科学省の2022年の調査によれば、中学校教員の約6割が週60時間以上働いているというデータがあります。
この数字は、過労死ラインとされる月80時間の残業に相当する労働時間に匹敵します。にもかかわらず、手当は月給のわずか4%。実態とかけ離れた給与体系が、教員のモチベーション低下や離職の一因になっているのです。
また、同調査によれば、小学校教員でも約4割が過労死ラインに相当する長時間勤務を強いられており、若手教員の離職率の高さも大きな課題となっています。
部活動や事務作業、保護者対応が重荷に
教員の仕事は授業だけではありません。部活動の顧問としての指導、各種報告書の作成、保護者からの電話・メール対応など、日々の業務は膨大です。
こうした「見えにくい仕事」に対して、正当な対価や時間管理がなされていない点が、現場の不満を生んでいます。
さらに、教員不足の影響で一人あたりの業務量が増加しており、精神的な負担も深刻です。日本教職員組合の2023年の調査によれば、約7割の教員が「メンタルヘルスに不安を抱えている」と回答しています。
そもそも、なぜ“教員の働き方改革”が注目されているのか
少子化や教員不足、長時間労働など、教育現場を取り巻く課題が深刻化する中、「教員の働き方改革」は国や地方自治体、メディアでも大きな関心を集めています。
とくに文部科学省が実施した勤務実態調査(2022年)によれば、教員の多くが過労死ラインを超える長時間労働に苦しんでおり、若手を中心に離職率が高まっている現状が浮き彫りとなっています。こうした背景から、教員の労働環境を法制度の面から見直す機運が高まっているのです。


改正案のポイントと進捗状況
給特法を見直す動きは、徐々に具体化しています。2023年から2024年にかけての議論の経過と、今後の見通しについて見ていきましょう。
2023年〜2024年の動き
2024年3月、中央教育審議会は給特法の改正を正式に提言しました。その主な内容は以下の通りです。
-
- 教職調整額の引き上げまたは変動制の導入
- 残業時間の上限規制(上限45時間など)
- 部活動指導員など外部人材の積極的な活用
これらの提言を受けて、文部科学省は2025年度中の法改正を目指して具体的な検討に入っています。
また、政府はこれに関連して、地方自治体への財政支援やガイドラインの整備も進める方針です。実際の法改正と同時に、現場の運用体制の整備が求められています。
現場からの声「本当に変わるのか?」
とはいえ、現場の教員からは懐疑的な声も聞かれます。「制度が変わっても、結局はサービス残業が残るのでは」という不安や、「自治体ごとの対応で格差が広がるのでは」といった懸念が上がっているのです。
NHKの特集(2023年11月放送)によれば、「制度が変わるだけでは、現場の働き方までは変わらない」という声が多く寄せられたといいます。制度だけでなく、学校文化や保護者の意識も含めた広範な改革が必要とされています。
給特法が支えてきた“教職の常識”
「教職は聖職であり、金銭的報酬よりも使命感が大切」という価値観が、長く教育現場に根づいてきました。給特法は、そうした時代の中で「時間外勤務を管理するより、一定の手当で包括的に評価しよう」という考え方のもと成立した制度です。
この“特別な扱い”が、制度的に教員を過酷な働き方へと追い込む構造にもつながってきたという側面があります。
他国と比べてどうなの?海外の教員労働の仕組み
日本の教員の労働時間は、国際的にも突出しています。他国と比較することで、いまの課題がより明確になります。
フィンランド:週20時間の授業+準備時間
フィンランドでは、教員の授業時間は週平均20時間程度に抑えられ、その分、授業準備や個別対応のための時間がしっかり確保されています。
また、校務の多くは事務職員が担い、教員は「教える」ことに専念できる体制が整っています。
OECDの調査(2021年)によれば、フィンランドの教員の自己裁量権の高さと業務の明確な分担が、仕事満足度の高さにもつながっているといいます。
イギリス:労働組合による残業拒否も可能
イギリスでは教員の労働環境を守るため、労働組合が強く機能しており、過剰な残業を拒否する権利が保障されています。
また、教育政策への市民参加も活発で、働き方を社会全体で議論する文化があります。
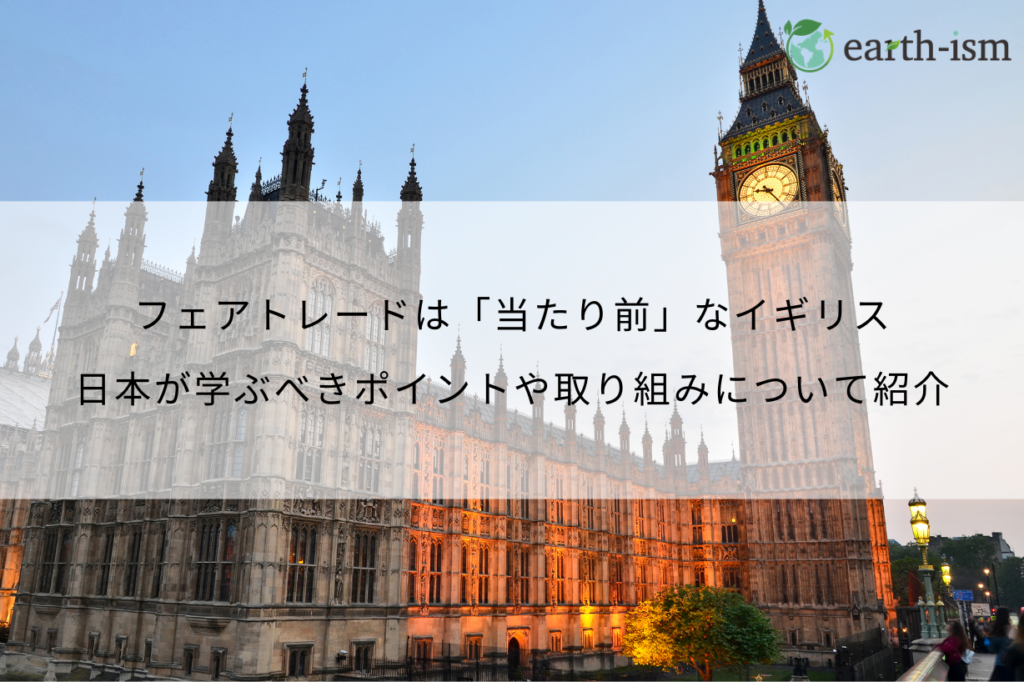
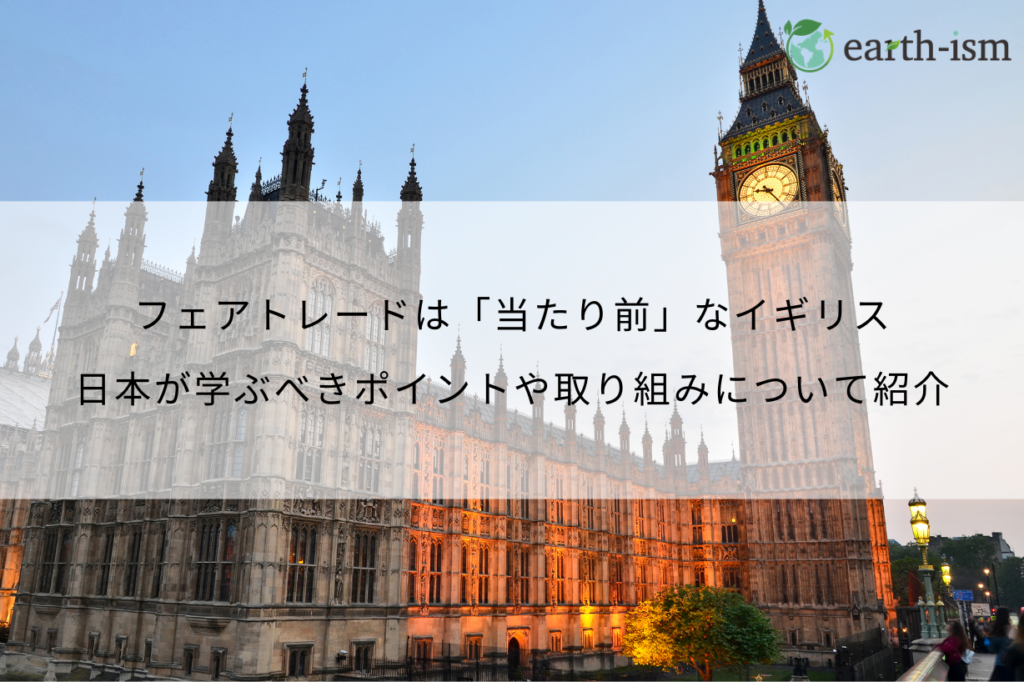
理想と現実のあいだにある壁
ここまで、給特法の問題点や改正案、そして海外の事例などを見てきました。しかし、どれほど制度が整っても、現場でそれが機能するとは限らないのが現実です。
実際に、学校という組織は保守的な性質を持ち、改革がトップダウンで進みにくい構造になっています。また、現場の教員は日々の業務に追われ、制度の変化を十分に理解し、活用する余裕すらないことも少なくありません。
さらに、部活動の外部化や事務作業のアウトソーシングといった改革案も、財源や人材確保の問題でスムーズに導入できないケースが続出しています。地方の小規模校では、そもそも外部人材を呼ぶための予算も確保されていない場合が多く、都市部との格差が拡大する可能性も指摘されています。
一方で、教員側の意識改革もまた課題です。長年にわたって「自己犠牲」や「奉仕」が美徳とされてきた現場において、自らの働き方を見直すことに罪悪感を抱く教員もいます。これは制度だけでは変えられない、教育文化そのものの問題といえるかもしれません。
こうした現実の中で、私たちに何ができるのか。それを考えることが、制度改革と同じくらい大切な視点となるでしょう。
私たちにできること:教員の働き方改革を支える行動
法律が改正されても、それだけでは現場のすべてが変わるわけではありません。だからこそ、私たち一人ひとりが「できること」を考え、行動することが求められています。
教員の働き方改革は、社会全体の協力によってこそ進むものです。以下に、家庭・地域・社会の立場から今すぐ取り組めるアクションを提案します。
家庭・保護者として
まず、家庭や保護者の立場からできることとして、学校からの連絡に対して即時の返信を求めるのではなく、ある程度の余裕を持って対応する姿勢が大切です。また、教員に対して感謝の言葉をかけることは、日々の業務の励みとなります。
そして、子どもに「先生も一人の人間なのだ」という視点を伝えることで、思いやりの心を育むことにもつながります。
地域・社会人として
次に、地域社会の一員として、部活動の外部指導者として関わる、学校行事や地域清掃などにボランティアで参加するなど、教員の業務を一部引き受ける形での支援が可能です。
また、教育政策や制度に関心を持ち、選挙などを通じて自分の意思を示すことも、間接的に教育環境の改善に貢献する行動です。
SNS時代の市民アクション
さらに、SNSやメディアにおける行動も重要です。教員の実態や現場の声を正しく伝えるアカウントをフォロー・シェアすることで、情報の可視化に貢献できます。
また、風評や一方的な批判に流されず、冷静に事実を見つめる姿勢を持つこと。
そして、教職を「奉仕の精神」に頼るのではなく、「専門職」としての対価と尊厳を認める価値観を社会に広げていくことが求められています。
まとめ:先生たちが笑顔で教壇に立てる未来へ
教職は、「やりがいがあるから」といった精神論だけで乗り越えられる仕事ではありません。毎日、子どもたちの命と未来に向き合い続けるその責任の重さに、正当な待遇と支援が伴ってこそ、真の意味での“誇りある仕事”となるのです。
給特法の改正は、単なる法律の見直しにとどまらず、「教育とは誰が担い、どう支えるべきか」という社会全体への問いかけでもあります。
現場にはまだ多くの課題が残されており、理想と現実のあいだには深い溝があるかもしれません。それでも、私たち一人ひとりが“できること”を重ねていくこと。それが、先生たちが安心して子どもと向き合える環境をつくり、教育の未来を守るための確かな一歩になるのではないでしょうか。
まずは、今日から。先生たちが笑顔で教壇に立てる社会を目指して、私たちもまた行動をはじめましょう。