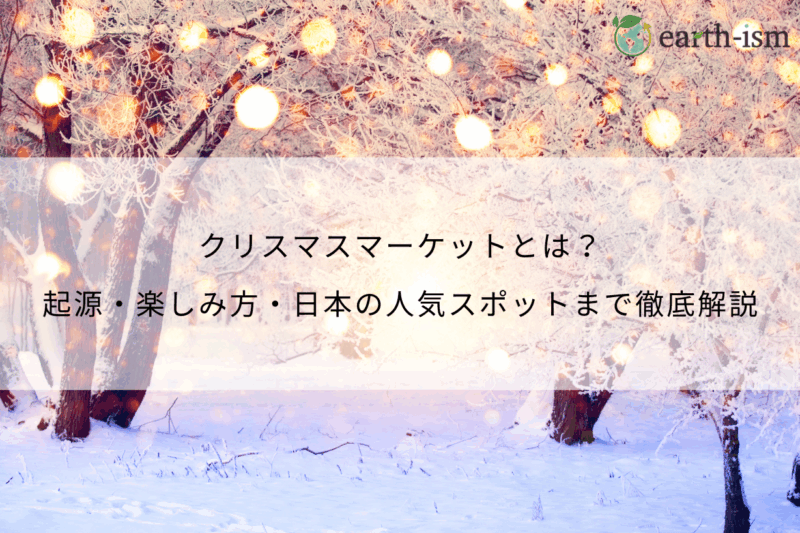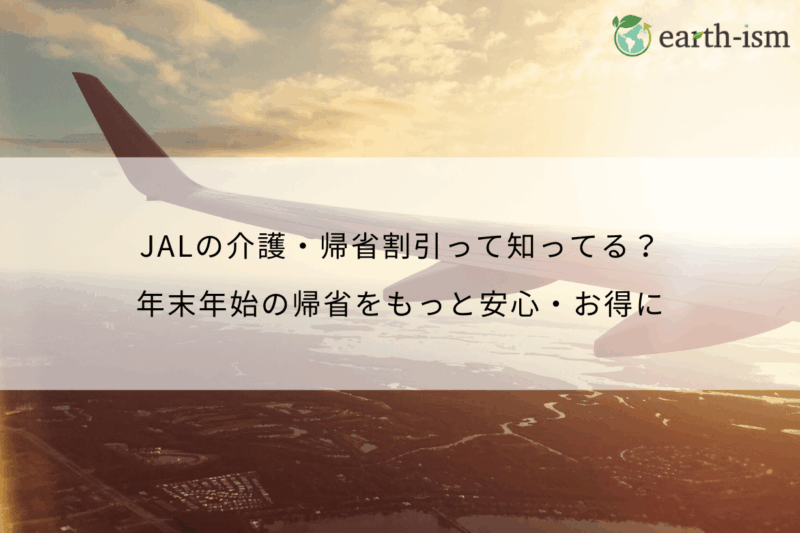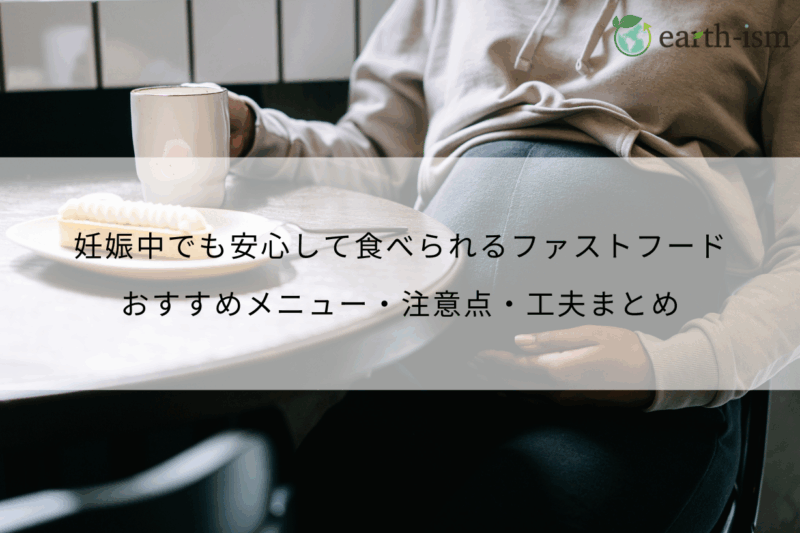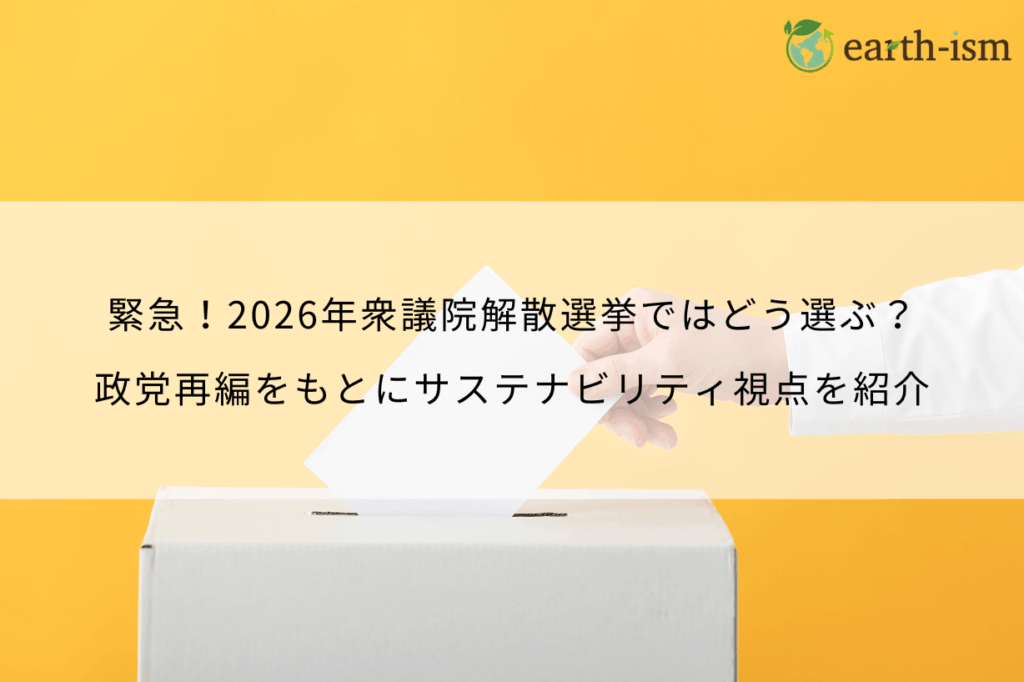ランドセルの修理はどうすればいい?自分でできるか、費用や保証書の有無などを解説


Contents
小学校に入学してから長期間使う「ランドセル」は頑丈で耐久性が高いものですが、万が一壊れたり不具合が起こったりした場合、修理はどうすればよいのか迷う方もいるでしょう。
実は、ランドセルは基本メーカーが無償で修理で対応してくれることが多いですが、状況によっては有償での対応になることもあります。
この記事では、ランドセルの修理はどうすればよいのかを詳しく解説します。
自分で修理はできるのかや、修理に出す場合の費用など、ランドセル修理に関する気になる情報をまとめましたので、ぜひ最後までお読みください。
ランドセルの修理が必要になる主なケース


ランドセルの修理が必要なケースにはどういったものがあるのでしょうか。まずは、ランドセルの修理が必要になる主なケースを紹介します。
1. 肩ベルトの破損
ランドセルの肩ベルト(ショルダーベルト)は、日々の使用で、特に負荷がかかる部分です。
そのため、以下のようなトラブルが発生しやすくなります。
- 肩ベルトの付け根が切れた
- 調整金具が壊れた
- 肩ベルトがちぎれそうになっている
肩ベルトは、付け根が切れるケースが多いです。また、肩ベルトの穴に亀裂が入ると、そこから次第にちぎれてしまうこともあります。調整器具が壊れてしまうことも珍しくありません。
肩ベルトが切れてしまうとランドセルを使用することができないため、何か問題が発生したら早めに修理に出すことをおすすめします。
2. 金具の不具合
ランドセルにはさまざまな金具が使われていますが、経年劣化や強い衝撃で破損するなど、ランドセルの金具に不具合が生じて、修理が必要になるケースがあります。
よくあるランドセル金具の不具合には、以下のようなものがあります。
- 錠前(かぶせ部分の留め具)が壊れた
- 肩ベルトのナスカン(金属フック)が折れた
- サイドポケットのファスナーが壊れた
特に錠前が壊れて留め具が閉まらなくなると、かぶせが揺れて周囲の人に当たる危険があります。安全のためにも、早めに修理しましょう。
最近では、錠前が自動ロックのものも多くありますが、手動タイプのものよりも壊れやすいため、定期的に状況を確認しておくと安心です。
3. 縫い目のほつれ・裂け
本革や人工皮革のランドセルでも、使い続けるうちに縫い目がほつれたり、表面の皮が裂けたりすることがあります。この場合も、必要であれば修理に出すとよいでしょう。
ほつれが小さい場合であれば、状況によっては手縫いで修繕できる可能性もあります。
また、かわいい刺繍が施されているタイプであれば、刺繍を何かにひっかけてほつれてしまうこともあるかもしれません。刺繍がほつれてしまった場合は、無理にひっぱらずハサミで切ることをおすすめします。
4. 底板や内部の劣化
ランドセルの底部分にある底板や内部が劣化で破損などしてしまった場合も、修理に出すケースがあります。
ただし、底板は外れても問題ありません。一般的なランドセルでは、底板はもともと外れるように作られているからです。
また、底板は必ず必要なものではありませんが、内部の破損を守ってくれる役割があるため、あると安心です。
自分で修理できる?DIYで直せるケース


ランドセルは、簡単な修理であれば、自分でできる可能性もあります。ここでは、DIYで直せるケースについて紹介します。
1. 縫い目のほつれ
ランドセルの縫い目がほつれてしまった場合、ほつれが小さければ、強度の高いナイロン糸を使って手縫いで補修することができます。
さらに、補強のために布用ボンドを併用すると、より丈夫に仕上がります。
2. ファスナーの不具合
ファスナーの引き手の部分「スライダー」が動きにくい場合は、ロウソクや鉛筆の芯(グラファイト)をこすりつけると滑りがよくなることがあります。
しかし、ファスナーが完全に壊れてしまった場合は、自分で交換するのは難しいため、修理店に依頼するのが無難です。
3. かぶせ(フタ)のゆるみ
ランドセルのフタ部分が浮いてきた場合、マジックテープを使って補強する方法もあります。
ただし、見た目が変わるため、気になる場合はメーカー修理を検討してください。
メーカー修理は可能?保証書がある場合とない場合


ランドセルは、ランドセル工房や製造元のメーカーに連絡すると、保証期間内であれば無料で修理が受けられることが多いです。
ただし、修理の対応範囲はメーカーによって異なり、保証書の有無によっても条件が変わるため注意が必要です。
保証書あり:無料修理の対象
保証書がある場合は、一般的に以下の内容は、無料での修理対象となります。
- 縫い目のほつれ
- 肩ベルトの付け根部分の破損
- 金具の不具合(ただし、故意の破損や過度な衝撃が原因の場合は有償)
日常で通常に使用していて破損してしまった部分に関しては、基本的に無料で修理してもらえることが多いです。
保証を利用する際の注意点
ランドセルの修理を保証で依頼する際は、修理に時間がかかる点に注意が必要です。
修理期間中は代わりのかばんが必要になるため、メーカーや工房に代替用のランドセルの貸し出しサービスがあるかどうかを事前に確認しておくと安心です。
また、通常のかばんで通学することも可能ですが、お子さんによっては抵抗を感じることもあります。そのため、修理に出すタイミングを考慮するとよいでしょう。
さらに、修理時の往復送料負担や、破損理由を不問で修理してくれるかどうかなど、対応内容は工房やメーカーによって異なります。保証を利用する前に、購入したランドセルの保証内容はしっかり確認しておきましょう。
有償修理になる場合
保証書がある場合でも、有償修理になるケースもあります。有償修理になるケースには、以下の内容が多いです。
- 破損が使用者の過失によるもの
- 自然劣化(経年劣化)による修理
- 保証期間を過ぎた修理
故意に壊した場合や、いたずら書きなどで汚した場合は、保証書があっても有償での修理となる可能性が高いです。
有償での修理を避けるためにも、ランドセルの扱い方を子どもたちにしっかり伝えておきましょう。
保証書がない場合の修理
保証書がない場合でも、購入履歴や製造番号から、無償で修理してくれることがあります。
もちろん対応は工房やメーカーによりますが、保証書がないからといってすぐにあきらめる必要はありません。
購入した工房やメーカーに、一度問い合わせてみてください。
ランドセル修理の費用相場
ランドセルは、基本的には無償で修理してもらえますが、有償での修理となった場合どれくらい費用がかかるのか気になる方もいるのではないでしょうか。
ランドセル修理の費用は、一般的に10,000円以内が目安となることが多いです。
もちろん破損個所や内容によっても費用は異なるため、有償で修理に出す場合は、事前に修理先の費用表の確認をしておきましょう。
ランドセル修理の依頼先


ランドセルの修理先は、購入した工房やメーカー以外にも依頼することも可能です。ここでは、ランドセルの修理の依頼先を紹介します。
1. 購入したメーカー
ランドセルの修理は、購入した工房やメーカーに修理に出すことが一般的です。
保証期間内であれば、無料で修理できることが多いので、まずは購入先に問い合わせてみましょう。
2. 修理専門店
ランドセルやかばん修理専門店も、修理先のひとつです。
専門店はかばんの修理に特化しているため、メーカーでは対応してもらえなかった修理も可能な場合もあります。
また、「肩ベルトを短くしたい」「金具を交換したい」など、使い勝手を良くするためのカスタマイズにも対応してくれることがあります。
3. 地元の靴・カバン修理店
地元の靴・カバン修理店でも、ランドセルの修理を受け付けている場合があります。
近くの店舗であれば、直接持ち込んで状態を見てもらいながら相談できるため、手軽に依頼できるのがメリットです。
修理を避けるためのランドセルの扱い方


修理を避けるためには、日常でのランドセルの扱い方も大切です。ランドセルの扱い方のポイントをまとめたので、ぜひ参考にしてください。
1. 重すぎる荷物を入れない
ランドセルは丈夫に作られていますが、過度に重い荷物を入れると、ベルトや金具が傷む原因になります。
必要のない荷物はできるだけ減らし、日頃からランドセルに負担をかけすぎないようにしましょう。
2. 直射日光や湿気を避ける
ランドセルを保管する際には、直射日光が当たらず、できるだけ風通しのよい場所で保管することが大切です。
これは、ランドセルの革部分が紫外線によって劣化しやすく、色落ちの原因になるためです。さらに、革製品は湿気にも弱いため、適切な保管環境を整えることが重要です。
また、きれいな状態を保つためには、定期的に柔らかい布で拭くとよいでしょう。
3. 雑に扱わない
ランドセルを修理に出さないためには、子どもにランドセルの正しい扱い方を教えることも重要なことです。
乱暴に扱うことは、金具が曲がったり、生地が破れたりする原因になります。
日頃から丁寧に扱い、大切に使うことで、きれいな状態を保ちやすくなるでしょう。
まとめ


ランドセルは丈夫に作られていますが、修理が必要になることもあります。もし修理が必要になった場合は、工房やメーカーに問い合わせると無償修理の対象となることが多いため、一度確認してみてください。
また、日頃から大切に扱うことで、6年間きれいな状態を保つことができます。長いこと使うものだからこそ、大切に扱っていきましょう。