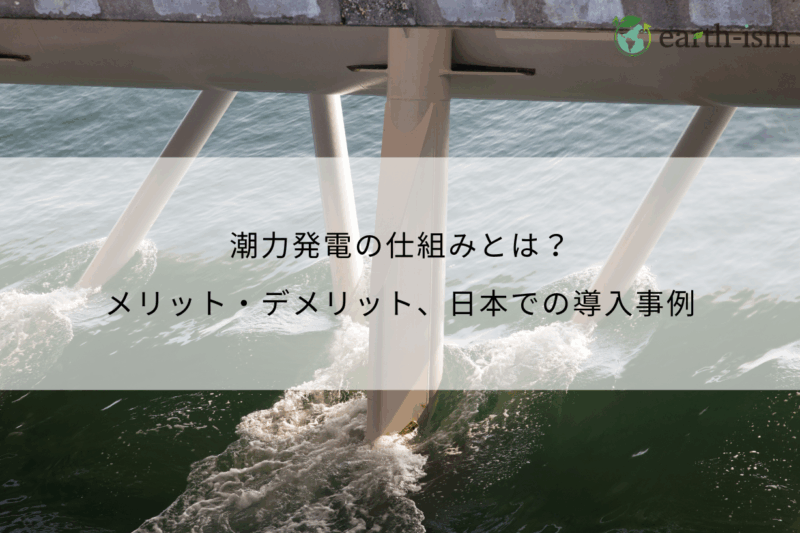見せかけのエコ「グリーンウォッシュ」に注意!事例や問題点を正しく理解しよう


Contents
近年、SDGsや環境問題、社会問題への関心が高まり、環境問題について考え行動する企業が増えてきました。
企業が環境問題について取り組むことで、個人が取り組むよりも大きな効果が期待できますが、消費者として気を付けておきたいのが「グリーンウォッシュ」です。
環境に配慮することが当たり前になりつつある今だからこそグリーンウォッシュとは何か、私たちが気を付けることはどんなことか、詳しく解説します。
グリーンウォッシュとは


グリーンウォッシュとは、企業などが実際はそれほど環境に対する取り組みを行なっていないのに、ブランドイメージを良くするために過度にアピールしたり、嘘をついたりする企業活動のことを指します。
「ごまかす」「上辺を取り繕う」といった意味を持つwhitewash(ホワイトウォッシュ)と、エコや環境を意味するgreen(グリーン)を組み合わせた造語です。
企業がグリーンウォッシュをする理由
近年、企業が社会的責任を果たすべきという考えが強く広まり、企業は環境に配慮した商品やサービスを提供することが今まで以上に求められるようになりました。
同時に消費者は何が環境に良いか悪いか知らないまま環境に良いと表記された商品を買うようになり、一部の企業は「環境に良い」「天然」などの言葉を科学的根拠がないのに使うようになりました。
グリーンウォッシュの問題点
では、グリーンウォッシュの何がいけないのでしょうか。
① 消費者の信頼を裏切り、業界の評判が下がる
消費者は地球に良い商品であると販売者を信頼して商品を購入しています。グリーンウォッシュを行うとはその信頼を裏切ってしまうということです。信頼が失われると、消費者は同業他社に対しても「グリーンウォッシュをしているに違いない」と疑いの目を向けるようになります。結果として、健全に運用してきた企業の評判も地に落ち、業界全体の信頼が揺らいでしまいます。
② 消費者の買い控え
グリーンウォッシュが増えていくと、消費者は「環境に良い」と表記された商品に対しても不信感を抱くようになります。その結果、環境に良い商品であっても買ってもらえなくなるという負の連鎖に陥ってしまいます。
③ 利益の悪化
グリーンウォッシュを行う企業のサービスや商品が売れてしまうと、真摯に対策に取り組んできた企業に収益が回ってこなくなります。結果として、健全に販売してきた企業の収益性が悪化し、環境に良い商品の開発に大きな影響を及ぼしてしまいます。
グリーンウォッシュの規制
残念ながら日本にはグリーンウォッシュそのものを罰する法律はありません。
しかし近年環境負荷低減効果についての表示が「景品表示法」に当たる(裏付けとなるデータを欠いている)と措置命令がでた事例があります。
また、2024年に景品表示法の改正が行われ違反者への制裁が強化されました。
ヨーロッパでは2024年2月、EU理事会がグリーンウォッシュを禁止する指令案を採択し数年内に各国で国内法が施行される予定です。
オーストラリアでもグリーンウォッシュに関する行為をした企業に罰金刑が課されたとニュースになりました。
グリーンウォッシュかどうか見分ける方法
グリーンウォッシュについて理解はしたけど、どう見分けたらいいのか分からないという人は多いと思います。
そこで、サステナブルな活動を推進するイギリスのPR会社Futerra社が発行している、グリーンウォッシュを防ぐためのガイド『Understanding and Preventing Greenwash:A Business Guide』にある、疑うべき10個のサインが参考になるのでご紹介します。
- あいまいな言葉を使っている(エコフレンドリーなど)
- 環境に負荷をかける製造ラインでつくられた、グリーンな商品(川を汚す工場で作られた効率的な電球など)
- エコを連想させる写真やイメージを使っている
- 1点の協調(他のすべてがエコでないときに、1つのエコ要素を強調)
- 業界1位という主張(環境への取り組みが遅れている業界の中で、少しでも配慮していることを強調)
- 信用できない(環境にやさしいタバコなど。タバコは体に悪影響を与えるのに環境に良く、安心だということを主張)
- 専門用語の乱用(専門家だけがわかる言葉を使い、消費者に伝わりにくい表現)
- 架空の友人を作り上げる(第三者機関に認証されたかのようなラベルを使用)
- 証拠がない
- 偽りの情報
この10個のサインを参考にしながら、日々の生活でこの企業活動や広報の内容に注意してみてください。
グリーンウォッシュに惑わされないためにできること


グリーンウォッシュに惑わされないため、私たち消費者にできることを3つご紹介していきます。
多くの事例を知る
前述のファーストフード店やファストファッションブランドの他にも、世界にはグリーンウォッシュの事例が多くあります。
これらの事例にアンテナを張ることで、怪しそうな企業活動に疑問を抱くことができるようになります。
あいまいな表現に注意を払う
エコ、ピュア、クリーン、グリーンなどの環境への配慮をイメージさせる言葉を安易に使っているものに気を付けましょう。
パッケージに花や森などのイメージが使われている場合も、原材料などをチェックして本当にエコな商品なのか判断するようにしましょう。
第三者による認証ラベルもひとつの判断基準になりますが、信ぴょう性のないラベルや独自に作成したラベルもあるので、ラベル自体もチェックするようにしましょう。
ウェブサイトで根拠を確認する
少し怪しいなと感じた商品があれば、企業の公式HPを確認してみましょう。
本当に環境に取り組んでいるのであればサイト上で具体的な内容が紹介されています。もしHP上であいまいな表現があれば避けましょう。
まとめ


今回はグリーンウォッシュについてご紹介しました。
グリーンウォッシュにだまされて消費活動などのアクションを起こしてしまうと、せっかくの気持ちや行動が無駄になってしまいます。
情報が多い現代社会では、入ってくる情報を鵜呑みにすることなく、その情報が正しいかどうか自分で判断することが必要になってきます。
それはSDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」にも関連してきます。
環境を守るために自分の選択が正しいかどうか、少し立ち止まって考えてみませんか。